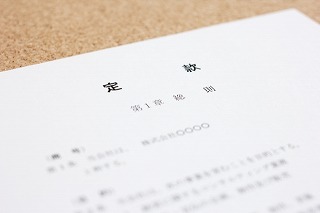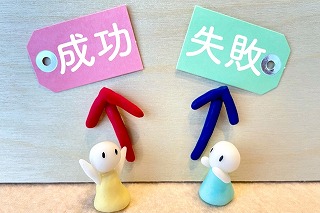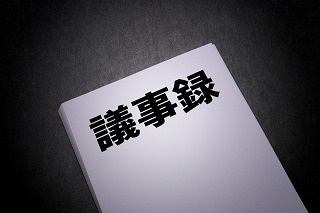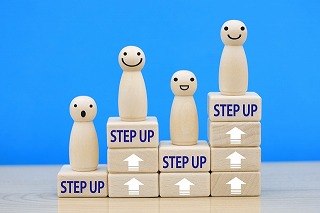
こんな悩みはありませんか?
医療法人の設立を検討しているけれど、「事業計画書」や「予算書」の作成が複雑で、何から手を付ければ良いか分からない、行政への提出書類に不備がないか心配…。
その悩みは今回の説明で解決できます。
医療法人の認可申請において、最も重要で作成に時間を要するこれら書類の作成における4つの重要なルールを、具体的な事例を交えて徹底解説します。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
これを読むことで、設立後の永続性を見据えた、説得力のある書類作成の道筋が見えてくるでしょう。
1 医療法人設立における事業計画書・予算書の基本的な考え方
医療法人を設立する際、避けて通れないのが「事業計画書」と「予算書」の作成です。
これらの書類は、単なる事務手続きではなく、「医業の永続性の確保」という医療法の趣旨に基づき、設立後の安定した経営を見込めるかを、行政機関に提示するための最も重要な資料となります。
特に、岩手県、宮城県を含む東北六県全域で、医療法人の設立を目指す医師・歯科医師の皆様にとって、地域の医療ニーズを踏まえた、具体的で実現性の高い計画を示すことが不可欠です。
1-1.医療法人が目指す「永続性」とは
医療法人は、営利を目的としない公益性の高い法人であり、その運営は安定的かつ継続的でなければなりません。
この「永続性」を証明するために、事業計画書と予算書では、原則として設立後2年間(初年度が6か月未満の場合は3年間)の事業見通しを示す必要があります。
この期間にわたって、必ず黒字が見込める予算であることが大前提です。
赤字の計画では、認可を得ることは極めて困難です。
1-2.事業計画書・予算書作成の4つのルール(必須ポイント)
これらの重要書類を作成するにあたり、失敗しないための核となる4つのルールを提示します。
ルール1:一貫性と矛盾の排除
ルール2:数字の裏付けとなる根拠の明確化
ルール3:設立趣意に基づくストーリー性
ルール4:行政への再提出がない初回での完成度
この4つのルールを意識することで、行政機関が納得する、説得力のある書類を作成することが可能になります。
2 説得力を高める!事業計画書・予算書作成の4つのルール詳細と具体的な手順
2-1.ルール1:一貫性と矛盾の排除(7つの重要書類の整合性)
事業計画書・予算書は、設立申請書に添付する他の重要書類と一貫性が保たれている必要があります。特に重要なのが、以下の7つの書類間での内容の整合性です。
①診療所概要(施設の構造・人員体制など)
②設立趣意書(設立の動機と目的)
③設立総会議事録(設立の意思決定)
④給与費内訳書
⑤予算明細書
⑥設立後2年間の予算書(収支見込)
⑦設立後2年間の事業計画書(資金計画・職員採用計画など)
【具体的な手順】
矛盾を避けるためには、具体的な数字や内容が決まっているものから先に作成していくのが鉄則です。
例えば、「①診療所概要」で定めた職員数や診療体制が、「④給与費内訳書」の人件費に反映され、最終的に「⑥予算書」の支出の根拠となるように、順序立てて作成することで、一貫性のある計画が生まれます。
2-2.ルール2:数字の裏付けとなる根拠の明確化(実績の活用と推計)
予算書に記載する収入(患者数、診療報酬単価など)と支出(人件費、医薬品費など)の数字には、明確な根拠が必要です。
(1)個人開業として実績がある場合
過去の実績(平均)をベースに作成します。
青色申告の決算書や、医師・歯科医師用の所得税の付表などを根拠資料として添付することで、数字の信頼性が高まります。
例えば、「過去3年間の平均患者数」や「平均診療報酬単価」に基づいて、設立後の売上を予測します。
(2)新規開業で実績がない場合
認可を下す行政側が納得できる数字を、客観的なデータに基づいて作り上げる必要があります。
〇収入の根拠例:
①患者数:
専門業者による診療圏調査の結果(一次・二次診療圏の推計患者数、傷病分類別・年代別推計患者数など)を根拠とします。
②診療報酬単価:
厚生労働省が公表している「医療費の動向」における診療科別の外来診療単価などを参考に、妥当な単価を設定します。
これらの客観的なデータに基づき、「これだけの患者数と単価が見込めるから、この収入となる」という論理的な説明ができるようにします。
2-3.ルール3:設立趣意に基づくストーリー性(具体性と整合性)
事業計画書は、単なる数字の羅列ではなく、設立趣意書で述べた理念を実現するための「ストーリー」でなければなりません。
このストーリーには、具体的な内容と、数字の整合性が必要です。
【計画の記載例】(指導する県による)
①建物・設備計画:
「〇年後に増改築を予定」「高額医療機器〇〇を購入予定」など、具体的な計画を記載します。
②職員採用計画:
必要な医療提供体制を維持するための、具体的な人員増計画などを記載します。
③資金計画・債務弁済計画:
借入金があれば、その返済計画を具体的に示し、安定した財務基盤を証明します。
特に、1年以内に定款変更の予定がある場合(例えば、診療所を追加するなど)は、その旨を必ず計画書に記載し、設立当初から将来のビジョンが明確であることを示します。
2-4.ルール4:行政への再提出がない初回での完成度(妥当な計画の提出)
一度行政機関に提出した設立申請書類は、原則として取り下げや大きな修正ができません。
これは、計画内容に行政の認可という重みが加わるためです。
したがって、最初の提出で、一貫性と妥当性のとれた完璧な計画となるように作成することが極めて重要です。
〇予算書のポイント:
運転資金の必要額を、人件費の抑制や支払いの遅延計算などで妥当な範囲で減らす工夫や、自費診療の積極的な見積もりなど、黒字化に向けた現実的な戦略を数字に落とし込みます。
3 まとめ
医療法人の設立、そしてそれに伴う行政機関への許認可の申請書作成や提出は、多くの医師や歯科医師にとって「何から手を付けていいか分からない」「本業に専念したいのに時間が割けない」といった大きな負担となりがちです。
複雑で多岐にわたる行政機関への対応は、専門知識と経験を要します。
そこで、専門家である行政書士にトータルで任せることで、お客様は本業である医療サービスの提供に集中でき、手続きの安心を得ることができます。
当事務所では、医療サイドに寄り添い、最善の解決策を提案いたします。
4 当事務所の「無限の可能性」となる3つの強み
他士業との強力な連携体制: 弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの他士業と強固な連携を組んでおり、医療法人経営で発生し得る様々な問題(法務、税務、労務など)に対して、ワンストップで、いち早く対応できる体制を整えています。
元岩手県職員としての行政機関への「強み」として、元岩手県職員(企業立地、県立大学新設の経験あり)としての経験から、国や県、そして保健所といった行政機関に対し、素早く的確な対応・調整が可能です。
これは、他事務所にはない、手続きをスムーズに進めるための当事務所最大の「強み」です。
また、お客様の利便性を優先した開業体制として、医師・歯科医師の皆様がお忙しいことを理解し、土日・祝日も、朝8時から夜20時まで開業しております。
お仕事の合間を縫って、ご相談いただけるよう、最大限の利便性を図っています。
★注意事項
厚生労働省(地方厚生局)や県、各保健所への申請手続きについて、行政書士は、法律に基づき、他人の依頼を受けて書類を作成し、提出の代理が唯一認められている国家資格者です。
行政書士以外の者が、報酬を得て、他人の依頼を受けてこれらの必要な申請や書類作成を代理することは、法律(行政書士法など)で禁止されています。安心して、適法な手続きを進めるためにも、国家資格者である行政書士にご依頼ください。
5 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ
https://office-fujiihitoshi.com/