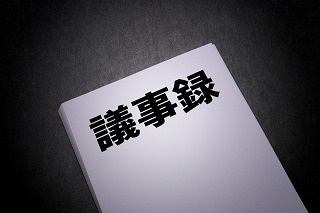「クリニックの収益は安定してきたが、所得税の負担が重くのしかかる…」
「将来の分院展開や事業承継を考えると、個人経営のままで良いのだろうか?」
このようなお悩みはありませんか?個人開業医の先生方が経営の次のステージに進む際、避けては通れないテーマが「医療法人化」です。
そのお悩み、本記事で解決の方向性が見えてきます。
今回は、節税という魅力的なメリットだけでなく、社会保険や運営面のデメリットまで、医療法人化のすべてを多角的に徹底比較し、先生が最善の選択をするための重要事項を詳しくご紹介します。
1 医療法人化は本当に「得」なのか?
クリニック経営が順調に成長し、所得が一定のラインを超えてくると、多くの先生が「医療法人」という選択肢を真剣に検討し始めます。
特に、個人の所得税・住民税の最高税率が合計55%に達するのに対し、法人税の実効税率は30%台であるため、課税所得が1,800万円を超えるあたりから、法人化による節税効果が現実味を帯びてきます。
しかし、「税金が安くなる」という一点だけで判断するのは非常に危険です。
医療法人化は、経営のあり方を根本から変える大きな決断であり、後戻りが難しい制度でもあります。
手続きの煩雑さ、経営の自由度の制限、そして何より社会保険の重い負担など、見過ごせないデメリットも数多く存在します。
大切なのは、目先の節税額だけでなく、将来のビジョン、スタッフの雇用、資産の管理、そして事業承継まで含めた総合的な視点で、メリットとデメリットを天秤にかけることです。
本記事で、その判断材料を一つひとつ丁寧に解説していきます。
2 医療法人化のメリット・デメリット徹底比較
2-1. 【メリット①】税金・相続面での大きな恩恵
医療法人化を推進する最大の原動力は、やはり税務上のメリットです。
正しく活用すれば、手元に残る資金を大きく増やすことが可能です。
⑴ 役員報酬による所得コントロール
個人事業の場合、売上から経費を引いた利益のすべてが院長の所得となり、高額な所得税が課されます。
法人化すれば、院長自身に役員報酬として給与を支払う形になり、「給与所得控除」が適用されます。
例えば、年収1,500万円の場合、給与所得控除額は195万円となり、その分だけ課税対象額を圧縮できるのです。
⑵ 所得の分散による世帯全体の節税
院長の配偶者やお子様など、ご家族を役員に就任させ、経理事務や総務、スタッフの労務管理といった業務内容に応じた適正な役員報酬を支払うことで、所得を効果的に分散できます。
これにより、院長一人に所得が集中して高い税率が適用されるのを防ぎ、世帯全体で見たときの手取り額を最大化できます。
ただし、勤務実態のない名ばかり役員への報酬は、税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。
⑶ 生命保険や退職金の戦略的活用
役員を被保険者とする生命保険(長期平準定期保険など)に加入し、その保険料を法人の経費として計上することが可能です。
これは、将来の勇退に備えた退職金の原資作りとして極めて有効な手段です。
計画的に保険料を支払いながら節税し、退職時に解約返戻金を受け取り、それを原資に退職金を支給します。
退職金は「退職所得控除」という税制上非常に優遇された制度が適用されるため、役員報酬として受け取るよりもはるかに税負担を抑えることができます。
これは個人事業では決して活用できない、法人ならではの大きな魅力です。
⑷ 円滑な事業承継と相続対策
現在の医療法人設立では、社員の退社時に払戻請求権が発生しない「出資持分なし医療法人」が主流です。
これにより、個人クリニックで問題となりがちな、院長の死亡に伴う事業用資産(不動産や医療機器など)への高額な相続税課税や、遺産分割による事業の停滞といったリスクを回避できます。
理事長の交代という形で、スムーズかつ計画的に次世代へクリニックを引き継ぐことが可能になります。
2-2. 【メリット②】事業拡大の可能性が広がる
医療法人は、単なる節税策に留まらず、クリニックの成長戦略を実現するための強固な基盤となります。
⑴ 分院展開(多角経営)の容易化
個人開業では院長自身が管理者でなければならず、分院展開には大きな制約があります。医療法人であれば、別の医師を管理者として雇用し、複数のクリニックや診療所を運営することが可能になります。
これにより、地域でのドミナント戦略や専門特化したクリニックの展開など、事業拡大の自由度が飛躍的に高まります。
⑵ 介護事業への参入による地域貢献
医療法人は、訪問看護ステーション、デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)といった介護保険事業を附帯業務として行うことができます。
地域包括ケアシステムが推進される中、医療と介護を一体的に提供できる法人は、地域になくてはならない存在となり、経営の安定化にも繋がります。
2-3. 【デメリット①】運営・手続き面の負担が増加
法人格を得る代償として、個人経営時代にはなかった数多くの事務的・法的な義務が生じます。
⑴ 煩雑かつ定期的な行政への報告
毎年、会計年度終了後に「事業報告書」「監事監査報告書」などを添付した決算届を都道府県に提出しなければなりません。
また、2年に1度の役員任期満了時には、法務局での登記変更と都道府県への「役員変更届」の提出が義務付けられます。
これらの書類作成は専門知識を要し、事務負担は確実に増加します。
⑵ 厳格化する行政のガバナンス
診療所の移転や附帯業務の追加など、法人の根幹に関わる変更を行う際は、その都度、詳細な事業計画書や収支予算書を添付して、都道府県の「定款変更認可」を受けなければなりません。
この審査は厳格で、認可が下りるまで数ヶ月を要することもあります。
個人経営のような機動的な意思決定が難しくなる場面があることは否めません。
2-4. 【デメリット②】社会保険への強制加入という大きな壁
これは、医療法人化の最大のハードルと言っても過言ではありません。
個人クリニックではスタッフが5人未満の場合、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は任意ですが、医療法人は役員1名であっても強制加入となります。
保険料は法人と個人で折半しますが、その負担は法人税や消費税以上に経営を圧迫する可能性があります。
例えば、院長の役員報酬を月額150万円と設定した場合、法人と個人の負担を合計すると、年間で実に400万円を超える社会保険料が発生することもあります。
役員であるご家族も加入対象となるため、世帯全体での負担はさらに膨らみます。
節税によるメリットが、この社会保険料負担の増加によって吹き飛んでしまうケースも決して珍しくありません。
法人化を検討する際は、税理士や社会保険労務士による精密なシミュレーションが不可欠です。
2-5. 【デメリット③】経費の増加と資金活用の制限
⑴ 専門家への継続的な報酬
法人化すると、複雑な法人税申告のために税理士との顧問契約が必須となります。
また、前述の登記手続きで司法書士、許認可申請で行政書士、労務管理で社会保険労務士と、様々な専門家のサポートが必要となり、これらの顧問料や手数料が継続的に発生します。
⑵ 「法人のお金」と「個人のお金」の厳格な分離
個人事業主の感覚で法人の預金口座から生活費を引き出すことは絶対にできません。
これは法人からの「借金(役員貸付金)」となり、法人はその貸付金に対して利息を受け取らなければなりません。
この役員貸付金が長期間残っていると、金融機関からの融資審査で著しく不利になるほか、税務調査で厳しく追及される原因となります。
個人の生活は、すべて役員報酬の範囲内で賄うという厳しい規律が求められます。
2-6. 【デメリット④】事業の廃止・承継の複雑さ
一度設立した医療法人を畳むのは、個人事業を廃業するようにはいきません。
法人の解散には、都道府県知事の認可を得た上で、清算人を選任し、債権者保護のために官報公告を行い、煩雑な清算手続きを経て、ようやく結了となります。
これには多大な時間と費用を要します。
また、旧法の「出資持分あり医療法人」の場合、相続時に出資持分の評価額が高騰し、後継者が買い取れなかったり、莫大な相続税が発生したりするという根深い問題も抱えています。
3 まとめ
医療法人化が単なる節税スキームではなく、法務、税務、労務が複雑に絡み合う高度な経営判断であることがお分かりいただけたかと存じます。
何から手をつけ、誰に相談すれば良いのか、途方に暮れてしまうのも無理はありません。
このような複雑で専門的な手続きは、ぜひ専門家である行政書士にお任せください。
先生方が日々の診療に安心して専念できるよう、私たちが羅針盤となって法人化への道をナビゲートいたします。
当事務所は、単に申請書類を作成する代行業者ではありません。
先生のクリニックが目指す未来像を共有し、その実現に向けた最適なプランを共に考え抜くパートナーです。
当事務所の最大の強みは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった各分野のプロフェッショナルとの強固なネットワークです。
設立時のシミュレーションから、設立後の運営サポート、そして将来の事業承継まで、あらゆるフェーズの課題に対して、ワンストップで迅速かつ最適なソリューションを提供できる体制を構築しております。
そして何より、私自身が元岩手県職員として、行政の内部で許認可業務に携わってきた経験があります。
行政機関が何を求め、どのような点を重視するのかを熟知しているからこそ、ポイントを押さえた円滑な申請が可能です。
この「行政との対話力」は、他の事務所にはないと自負する、当事務所ならではの強みです。
貴重な時間を煩雑な手続きに費やすことなく、先生は目の前の患者様と向き合うことに集中してください。
まずはお悩みをお聞かせいただくことから、すべてが始まります。
お気軽にご相談ください。
4 注意事項
厚生労働省(地方厚生局)や県、保健所への医療法人設立認可申請などの代理業務は、行政書士法に基づき、「行政書士のみ」が行うことを許された業務です。
行政書士以外の者が、これらの申請を代理することは、法律で固く禁じられています。
5 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ
https://office-fujiihitoshi.com/