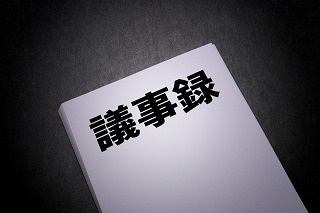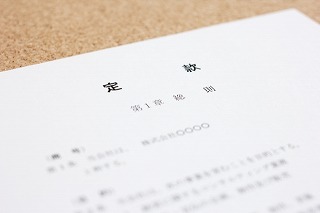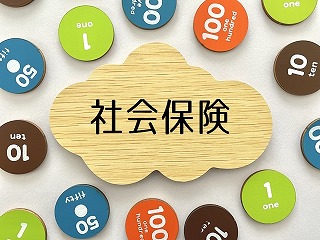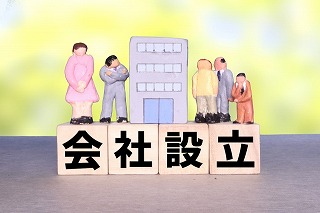「医療法人を設立したいが、事業計画や予算書の作り方が複雑で分からない」
「数字が苦手で、どこから手をつけていいか…」
こんな悩みはありませんか?
そのお悩み、この記事で解決できます。
医療法人設立の最難関の一つ「収入・支出予算明細書」には、特有のルールがあるのです。
今回は、多忙な先生方のために、予算書作成でつまずかないための重要ポイントを分かりやすく紹介します。
1 医療法人設立における「収入・支出予算明細書」の基本
医療法人設立の許認可申請において、「収入・支出予算明細書」は事業計画の根幹をなす最重要書類の一つです。
これは、新しく設立する法人が、設立後2年間、安定して医業を継続できるか、その財産的基礎を審査するために作成します。
この予算書作成における最大の基本原則は、「キャッシュフロー(現金の流れ)」で作成する、という点です。
1-1. 会計上の「利益」ではなく「現金の流れ」で計上する
一般的な企業会計では「発生主義」に基づき、現金の動きがなくても費用や収益を計上します(例:減価償却費、各種引当金)。
しかし、医療法人の設立予算書は、あくまで「設立後の運転資金が枯渇しないか」を見るためのものです。
そのため、以下のような会計処理が求められます。
⑴ 減価償却費・引当金は計上しない
これらは会計上の費用ですが、実際に現金が社外に出ていくわけではないため、支出予算には計上できません。
⑵ 消費税は「税込」で計上する
キャッシュフロー、つまり実際の現金の出入りを記すため、収入(診療報酬など)も支出(医薬品仕入、経費支払など)も、すべて消費税込みの金額で作成する必要があります。
この「キャッシュフローベース」という原則を間違うと、すべての数字が連鎖的に狂ってしまい、申請書の大幅な修正(最悪の場合、差し戻し)につながるため、絶対に押さえておく必要があります。
2 「収入予算明細書」作成で押さえるべきポイント
収入予算は、法人がどれだけの収入を見込めるかを行政に示す部分です。
ここが曖昧だと、「本当に経営が成り立つのか?」と厳しく見られます。
2-1. 実績ベースか、合理的根拠ベースか
最も説得力のある収入予算は、「実績」です。
⑴ 個人開業からの法人成り(医療法人化)の場合
過去の確定申告書などに基づき、直近1〜3年間の「1日平均患者数」や「平均診療単価」を算出します。
この実績値をベースに、設立初年度・次年度の収入を計算します。これが最も強力な根拠となります。
⑵ 新規開業(実績がない)の場合
実績がないため、収入見込みの「合理的根拠」を示す書類を添付する必要があります。
例えば、近隣の競合クリニックの状況、診療圏調査のデータ、連携予定の病院からの紹介患者数の見込みなどを具体的に示し、設定した患者数や単価が妥当であることを証明しなくてはなりません。
2-2. 診療日数の計算と医業外収入
患者数の計算式 「1日平均患者数(人)× 1カ月の診療日数 × 12カ月」で計算します。
ここで注意すべきは、「1カ月の診療日数」です。
この日数は、申請書類の一部である「開設しようとする診療所の概要」に記載する診療日数と、必ず一致している必要があります。
〇 医業外収入の取り扱い
歯科クリニックで歯ブラシを販売するなど、医業以外の収入を計上する場合、注意が必要です。
これは、医療法人が本来業務(医業)に附随して行うものか、という視点で審査されます。
単なる物販と見なされると、定款変更や別事業としての扱いが必要になるケースもあります。
自治体(都道府県)によっても見解が分かれるため、「来院した患者への療養の向上」という目的の範囲内であることを明確にする必要があります。
3 最難関!「支出予算明細書」作成の重要ルール
支出予算は、収入に対して経費が過大になっていないか、必要な支出が漏れていないかを審査されます。
特に以下の項目は、行政が厳しくチェックするポイントです。
3-1. 職員給与と役員報酬の注意点
⑴ 職員給与
「職員給与内訳書」という別紙を作成し、その合計金額と支出予算書の金額を完全に一致させる必要があります。
⑵ 役員報酬(理事長給与)
理事長が院長(管理者)を兼務する場合、その給与設定には注意が必要です。
特に「希望額」で設定すると、支出が膨らみ、収支が赤字になる(または黒字が極端に少なくなる)ケースが散見されます。
予算書作成のテクニックとして、「役員報酬は、まず最低限の生活ができるラインで設定する」ことをお勧めします。
まずは予算書上の収支を安定させ、法人設立後に経営が軌道に乗り、利益(剰余金)が確保できてから、社員総会の決議を経て報酬を増額する、という方針のほうが、設立認可は格段にスムーズに進みます。
3-2. 法定福利費と契約ベースの費用
⑴ 法定福利費(社会保険料など)
これは法律で定められた必須の支出です。
計上漏れは絶対に許されません。
ただし、設立時点での厳密な計算は困難なため、予算書作成段階では、人件費(職員給与+役員報酬)の約10%〜20%程度の概算額を計上すれば問題ありません。
⑵ 家賃・リース料・駐車場代
これらの費用は、必ず「契約書」と金額を一致させます。
契約書に記載のない管理費や共益費は、「その他の費用」などに計上します。
※ 特に注意したいのが駐車場
患者用・職員用の駐車場代を法人の経費とすることは認められますが、「理事長(院長)個人用の駐車場代」を経費として計上することは、原則として認められません。
3-3. 盲点となる「医療機器のリース」
個人開業医から法人成りする際、先生個人が所有する医療機器をどう法人に移すかは大きな問題です。
⑴ 法人が買い取る(売買)
分割払い(割賦)での支払いも可能であり、予算書上も処理しやすいです。
⑵ 法人に貸し出す(賃借)
ここに大きな落とし穴があります。
先生個人が、医療法人に対して「業として」医療機器を賃貸する場合、「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」が関わってきます。
その機器が高度管理医療機器であれば「賃貸業の許可」、管理医療機器であれば「賃貸業の届出」が別途必要になるのです。
これは会計の問題ではなく、法務・許認可の問題であり、知らないまま進めると設立手続きが頓挫する可能性があります。
3-4. 法人税の計上
医療法人も利益(正確には所得)が出れば納税義務が発生します。
実際の納税は翌年度になりますが、予算書上は「発生主義」に基づき、当期の支出として計上(引当)する必要があります。
目安として、「税引前利益(剰余金)の約30%」を法人税等として計上します。
【最重要注意点】
この税引前利益とは、「キャッシュフロー計算書の剰余金」のことではありません。
前述の通り、予算書はキャッシュフローで作成するため、減価償却費などが含まれていません。
税金の計算(課税所得の計算)は、そこから減価償却費などを考慮し直して行う必要があります。
ここを混同すると、税額の計算が全く合わなくなります。
4 確定申告書の添付
個人開業からの法人成りの場合、県によっては、「直近の確定申告書の写し」を提出することで、事業計画書や予算書の作成・提出が一部不要になるケースがあります。
これは、確定申告書が、その診療所の経営実態を客観的に証明する最も信頼性の高い資料だからです。
ただし、条件があります。
提出する確定申告書に、「税務署の収受印」が押されていること、または電子申告(e-Tax)の場合は「受付結果(受信通知)」が添付されていることが必須です。
これが無いと、正式な書類として認められません。
5 複雑な医療法人設立手続きは専門家にお任せください
医療法人の設立、そしてその後の行政機関への各種許認可・届出の申請書作成や提出方法について、「何から手を付けていいか分からない」というのが多くの先生方の本音ではないでしょうか。
診療の傍ら、これらの複雑で膨大な書類を作成し、行政の窓口と何度も折衝するのは、時間的にも精神的にも大きな負担となります。
このような手続きは、専門家である行政書士にトータルで任せることで、先生は本業である医療に集中でき、確実な手続きによる「安心」を得ることができます。
★ 当事務所ならではの「強み」
当事務所にご依頼いただくメリットとして、他にはない以下の「強み」があります。
⑴ ワンストップの連携体制
当事務所の最大の特徴は、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった他士業と強固な連携を組んでいる点です。
医療法人の設立(登記)から税務、労務問題まで、発生する様々な問題に対し、当事務所を窓口としてワンストップで対応できる体制を構築しています。
⑵ 行政機関との調整力(元岩手県職員)
元岩手県職員としての実務経験(企業立地、県立大学新設業務など)がございます。
国や県、保健所といった行政機関の「考え方」や「手続きの進め方」を熟知しており、申請がスムーズに進むよう、素早く的確な調整・対応ができる点が、他事務所にはない絶対的な強みです。
⑶ 土日営業等
多忙な先生方に合わせた利便性 他の事務所と異なり、土日・祝日も営業しております。
また、営業時間も朝8時から夜20時までとしており、診療後や休診日など、先生方のご都合に合わせて、いつでもご相談いただける体制を整えております。
岩手県(北上市ほか全域)、宮城県(仙台市ほか全域)、そして東北6県の医療法人の設立、運営サポートは、ぜひ当事務所にお任せください。
医療サイドに徹底的に寄り添い、最善の解決策をご提案いたします。
【注意事項】
厚生労働省(地方厚生局)、県庁、各保健所への医療法人に関する許認可申請や届出は、業として(報酬を得て)他人の依頼に基づき代理作成・提出できるのは、行政書士のみです。
行政書士の資格を持たない者が、これらの申請代行業務を行うことは、法律(行政書士法)で固く禁止されています。
6 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ
https://office-fujiihitoshi.com/