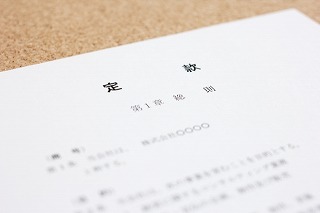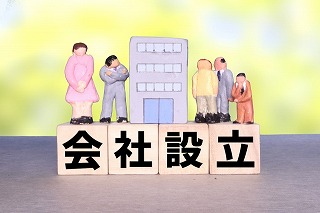「医療法人化すれば節税メリットが大きいと聞くが、個人開業時代に借りた多額の設備ローンはどうなるのか?」
「運転資金の借入も、もちろんクリニックのために使ったのだから引き継げるはずだ」
こんなお悩みや疑問はありませんか?
そのお悩み、今回の説明で解決できます。医療法人設立時の「負債引継ぎ」は、非常に厳格なルールがあり、この手続きを誤ると、将来のキャッシュフロー計画に重大な支障をきたす可能性があります。
今回の提案は、先生方のお困りごとを解決するため、医療法人設立における「負債引継ぎ」の核心部分と、絶対に押さえるべき重要ルールについて、専門家の視点から詳しく紹介します。
1 なぜ「負債の引継ぎ」が重要なのか?
個人事業であるクリニックを法人化(医療法人設立)する際、先生個人が所有していた医療機器や内装設備といった「財産」を、新しく設立する医療法人に「拠出(または寄附)」します。
同時に、もしその財産を取得するために金融機関から借りたローン(負債)が残っている場合、その返済義務も医療法人に引き継がせたいと考えるのが自然です。
1-1. もし負債を引き継がなかったら?
仮に負債を医療法人に引き継がず、先生個人が返済を続ける場合、どのようなことが起こるでしょうか。
先生は医療法人の理事長として「役員報酬」を受け取ることになりますが、その役員報酬(給与所得)の中から、個人の借入金を返済し続けることになります。
役員報酬には当然、所得税や住民税、社会保険料がかかります。
つまり、税金や社会保険料が引かれた「後」の手取り収入から、多額のローン返済を行わなければならないのです。
1-2. 負債引継ぎがもたらす最大のメリット
一方、負債引継ぎが認められれば、医療法人が金融機関への返済を行います。
法人は役員報酬とは無関係に、クリニックの医業収益から直接返済できるため、先生個人の税負担を不必要に増やすことがありません。
この「個人の税負担軽減」こそが、負債引継ぎを検討する最大のメリットです。
しかし、この引継ぎには厳格な条件が設けられています。
2 引継ぎの絶対条件
行政(都道府県や厚生労働省)が負債の引継ぎを認めるかどうか、その最大の分岐点は「借入金の使い道(資金使途)」です。
2-1. 引き継ぎが認められる負債
引き継ぎが認められるのは、「医療法人へ拠出する財産の取得そのものに要した借入金」に限られます。
〇具体例:
・クリニックの内装工事費用
・CT、MRI、レントゲンなどの高額な医療機器の購入費用
・拠出する場合の、土地や建物の取得費用
これらは「設備資金」と呼ばれ、法人が事業を行う上で必須の財産(資産)と、それに紐づく負債として一体的に引き継ぐことが認められやすいです。
2-2. 引き継ぎが認められない負債
一方で、たとえクリニックの運営のために借りたお金であっても、「運転資金」に分類される借入金は、原則として引き継ぐことができません。
〇具体例:
・スタッフの賞与(ボーナス)支払いのための借入
・医薬品や消耗品の仕入れ費用
・広告宣伝費、交際費
・短期のつなぎ資金
これらは法人の「財産」として残らないため、負債だけを引き継ぐことは認められません。
3 なぜ「運転資金」の引継ぎは認められないのか?
多くの院長先生が疑問に思われるのが、この点です。
「クリニック運営のために借りたお金なのに、なぜ引き継げないのか」と。
これには、医療法の根本的な考え方に基づいた、明確な理由が存在します。
3-1. 理由1
運転資金は、その時々のクリニック運営(個人事業)に使われ、その結果として生じた利益は、すでに個人事業主である先生個人の所得となっています。
すでに個人がその恩恵(利益)を受けているにもかかわらず、その元手となった負債だけを新設の医療法人に負担させることは、「法人から個人への利益供与」とみなされる恐れがあります。
3-2. 理由2
運転資金は、その性質上、様々な支払いに充当されます。
行政側から見れば、「本当にすべてがクリニック運営に使われたのか?」という証拠(エビデンス)を厳密に確認することが困難です。
「先生個人の生活費や、お子様の学費の一部に使われていた可能性も否定できない」と判断されてしまいます。
3-3. 理由3
医療法人は、株式会社とは異なり「非営利性」が求められ、利益が出ても出資者に配当(剰余金の配当)することが禁じられています。
もし、使途が曖昧な個人の負債を法人が肩代わりすることを無制限に認めれば、それは実質的な「剰余金の配当」や「個人への利益供与」と同じ行為になってしまい、医療法の根本原則に抵触してしまうのです。
だからこそ、行政は「法人が引き継ぐ資産(設備)と明確に紐づく負債」以外は、一切認めないという厳格な姿勢をとっています。
4 負債引継ぎを成功させる「4つの必須ルール」
では、引継ぎ可能な「設備資金」の負債を、実際に引き継ぐためには何をすべきでしょうか。
ここでは、行政への認可申請をクリアするために必須となる「4つのルール」を解説します。
⑴ ルール1
まず大前提として、その借入金が「運転資金」ではなく「設備資金」であることを証明しなくてはなりません。
金融機関との「金銭消費貸借契約書(ローン契約書)」において、資金使途が「設備資金」「医療機器購入費」などと明確に記載されている必要があります。
もし「運転資金」や「開業資金(一式)」といった曖昧な名目になっている場合、その全額、あるいは一部が否認されるリスクが高まります。
⑵ ルール2
申請時には、その負債が拠出財産とイコールであることを証明する、客観的な資料一式を求められます。
① 金銭消費貸借契約書
② 返済予定表(申請日現在の残高が分かるもの)
③ 領収書、請求書、売買契約書(医療機器の購入や内装工事の支払い事実を証明するもの)
特に重要なのは「日付」です。
融資の実行日以降の日付で、実際に設備投資の支払いが行われたことを示す領収書などがなければ、関連性を証明できません。
これらの資料が一つでも欠けていれば、引継ぎは認められません。
⑶ ルール3
これが手続き上、最も重要かつ時間を要するポイントです。
負債を引き継ぐということは、金融機関(銀行など)から見れば、「債務者が個人(先生)から医療法人に変わる」ことを意味します。
そのため、金融機関(債権者)の「承諾」が絶対条件となります。
行政へ申請書類を提出する前に、金融機関に「負債残高証明書」および「債務引継承認願」といった書類への署名・捺印をもらう必要があります。
銀行内部では、個人の信用から法人の信用へと切り替えるための「稟議(りんぎ)」が必要となり、これには数週間から1ヶ月以上かかるケースも珍しくありません。
スケジュールに余裕を持った早めの相談が不可欠です。
⑷ ルール4
借入が単純でない場合、さらに専門的な処理が求められます。
① 按分(あんぶん)計算が必要なケース
・例えば「借入金5,000万円」のうち、資金使途が「設備資金3,000万円+運転資金2,000万円」と混在している場合。
・この場合、引継ぎ可能なのは設備資金部分(3,000万円)に対応する負債残高のみです。
・未返済額(例:残り4,000万円)に、当初の設備資金の割合(3,000万/5,000万=60%)を乗じて計算(4,000万×60%=2,400万円)するなど、合理的な按分計算と、その根拠を金融機関・行政の双方に説明する必要があります。
② 「借換」を行っているケース
・当初は設備資金として借りたものの、その後に他の借入(コロナ融資などの運転資金)と一本化(借換)してしまった場合、元の設備資金との関連性が途切れてしまい、引継ぎが極めて困難になります。
・この場合も、借換直前の対象額を算出するなど、複雑な作業が求められます。
これらの複雑な計算や銀行折衝は、専門家である行政書士などと、緊密に連携して進めなければ、手続きが頓挫する原因となります。
5 まとめ
医療法人の設立、そして行政機関への許認可申請、特にこの「負債引継ぎ」の手続きは、何から手を付けていいか分からないほど複雑です。
「この借入は引き継げるのか?」「銀行には何と説明すればいいのか?」「どの書類を集めればいいのか?」…先生ご自身が診療の傍らでこれら全てを調査し、実行するのは現実的ではありません。
このような複雑な行政機関への対応こそ、専門家である行政書士に、ご依頼いただく最大のメリットがあります。
煩雑な書類作成、金融機関との折衝、そして行政窓口(都道府県や保健所)との調整までをトータルで任せていただくことで、先生は「安心」と「時間」を手に入れ、本来の診療業務に集中することができます。
当事務所は、単なる手続き代行に留まりません。
医療サイドに常に寄り添い、先生のクリニックにとって何が最善の解決策となるかを一緒に考え、ご提案します。
★ 信頼できる専門家ネットワークと、他にはない「強み」 ★
① 当事務所の最大の強みは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労士といった他士業の専門家と強固な連携体制を組んでいることです。
医療法人設立(登記)から税務、労務問題まで、あらゆる問題にワンストップで迅速に対応が可能です。
② さらに、私自身が元岩手県職員としての実務経験(企業立地、県立大学新設など)を有しております。国や県、保健所といった行政機関の思考や手続きの流れを熟知しているからこそ、他の事務所にはない「調整力」と「スピード感」で、認可取得までスムーズにご案内できると自負しております。
③ 東北(岩手、宮城)の医療の未来を支える先生方を全力でサポートするため、当事務所は土日、祝日も開業(8時~20時)し、多忙な先生方の利便性を最優先に考えております。
医療法人化に関するご相談、負債引継ぎに関するご不安は、ぜひ一度、行政書士藤井等事務所にお聞かせください。
【注意事項】
厚生労働省(地方厚生局)、都道府県、各保健所への許認可申請や届出は、法律により、行政書士が唯一、申請を代理することが認められている国家資格者です。
行政書士の資格を持たない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て、これらの申請代理業務を行うことは、行政書士法違反として固く禁止されています。大切な許認可手続きは、必ず正規の行政書士にご相談ください。
6 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ
https://office-fujiihitoshi.com/