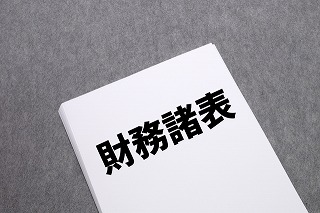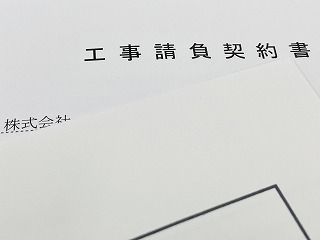「工場の機械を設置したいけど、どの建設業許可が必要?」「機械器具設置工事って、どんな工事のこと?」「太陽光パネルの設置は、電気工事と屋根工事のどっち?」
こんな疑問や不安はありませんか?
建設業許可を申請するにあたって、自社が行う、あるいはこれから行う「建設工事」の概要を具体的に知っておくことは必須です。
特に、機械の設置工事や太陽光パネルの設置工事は、複数の業種に該当する可能性があり、判断が難しいケースも少なくありません。
ご安心ください。
今回の記事では、機械の設置工事や太陽光パネルの設置工事について、建設業許可の業種判断のポイントを、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
この記事を読めば、必要な許可業種が明確になり、安心して事業を進められるようになります。
岩手県、宮城県(仙台市含む)で建設業を営む皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1機械の設置工事、どの業種?建設業許可の基本
建設業許可は、工事の種類によって29の業種に分かれています。
機械の設置工事は、その種類や設置方法、工事の規模、さらには関連する工事の内容によって、複数の業種に該当する可能性があるため、注意が必要です。
ここでは、建設業許可における機械設置工事の位置づけと、業種判断の基本的な考え方について、さらに詳しく解説します。
1-1. 「機械器具設置工事」だけじゃない!:多岐にわたる業種の可能性
「機械の設置工事」と聞くと、多くの方がまず「機械器具設置工事」という業種を思い浮かべるかもしれません。
確かに、「機械器具設置工事」は、機械器具の設置工事を専門とする業種ですが、建設業許可において、すべての機械の設置工事が「機械器具設置工事」に該当するわけではありません。
例えば、以下のようなケースでは、「機械器具設置工事」以外の業種に該当する可能性があります。
(1)電気工事: 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備など、電気工作物の設置工事は「電気工事」に該当します。
これには、太陽光発電設備の設置工事(屋根置きタイプで、電気工事が主となる場合)も含まれます。
(2)管工事: 冷暖房設備、空調設備、給排水・給湯設備、ガス配管設備など、配管工事を伴う設備の設置工事は「管工事」に該当します。
例えば、業務用エアコンの設置や、ボイラーの設置などがこれにあたります。
(3)とび・土工・コンクリート工事: 重量物の運搬・配置、アンカー固定、コンクリート基礎の設置など、機械の設置に付随する基礎工事や準備工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
例えば、大型機械の搬入・据付、機械を固定するためのアンカーボルトの設置、機械を設置するためのコンクリート基礎の打設などがこれにあたります。
(4)消防施設工事: 消火設備に関する工事は、「消防施設工事」に該当します。消火栓、スプリンクラー、火災報知機など。
(5)清掃施設工事: ごみ焼却設備や、し尿処理設備に関する工事は、「清掃施設工事」に該当します。
このように、機械の設置工事は、その機械の種類や設置場所、工事の内容によって、様々な業種に該当する可能性があるため、注意が必要です。
1-2. 他の業種に該当するケースも:具体例と判断のポイント
具体的に、どのような場合に他の業種に該当するのか、いくつかの例を挙げてみましょう。
・工場の生産ラインに産業用ロボットを設置する場合:
ロボットの設置自体は、「機械器具設置工事」に該当する可能性があります。
しかし、ロボットに電気配線工事を行う場合は、「電気工事」の許可が必要です。
ロボットを設置するための架台を設置する場合は、「とび・土工・コンクリート工事」または「鋼構造物工事」の許可が必要になる場合があります。
ロボットが空調設備の一部である場合は、「管工事」の許可が必要になる場合があります。
・ビルの屋上に冷却塔(クーリングタワー)を設置する場合:
冷却塔の設置自体は、「機械器具設置工事」に該当する可能性があります。
しかし、冷却塔に給排水管を接続する場合は、「管工事」の許可が必要です。
冷却塔を屋上にクレーンで揚重する場合は、「とび・土工・コンクリート工事」の許可が必要です。
・店舗に業務用冷蔵庫を設置する場合:
業務用冷蔵庫の設置自体は、専門業者に依頼する場合は「機械器具設置工事」に該当する可能性があります。
しかし、冷蔵庫に電気配線工事を行う場合は、「電気工事」の許可が必要です。
冷蔵庫の設置に伴い、床の補強工事を行う場合は、「とび・土工・コンクリート工事」または「内装仕上工事」の許可が必要になる場合があります。
これらの例からも分かるように、機械の設置工事は、単に機械を設置するだけでなく、電気工事、配管工事、基礎工事など、様々な付帯工事を伴うことが多く、複数の業種の許可が必要になるケースが少なくありません。
1-3. 正しい業種判断が重要な理由:違反のリスクと事業への影響
もし、誤った業種で建設業許可を取得してしまったり、許可が必要な業種で許可を取得していなかったりすると、建設業法違反となり、様々なリスクが生じます。
(1)罰則: 建設業法では、無許可営業や許可外の業種の工事を請け負った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則が科せられます(建設業法第47条)。
(2)行政処分: 罰則に加えて、指示処分、営業停止処分、許可の取消しといった行政処分を受ける可能性があります(建設業法第28条、第29条)。
許可が取り消されると、その後5年間は新たな許可を取得できなくなるなど、事業継続に大きな影響を及ぼします。
(3)入札参加資格の喪失: 公共工事の入札に参加するためには、建設業許可が必要であり、かつ、入札参加資格審査を受ける必要があります。
建設業法違反があると、この入札参加資格を喪失する可能性があります。
(4)社会的信用の失墜: 建設業法違反は、企業の社会的信用を大きく損ないます。
取引先や金融機関からの信頼を失い、今後の事業活動に支障をきたす可能性があります。
(5)損害賠償請求: 建設業法違反によって発注者や第三者に損害を与えた場合、損害賠償を請求される可能性があります。
これらのリスクを避けるためにも、機械の設置工事を行う場合は、事前に必ず、必要な許可業種を正確に判断し、適切な許可を取得しておくことが重要です。
2建設業許可「とび・土工・コンクリート工事」とは?
とび・土工・コンクリート工事は、建設業許可の中でも、非常に幅広い工事内容を含む業種です。
「とび・土工・コンクリート工事」という名称から、高所作業や土木工事、コンクリート工事をイメージする方が多いと思いますが、実際には、これら以外にも様々な工事が含まれています。
ここでは、とび・土工・コンクリート工事の内容、具体的な工事例、機械の設置工事との関係について、さらに詳しく解説します。
2-1. とび・土工・コンクリート工事の内容:国土交通省の定義
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると、とび・土工コンクリート工事の内容は、以下のとおりです。
・足場の組立て、機械器具・建設資材の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事:
これは、建設工事の現場で、足場を組み立てたり、クレーンなどの重機を使って、機械器具や建設資材を運搬・配置したり、鉄骨を組み立てたりする工事のことです。
これらの工事は、高所作業や重量物の取り扱いを伴うため、専門的な技術や知識が必要となります。
・くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事:
これは、建物の基礎を支えるための杭(くい)を地中に打ち込んだり、引き抜いたり、現場でコンクリートを流し込んで杭を造ったりする工事のことです。
これらの工事は、建物の安全性や耐久性に大きく影響するため、高度な技術と経験が必要となります。
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事:
これは、土地を掘削したり、土砂を盛り上げたり、締め固めたりする工事のことです。
道路や宅地の造成、河川の改修、ダムの建設など、様々な土木工事の基礎となる工事です。
・コンクリートにより工作物を築造する工事:
これは、コンクリートを使って、建物や橋梁、ダム、トンネルなどの構造物を造る工事のことです。
コンクリートの打設、型枠の設置、鉄筋の組み立てなど、様々な作業が含まれます。
・その他上記の基礎的工事、準備的工事:
これは、上記の工事に付随して行われる、様々な基礎工事や準備工事のことです。
具体的には、地盤改良工事、土留め工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、外構工事、はつり工事、アンカー工事など、多岐にわたります。
2-2. 具体的な工事例:多岐にわたる工事
とび・土工・コンクリート工事には、以下のような工事が含まれます。
・とび工事:
建設現場の足場の組立て、解体
鳶(とび)工事(高所での作業全般)
・ひき工事:
重量物のクレーン等による運搬、配置(機械器具、建設資材など)
建物や設備の解体、撤去
・土工事:
掘削工事(土地の掘削、溝掘りなど)、盛土工事(土砂を盛り上げて土地を造成する)、埋め戻し工事(掘削した場所に土砂を戻す)、地盤改良工事(軟弱な地盤を改良する)
・コンクリート工事:
コンクリート打設工事(型枠にコンクリートを流し込む)
コンクリートブロック据付け工事(コンクリートブロックを積み上げて構造物を造る)
コンクリート製品の製造、加工、設置
・基礎工事:
杭打ち工事(既製杭、場所打ち杭など)、杭抜き工事、基礎コンクリート工事
・その他:
地すべり防止工事、土留め工事(山留め工事)、仮締切り工事、吹付け工事(モルタル吹付け、コンクリート吹付けなど)、法面保護工事(斜面の保護)、道路付属物設置工事(ガードレール、標識、カーブミラーなど)、屋外広告物設置工事(完成品の看板の設置)、捨石工事、外構工事(塀、門扉、駐車場などの工事)、はつり工事(コンクリートなどを削ったり、壊したりする)、アンカー工事(アンカーボルトの設置)、あと施工アンカー工事、潜水工事
2-3. 機械の設置工事との関係:重量物運搬、アンカー固定、基礎工事
機械の設置工事の中には、とび・土工・コンクリート工事に該当するものがあります。
具体的には、以下のようなケースです。
・重量物の運搬・配置:
工場やプラントなどに大型の機械を設置する際、移動式クレーンなどの重機を使用して、機械を所定の位置に運搬し、設置する工事は、「とび・土工・コンクリート工事」の「機械器具・建設資材の重量物のクレーン等による運搬配置」に該当します。
この場合、機械の据え付け自体は「機械器具設置工事」に該当する可能性がありますが、機械を運搬し、配置する作業は、「とび・土工・コンクリート工事」となります。
・アンカー固定:
機械を安定させるために、地面や床にアンカーボルトで固定する工事は、「とび・土工・コンクリート工事」の「アンカー工事」または「あと施工アンカー工事」に該当します。
アンカーボルトの種類や施工方法によって、必要な技術や知識が異なるため、専門的な業者に依頼することが一般的です。
・コンクリート基礎の設置:
機械を設置するためのコンクリート基礎を築造する工事は、「とび・土工・コンクリート工事」の「コンクリートにより工作物を築造する工事」に該当します。
この場合、コンクリートの打設、型枠の設置、鉄筋の組み立てなど、様々な作業が必要となります。
これらの工事は、機械の設置工事に付随して行われることが多いですが、工事の内容によっては、「とび・土工・コンクリート工事」の許可が別途必要になる場合があるため、注意が必要です。
3建設業許可「機械器具設置工事」とは?
機械器具設置工事は、その名の通り、機械器具を設置する工事ですが、他の業種との区別がつきにくく、判断に迷うことが多い業種です。
ここでは、機械器具設置工事の内容、具体的な工事例、他の業種との違いについて、さらに詳しく解説します。
3-1. 機械器具設置工事の内容:国土交通省の定義
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると、機械器具設置工事の内容は、以下のとおりです。
・機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
この定義は、一見すると非常にシンプルですが、解釈が難しく、他の業種との区別がつきにくい要因となっています。
ポイントは、「機械器具の組立て等により」という部分と、「工作物に機械器具を取り付ける」という部分です。
3-2. 2種類の工事:組立てと取付け
機械器具設置工事は、大きく分けて以下の2種類の工事に分類されます。
・機械器具の組立て等により工作物を建設する工事:
これは、プラント設備工事や立体駐車場設備工事など、現場で機械器具を組み立てて、一つの工作物(建物や設備)を建設する工事を指します。
例えば、発電所のタービンやボイラー、石油化学プラントの反応塔や貯槽、工場の生産ライン設備、遊園地のジェットコースターや観覧車などが該当します。
これらの工事は、単に機械器具を設置するだけでなく、機械器具を組み立てて、建物や設備全体を造り上げるという点が特徴です。
多くの場合、大規模な工事となり、高度な技術力や専門知識、そして複数の専門工事業者を統括するマネジメント能力が必要となります。
・工作物に機械器具を取り付ける工事:
これは、既存の建物や設備に、特定の機能を持つ機械器具を取り付ける工事を指します。
例えば、ビルのエレベーターやエスカレーター、工場のクレーン、換気扇、空調設備(冷暖房設備は除く)、自動ドアなどが該当します。
これらの工事は、建物や設備に新たな機能を追加したり、既存の機能を向上させたりすることを目的としています。
機械器具の取り付けだけでなく、それに伴う配線工事や配管工事、試運転調整なども含まれる場合があります。
3-3. 具体的な工事例:多岐にわたる機械器具
機械器具設置工事には、以下のような工事が含まれます。
・プラント設備工事: 発電プラント、石油化学プラント、製鉄プラント、ガス製造プラント、ごみ処理プラントなど、各種プラント設備の設置工事。
これらのプラント設備は、複数の機械器具が複雑に組み合わさって構成されており、高度な技術と専門知識が必要とされます。
・運搬機器設置工事:
エレベーター、エスカレーター、リフト、ゴンドラ、クレーンなど、人や物を運搬するための機械器具の設置工事。
これらの機器は、建物や施設の安全性や利便性に大きく関わるため、確実な施工が求められます。
・内燃力発電設備工事:
ガスタービン、ディーゼルエンジンなど、内燃機関を用いた発電設備の設置工事(電気工事に該当するものを除く)。
これらの設備は、非常用電源や自家発電設備として利用されることが多く、安定した電力供給を確保するために重要な役割を果たします。
・集塵機器設置工事:
集塵機、排煙脱硫装置、排煙脱硝装置など、大気汚染物質を除去するための機械器具の設置工事。
これらの機器は、工場や発電所などから排出される有害物質を削減し、環境保護に貢献します。
・給排気機器設置工事:
換気扇、ダクト、送風機、排気筒など、空気の給排気を行うための機械器具の設置工事(管工事に該当するものを除く)。
これらの機器は、建物内の空気環境を快適に保つために重要な役割を果たします。
・揚排水機器設置工事:
ポンプ、水門、除塵機など、水やその他の液体を揚水・排水するための機械器具の設置工事。
これらの機器は、農業用水の供給、下水道の処理、洪水対策など、様々な場面で利用されます。
・ダム用仮設備工事:
ダム建設工事において、一時的に使用される仮設の設備(ケーブルクレーン、バッチャープラントなど)の設置工事。
これらの設備は、ダム建設を円滑に進めるために不可欠なものです。
・遊戯施設設置工事:
ジェットコースター、観覧車、メリーゴーラウンドなど、遊園地やレジャー施設に設置される遊戯施設の設置工事。
これらの施設は、安全性が最も重要であり、高度な技術と厳格な品質管理が求められます。
・舞台装置設置工事:
劇場やホールなどに設置される舞台の昇降装置、音響設備、照明設備などの設置工事。
これらの装置は、舞台芸術の表現を豊かにするために欠かせないものです。
サイロ設置工事: 穀物や飼料などを貯蔵するためのサイロの設置工事。これらのサイロは、食料や飼料の安定供給に貢献します。
・立体駐車場設備工事:
機械式の立体駐車場設備の設置工事。これらの設備は、限られたスペースを有効活用し、駐車場の収容台数を増やすことができます。
3-4. 他の業種との違い:専門工事との線引き
機械器具設置工事は、他の専門工事(電気工事、管工事、とび・土工・コンクリート工事など)との区別が難しい場合があります。
国土交通省のガイドラインでは、「機械器具設置工事」は、他の専門工事のいずれにも該当しない機械器具、あるいは複合的な機械器具の設置工事である、とされています。
つまり、
①電気工事:
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備など、電気工作物の設置工事は「電気工事」に該当します。
太陽光発電設備の設置工事も、原則として「電気工事」となります(ただし、屋根一体型の場合は「屋根工事」となる場合があります)。
②管工事:
冷暖房設備、空調設備、給排水・給湯設備、ガス配管設備など、配管工事を伴う設備の設置工事は「管工事」に該当します。
とび・土工・コンクリート工事: 重量物の運搬・配置、アンカー固定、コンクリート基礎の設置など、機械の設置に付随する基礎工事や準備工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
③消防施設工事:
消火設備に関する工事は、「消防施設工事」に該当します。
消火栓、スプリンクラー、火災報知機など。
④清掃施設工事:
ごみ焼却設備や、し尿処理設備に関する工事は、「清掃施設工事」に該当します。
これらの専門工事に該当しない、あるいは、これらの専門工事が複合的に組み合わさって、一つの機械器具として機能するような設備の設置工事が、「機械器具設置工事」に該当すると考えられます。
例えば、
工場の生産ライン設備は、電気配線工事(電気工事)、配管工事(管工事)、重量物の運搬・配置(とび・土工・コンクリート工事)など、様々な専門工事が組み合わさって構成されています。
しかし、これらの専門工事を総合的にマネジメントし、生産ライン全体を一つの機械器具として設置する場合は、「機械器具設置工事」に該当します。
ビルのエレベーターは、電気配線工事(電気工事)や、かごやレールの設置(とび・土工・コンクリート工事)などが必要ですが、エレベーター全体を一つの機械器具として設置する場合は、「機械器具設置工事」(運搬機器設置工事)に該当します。
機械器具設置工事に該当するかどうかの判断は、個別のケースごとに、工事の内容、機械器具の種類、設置場所、関連する工事などを総合的に考慮して行う必要があります。
判断に迷う場合は、行政(岩手県や宮城県など)や、建設業許可を専門とする行政書士に相談することをおすすめします。
4太陽光パネル設置工事の業種判断
近年、地球温暖化対策や再生可能エネルギーの普及促進などを背景に、太陽光パネルの設置工事の需要が高まっています。
しかし、太陽光パネルの設置工事は、建設業許可の業種区分において、複数の業種に該当する可能性があり、その判断は容易ではありません。
ここでは、太陽光パネルの設置工事について、設置場所や工事の内容、関連する法規制などを考慮しながら、ケース別に業種判断のポイントをさらに詳しく解説します。
4-1. 基本的な考え方:電気工事、屋根工事、とび・土工・コンクリート工事
太陽光パネルの設置工事は、主に以下の3つの業種に該当する可能性があります。
①電気工事:
太陽光パネルの設置、配線工事、パワーコンディショナー(パワコン)の設置、系統連系工事など、電気工事を伴う場合。
太陽光発電システムは、電気を生成し、電力系統に接続するため、原則として「電気工事」の許可が必要となります。
②屋根工事:
太陽光パネルを屋根に設置する場合で、太陽光パネルが屋根材としての機能を持つ場合(屋根一体型、屋根材型)。
この場合、太陽光パネルの設置は、屋根を葺く工事とみなされるため、「屋根工事」の許可が必要となります。
③とび・土工・コンクリート工事:
太陽光パネルの架台の設置工事、土地の造成工事(小規模なもの)、基礎工事など。太陽光パネルを支える架台を設置したり、土地を造成したりする場合は、「とび・土工・コンクリート工事」の許可が必要となる場合があります。
④土木一式工事:土地を造成する場合で、その規模が大きい場合
4-2. ケース1:住宅の屋根に設置(屋根置きタイプ):電気工事が中心
・工事内容: 既存の住宅の屋根の上に、金属製の架台などを設置し、その上に太陽光パネルを設置する。
・必要な許可業種:
-電気工事: 太陽光パネルの設置、配線工事、パワーコンディショナーの設置、系統連系工事など、電気工事全般。太陽光発電システムの設置工事において、最も重要な部分であり、原則として「電気工事」の許可が必要となります。
-とび・土工・コンクリート工事: 架台の設置工事。架台の構造や規模によっては、この許可が不要な場合もあります。例えば、軽量な架台で、アンカーボルトを使用しない場合などは、「とび・土工・コンクリート工事」の許可は不要と判断されることがあります。
このケースでは、「電気工事」が主たる工事となり、「とび・土工・コンクリート工事」は付帯工事となる場合が多いです。
4-3. ケース2:住宅の屋根に設置(屋根一体タイプ):屋根工事と電気工事
・工事内容: 太陽光パネル自体が屋根材としての機能を持つ(屋根一体型、屋根材型)ものを設置する。
・必要な許可業種:
-屋根工事: 太陽光パネルが屋根材を兼ねているため、太陽光パネルの設置は、屋根を葺く工事とみなされ、「屋根工事」に該当します。
-電気工事: 太陽光パネルの配線工事、パワーコンディショナーの設置、系統連系工事など。
このケースでは、「屋根工事」と「電気工事」の両方の許可が必要となる場合があります。
4-4. ケース3:野立て(地上設置):とび・土工・コンクリート工事、電気工事
・工事内容: 土地を造成し、コンクリート基礎や金属製の架台を設置して、太陽光パネルを設置する。
・必要な許可業種:
-土木一式工事: 土地の造成工事(大規模な場合)。大規模な土地の造成工事を伴う場合は、「土木一式工事」の許可が必要となります。
-とび・土工・コンクリート工事: 架台の設置工事、土地の造成工事(小規模な場合)、基礎工事。
-電気工事: 太陽光パネルの設置、配線工事、パワーコンディショナーの設置、系統連系工事など。
このケースでは、「とび・土工・コンクリート工事」と「電気工事」の両方の許可が必要となる場合が多い状況です。
また、土地の造成工事の規模によっては、「土木一式工事」の許可が必要となる場合もあります。
4-5. 複数の業種にまたがる場合:許可の取得方法
太陽光パネルの設置工事は、上記のように、複数の業種にまたがるケースが多くあります。
この場合、以下のいずれかの対応が必要です。
・それぞれの業種の許可を取得する:
例えば、「電気工事」と「とび・土工・コンクリート工事」の両方の許可を取得する。
これが最も確実な方法ですが、許可取得の手間や費用がかかります。
・主たる工事の許可を取得し、付帯工事として他の工事を行う:
例えば、「電気工事」を主たる工事とし、「とび・土工・コンクリート工事」を付帯工事として行う。
ただし、付帯工事として認められる範囲には制限があるため、注意が必要です。
建設業法では、主たる工事に付随する小規模な工事であれば、付帯工事として、許可がなくても施工できるとされています。
しかし、何をもって「小規模」とするか、明確な基準はありません。
一般的には、工事の請負金額や工事の規模、専門性などを総合的に考慮して判断されます。
・元請として工事を請け負い、それぞれの業種の許可を持つ下請業者に工事を発注する:
この場合は、元請業者自身は、必ずしも全ての業種の許可を持っている必要はありません。ただし、下請業者を選定し、工事を適切に管理する責任があります。
どの方法を選択するかは、工事の内容、自社の状況、費用などを総合的に考慮して判断する必要があります。
判断に迷う場合は、行政や建設業許可を専門とする行政書士に相談することをおすすめします。
4-6. 「電気工事」と「屋根工事」について
①「電気工事」:一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事です。
・一般用電気工作物: 一般住宅や小規模な店舗など、低圧(600V以下)で受電する電気工作物。
・自家用電気工作物: 工場やビルなど、高圧(600Vを超える)で受電する電気工作物、または、小出力発電設備
(太陽光発電設備など)を設置する電気工作物。
具体例として、
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 などがあります。
②「屋根工事」: 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です。
具体例として、屋根ふき工事 があります。
また、太陽光発電パネルの設置工事は、太陽光発電パネルを支持する部分等の屋根をふく工事は、屋根工事となりますが、太陽光発電パネルを屋根に設置する工事は、「電気工事」となります。
5まとめ
機械の設置工事や太陽光パネルの設置工事は、建設業許可の業種判断において、特に注意が必要な工事です。
これらの工事は、複数の業種に該当する可能性があり、工事の内容や規模、設置場所などによって、必要な許可が異なります。
今回の記事で解説した内容を参考に、工事名だけでなく、工事の「内容」をしっかりと確認し、適切な業種の許可を取得・更新しましょう。
「機械器具設置工事」「とび・土工・コンクリート工事」「電気工事」「屋根工事」などの違いを理解し、自社の工事がどの業種に該当するのかを正確に判断することが重要です。
「自社の工事はどの業種に該当する?」「複数の業種が含まれる場合はどうすれば?」など、業種判断に関する疑問や不安があれば、専門家である行政書士にご相談ください。
建設業許可の取得・更新は、事業の発展に欠かせない重要な手続きです。
しかし、法改正や制度の複雑さから、「難しそう…」「面倒…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
行政書士藤井等事務所は、建設業許可の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」「どの業種に該当するか分からない」という相談だけでも構いません。
建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ<許認可申請>


.jpg)