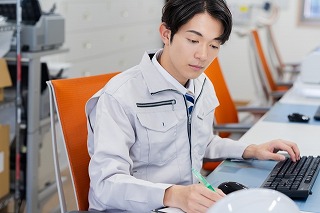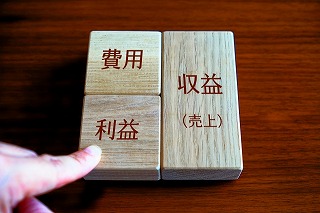
「建設業許可の更新時期が近づいてきたけど、手続きが複雑で何から手をつければいいか分からない…」
「公共工事の入札に参加したいけれど、経営事項審査(経審)の評点が上がるか不安だ…」
「毎年の財務諸表作成、これで本当に建設業法や経審の基準を満たせているのだろうか?」
こんなお悩みや疑問を抱えていらっしゃいませんか?
ご安心ください。
そのお悩み、この記事をしっかりお読みいただくことで、解決への道筋が見えてきます。
今回の記事では、建設業許可の取得・維持、そして経審での高評価獲得に不可欠な「建設業財務諸表」、特にその中でも重要な「損益計算書」と「完成工事原価報告書」の作成における4つの肝となるポイントを、具体例を交えながら分かりやすくご紹介します。
この記事が、皆様のお困りごとを解決する一助となれば幸いです。
建設業を営む上で、建設業許可の取得・維持は事業継続の生命線であり、公共工事への参入を目指す企業にとっては経営事項審査(経審)での高評価獲得が極めて重要です。
これらの手続きにおいて、正確かつ法令に準拠した「建設業財務諸表」の作成は、避けて通れない、そして最も神経を使う部分の一つと言えるでしょう。
特に、損益計算書や完成工事原価報告書は、企業の経営実態を映し出す鏡であり、審査機関が重視するポイントが数多く潜んでいます。
本記事では、これらの書類作成における重要な「4つの肝」を深掘りし、皆様がスムーズに手続きを進められるよう、具体的な注意点や国土交通省の指導方針などを踏まえて徹底解説いたします。
1最重要ポイント!人件費
建設業財務諸表、特に損益計算書や完成工事原価報告書を作成する上で、最初にして最大の関門とも言えるのが「人件費」の取り扱いです。
人件費と一口に言っても、その性質や関わる業務内容によって、計上すべき勘定科目が異なります。
この区分を誤ると、企業の収益構造を正確に把握できないだけでなく、経審の評価においても不利益を被る可能性があります。
まずは、建設業財務諸表に出てくる主な人件費の区分を整理し、それぞれの具体的な計上方法について見ていきましょう。
1-1.人件費の4つの顔
建設業の財務諸表には、主に以下の四つの区分で人件費に関連する費用が登場します。
① 販売費及び一般管理費(販管費)内の「従業員給料手当」
② 完成工事原価報告書内の「労務費」
③ 完成工事原価報告書内の「経費のうち人件費」
④ 兼業事業売上原価報告書内の「兼業原価の労務費」(兼業事業がある場合)
これらの区分を正しく理解することが、適切な財務諸表作成の第一歩です。
1-2. 大原則
建設業財務諸表における人件費の基本的な考え方は、その従業員が「建設工事に直接関与しているか否か」で大きく分類されます。
⑴工事に直接関与しない従業員の人件費
工事現場での作業には直接従事しないものの、会社運営に不可欠な従業員の給与などが該当します。
この区分はさらに、その業務内容によって細分化されます。
①本社・支店等での内勤業務に従事する従業員の給与
これは、主に販売費及び一般管理費の「従業員給料手当」として計上されます。
具体的な例を挙げると、本社の総務部、経理部、人事部、営業部などで働く事務スタッフや管理部門の従業員の給与、諸手当、賞与などがこれに該当します。
彼らは建設工事の現場作業には直接タッチしませんが、会社全体の運営や営業活動を支える重要な役割を担っています。
国土交通省の「建設業財務諸表の作成の手引き」においても、工事施工に直接関わらない本社、支店、営業所等の従業員の給与手当は販管費として処理するよう明記されています。
②建設工事以外の事業(兼業事業)に従事する従業員の労務費
建設業者が建設工事以外の事業、例えば不動産賃貸業、物品販売業、保守点検サービス業などを兼業している場合、その兼業事業に専ら従事する従業員の人件費は、「兼業事業売上原価報告書」の「兼業原価の労務費」として計上します。
具体的なイメージとしては、建設工事とは別に、ビルメンテナンス契約に基づく定期的な保守点検業務や清掃業務、管理業務を専門に行っている従業員の給与や作業手当が挙げられます。
建設工事に係る人件費と明確に区分することが重要です。この区分が曖昧だと、建設事業本体の原価計算が不正確になり、経審における完成工事高や利益率の評価にも影響が出かねません。
⑵工事に直接関与する従業員の人件費
ここが建設業特有の費用の捉え方であり、特に注意が必要です。
工事に直接関わる従業員の人件費も、その職務内容や雇用形態によって、計上科目が変わってきます。
①工事部門の技術職員・事務職員等の給与(現場管理等)
これは、完成工事原価報告書の「経費のうち人件費」に計上されます。
具体的なイメージとしては、工事現場の施工管理を行う主任技術者や監理技術者、現場事務所で働く事務員、積算業務や資材調達、測量などを担当する技術職員など、いわゆる「現場監督」や「現場スタッフ」の給料、諸手当、賞与が該当します。
重要なのは、彼らが自社の正規従業員(正社員や契約社員など、継続的な雇用関係にあり、社会保険の被保険者となっている者)であるという点です。
彼らは直接的な肉体労働(作業)を行うわけではありませんが、工事の品質管理、工程管理、安全管理、原価管理といった重要な業務を担っており、その人件費は工事原価の「経費」として扱われます。
②工事現場の作業員の賃金(直接作業)
これは、完成工事原価報告書の「労務費」に計上されます。
具体的なイメージとしては、建設工事現場で実際に建設作業に従事する職人さんや作業員の方々に支払われる賃金です。
特に、日雇い労働者や期間契約の作業員、アルバイトなど、主に現場での直接的な作業を目的として雇用される人々の賃金、手間賃、日当などがここに分類されます。
自社で直接雇用している作業員だけでなく、一人親方であっても実質的に自社の指揮命令下で作業に従事し、その対価が時間や日数ベースで支払われる場合も、この労務費に含めるケースがあります。
ただし、請負契約に基づく外注の場合は「外注費」となるため、契約形態の確認が不可欠です。
この人件費の適切な区分は、正確な原価計算の基礎であり、経審における技術力評価(完成工事高に対する技術職員数など)や労働福祉の状況(Z点の一部)にも間接的に影響を与えるため、細心の注意を払う必要があります。
不明な点があれば、建設業専門の行政書士に確認することをお勧めします。
2「完成工事原価報告書」核心的ポイント
完成工事原価報告書は、建設業者がその会計期間中に完成させた工事について、どれだけの費用がかかったかを詳細に示す書類です。
経審においては、企業の収益性や生産性を分析する上で極めて重要な資料となります。
ここでの計上ミスや計上漏れは、評点に直接的な悪影響を及ぼす可能性があります。
2-1. 完成工事原価報告書の基本構成
まず、完成工事原価報告書の主要な項目構成を再確認しましょう。
⑴ Ⅰ 材料費:工事のために購入した資材や部品の費用
⑵ Ⅱ 労務費:前述の通り、現場作業員の賃金
⑶ (うち労務外注費):労務費のうち、実質的に外注(手間請けなど)に該当する部分を内数で記載
⑷ Ⅲ 外注費:他の業者に工事の一部または全部を請け負わせた場合の費用
⑸ Ⅳ 経費:上記①~③以外で工事遂行に必要な諸費用(機械器具のリース料、水道光熱費、設計費、そして後述する重要な「人件費」など)
⑹ (うち人件費):経費のうち、前述の現場技術職員や現場事務員の給与など
2-2. 「経費のうち人件費」ゼロ計上は原則NG!
完成工事原価報告書の項目の中で、特に⑹の「(経費の)うち人件費」の取り扱いは極めて重要です。
原則として、この欄がゼロ(0円)であってはなりません。
その理由は、建設業法第26条に明確に規定されています。
建設業法では、建設業者は請け負った建設工事を施工する際、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、必ず「主任技術者」または「監理技術者」を配置しなければならないと義務付けています。
これは、工事の規模の大小、元請・下請の別、請負金額の多寡にかかわらず、全ての建設工事に適用される絶対的なルールです。
主任技術者や監理技術者は、通常、その会社の正規の技術職員が務めます。
したがって、彼らに支払われる給与は、完成工事原価報告書の「経費のうち人件費」として計上されるべきものなのです。
もしこの欄がゼロであれば、審査機関は「この会社は工事現場に法律で義務付けられた技術者を配置していないのではないか?」という疑念を抱きます。
これは建設業法違反を疑わせる状況であり、最悪の場合、許可行政庁による調査や指導、さらには営業停止処分といった厳しい行政処分につながる可能性すらあります。
2-3. 「社長一人」の建設会社における例外
ただし、例外的なケースも存在します。
それは、いわゆる「一人親方」から法人成りしたような、実質的に社長一人のみで会社を運営している小規模な建設会社の場合です。
社長自身が現場の技術者であり、かつ経営業務の管理責任者も兼ねているようなケースです。
この場合、社長に支払われる報酬は「役員報酬」として、販管費または一般管理費に計上されるため、完成工事原価報告書の「経費のうち人件費」に従業員としての給与を計上することができません。
このような特別な事情がある場合は、同欄がゼロであっても直ちに建設業法違反とは断定されません。
しかし、その理由を明確に説明できるようにしておく必要があります。
例えば、株主総会議事録や取締役会議事録で役員報酬の決定根拠を示し、社長が技術者資格を有していることを証明する書類(資格者証の写しなど)を整理しておくことが望ましいでしょう。
経審の際には、これらの状況を審査員に口頭で説明したり、補足資料として提出したりする準備も有効です。
2-4. 労務費ゼロや外注費偏重も危険信号!一括下請負(丸投げ)の疑い
「経費のうち人件費」だけでなく、⑵の「労務費」が全く計上されていない、あるいは極端に少ない場合も問題視されることがあります。
自社で雇用している現場作業員が一人もいない、ということになり、事業の実態として不自然と見なされる可能性があります。
さらに注意が必要なのは、⑷の「外注費」の割合が極端に高いケースです。
特に、材料費や労務費、経費(うち人件費を含む)の計上がほとんどなく、完成工事原価の大部分が外注費で占められているような財務諸表は、「一括下請負(工事の丸投げ)」を行っているのではないかという強い疑念を招きます。
建設業法第22条では、原則として一括下請負を禁止しています(発注者の書面による承諾がある場合など、一定の例外を除く)。
これは、建設工事の責任体制の不明確化や施工品質の低下、中間搾取による下請業者へのしわ寄せなどを防ぐための重要な規定です。
もし一括下請負が常態化していると判断されれば、これもまた建設業法違反として、営業停止処分や許可取消といった非常に重い行政処分の対象となります。
2-5. 税務申告と建設業財務諸表の「目的」の違いを認識する
税務署に提出する法人税申告書等に添付する決算報告書と、建設業許可行政庁や経審の審査機関に提出する建設業財務諸表は、その作成目的が根本的に異なります。
税務申告の最終目的は、あくまで「正確な課税所得を算出し、適正な法人税額等を納付すること」にあります。
そのため、費用の勘定科目区分については、税法上の損金算入が認められる範囲であれば、ある程度の集約や簡略化が許容される側面があります。
一方、建設業財務諸表は、国土交通省(または都道府県知事)に対して、その建設業者の経営状況や施工能力、法令遵守状況などを報告し、建設業許可の維持や公共工事の入札参加資格を得るためのものです。
そのため、建設業法や関連通達、国土交通省のガイドラインに沿った、より詳細で厳格な科目分類と計上が求められます。
この「目的の違い」を理解せず、税務署提出用の決算書をそのまま流用すると、思わぬ指摘を受けたり、経審で不利な評価を受けたりする可能性があるため、十分な注意が必要です。
3役員報酬と法定福利費の計上は絶対条件
建設業許可を維持し、企業として健全な経営を行っていることを示す上で、役員報酬と法定福利費の適切な計上は、もはや「任意」ではなく「絶対条件」と言っても過言ではありません。
これらの計上漏れや不備は、許可の更新時に重大な問題となる可能性があります。
3-1. 役員報酬
建設業許可の要件の一つに、「経営業務の管理責任者(経管)」を常勤役員等の中から置くことが定められています。
この「常勤役員等」とは、原則として法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は事業主本人または登記された支配人を指します。
「常勤」であることの証明の一つとして、適切な役員報酬が支払われていることが挙げられます。
もし、経管としての職務を担うべき役員に対して、役員報酬が支払われておらず、代わりに「従業員給料」として処理されていたり、あるいは極端に低い役員報酬しか支払われていなかったりする場合、「本当に常勤として経営業務に専従しているのか?」という疑義が生じます。
これは、建設業法で求められる経管の常勤性の要件を満たしていないと判断され、最悪の場合、許可の更新が認められないリスクに繋がります。
したがって、経管たる役員には、その職責に見合った役員報酬を株主総会等で適正に決定し、毎月定額で支払い、それを「役員報酬」として明確に会計処理することが不可欠です。
3-2. 法定福利費(社会保険の義務)
法定福利費とは、法律で事業者に負担が義務付けられている社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料など)の事業主負担分を指します。
近年、建設業界においても、社会保険への適正な加入が強く求められています。
建設業法の改正等により、社会保険への加入は建設業許可の要件としても位置づけられており、未加入の企業に対しては許可行政庁からの指導が強化されています。
具体的には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が原則として義務付けられています(適用除外に該当する場合を除く)。
これらの保険に加入していれば、当然ながら法定福利費が発生し、損益計算書の販管費や完成工事原価報告書の経費に計上されていなければなりません。
もし法定福利費の計上がない、あるいは極端に少ない場合、社会保険への未加入を疑われ、許可の更新が難しくなるだけでなく、経審においても「労働福祉の状況(Z点)」で大幅な減点対象となります。
国土交通省は、建設業界における担い手確保や若年層の入職促進のためにも、社会保険加入の徹底を推進しています。
法定福利費の適切な計上は、法令遵守はもちろんのこと、企業の社会的責任を果たす上でも非常に重要です。
4損益計算書の「10%ルール」とは?
損益計算書を作成する際には、費用の表示方法に関する一定のルールがあります。
その一つが、通称「10%ルール」と呼ばれるものです。
これは、財務諸表の透明性を高め、利害関係者が企業の経営実態をより正確に把握できるようにするための重要な会計原則です。
4-1. 10%ルールの具体的な内容
損益計算書の10%ルールとは、販売費及び一般管理費(販管費)や営業外費用、特別損失などの各費用の区分において、その総額の10%を超える金額の勘定科目については、「雑費」や「その他経費」といった包括的な名称で一括りにせず、その具体的な内容を示す固有の名称(例えば「広告宣伝費」「支払手数料」「賃借料」など)で個別に表示しなければならない、というルールです。
例えば、販管費の総額が1,000万円だった場合、その10%である100万円を超える費目については、「地代家賃 150万円」「減価償却費 120万円」のように、独立した科目として明示する必要があります。
「雑費 200万円」といった表示は、その内容が不明瞭であるため認められにくくなります。
4-2. 10%ルールの趣旨と建設業における重要性
このルールの趣旨は、財務諸表の利用者が、企業の費用構造をより詳細に理解できるようにすることにあります。
多額の費用が「雑費」などの曖昧な科目で処理されていると、その企業が何にどれだけのコストをかけているのかが不透明になり、適切な経営分析や投資判断が困難になります。
建設業においては、許可行政庁や経審の審査機関が、この10%ルールに基づいて財務諸表の適正性をチェックします。
特に経審では、企業の収益性や効率性を分析するために、販管費の内容が重視されます。
10%ルールを遵守し、費用の内容を明瞭に開示することは、審査機関に対して誠実な経営姿勢を示すことにもつながり、結果として円滑な審査や適正な評価に結びつく可能性があります。
逆に、このルールを無視した財務諸表は、内容の信頼性を疑われ、説明を求められたり、補正を指示されたりすることもあるため、注意が必要です。
建設業財務諸表の作成は、単なる数字の集計作業ではありません。
建設業法や関連法令、会計基準を深く理解し、自社の経営実態を正確かつ適切に反映させることが求められる専門的な業務です。
これらのポイントを押さえ、細心の注意を払って作成することが、建設業許可の維持、そして事業の更なる発展への礎となるのです。
5まとめ
建設業許可申請や経営事項審査(経審)は、特に公共工事の元請業者としての立場を目指す、あるいは維持する事業者にとって、絶対に欠かせない極めて重要な手続きです。
これらは、企業の信頼性や技術力を公的に証明し、事業展開の幅を大きく広げる可能性を秘めています。
しかしながら、その制度の煩雑さ・複雑さ、そして毎年のように行われる細かな改正から、「何から手をつければ良いのか分からない…」「書類作成が難解で、時間ばかりかかってしまう…」「これで本当に許可が取れるのか、経審で良い点が取れるのか不安だ…」と感じていらっしゃる経営者様やご担当者様も決して少なくないのではないでしょうか。
確かに、建設業法や会計基準、国土交通省の通達などを読み解き、正確な申請書類一式を自社だけで作成するには、多大な時間と労力、そして専門的な知識が要求されます。
当事務所は、岩手県内を中心に全国の建設業者様をサポートする、建設業許可申請および経営事項審査(経審)手続きの専門家です。
長年にわたり培ってきた豊富な経験と最新の法令知識に基づき、お客様一人ひとりの状況やご要望を丁寧にお伺いし、それぞれに合わせた最適なサポートプランをご提案いたします。
新規許可取得から更新手続き、業種追加、そして経審の評点アップ戦略まで、あらゆるニーズに全力でお応えします。
法律の規定や申請手続きは、一見すると非常に複雑で分かりにくいものです。
ご自身で貴重な時間を割いて調査・検討されるよりも、専門家である行政書士にご相談いただく方が、結果として迅速かつ確実、そして安心に繋がるケースがほとんどです。
時間的コスト、精神的コストを大幅に削減し、本業である建設業務に専念できる環境づくりをお手伝いします。
「とりあえず、自社が許可を取得できる可能性があるのかどうかだけでも知りたい」「経審の評点がどのくらいになるのか、概算でもいいから教えてほしい」といった初期段階でのご相談も、もちろん大歓迎です。
当事務所の最大の強みは、単独の行政書士事務所としての専門性に加え、他士業との強固な連携体制を構築している点にあります。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーといった各分野の専門家と『士業の会』を主宰しており、お客様が抱える建設業許可や経審にとどまらない、法務・税務・労務・不動産など、多種多様かつ複合的な問題に対しても、ワンストップで、かつ迅速に解決策をご提案できる体制を整えております。
さらに、当方は、元岩手県職員としての行政実務経験(企業誘致、岩手県立大学の新規設置)を有しております。
この経験から、国や都道府県、市町村といった行政機関の考え方や手続きの進め方を熟知しており、各種申請や折衝・調整業務において、他の事務所にはないスムーズかつ的確な対応ができるという「強み」を持っています。
この「行政との調整力」は、特に許認可申請において大きなアドバンテージとなります。
岩手県内はもちろん、全国の建設業者様で、建設業許可の新規取得や更新、経営事項審査(経審)の申請をご検討されていらっしゃるのであれば、どうぞお気軽に、当事務所までご相談ください。
お客様の事業の発展を、全力でサポートさせていただきます。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>
https://office-fujiihitoshi.com/