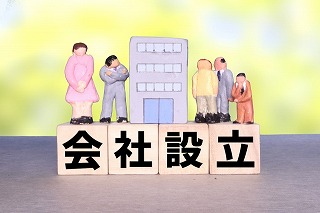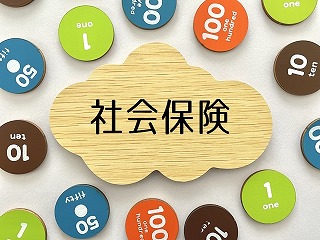
「医療法人設立を考えているけど、手続きが複雑で…」
「個人開業医だけど、医師国保は継続できる?」
「医療法人化すると、税金や社会保険はどうなるの?」
「医療法人の設立認可申請や、保健所への手続きは、自分だけでできるの?」
こんなお悩みはありませんか?
医療法人設立には、多くのメリットがある一方で、手続きが煩雑で、専門的な知識も必要です。
特に、社会保険の手続きや、行政機関への許認可申請・届出は、複雑で、時間も手間もかかります。
さらに、設立後の運営についても、個人開業医とは異なる点が多く、注意が必要です。
ご安心ください!
今回の記事では、医療法人設立のメリット・デメリット、社会保険の手続き、行政機関への許認可申請・届出、設立後の注意点などを、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、医療法人設立に関する疑問が解消され、スムーズな設立・運営のための準備ができます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)で、医療法人設立を検討されている医師・歯科医師・医療事務職員の皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1医療法人とは?(個人開業医との違い)
医療法人とは、医療法に基づいて設立される法人です。
病院、医師または歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設などを開設することを目的として設立されます。
個人開業医との主な違いは、以下の点です。
(1)法人格の有無:
個人開業医は、個人事業主として事業を行いますが、医療法人は、法人格を持つため、法人として契約や財産所有などができます。
(2)事業の継続性:
個人開業医は、院長が引退したり、亡くなったりした場合、診療所は廃止となりますが、医療法人は、理事長が交代しても、法人として存続し、事業を継続できます。
(3)社会保険:
個人開業医は、常勤職員が5人未満の場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務はありませんが、医療法人は、常勤職員が1人でもいる場合、社会保険の加入義務があります。
(4)税金:
個人開業医は、所得税が課税されますが、医療法人は、法人税が課税されます。所得によっては、法人税の方が税率が低くなる場合があります。
(5)融資:
個人開業医よりも、医療法人のほうが、一般的に金融機関からの融資を受けやすいと言われています。
2医療法人設立のメリット・デメリット
医療法人設立には、多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。
設立を検討する際は、両方を比較検討し、慎重に判断する必要があります。
2-1. メリット
(1)節税効果:
所得によっては、法人税の方が所得税よりも税率が低くなるため、節税効果が期待できます。
また、理事長や家族への給与支払いが可能となり、所得分散による節税も可能です。
(2)事業承継の円滑化:
医療法人は、法人格を持つため、事業承継がスムーズに行えます。
後継者に、医療法人の出資持分を贈与または譲渡することで、事業承継が可能です。
(3)社会的信用度の向上:
医療法人化することで、金融機関からの融資が受けやすくなったり、優秀な人材を確保しやすくなったりするなど、社会的信用度が向上します。
(4)分院展開が可能:
医療法人は、分院(分院)を開設することができます。
(5)介護事業への参入が容易:
医療法人は、介護老人保健施設や訪問看護ステーションなど、介護事業を運営することができます。
2-2. デメリット
(1)設立手続きが煩雑:
医療法人設立には、都道府県知事(または地方厚生局長)の認可が必要であり、多くの書類作成や手続きが必要です。
(2)運営コストの増加:
社会保険料の負担が増加する、税理士報酬などの費用が発生するなど、運営コストが増加します。
(3)会計処理が複雑:
法人会計のルールに従って会計処理を行う必要があり、個人開業医よりも会計処理が複雑になります。
(4)剰余金の配当禁止:
医療法人は、剰余金の配当が禁止されています。利益は、医療法人の運営や設備投資などに充てる必要があります。
(5)解散手続きが煩雑:
医療法人を解散する際も、多くの手続きが必要です。
役員変更の際、その都度、都道府県知事(または地方厚生局長)への届出が必要
3医療法人設立後の社会保険
医療法人設立後、社会保険の手続きは、大きな変更点の一つです。
特に、医師国保に加入している場合は、注意が必要です。
3-1. 社会保険加入義務
個人開業医の場合、常勤職員が5人未満であれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務はありません。
しかし、医療法人になると、常勤職員が1人でもいる場合、社会保険の加入義務が発生します。
ここでいう常勤職員とは、正職員だけでなく、正職員の勤務時間の4分の3以上を勤務しているパート職員も含まれます。
3-2. 健康保険の選択肢
医療法人設立後の健康保険は、以下の4つのパターンが考えられます。
(1)協会けんぽ + 厚生年金保険:
これが原則的な組み合わせです。
(2)医師国保(継続)+ 厚生年金保険:
個人開業医の時から医師国保に加入している場合に限り、例外的に認められます。
(3)歯科医師国保(継続) + 厚生年金保険:
個人開業医の時から歯科医師国保に加入している場合に限り、例外的に認められます。
(4)その他の健康保険組合 + 厚生年金保険:
一部の業種では、独自の健康保険組合を持っている場合があります。
3-3. 医師国保継続の注意点「14日ルール」
個人開業医の時から医師国保に加入している場合、医療法人設立後も、引き続き医師国保に加入することができます。
このためには、原則として、医療法人設立後(診療所開設許可日から)「14日以内」に、年金事務所で「健康保険被保険者適用除外承認申請」の手続きを行う必要があります。
この「14日ルール」を過ぎてしまうと、原則として医師国保の継続加入は認められず、協会けんぽに加入することになります。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、14日を過ぎても認められる場合がありますので、年金事務所に相談しましょう。
3-4. 医師国保と協会けんぽ
(1)協会けんぽ:
保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に、保険料率を掛けて計算します。
標準報酬月額は、基本給だけでなく、各種手当、残業手当、交通費なども含めた金額で決まります。
保険料は、事業主と従業員で折半します。
賞与にも保険料がかかります。
(2)医師国保:
保険料は、加入する組合員の種別(医師、看護師など)や、家族の人数などによって決まります。
一般的に、所得が高い医師や、単身者の場合は、医師国保の方が保険料が安くなる傾向があります。
事業主は、保険料を負担する義務はありません(ただし、負担することも可能です)。
賞与に対する保険料負担はありません。
3-5. 医師国保の自家診療制限
医師国保に加入している場合、保険に加入している職員や家族を診察することは、自家診療となり、保険請求ができません。
一方、協会けんぽの場合は、自家診療の制限はありません。
4医療法人設立の手続き
医療法人設立の手続きは、大きく分けて以下の5つのステップで進められます。
4-1. 事前準備
(1)設立する医療法人の種類を決定する:
社団医療法人(出資持分あり・なし)、財団医療法人など、どの種類の医療法人を設立するかを決定します。
(2)定款・寄附行為の作成:
医療法人の根本規則である定款または寄附行為を作成します。
(3)設立総会の開催:
設立総会を開催し、定款・寄附行為の承認、役員の選任、事業計画の承認などを行います。
・設立趣意書の作成
・財産目録の作成
・役員名簿、履歴書の作成
・開設する診療所の賃貸借契約書の写しの作成
4-2. 設立認可申請(都道府県知事または地方厚生局長)
都道府県知事(または地方厚生局長)に、医療法人設立認可申請を行います。
申請には、多くの書類が必要であり、審査にも時間がかかります(通常、数ヶ月程度)。
申請窓口は、開設する医療機関(病院・診療所)の所在地を管轄する都道府県庁(または地方厚生局)になります。
4-2-1 主な必要書類
・医療法人設立認可申請書
・定款または寄附行為
・設立総会議事録
・財産目録
・事業計画書
・役員名簿、履歴書
・開設する診療所の賃貸借契約書の写し
・その他、都道府県(または地方厚生局)が必要と認める書類
4-3. 設立登記
設立認可後、法務局で医療法人設立登記を行います。
登記が完了することで、医療法人が正式に成立します。
4-4. 診療所開設許可申請・届出(保健所)
新たに診療所を開設する場合は、保健所に診療所開設許可申請を行います。
既に個人開業医として診療所を開設している場合は、診療所開設届(個人から法人への名義変更)を提出します。
4-5. 保険医療機関指定申請(地方厚生局)
保険診療を行うためには、地方厚生局に保険医療機関指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
5医療法人設立後の注意点
医療法人設立後も、様々な手続きや注意点があります。
5-1. 社会保険・労働保険の手続き
(1)社会保険:
医療法人設立後、速やかに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続きを行う必要があります。
(2)労働保険:
従業員を雇用する場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きも必要です。
5-2. 税務署への届出
(1)法人設立届出書:
法人設立後、税務署に法人設立届出書を提出する必要があります。
(2)青色申告の承認申請書:
青色申告を行う場合は、青色申告の承認申請書を提出する必要があります。
(3)給与支払事務所等の開設届出書:
従業員に給与を支払う場合は、給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があります。
5-3. 役員変更の届出
理事長や理事などの役員に変更があった場合は、都道府県知事(または地方厚生局長)に役員変更届を提出する必要があります。
5-4. 定款・寄附行為の変更
定款または寄附行為に変更があった場合は、都道府県知事(または地方厚生局長)の認可を受ける必要があります。
6まとめ
医療法人設立は、多くのメリットがある一方で、手続きが煩雑で、専門的な知識も必要です。
また、設立後の運営についても、個人開業医とは異なる点が多く、注意が必要です。
「何から手を付けていいか分からない」「手続きが複雑で面倒」「専門的なアドバイスが欲しい」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
行政書士は、医療法人設立に関する専門知識を持ち、必要書類の作成、行政機関への申請・届出など、設立手続きをトータルでサポートすることができます。
また、設立後の運営に関する相談や、各種変更手続きの代行も可能です。
当事務所では、医療法人設立に関するご相談を幅広く承っており、お客様の状況に合わせて、最善の解決策をご提案いたします。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や都道府県といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。
医療法人について、何から手を付けていいか分からない、専門的なアドバイスが欲しいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします。
この記事を読んで、少しでも医療法人設立について考えるきっかけになれば幸いです。
<注意事項>
①厚生労働省(地方厚生局)や都道府県、各保健所への申請は、行政書士が、唯一行政機関への申請が認められている国家資格者です。
②行政書士以外の者(医療コンサルタントなど)が、他人の依頼を受けて、必要な申請などを代理することは、法律で禁止されています。
③行政書士以外の者が、違法な申請代理をした場合は「罰則」が適用されるので、十分注意すること。
7お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ