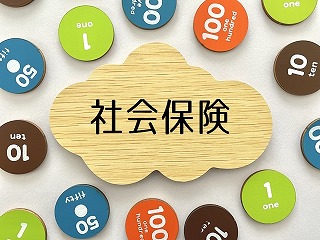「医療法人化を進めたいが、高額な医療機器のリースはどうなる?」
「MS法人からのリースが、設立の妨げにならないか不安だ…」
「ただでさえ多忙なのに、リース会社や行政との複雑な手続きまで手が回らない」
こんな悩みはありませんか?
その悩み、本記事で解決できます。
医療法人設立時のリース資産引継ぎは、特にMS法人が絡む場合、行政の厳しい審査が入る最重要ポイントです。
今回は、東北(岩手・宮城)で法人化を目指す先生方へ、リース引継ぎの難関と、それをクリアする具体的なテクニックを紹介します。
1 医療法人化と「リース資産引継ぎ」というハードル
個人開業医(クリニック・診療所)として経営が軌道に乗ると、多くの先生方が節税対策や事業承継、分院展開を見据えて「医療法人化(法人成り)」を検討されます。
しかし、医療法人の設立は、単に登記をすれば完了というわけではありません。
都道府県(岩手県や宮城県など、窓口は保健所等)の厳格な審査と「認可」が必要不可欠です。
この認可手続きの中で、特に多くの先生方が頭を悩ませ、行政側も厳しく目を光らせるポイントが、個人開業時代に使用していた資産・負債の引継ぎです。
なかでも、高額な医療機器(CT、MRI、ユニットチェアなど)で利用される「リース資産の引継ぎ」は、手続きが非常に煩雑であり、もし引継ぎの設計を誤ると「設立認可が下りない」という最悪の事態にも陥りかねない、重大なハードルとなります。
1-1. なぜリース資産の引継ぎが厳しく審査されるのか?
医療法人は、その公益性・非営利性の観点から、株式会社などの一般企業とは比較にならないほど厳格な規制の下に置かれています。
行政(都道府県)が最も懸念するのは、「医療法人の財産が不当に流出すること」そして「理事長やその親族が、法人を私物化すること(利益相反)」です。
リース資産の引継ぎは、まさにこの「資産と負債の移転」そのものです。
そのため、行政は「設立される医療法人が、不当に高額なリース料を支払う契約になっていないか?」「実態のないリース契約で、特定の個人(MS法人など)に利益を移転させる仕組みになっていないか?」を徹底的に審査するのです。
2 【パターン別】リース引継ぎを突破する4つの重要ポイント
リースの引継ぎは、相手が誰かによって難易度が激変します。
ここでは、一般的なリース会社の場合と、最も問題となりやすい「MS法人」の場合に分け、行政の審査をクリアするための4つの重要ポイントを徹底解説します。
2-1. ポイント1:一般的なリース会社からの引継ぎ
ファイナンスリース会社(医療機器専門のリース会社など)から個人名義でリースしている機器を、新設する医療法人へ引き継ぐパターンです。
2-1-1. 必要書類と手続きの流れ
このケースは、引継ぎの相手が客観的な第三者であるため、行政側も比較的スムーズに認めてくれる傾向にあります。
ただし、スムーズに進むといっても、以下の書類を正確に揃えることが大前提です。
⑴ リース契約書(写し): 現在の契約内容の証明
⑵ 支払予定表(リース料残高一覧): 引き継ぐ負債額の証明
⑶ リース会社の引継承諾書(内諾書): 第三者(リース会社)が、名義変更を認めている証明
特に注意すべきは、個人事業の会計処理で「リース資産」として固定資産台帳に計上している場合です。
この場合は、上記の書類に加え、
⑷ 固定資産台帳(写し)
⑸ リース料の未払金残高が確認できる書類(試算表など)
といった追加資料を求められるケースが増加します。
これは、法人が引き継ぐ「資産(リース資産)」と「負債(未払金)」の額を、客観的な会計資料で正確に証明するためです。
2-1-2. 将来を見据えるなら「医療専門リース会社」が鉄則
一般的なリース会社であっても、法人成りに伴う名義変更手続きは煩雑なものです。
銀行などと同様、書類の発行に時間がかかるケースも少なくありません。
もし、これから機器の導入を検討しており、将来的な法人化も視野に入れているのであれば、最初から医療機関の法人成りに強いリース会社を選ぶことが、将来の自分を助ける最善の策となります。
医療専門のリース会社であれば、法人成り時の手続きを熟知しており、行政へ提出する書類の準備も非常に迅速です。
2-2. ポイント2:MS法人からのリース引継ぎ(最重要関門)
今回の最大の難関が、先生ご自身やご親族が経営する「MS法人(メディカル・サービス法人)」から、医療機器等をリースしているパターンです。
これは、行政から「利益相反取引」の典型例として、最も厳しく審査されるケースです。
2-2-1. なぜMS法人からの引継ぎは厳しく審査されるのか?
MS法人は営利企業、医療法人は非営利法人です。
この二つの法人の間で、理事長(先生)が双方の役員を兼務していると、「医療法人の利益を犠牲にして、MS法人に不当な利益を移転させる」ことが可能になってしまいます。
例えば、市場価格より遥かに高額なリース料をMS法人に支払わせることで、医療法人の利益を圧縮し、MS法人(=個人の資産管理会社)にお金を還流させることができてしまいます。
これを防ぐため、行政はMS法人との取引に「待った」をかけるのです。
2-2-2. 対策:役員の兼務は「設立前」に解消する
まず、設立認可申請の前提として、MS法人と新設医療法人の役員兼務は、原則として解消しておく必要があります。(兼務の解消を強く指導されるのが一般的)
行政は、MS法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出を求め、役員構成を厳しくチェックします。
「設立後に解消する予定」といった言い分は通用しません。
審査の段階で、利益相反のリスクが排除されている体制を構築しておくことが必須です。
2-3. ポイント3:「リース料率」の適正な算定根拠の提示
MS法人からの引継ぎで、役員兼務の次に問題となるのが「リース料の算定根拠」です。
2-3-1. 利益移転を疑われないための設定
前述の通り、恣意的に決められたリース料は絶対に認められません。
リース料が「第三者間取引における適正な市場価格」であることを、客観的な根拠をもって証明する必要があります。
一般的にリース料は、MS法人が購入した資産の取得価額に、一定の「リース料率」を乗じて計算します。
注意したいのは、この「リース料率」は、銀行の「金利(年利)」とは全く異なる概念であるという点です。
リース料率には、金利の他に、固定資産税、保険料、リース会社の利益(手数料)などが含まれます。
2-3-2. 参考にすべき公的な基準
では、適正なリース料率はどう設定すればよいのでしょうか。
一つの客観的な基準として、中小企業庁(または関連団体)の「小規模企業設備貸与制度(設備貸与事業)」におけるリース料率などが参考になります。
これらの公的な制度の料率を参考に、リース期間(耐用年数)などに応じて適正な料率を設定し、「このリース料は、不当に高額なものではなく、公的基準に準拠した適正なものである」と行政に説明できる資料を準備することが不可欠です。
2-4. ポイント4:契約書の透明性の確保
MS法人とのリース契約において、行政は契約書の中身も精査します。
口約束はもちろん、当事者間で作成した簡素な契約書一枚だけでは、「実態のある適正な取引である」という証明には不十分と判断される可能性が極めて高いです。
県(保健所)によっては、
⑴ リース契約約款
⑵ 詳細な支払予定表
⑶ 対象機器の購入時の見積書・請求書(取得価額の証明)
といった、リース取引の透明性を担保する詳細な資料一式を求められます。
これは、その取引が名目だけの架空取引ではなく、医療法人側に不当に不利な条件(高額な違約金や中途解約不可など)が隠されていないかを審査するためです。
3 複雑なリース引継ぎを専門家に任せるメリット
ここまでご覧いただいた通り、医療法人の設立、特にリース引継ぎが絡む手続きは、先生ご自身が診療の傍らで対応するには、あまりにも専門的かつ煩雑です。
3-1. 行政との事前調整(ヒアリング)の代行
リース引継ぎの可否は、最終的には各都道府県(岩手県、宮城県など)のローカルルールや担当者の裁量に左右される部分が少なくありません。
私達のような専門家は、申請書を提出する前に、行政の担当窓口(保健所など)と入念な「事前調整(ヒアリング)」を行い、「このMS法人との引継ぎスキームで認可の見込みがあるか」の感触を探り、必要に応じて軌道修正を行います。
3-2. スケジュール管理と書類の不備防止
医療法人の設立は、「〇月〇日までに認可を受け、〇月〇日に登記を完了する」という厳密なスケジュール管理が求められます。
リース会社やMS法人から必要書類を取り寄せ、行政の求める膨大な申請書類を作成するプロセスには、多くの時間と労力がかかります。
専門家にご依頼いただくことで、これらの煩雑な作業から解放され、先生は診療という本来の業務に集中していただけます。
3-3. MS法人との適正な取引設計の助言
MS法人からの引継ぎは、税務上の問題も絡むため、顧問税理士との連携も不可欠です。
私たちは、行政書士の視点(=行政の審査をクリアする)と、税理士の視点(=税務上問題ない)の双方を満たす、適正な取引の設計をトータルでサポートします。
4 まとめ
医療法人の設立、そして行政機関への許認可申請は、何から手を付けていいか分からない、というのが多くの先生方の本音ではないでしょうか。
特にリース資産の引継ぎやMS法人が関わるスキームは、行政の審査が最も厳しくなるポイントであり、専門的な知見なくして乗り越えるのは困難です。
そこで、専門家である行政書士に、設立計画の策定から行政との折衝、複雑な申請書の作成・提出までをトータルでお任せいただくことで、先生は「安心」と「時間」を手に入れることができます。
当事務所は、単に書類を作成するだけではありません。
医療の最前線に立つ先生方に寄り添い、現状と将来の展望を丁寧にお伺いした上で、最善の解決策をご提案します。
また、当事務所の最大の強みは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった他士業との強力な連携体制にあります。
医療法人設立に伴う登記(司法書士)や税務(税理士)、人事労務(社労士)といった様々な問題にも、ワンストップで迅速に対応が可能です。
さらに、私は元岩手県職員として、企業誘致や県立大学新設といった行政内部での調整業務に携わってきた経験があります。
国、県、保健所といった行政機関の「考え方」や「判断基準」を熟知しており、行政に対しスピーディーかつ的確な対応・調整を行える点は、他の事務所にはない独自の「強み」であると自負しております。
他の事務所と異なり、土日・祝日も営業し、朝8時から夜20時まで対応しております。
多忙な先生方のスケジュールに合わせて、柔軟にご相談いただけます。
★注意事項
厚生労働省(地方厚生局)や都道府県、各保健所への許認可申請(医療法人設立認可申請など)は、その申請代理を行政書士の独占業務と定めています。
行政書士の資格を持たない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て、これらの申請を代理する(書類作成や提出代行を含む)ことは、法律で固く禁止されています。
5 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ:
https://office-fujiihitoshi.com/