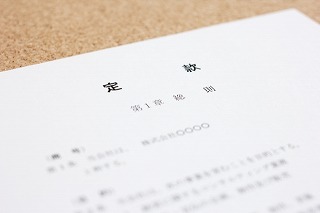「医療法人化って、具体的にどうすればいいの?」
「個人開業医と比べて、どんなメリットがあるの?」
「税金や社会保険はどう変わる?」
「手続きが複雑そうで不安…」
こんな悩みはありませんか?
医療法人化は、節税効果や事業承継の円滑化など、多くのメリットがある一方で、設立手続きの煩雑さや、運営上の制約など、注意すべき点も少なくありません。
ご安心ください!
今回の記事では、医療法人設立について、メリット・デメリット、個人開業医との違い、設立・運営の手続き、注意点などを、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、医療法人化に関する疑問が解消され、あなたのクリニックにとって最適な選択をするための判断材料が得られます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)でご開業の先生方、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1医療法人と個人開業の違い
個人でクリニック(診療所)を経営されている先生から、「医療法人にした方が良いのか?」「メリット・デメリットは?」というご質問をよくいただきます。
医療法人化を検討する際には、売上だけでなく、所得金額を考慮することが重要です。
また、節税という側面だけでなく、医療法人化のメリット・デメリットを総合的に理解しておく必要があります。
ここでは、7つの視点から、医療法人と個人開業の違いを詳しく比較します。
1-1. 税金面での違い
医療法人化の最大のメリットの一つは、節税効果です。
個人開業医と医療法人では、適用される税金の種類や税率、所得の計算方法、経費の範囲などが異なります。
1-1-1. 税率の違い
(1)個人開業医:
所得税は超過累進税率が適用されます。
所得税は、所得が高いほど税率が高くなる仕組みで、最高税率は45%です(住民税と合わせると55%)。
(2)医療法人:
法人税は段階税率が適用されます。
法人税は、所得に応じて税率が決まり、中小法人(資本金1億円以下)の場合、所得800万円以下の部分は約15%、800万円を超える部分は約23.2%です(実効税率は、地方税を含めると約21%~34%程度)。
一般的に、所得が高いほど、医療法人の方が税負担が軽くなる傾向があります。
ただし、医療法人は赤字であっても法人住民税の均等割(一定額の税金)を負担する必要があります(年間約7万円~)。
一方、個人開業医は、赤字の場合は所得税がかかりません(消費税は預り金の精算なので、赤字でも納税額が発生することがあります)。
1-1-2. 所得の種類
(1)個人開業医:
事業所得として課税されます。
事業所得は、診療報酬などの売上から、必要経費(人件費、家賃、医療機器の減価償却費など)と青色申告特別控除(最大65万円)を差し引いた金額です。
(2)医療法人:
理事長は、法人から役員報酬を受け取ります。
役員報酬は給与所得となり、給与所得控除の適用を受けることができます。
給与所得控除は、収入金額に応じて一定額を控除できる制度で、年収1,800万円超の場合、上限額は195万円です。実際に経費がかからなくても控除できるため、節税効果があります。
1-1-3. 親族への給与
(1)個人開業医:
同一生計の親族への給与は、原則として必要経費にできません。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出し、承認を受けた場合に限り、一定の要件のもとで経費にすることができます。
また、専従者は、原則として他の仕事に就くことができません(常勤はもちろん、非常勤も制限されます)。
(2)医療法人:
同一生計・別生計を問わず、親族に支払った給与は、勤務実態に応じて必要経費にすることができます。
税務署への届出も不要です。
常勤・非常勤を問わず、勤務実態に応じた給与を支払うことができ、理事長(院長)の配偶者や子などに給与を支払うことで、所得を分散し、世帯全体での税負担を軽減することができます。
1-1-4. 退職金
(1)個人開業医:
院長自身や家族に対して、退職金を支払うことはできません。
退職金制度としては、小規模企業共済(掛金は月額最大7万円、全額所得控除)がありますが、医療法人化すると加入できなくなります(医療法人化に伴い脱退した場合、脱退金は退職所得扱いとなります)。
(2)医療法人:
理事長や役員(家族を含む)に対して、退職金を支払うことができます。
退職金は、役員報酬と同様に、法人の経費にすることができます。
また、退職金は、退職所得として、他の所得と分離して課税され、税負担が軽減される場合があります。
退職金の原資として、生命保険を活用することも可能です。
1-1-5. 経費の範囲
(1)個人開業医:
事業に直接関係のある費用のみが経費として認められます。
例えば、自家用車を診療にも使用している場合、経費にできるのは事業に使用した割合に応じた部分のみです(家事按分)。
自宅兼診療所の場合も、家賃や光熱費などを家事按分する必要があります。
(2)医療法人:
法人名義の資産(車両、建物など)は、基本的に全額経費にすることができます。
また、理事長や役員の社宅(家賃の一部を法人が負担)も経費として認められます。
例えば、理事長の自宅を法人名義で借り上げ、家賃の8割~9割を法人が負担し、残りを理事長が自己負担とする、といった方法が可能です。
1-2. 手続き・運営面での違い
医療法人化すると、設立手続きや、その後の運営において、個人開業医にはない負担が生じます。
(1)個人開業医:
開業・廃業の手続きは比較的簡単です。
診療所開設届を保健所に提出するだけで開業でき、廃業する場合も診療所廃止届を提出するだけです。
診療時間や診療科目の変更なども、保健所への届出で済みます。
(2)医療法人:
設立には都道府県の認可が必要であり、手続きが煩雑です。
定款の作成、設立総会の開催、設立認可申請書の提出など、多くの手続きが必要であり、時間もかかります(通常、申請から認可まで6ヶ月程度)。
また、毎年、事業報告書等を都道府県に提出する義務があります。
役員の変更などがあった場合も、その都度、届出が必要です(役員任期は最長2年)。
1-3. 事業の拡大性
(1)個人開業医:
原則として、1つの診療所しか開設できません(管理者の兼務制限)。
(2)医療法人:
複数の診療所(分院)を開設することができます。
また、介護老人保健施設、訪問看護ステーションなど、介護事業への進出も可能です(定款に定める必要があります)。
事業規模の拡大を目指すのであれば、医療法人化が有利です。
1-4. 事業承継
(1)個人開業医:
事業承継の際は、既存の診療所を廃止し、承継者が新たに診療所を開設する必要があります。
保険医療機関の指定も、新たに受け直す必要があります。
また、診療所の土地・建物、医療機器などの資産は、個別に譲渡・贈与・相続などの手続きが必要です。
(2)医療法人:
理事長を変更するだけで、事業を承継することができます。
資産の移転も、個々に行う必要がありません。
医療法人であれば、親族への承継だけでなく、第三者への承継(M&A)も比較的スムーズに行うことができます。
1-5. 財産の所有
(1)個人開業医:
診療所の財産(土地、建物、医療機器、預貯金など)は、すべて院長個人のものです。
(2)医療法人:
診療所の財産は、法人のものです。
たとえ理事長であっても、法人の財産を自由に使うことはできません。
理事長は、法人から役員報酬を受け取り、その中から生活費などを支出することになります。
1-6. 業務の制限
(1)個人開業医:
業務範囲に制限はありません。
医療行為以外にも、不動産賃貸業など、自由に事業を行うことができます。
(2)医療法人:
医療法で定められた業務(病院、診療所、介護老人保健施設などの運営)および、附帯業務(医療関係者の養成、医学研究など、都道府県知事の認可を受けたもの)に限られます。
収益を目的とする事業(不動産賃貸業など)は、原則として行うことができません。
1-7. 社会保険
(1)個人開業医:
従業員が5人未満の場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)は任意加入です。
5人以上の場合は、強制加入となり、健康保険は協会けんぽ、年金は厚生年金となります。
院長本人は、国民健康保険・国民年金となります。
(2)医療法人:
強制加入で、健康保険は協会けんぽ、年金は厚生年金となります。
院長本人も、健康保険・厚生年金に加入します。
医療法人化によって、社会保険料の負担が増えるケースがあります。
加入する保険の種類が変わるので、保険料や給付内容を比較検討が必要です。
2医療法人設立の手続き
医療法人設立の手続きは、多くの書類作成や行政機関とのやり取りが必要であり、時間と労力がかかります。
ここでは、医療法人設立の手続きの流れを、5つのステップに分けて、詳しく解説します。
2-1. STEP1:事前準備
医療法人設立の最初のステップは、設立計画の策定です。
具体的には、以下の事項を検討し、決定します。
(1)設立する医療法人の種類:
①社団医療法人:
複数の社員(出資者)によって構成される医療法人です。
現在、新規設立できる医療法人のほとんどは、出資持分のない社団医療法人です。
②財団医療法人:
個人または法人が寄附した財産によって設立される医療法人です。
③特定医療法人:
公益性の高い医療法人として、税制上の優遇措置があります。
④社会医療法人:
地域医療支援病院、救急医療など、公益性の高い医療を提供する医療法人です。
(2)法人の基本事項:
①法人名: 既存の医療法人と同一または類似の名称は避ける必要があります。
②所在地: 主たる事務所の所在地を決定します。
③役員構成: 理事3名以上、監事1名以上が必要です。理事長は、医師または歯科医師でなければなりません。
④事業内容: 病院、診療所、介護老人保健施設など、どのような事業を行うかを決定します。
⑤資産: 設立時に拠出する財産(現金、不動産、医療機器など)を決定します。
⑥会計年度: 法人の会計年度(事業年度)を決定します(通常は4月1日から3月31日まで)。
(3)設立総会(社員総会)の開催:
①設立趣意書: 医療法人設立の目的、設立後の事業計画などを記載します。
②定款: 法人の組織、運営に関する基本規則を定めます。
③役員名簿: 理事、監事の氏名、住所などを記載します。
④財産目録: 設立時に拠出する財産の種類、価額などを記載します。
⑤設立総会議事録: 設立総会での議事内容を記録します。
これらの書類を作成し、設立総会(社員総会)で承認を得る必要があります。
2-2. STEP2:都道府県への設立認可申請
設立計画がまとまったら、都道府県(または保健所)に医療法人設立認可申請を行います。
申請には、多くの書類が必要であり、不備があると受理されないため、注意が必要です。
(1)必要書類の作成:
①医療法人設立認可申請書
②定款
③設立総会議事録
④役員の就任承諾書
⑤役員の履歴書
⑥役員の印鑑証明書
⑦財産目録
⑧不動産の登記事項証明書
⑨預貯金残高証明書
⑩負債がある場合は、その明細書および債務引受承諾書
⑪開設しようとする診療所(病院)の概要
⑫診療所(病院)の図面(平面図、付近の見取図)
⑬医師・歯科医師免許証の写し
⑭管理者の履歴書
⑮その他、都道府県が求める書類
これらの書類を、都道府県が定める様式に従って作成します。
(2)都道府県への申請:
①申請窓口: 医療法人設立認可申請の窓口は、都道府県の医療政策課(またはそれに準ずる部署)または保健所です。
②申請時期: 多くの都道府県では、医療法人設立認可申請の受付期間が年に2回程度と限られています。事前に確認し、スケジュールに余裕を持って準備を進めましょう。
③提出方法: 申請書類は、原則として、窓口に持参します。郵送での受付は、認められない場合が多いです。
2-3. STEP3:設立認可(都道府県)
都道府県は、提出された申請書類に基づいて、医療法人設立の認可審査を行います。
(1)都道府県による審査:
①書類審査: 提出された書類に不備がないか、法令に適合しているかなどを審査します。
②現地調査: 必要に応じて、診療所の現地調査が行われる場合があります。
③面接(ヒアリング): 申請者(設立代表者)に対して、設立の趣旨や事業計画などについて、面接(ヒアリング)が行われる場合があります。
(2)認可書の交付:
審査の結果、問題がなければ、都道府県知事から「医療法人設立認可書」が交付されます。
認可書の交付には、申請から通常6ヶ月程度かかります。
2-4. STEP4:設立登記(法務局)
医療法人設立認可書の交付を受けたら、法務局で医療法人の設立登記を行います。
(1)法務局への申請:
①申請期限: 設立認可書の交付日から2週間以内
②必要書類:
・医療法人設立登記申請書
・定款
・医療法人設立認可書
・理事長の就任承諾書
・理事長の印鑑証明書
・その他、法務局が求める書類
③登録免許税: 収入印紙で納付します(金額は、出資額などによって異なります)。
(2)法人の成立:
設立登記が完了すると、医療法人が正式に成立します。
登記完了後、法務局から登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。
2-5. STEP5:設立後の手続き
医療法人設立登記が完了したら、関係機関への届出を行います。
(1)保健所への届出:
①診療所開設許可申請: 医療法人として診療所を開設するための許可申請です。
②診療所開設届: 診療所を開設したことを届け出ます。
③その他: エックス線装置設置届、麻薬管理者免許申請など、必要に応じて届出を行います。
(2)地方厚生局への届出:
①保険医療機関指定申請: 保険診療を行うために必要な手続きです。
(3)税務署への届出:
①法人設立届出書
②青色申告の承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
⑤消費税関連の届出(課税事業者になる場合)
(4)都道府県税事務所・市町村役場への届出:
①法人設立届出書
(5)社会保険事務所への届出:
①新規適用届
②被保険者資格取得届
③被扶養者異動届
(6)労働基準監督署への届出:
①保険関係成立届
②概算保険料申告書
(7)公共職業安定所(ハローワーク)への届出:
①雇用保険適用事業所設置届
②雇用保険被保険者資格取得届
これらの手続きは、期限が定められているものもあるため、注意が必要です。
3医療法人設立の注意点
医療法人設立は、多くのメリットがある一方で、注意すべき点も少なくありません。
ここでは、医療法人設立にあたって、特に注意すべき4つのポイントを詳しく解説します。
3-1. スケジュール管理
医療法人設立の手続きは、多くの書類作成や行政機関とのやり取りが必要であり、時間と手間がかかります。
特に、都道府県への設立認可申請は、受付期間が年に2回程度と限られている場合が多いため、注意が必要です。
(1)申請スケジュール:
多くの都道府県では、医療法人設立認可申請の受付期間を、年2回(例えば、春と秋)設けています。
受付期間は、都道府県によって異なりますので、事前に確認が必要です。
申請書類の提出期限は、受付期間の最終日となります。
申請から認可までの期間は、通常6ヶ月程度かかります。
(2)スケジュール管理のポイント:
①早めの準備:
申請書類の作成には、時間がかかるため、早めに準備を始めることが重要です。
②情報収集:
都道府県のホームページなどで、最新の申請スケジュールや必要書類を確認しましょう。
③専門家への相談:
手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談し、スケジュール管理をサポートしてもらうことをおすすめします。
④余裕を持った計画:
申請期限ギリギリではなく、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。
3-2. 専門家への相談
医療法人設立の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。
申請書類の不備や、法令違反などがあると、認可が下りない場合や、設立後に問題が発生する可能性があります。
(1)専門家の必要性:
①法令の知識:
医療法人設立には、医療法、会社法、税法など、様々な法律の知識が必要です。
②手続きの煩雑さ:
申請書類の作成、行政機関とのやり取りなど、手続きが煩雑です。
③時間と労力の節約:
専門家に依頼することで、時間と労力を節約できます。
④リスクの回避:
不備のない申請書類を作成し、法令を遵守することで、設立後のトラブルを回避できます。
(2)行政書士の活用:
①行政書士は、医療法人設立に関する専門知識を持ち、申請書類の作成や提出代行、行政庁との交渉など、設立手続きをトータルでサポートできます。
②また、医療法だけでなく、会社法など関連法規にも精通しているため、総合的なアドバイスを受けることができます。
③なお、行政書士は地域に密着した活動を行っているため、地域の医療事情にも詳しく、適切なアドバイスを受けることができます。
3-3. 資金計画
医療法人設立には、設立費用と、設立後の運転資金が必要です。
事前に、資金計画をしっかりと立てておくことが重要です。
(1)設立費用:
①登録免許税: 医療法人設立登記の際に、法務局に納める税金です。
②定款認証手数料: 公証役場で定款の認証を受ける際に、公証人に支払う手数料です。
③行政書士報酬: 行政書士に設立手続きを依頼する場合の報酬です。
④その他: 登記事項証明書の取得費用、印鑑作成費用など。
(2)運転資金:
①人件費: 医師、看護師、事務職員などの給与、賞与、社会保険料など。
②家賃: 診療所の家賃、駐車場代など。
③医療機器購入費・リース料: 医療機器の購入費用やリース料。
④医薬品・診療材料費: 医薬品や診療材料の購入費用。
⑤水道光熱費、通信費、広告宣伝費
⑥その他: 消耗品費、交通費、交際費など。
資金計画は、医療法人の規模や診療科目、地域などによって大きく異なります。
事前に、詳細なシミュレーションを行い、必要な資金を確保しておく必要があります。
3-4. 役員構成
医療法人の役員は、理事3名以上、監事1名以上が必要です。
理事長は、原則として、医師または歯科医師である理事の中から選出します。
(1)理事長の要件:
原則として、医師または歯科医師であること。
都道府県知事の認可を受けた場合は、医師または歯科医師でない理事を理事長に選出することも可能。
(2)理事の要件:
原則として、自然人(個人)であること。法人は理事になれません。
医療法に定められた欠格事由に該当しないこと。
(3)監事の要件:
医療法人の理事、職員、またはその配偶者、親族などは、監事になることができません。
(4)役員構成の注意点:
役員は、医療法人の運営に責任を負うことになります。
信頼できる人を選び、責任の所在を明確にしておきましょう。
親族を役員にする場合は、同族経営による弊害(経営の透明性欠如など)が生じないよう、注意が必要です。
役員報酬は、不当に高額にならないように注意が必要です。
4まとめ
医療法人設立は、多くのメリットがある一方で、手続きが煩雑であり、専門的な知識が必要です。
また、設立後の運営についても、様々な注意点があります。
「医療法人設立を検討しているけど、何から始めればいいか分からない」「手続きが複雑で不安」「専門家のアドバイスが欲しい」など、医療法人設立に関するお悩みは、専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士は、医療法人設立に関する専門知識を持ち、申請書類の作成や提出代行、行政庁との交渉など、設立手続きをトータルでサポートできます。
また、医療法人設立後の運営に関する相談や、各種変更手続きの代行も可能です。
当事務所では、医療法人設立に関するご相談を幅広く承っており、お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や都道府県といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。
医療法人について、何から手を付けていいか分からない、専門的なアドバイスが欲しいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします。
この記事を読んで、少しでも医療法人設立について考えるきっかけになれば幸いです。
<注意事項>
①厚生労働省(地方厚生局)や都道府県、各保健所への申請は、行政書士が、唯一行政機関への申請が認められている国家資格者です。
②行政書士以外の者(医療コンサルタントなど)が、他人の依頼を受けて、必要な申請などを代理することは、法律で禁止されています。
③行政書士以外の者が、違法な申請代理をした場合は「罰則」が適用されるので、十分注意すること。
5お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ