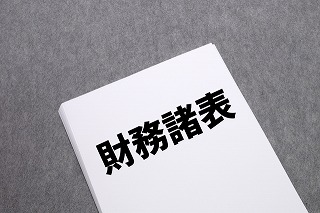「建設業の損益計算書って、普通のP/Lと違うの?」
「『完成工事高』と『完成工事原価』の計算方法は?」
「兼業の売上や原価はどう書けばいい?」
「完成工事原価報告書って、損益計算書とどう関係があるの?」
こんな疑問をお持ちではありませんか?
建設業許可の申請や更新、経営事項審査(経審)では、会社の経営成績を示す損益計算書の提出が求められます。
しかし、建設業の損益計算書には、一般企業の会計とは異なる特有の勘定科目やルールが存在し、正確な作成には注意が必要です。
ご安心ください!
今回の記事では、建設業財務諸表における損益計算書の基本的な作成方法と、特に重要な「完成工事原価報告書」との関連について、初心者の方にも分かりやすく解説します。
この記事を読めば、建設業の損益構造を正しく把握し、適切な財務諸表を作成するための知識が身につきます。
建設業の損益計算書(P/L)は、一定期間(通常は1事業年度)における会社の経営成績、つまりどれだけ儲かったか(または損したか)を示す重要な財務書類です。
基本的な構造は一般企業の損益計算書と同じですが、建設業特有の勘定科目や考え方があります。
ここでは、その特徴的な勘定科目と、密接に関連する「完成工事原価報告書」について詳しく見ていきましょう。
1損益計算書の特徴的な勘定科目
建設業財務諸表の損益計算書(様式第16号)で特に注意が必要なのは、「売上高」と「売上原価」の項目です。
1-1. 売上高:工事の売上とそれ以外の売上を分ける
1-1-1. 完成工事高
建設業の主たる事業である「建設工事」によって得られた売上高を計上します。
これが建設業における最も重要な売上項目です。
具体的には、以下の合計額となります。
①当期中に完成し、引き渡した工事の請負代金
②(収益認識基準を適用している場合)当期中の工事進捗度に応じて認識した収益額
(ポイント)
ここに計上する「完成工事高」の金額は、建設業許可申請書(様式第一号)に添付する「直前3年の各事業年度における工事施工金額」(様式第三号)の、直近事業年度の合計額と必ず一致させる必要があります。
整合性が取れていないと、申請が受理されない、あるいは審査で指摘される可能性があります。
1-1-2. 兼業事業売上高
建設業以外の事業から得られた売上高を計上します。
建設業者が行う事業は多岐にわたるため、本業である建設工事以外の収益も正確に把握し、区分表示する必要があります。
(具体例)
・建設業許可が不要な軽微な工事の売上(例:税抜500万円未満の小規模リフォームなど )
・建設資材(砂利、セメントなど)の販売収入
・不動産賃貸収入(例:所有する土地や建物の賃料)
・保守点検、メンテナンス収入(例:完成後の建物の保守契約など)
・清掃事業収入
・除雪・除草・草刈り・剪定などの作業収入
・物品販売収入(例:工事に関連しない物品の販売)
・太陽光発電などの売電収入
1-2. 売上原価:売上に対応するコストを把握する
1-2-1. 完成工事原価
上記の「完成工事高」に対応する原価(工事を完成させるために直接かかった費用)を計上します。
この金額は、損益計算書に直接記入するのではなく、別途作成する「完成工事原価報告書」の合計額と必ず一致させる必要があります。
つまり、「完成工事原価報告書」を先に作成し、その結果を損益計算書に転記する、という流れになります。
1-2-2. 兼業事業売上原価
上記の「兼業事業売上高」に対応する原価を計上します。
これも、基本的には別途作成する「兼業事業売上原価報告書」(建設業法施行規則様式第二十五号の十二、ただし都道府県によっては独自の様式を指定している場合あり)の合計額と一致させる必要があります。
兼業事業の内容に応じて、仕入原価や製造原価などが含まれます。
1-3. 売上総利益(または売上総損失)<粗利>
売上総利益(粗利)は、建設業の損益計算書では、以下の2つに分けて計算し、表示します。
①完成工事総利益 = 完成工事高 - 完成工事原価
②兼業事業総利益 = 兼業事業売上高 - 兼業事業売上原価
これにより、主たる建設事業の収益性と、それ以外の兼業事業の収益性をそれぞれ把握することができます。
もちろん、それぞれの事業で損失が出た場合は、「売上総損失」として表示されます。
2完成工事原価報告書
損益計算書の「完成工事原価」の内訳を示す重要な書類が、「完成工事原価報告書」です。
建設業財務諸表を作成する上で、損益計算書とセットで必ず作成する必要があります。
この報告書は、工事原価を「材料費」「労務費」「外注費」「経費」の4つの費目に分類して記載します。
2-1. 材料費
工事を施工するために直接購入した物品や、自社で保有していた材料を使用した際の費用を計上します。
(具体例)
・工事に使用する素材(木材、鉄骨、コンクリート、砂利、電線、配管など)
・半製品、製品(既製のドア、窓サッシ、ユニットバスなど)
・工事現場で使用する消耗品(釘、ボルト、塗料、接着剤など)
・自社の材料置場などから現場に持ち出した材料(材料貯蔵品からの振替額)
・機械の燃料費(重油、軽油など)も、工事に直接使用される場合は材料費に含めることがあります。
2-2. 労務費
工事現場で直接作業に従事した自社雇用の作業員(職人、とび工、運転手など)に支払われる賃金、給料、各種手当などを計上します。
(具体例)
・直接雇用の現場作業員の給与、賃金
・残業手当、休日出勤手当、危険手当などの各種手当
・賞与、退職金(工事に直接関わる部分)
・法定福利費(社会保険料の会社負担分など、現場作業員に対応するもの)
(ポイント)
いわゆる日雇いや日給月給制の作業員だけでなく、現場作業に従事する正社員の給与もここに含まれます。
役員報酬や、本社・支店の事務職員、営業職員の給与は、原則としてここには含めず、「販売費及び一般管理費」として処理します
(ただし、現場兼任の場合は按分計算が必要な場合もあります)。
(補足:労務外注費について)
様式には「(うち労務外注費)」という内訳欄がありますが、これは実務上、純粋な「手間請け」(材料を支給し、労務だけを外注する形態)のようなケースを想定しています。しかし、現在ではこのような形態は少なく、一般的な下請契約(材料費等も含む)が多いため、この欄に金額が計上されるケースは稀です。
多くの場合は「外注費」として処理されます。
2-3. 外注費
自社で施工せず、他の建設業者(下請業者)に工事の一部または全部を依頼した場合に支払う費用を計上します。
建設業では外注費の割合が高くなる傾向があります。
(具体例)
・下請業者への工事請負代金の支払い
・警備会社への交通誘導などの業務委託費
・設計事務所への設計委託費(工事原価として処理する場合)
2-4. 経費
上記の材料費、労務費、外注費のいずれにも該当しない、「工事を施工するため」にかかった費用を計上します。
非常に多岐にわたる費用が含まれます。
(具体例)
・現場従業員の人件費(経費の内訳として表示)
・地代家賃: 現場事務所や資材置場の賃借料
・水道光熱費: 現場事務所や工事で使用する電気・ガス・水道代
・機械等経費: 自社保有の建設機械の減価償却費、修繕費、リース料、レンタル料
・特許権使用料: 特定の工法などを使用するためのライセンス料
・技術研究開発費: 工事施工に関する研究開発費用
・保険料: 工事保険料、労災保険料(現場作業員分)など
・設計費: 外注した設計費用(外注費と区分する場合)
・福利厚生費: 現場従業員の慰安費用など
・通信交通費: 現場事務所の電話代、現場への交通費
・租税公課: 工事に関連する印紙税など
・事務用品費: 現場事務所で使用する文具など
・その他: 上記以外で工事施工に直接必要な経費
(重要:経費(うち人件費)について)
経費の中には、「(うち人件費)」という内訳欄があります。
ここに計上するのは、「工事現場の管理業務」などに従事する「自社の正社員」の給料、手当、賞与、法定福利費などです。
具体例: 現場監督(主任技術者、監理技術者)、現場事務員、現場管理部門の社員など。
(労務費との違い)
「労務費」が現場で直接作業を行う作業員の賃金であるのに対し、「経費(うち人件費)」は現場の管理などに従事する社員の給与、という違いがあります。
この区別は、原価計算の正確性や経審の評価(特に技術力Z評点)にも関わるため、重要です。
3まとめ
建設業の損益計算書と完成工事原価報告書は、単に許可申請や経審のためだけでなく、自社の経営成績や利益構造を正確に把握するための重要なツールです。
「完成工事高」に対してどれだけの「完成工事原価」がかかったのか、その原価の内訳(材料費、労務費、外注費、経費)はどうなっているのかを分析することで、コスト削減のポイントや収益改善のヒントが見えてきます。
しかし、これらの書類の作成には、建設業特有の勘定科目やルール、関連様式(完成工事原価報告書など)の正確な理解が不可欠です。
「どの費用がどの科目に該当するのか分からない」「完成工事原価報告書の作り方が難しい」「経審で有利になるような財務諸表を作成したい」
このような課題をお持ちの建設業者様は、建設業専門の行政書士にご相談いただくのが確実です。
当事務所は、建設業許可・経営事項審査(経審)の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
複雑な建設業財務諸表の作成はもちろん、経営分析に基づいたアドバイスや、経審の評点アップに向けた戦略的なサポートも可能です。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーと、『士業の会』を主宰しており、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという、他の事務所にない「強み」を持っているところです。
建設業許可及び経営事項審査(経審)を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
4お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>
https://office-fujiihitoshi.com