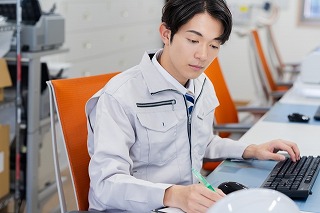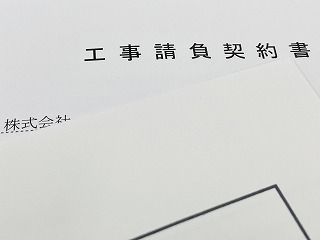「建設業の貸借対照表、普通の会社とどこが違うの?」
「『ワンイヤールール』って建設業でも使うの?」
「役員からの借入金、短期?長期?どっち?」
「経審や特定建設業の許可にどう影響するの?」
こんな疑問や不安を感じていませんか?
建設業許可の申請・更新や経営事項審査(経審)では、建設業法に則った財務諸表の提出が不可欠です。
特に貸借対照表は、会社の財政状態を示す重要な書類ですが、その作成には建設業特有のルールや一般企業会計とは異なる考え方があり、注意が必要です。
ご安心ください!
今回の記事では、建設業の貸借対照表を作成する上で絶対に押さえておくべき重要なルール、特に「ワンイヤールール」と「正常営業循環基準」を中心に、分かりやすく徹底解説します。
この記事を読めば、正しい貸借対照表の作成方法が分かり、経審や特定建設業許可申請を有利に進めるためのヒントが得られます。
1大原則!「ワンイヤールール(1年基準)」とは?
建設業の貸借対照表を作成する上で、まず理解しておくべき大原則が「ワンイヤールール(1年基準)」です。
これは、資産や負債を「流動」と「固定」に分類するための基本的な考え方です。
1-1. 流動と固定を分ける「1年」というモノサシ
ワンイヤールールは、決算日の翌日から起算して1年以内に、現金化される(資産)、または支払期限が到来する(負債)かどうかを基準に、流動項目と固定項目を分類するルールです。
① 1年以内に現金化・支払期限到来 → 流動資産・流動負債
② 1年を超えて現金化・支払期限到来 → 固定資産・固定負債
このルールは、一般的な企業会計の基礎となる「企業会計原則」およびその注解(注16)で定められています。
企業会計原則は法律ではありませんが、すべての企業が財務諸表を作成する際に従うべき、公正妥当と認められた会計の慣行をまとめたものです。
建設業の財務諸表も、この原則に基づいて作成されます。
【具体例:借入金の場合】
①短期借入金(流動負債):
決算日の翌日から1年以内に返済期限が到来する借入金。
②長期借入金(固定負債):
返済期限が決算日の翌日から1年を超える借入金(例:設備投資のための長期ローンなど)。
③1年以内返済長期借入金(流動負債):
もともと長期借入金だったもののうち、決算日の翌日から1年以内に返済期限が到来する部分。
長期借入金の中から、この部分だけを流動負債に振り替えます。
1-2. 「役員借入金」の扱いに要注意!流動比率への影響
ワンイヤールールの適用で特に注意が必要なのが、「役員借入金」の扱いです。
これは、社長やその親族などの役員が、会社に対して個人的にお金を貸し付けている場合や、役員報酬の一部が未払いのままになっているケースなどを指します。
多くの場合、この役員借入金が、便宜上「短期借入金」(流動負債)として計上されたまま、長期間放置されているケースが見受けられます。
しかし、実態として返済予定が1年以内にないのであれば、ワンイヤールールに基づき、「長期借入金」(固定負債)として計上するのが正しい処理です。
○なぜこれが問題になるのか?
実は、この役員借入金の流動・固定の区分が、特定建設業許可の取得・更新や経営事項審査(経審)の評価に、直接的な影響を与える可能性があるからです。
⑴特定建設業許可の財産要件:
特定建設業許可を取得・維持するためには、厳しい財産要件を満たす必要があります。
その一つに「流動比率が75%以上であること」という基準があります。
★流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 (%)
⑵経審の評価:
経審においても、財務状況の健全性を示す指標として、流動比率などの経営状況分析(Y点)が評価されます。
もし、長期化している役員借入金を誤って流動負債(短期借入金)のままにしておくと、計算式の分母である「流動負債」の額が大きくなり、流動比率が低く算出されてしまいます。
その結果、特定建設業許可の基準である75%を下回ってしまったり、経審の評点が下がってしまったりする可能性があるのです。
税務申告上(法人税の確定申告など)は、役員借入金の流動・固定の区分が問題視されることは少ないため、税理士事務所でも見過ごされがちですが、建設業許可や経審においては非常に重要なポイントとなります。
自社の貸借対照表を確認し、役員借入金などが実態に合わせて正しく分類されているか、今一度チェックしてみましょう。
2正常営業循環基準
ワンイヤールールと並んで重要なのが、「正常営業循環基準」です。
これは、建設業のように、事業サイクルが1年を超えることが常態である業種特有の考え方と言えます。
2-1. 営業サイクル内の資産・負債は「流動」扱い
正常営業循環基準とは、企業の主たる営業活動(仕入→製造・施工→販売・完成→代金回収)のプロセスの中で発生する資産や負債は、その回収期間や支払期間が1年を超えるものであっても、「流動資産」または「流動負債」として分類するというルールです。
これも企業会計原則で定められています。
建設業においては、工事の着工から完成・引渡し、そして代金の回収までに1年以上かかることは珍しくありません。
もしワンイヤールールだけを厳密に適用すると、これらの工事に関連する資産や負債の多くが固定項目になってしまい、企業の短期的な支払い能力や資金繰りの実態を正しく反映できなくなってしまいます。
そのため、建設業の会計では、正常な営業サイクルの中で発生するものは、期間にかかわらず流動項目として扱います。
2-2. 建設業における具体例
①未成工事支出金(流動資産):
工期が1年を超える長期の工事であっても、その工事のために支出した材料費や労務費などは、完成するまで流動資産として計上されます。
②完成工事未収入金(流動資産):
工事が完成・引渡し後、代金の回収までに1年以上かかる場合でも、流動資産として計上されます。
③未成工事受入金(流動負債):
工期が1年を超える長期の工事であっても、発注者から前受けした工事代金は、完成するまで流動負債として計上されます。
3ルールの適用順序:どっちが優先?
では、「ワンイヤールール」と「正常営業循環基準」は、どちらが優先されるのでしょうか?
答えは、「正常営業循環基準」が優先されます。
まず、その資産や負債が、企業の正常な営業サイクルの中から発生したものかどうかを判断します。
もし、正常な営業サイクルの中から発生したものであれば、期間にかかわらず「流動項目」となります(正常営業循環基準)。
正常な営業サイクルの中から発生したものでない場合に限り、「ワンイヤールール」を適用し、1年以内に現金化・支払期限が到来するかどうかで流動・固定を判断します。
【フローチャート】
①その資産・負債は、正常な営業サイクルから発生したものか?
YES → 流動項目(正常営業循環基準を適用)
NO → STEP 2へ
②決算日の翌日から1年以内に現金化・支払期限が到来するか?
YES → 流動項目(ワンイヤールールを適用)
NO → 固定項目(ワンイヤールールを適用)
この2つのルールと優先順位を正しく理解し、適用することが、適切な建設業の貸借対照表を作成し、特定建設業許可や経審で不利にならないための重要な鍵となります。
4細かいけど重要!「5%ルール」
建設業の貸借対照表(様式第十五号)には、「その他」という勘定科目があります。
しかし、この「その他」には注意が必要です。
国土交通省が定める様式第十五号の記載要領では、「流動資産」「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」の各区分において、個別の勘定科目の金額が、それぞれの区分計ではなく『総資産』(資産合計)の5%を超える場合には、「その他」に含めずに、その勘定科目名を個別に表示しなければならない、と定められています。
例えば、「投資その他の資産」の中に多額の「長期貸付金」があり、その金額が総資産の5%を超えているにもかかわらず、「投資その他の資産その他」としてまとめて計上してしまうと、記載要領違反となる可能性があります。
少額で重要性の低い科目を「その他」にまとめるのは問題ありませんが、金額的な重要性がある科目は、きちんと独立させて表示する必要があります。
5固定資産の表示方法:「科目別間接控除法」
建設業財務諸表における有形固定資産(建物、機械など)の表示方法は、「科目別間接控除法」と定められています。
これは、
①各固定資産の勘定科目ごとに「取得価額」を記載する。
②そのすぐ下に、控除項目として「減価償却累計額」を記載する。
という表示方法です。
一般的な会計ソフトで作成される貸借対照表では、取得価額から減価償却累計額を差し引いた「帳簿価額(簿価)」のみが表示されることが多いですが、建設業財務諸表では、取得価額と減価償却累計額をそれぞれ明記する必要があります。
もし、税務申告用に作成した貸借対照表が帳簿価額表示になっている場合は、建設業財務諸表を作成する際に、法人税申告書に添付した「別表十六(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)」などを確認し、取得価額と期末時点での減価償却累計額を正確に転記する必要があります。
6まとめ
建設業許可申請や経営事項審査(経審)をスムーズに進めるためには、建設業法に基づいた正確な財務諸表の作成が不可欠です。
特に貸借対照表は、ワンイヤールール、正常営業循環基準といった会計原則の正しい理解に加え、建設業特有のルール(5%ルール、固定資産の表示方法など)を踏まえる必要があり、専門的な知識が求められます。
「ルールが複雑でよく分からない…」「自社で作成した財務諸表が正しいか心配…」「経審の評点を上げるために、財務内容を見直したい」
このようなお悩みやご要望をお持ちの建設業者様は、ぜひ建設業専門の行政書士にご相談ください。
当事務所は、建設業許可・経営事項審査(経審)の専門家として、複雑な財務諸表の作成から各種申請手続きまで、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーと、『士業の会』を主宰しており、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという、他の事務所にない「強み」を持っているところです。
建設業許可及び経営事項審査(経審)を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
7お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>
https://office-fujiihitoshi.com/