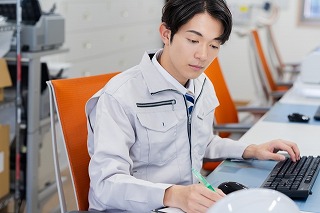
「出向社員を経営業務の管理責任者や専任技術者にできる?」
「在籍出向と移籍出向、建設業許可ではどう違うの?」
「実務経験って、具体的にどんな業務が認められるの?」
こんな疑問はありませんか?
ご安心ください。
今回の記事では、建設業許可における出向者の扱い、経営業務の管理責任者・専任技術者の要件、そして実務経験として認められる業務・認められない業務について、詳しく解説します。
この記事を読めば、出向者に関する疑問や、実務経験の不安が解消され、建設業許可取得への道筋が見えてきます。
岩手県で建設業許可取得・更新をお考えの皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1出向社員でもOK?:経営業務の管理責任者・専任技術者の要件
岩手県で建設業を営む皆様、建設業許可の取得・更新において、「経営業務の管理責任者」(経管)と「専任技術者」(専技)の選任は避けて通れません。
では、出向社員をこれらの重要なポジションに据えることはできるのでしょうか?
ここでは、出向社員と建設業許可の関係について、さらに詳しく解説します。
1-1. 「出向」とは?:2つの種類を正しく理解する
まず、「出向」という言葉の定義と、その種類について整理しましょう。
「出向」には、大きく分けて「在籍出向」と「移籍出向(転籍)」の2つがあります。
(1) 在籍出向:
出向元企業との雇用契約を維持したまま、出向先企業で働く形態です。
出向元企業に籍を残したまま、出向先企業の指揮命令下で業務を行います。
この場合、労働者は出向元企業と出向先企業の両方と労働契約関係にあることになります(二重労働契約関係)。
給与の支払いや社会保険の加入などは、出向契約の内容によって異なりますが、一般的には、出向元企業が給与を支払い、出向先企業がその一部または全部を負担する形が多いです。
(2) 移籍出向(転籍):
出向元企業との雇用契約を終了し、出向先企業と新たに雇用契約を結ぶ形態です。
籍も出向先企業に移るため、実質的には転職と同じです。
給与の支払いや社会保険の加入などは、すべて出向先企業が行います。
1-2. 経管・専技に求められるのは「常勤性」と「専任性」
建設業法では、経管と専技に対して、「常勤性」と「専任性」を求めています。
これらの要件は、建設業の経営や技術の質を確保するために、非常に重要なものです。
(1)常勤性:
原則として、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること。
つまり、通常の勤務時間中は、その営業所に勤務している必要があります。
・具体例:
正社員として、毎日9時から18時まで勤務している。
契約社員として、週5日、1日6時間勤務している。
テレワークで、毎日所定の時間、自宅で業務を行っている。
・認められない例:
パートタイマーとして、週3日、1日3時間しか勤務していない。
他の会社の役員を兼務しており、建設業の業務に十分な時間を割けない。
住所が営業所から遠く、毎日通勤することが困難である。
(2)専任性(専任技術者の場合):
その営業所に常勤して、専らその職務に従事すること。
つまり、他の業務を兼務せず、専任技術者としての業務に専念する必要があります。
・具体例:
建設業の営業所で、専任技術者として、見積もり、契約、技術指導などの業務を行っている。
・認められない例:
建設業の営業所で、経理事務と兼務している。
他の営業所の専任技術者を兼務している。
工事現場の主任技術者や監理技術者を兼務している(原則)。
1-3. 出向社員でも経管・専技になれる!:法的根拠と実務上の注意点
結論から言うと、出向社員でも、上記の「常勤性」と「専任性」を満たせば、経管や専技になることができます。
建設業法上、経管や専技が、所属する建設業者と直接の雇用関係になければならない、というルールはありません。
役員の場合は、会社との関係は委任契約になるので、雇用関係は求められていません。
国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」第7条にも、その旨が明記されています。
具体的には、「建設業者の営業所における常勤性は、当該営業所に勤務することを通常の勤務形態とすることをもって確認するものであり、当該建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係(雇用関係に準ずる関係を含む。)があることを要する。」とされています。
ここでいう「雇用関係に準ずる関係」とは、出向契約などが該当します。
つまり、出向社員であっても、出向先企業との間で、実質的に雇用関係と同様の関係が認められれば、常勤性・専任性を満たすと判断されるのです。
ただし、出向社員が経管や専技になる場合は、以下の点に注意が必要です。
・出向契約の内容:
出向契約の内容が、常勤性・専任性を満たすものであるか、十分に確認する必要があります。
・行政庁の判断:
最終的な判断は、許可申請を行う行政庁が行います。事前に相談し、必要な書類や手続きを確認しておくことが重要です。
2出向形態で異なる!:経管・専技の常勤性確認
出向社員が経管や専技になる場合、その出向形態によって、常勤性の確認方法が異なります。
ここでは、「在籍出向」と「移籍出向」の場合に分けて、さらに詳しく解説します。
2-1. 移籍出向(転籍)の場合:転職と同じ扱い、確認書類もシンプル
移籍出向(転籍)の場合は、出向元企業との雇用関係を終了し、出向先企業との間に新たな雇用関係が生まれるため、実質的には転職と同じです。
そのため、常勤性の確認は、通常の社員と同様に行われます。
〇確認書類の例
・健康保険証:
出向先企業で健康保険に加入していることを確認します。
健康保険証の事業所名が出向先企業になっていることがポイントです。
・役員報酬(役員の場合):
常勤に相応した役員報酬が出向先企業から支払われていることを確認します。
役員報酬の金額は、出向先企業の他の役員とのバランスや、業務内容などを考慮して判断されます。
・住民票、通勤経路、通勤手段など:
住所と営業所の所在地を確認し、毎日通勤できる距離であるかを確認します。
通勤経路や通勤手段も確認される場合があります。
・雇用契約書(必要な場合):
出向先企業との雇用契約書を確認する場合があります。
2-2. 在籍出向の場合:出向契約の内容が重要、多角的な確認
在籍出向の場合は、出向元企業に籍を置いたまま、出向先企業で勤務するため、常勤性の確認はより慎重に行われます。
通常の確認書類に加えて、出向契約の内容も確認されます。
これは、出向元企業と出向先企業の両方との関係性を考慮する必要があるためです。
〇確認書類の例
・健康保険証:
出向先企業で健康保険に加入していることが望ましいですが、出向元企業の健康保険証でも、出向契約の内容によっては認められる場合があります。
・出向契約書:
出向契約書は、常勤性を確認するための最も重要な書類です。
出向期間、給与支払、社会保険の適用、服務規律など、詳細な内容が確認されます。
・給与明細:
出向先企業から適切な給与が支払われていることを確認します。
出向元企業から給与が支払われている場合は、出向先企業がその費用を負担していることを示す書類(負担金請求書など)が必要になる場合があります。
・出向元企業の辞令、出向先企業の辞令:
出向の事実を確認します。
・その他、常勤性を証明できる書類:
必要に応じて、追加の書類を求められる場合があります。
出向契約書では、特に以下の点がチェックされます。
・出向期間:
長期間の出向であるか。
一時的な出向や短期間の出向の場合は、常勤性が認められない可能性があります。
・給与支払:
出向先企業から適切な給与が支払われているか。
出向元企業が給与を支払い、出向先企業がその一部または全部を負担する場合は、その負担割合や支払い方法が明確に定められている必要があります。
・社会保険:
原則として、出向先企業で社会保険に加入することが望ましいです。
出向元企業の社会保険を継続する場合は、その理由や出向契約の内容などを総合的に判断して、常勤性が認められるかどうかが決まります。
・服務規律:
出向先企業の指揮命令系統に従い、出向先企業の就業規則に基づいて勤務することが明記されている必要があります。
・人事権:
出向先企業が、出向者の人事考課や昇進・昇格などについて、一定の権限を持っていることが望ましいです。
これらの情報を総合的に判断して、常勤性が認められるかどうかが決まります。
出向契約の内容によっては、常勤性が認められない場合もあるため、注意が必要です。
3実務経験の落とし穴:認められる経験・認められない経験
一般建設業許可の専任技術者になるためには、国家資格がなくても、一定期間の実務経験があれば、資格要件を満たすことができます。
しかし、どんな業務経験でも認められるわけではありません。
ここでは、実務経験として認められるものと、認められないものについて、さらに詳しく解説します。
3-1. 実務経験として認められるもの:幅広い業務が対象
一般建設業許可の専任技術者に認められる実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験です。
これは、単に工事現場での作業だけでなく、建設工事に関わる幅広い業務が含まれます。
〇具体的な業務の例
工事現場での施工管理: 工程管理、品質管理、安全管理、原価管理など、工事が計画通り、安全かつ高品質に進むように管理する業務です。
・建設機械の操作:
クレーン、ショベルカー、ブルドーザーなど、建設機械を操作して、実際に工事を行う業務です。
・設計図書の作成:
建設工事に必要な設計図や施工図を作成する業務です。CADオペレーターとしての経験も含まれます。
・積算業務:
建設工事にかかる費用を詳細に計算する業務です。
・建設工事の発注にあたって、設計技術者として設計業務に従事した経験:
建設工事の注文者(発注者)の立場で、設計事務所などと協力して、建物の設計を行う業務です。
(現場監督の補助)
・大工工事、とび、土木工事などの作業員
これらの経験は、建設工事の請負人(元請、下請)としての立場で行った経験だけでなく、建設工事の注文者(発注者)としての立場で行った経験も含まれます。
また、アルバイトやパートとしての経験も、実務経験として認められる場合があります。
3-2. 実務経験として認められないもの:技術的要素が薄い業務は対象外
一方、以下のような経験は、実務経験として認められません。
・単なる雑用:
現場の片付け、清掃、資材の運搬など、技術的な要素が薄い業務は、実務経験として認められません。
・事務作業:
経理、庶務、人事、総務など、建設工事の施工に直接関係のない業務は、実務経験として認められません。
・資格が必要な業務を無資格で行った場合:
電気工事や消防施設工事など、特定の資格がないと従事できない業務を無資格で行った場合、その期間は実務経験として認められません。
・電気工事:
電気工事士法により、電気工事士の資格が必要です。
・消防施設工事:
消防法により、消防設備士の資格が必要です。
・解体工事の経験(一部例外あり):
建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、原則として「とび・土工工事業」の許可がある業者での経験、または建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」を行っている業者での経験でなければ、実務経験として認められません。
*ただし、平成28年5月31日までの、「とび・土工工事業許可」で請け負った解体工事業における実務経験の期間については、二重に計算することが認められ、重複して計算することができます。
3-3. 実務経験の期間計算:注意点と具体例
実務経験の期間計算には、いくつかの注意点があります。
・原則1業種のみ:
経験期間として認められるのは、原則として1業種のみです。
複数業種を経験していても、重複して計算することはできません。
例えば、管工事と電気工事の両方の経験がある場合でも、どちらか一方の業種の実務経験としてしか認められません。
・連続でなくてもOK:
経験期間は、連続している必要はありません。
複数の会社での経験や、ブランクがある場合でも、合計して要件を満たせば認められます。
例えば、A社で3年間、B社で2年間、C社で5年間、同じ業種の実務経験があれば、合計10年の実務経験として認められます。
・なお、指定学科卒業などの概要は、以下のとおりです。
詳細は、手引き等で確認願います。
〇指定学科卒業+実務経験
①大学卒業+3年以上の実務経験
②高等専門学校(高専)卒業+3年以上の実務経験
③専門学校卒業(高度専門士、専門士)+3年以上の実務経験
④専門学校卒業(上記以外)+5年以上の実務経験
⑤高等学校等卒業+5年以上の実務経験
⑥①~⑤以外の学歴の場合は、10年以上の実務経験
⑦複数業種について、一定期間以上の実務経験
*①~⑤は、いずれも指定学科を卒業していることが必要
*指定学科については、岩手県の「建設業許可申請の手引き」を参照のこと。
*学科名などは、各高校や大学によって異なるので、指定学科に該当するかどうか判断に困る場合は、事前に行政側に確認することが必要です。
3-4. 実務経験を証明する書類:何が必要?
実務経験を証明するためには、以下の書類が必要になります。
・実務経験証明書(指定様式):
経験した会社ごとに作成し、代表者印(または代表取締役印)を押印してもらう必要があります。
・工事請負契約書、注文書、請求書など:
実務経験証明書に記載した工事内容を裏付ける書類です。原本証明が必要です。
・その他:
場合によって、追加の書類を求められることがあります。
実務経験証明書は、各県によって様式が異なる場合があります。
必ず、申請する県の様式を使用してください。
4まとめ
出向社員の建設業許可における取り扱いや、実務経験の要件について解説しました。
建設業許可の取得・更新は、専門的な知識が必要なだけでなく、手続きも煩雑です。
「出向社員は経管・専技になれる?」「自分の実務経験は認められる?」など、疑問や不安があれば、お気軽に専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士藤井等事務所は、建設業許可の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
5お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ<許認可申請>






