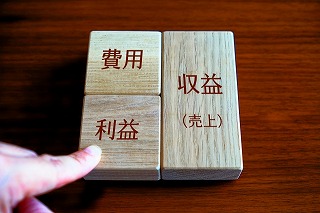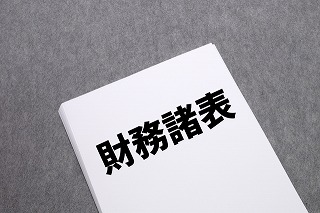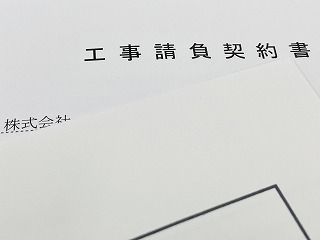「建設業許可の申請、自分でできる?」「経営経験がないと許可は取れないの?」「忙しくて手続きする時間がない…」こんな悩みはありませんか?ご安心ください。
今回の記事では、建設業許可の要件や、経営経験がない場合の対処法など、許可取得のポイントを詳しく解説します。
その悩みは今回の説明で解決できます。
岩手県で建設業許可取得をお考えの皆様、必見の内容です。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1建設業許可取得への道:あなたの会社は大丈夫?4つの必須要件を徹底解説!
岩手県で建設業を営む皆様、建設業許可は、事業拡大の大きな一歩となります。
しかし、許可を得るためには、いくつかの「関門」をクリアしなければなりません。
ここでは、その「関門」である4つの必須要件について、わかりやすく解説します。
1-1. 「経営のプロ」がいますか?:経営体制と適切な社会保険加入の重要性
まず、御社には「建設業の経営」を適切に行える体制が整っていますか?
具体的には、「経営業務の管理責任者」と呼ばれる、建設業の経営経験が豊富な人材が必要です。
さらに、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への適切な加入も義務付けられています。
これは、従業員の福利厚生を守り、安心して働ける環境を整えるためです。
〇経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の経営について総合的に管理する責任者のことです。
具体的には、以下のいずれかの経験が必要です。
・建設業を営む会社で役員として5年以上の経験
・建設業を個人事業主として5年以上営んだ経験
・建設業に関して、上記と同等以上の能力を有すると認められた者
(参考:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」、岩手県「建設業許可申請の手引き」)
1-2. 「技術のスペシャリスト」を確保!:専任技術者の配置
次に、各営業所には、許可を受けようとする建設業の種類に応じた「専任技術者」が必要です。
専任技術者は、工事の品質を確保するための、いわば「技術の番人」です。
国家資格保有者や、一定の実務経験を持つ者が該当します。
〇専任技術者になれる人
・許可を受けようとする建設業の種類に関する国家資格者(例:1級建築士、1級土木施工管理技士など)
・許可を受けようとする建設業の種類に関して、10年以上の実務経験がある者
・大学や高校で、許可を受けようとする建設業の種類に関する学科を卒業し、一定の実務経験がある者
1-3. 「正直さ」は信頼の証:誠実性の要件
当然のことですが、請負契約に関して、不正な行為や不誠実な行為をする恐れがない「誠実性」も求められます。
過去に不正行為を行った経歴があると、許可が下りない可能性があります。
1-4. お金の心配は無用?:財産的基礎の要件
最後に、請負契約をきちんと履行できるだけの「財産的基礎」も必要です。
具体的には、自己資本の額や資金調達能力などが審査されます。
〇財産的基礎の要件(一般建設業の場合)
・自己資本の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・直前5年間の許可実績があること
1-5. 許可を受けられないケースも…:欠格要件
上記の要件を満たしていても、建設業法に定められた「欠格要件」に該当する場合は、許可を受けられません。
例えば、破産者で復権を得ない者や、暴力団員などが該当します。
2経営経験ゼロからのスタート?!:起業家が直面する「経営業務の管理責任者」の壁
建設業許可の要件の中でも、特に起業家を悩ませるのが「経営業務の管理責任者」の要件です。
「サラリーマンを辞めて、すぐに建設会社を立ち上げたい!」と考えている方にとっては、大きなハードルとなります。
2-1. なぜ「経営経験」が必要なのか?
建設業は、一つのミスが大きな事故につながる可能性のある、責任の重い仕事です。
そのため、経営者には、単に技術力があるだけでなく、経営に関する知識や経験も求められます。
2-2. 経営業務の管理責任者になれる人の「方程式」
経営業務の管理責任者になれる人の要件は、以下の「方程式」で表すことができます。
◆経営業務の管理責任者(個人)=現在の地位+(過去の地位×経験)
-現在の地位: 常勤の取締役、個人事業主、支配人など
-過去の地位: 取締役、令3条使用人(支店長など)、個人事業主、支配人など
-経験: 建設業に関する5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
2-3. 具体例でチェック!:あなたの場合はどうなる?
例えば、あなたが長年建設会社で現場監督として働いてきたとします。
しかし、役員や事業主としての経験がない場合、残念ながら「経営業務の管理責任者」にはなれません。
3諦めるのはまだ早い!:起業直後でも建設業許可を取得する3つの方法
「経営経験がないから、建設業許可は無理…」と諦める必要はありません!
ここでは、起業直後でも建設業許可を取得するための3つの方法を紹介します。
3-1. 救世主を迎え入れる!:経験豊富な役員を招聘
最も確実な方法は、建設業の経営経験が豊富な方を「役員」として迎え入れることです。
例えば、長年建設会社を経営してきた方を常勤取締役に迎えれば、「経営業務の管理責任者」の要件を満たすことができます。
〇成功事例:Aさんのケース
-45歳のAさんは、長年大手ゼネコンで現場監督として働いてきましたが、経営経験はありませんでした。
-そこで、Aさんは、引退した建設会社の元社長Bさんを常勤取締役として迎え入れました。
-Aさんは専任技術者、Bさんは経営業務の管理責任者となり、無事に建設業許可を取得できました。
3-2. 「組織」としての経験を活かす:組織としての経営経験を証明
個人としての経営経験がなくても、「組織」としての経営経験を証明することで、経営業務の管理責任者の要件を満たせる場合があります(建設業法施行規則第7条第1号ロ)。
ただし、この方法は、証明が非常に複雑で、多くの書類が必要となります。
3-3. 奥の手!:500万円以上の資金調達能力を証明
一般建設業許可の場合、500万円以上の資金調達能力を証明できれば、財産的基礎の要件を満たすことができます。
金融機関からの融資証明書や、残高証明書などを提出します。
4難関突破の鍵:「部長」は経営業務の管理責任者になれるのか?
「部長」という役職は、会社によって位置づけが異なります。
ここでは、「部長」が経営業務の管理責任者として認められるための条件を解説します。
4-1. 「常勤役員等」とは?:国土交通省のガイドラインを読み解く
国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」によると、「常勤役員等」とは、具体的には以下の者を指します。
・業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)
・取締役(株式会社の取締役)
・執行役(指名委員会等設置会社の執行役)
・これらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事など)
4-2. 「準ずる者」として認めてもらうには?:膨大な書類が必要!
「部長」が「これらに準ずる者」として認められるためには、以下の点を証明する必要があります。
・部長の地位が、「業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位」にあること
・部長が「建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て、取締役会又は代表取締役から、具体的な権限移譲を受けた」こと
・これを証明するためには、組織図、業務分掌規程、定款、執行役員規程など、非常に多くの書類が必要となります。
4-3. 事前確認が重要!:役所の窓口で相談を
「部長」を経営業務の管理責任者として申請する場合は、事前に役所の窓口で相談することを強くおすすめします。
会社によって体制が異なり、必要な書類も変わってくるため、個別の確認が必要です。
5岩手県での建設業許可申請:地域特有の情報をチェック!
岩手県で建設業許可を申請する際には、以下の点に注意しましょう。
・申請窓口: 岩手県内の各地方振興局(土木担当の部局)
・申請書類: 岩手県のホームページからダウンロードできます。
・手数料: 新規申請の場合、9万円(岩手県収入証紙で納付)
6建設業許可取得後の注意点:許可を維持するために
建設業許可は、取得して終わりではありません。
許可を維持するためには、以下の点に注意しましょう。
・毎年の決算変更届の提出
・役員や専任技術者の変更があった場合の変更届の提出
・5年ごとの更新申請
これらの手続きを怠ると、許可が取り消される可能性があります。
7まとめ
建設業許可の取得、そして維持には、法律の規定や申請手続きなど、複雑で分かりにくい点が多々あります。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家である行政書士に相談することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という、ちょっとした相談だけでも構いません。
建設業許可取得を検討されている事業者様は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。
8お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ<許認可申請>