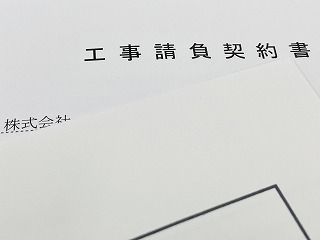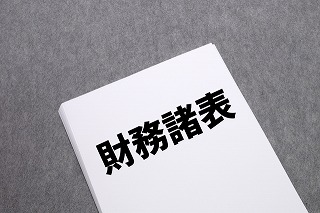「建設業許可に必要な専任技術者って、どんな資格が必要なの?」
「現場に出られないって本当?」
「ウチの社員は要件を満たしている?」
こんな疑問や不安はありませんか?
ご安心ください。
今回の記事では、建設業許可に不可欠な「専任技術者」について、資格要件や「専任」の意味、役割、そして経営業務の管理責任者との兼務についてなど、詳しく解説します。
この記事を読めば、専任技術者に関する疑問が解消され、許可取得への道筋が見えてきます。
岩手県で建設業許可取得・更新をお考えの皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1建設業許可に必須!「専任技術者」とは?
岩手県で建設業を営む皆様、建設業許可を取得・更新するためには、「営業所ごとに専任技術者を配置すること」が必須要件となっています。
ここでは、専任技術者の役割と、なぜ必要なのかをわかりやすく解説します。
1-1. 専任技術者って何をする人?
専任技術者とは、建設工事に関する専門知識を持ち、営業所において、請負契約の適正な締結や履行を確保する役割を担う技術者のことです。
具体的には、以下のような業務を行います。
・見積もり、入札、請負契約締結などの技術的サポート
・工法の検討、注文者への技術的な説明
・工事現場の技術者への指導監督
1-2. なぜ専任技術者が必要なの?
建設工事は、専門的な知識や技術が必要なだけでなく、一つのミスが大きな事故につながる可能性もある、責任の重い仕事です。
そのため、営業所ごとに専門知識を持った技術者を配置することで、工事の品質を確保し、安全性を高めることが求められています。
2これで安心!専任技術者の資格要件を徹底解説
専任技術者になるためには、一定の資格や実務経験が必要です。
ここでは、一般建設業許可と特定建設業許可の場合に分けて、資格要件を詳しく解説します。
2-1. 一般建設業許可の場合
一般建設業許可の場合、専任技術者になるための資格要件は、以下のいずれかを満たす必要があります。
(1)学校卒業+一定期間の実務経験
〇高校(指定学科)卒業後、5年以上の実務経験
〇大学(指定学科)卒業後、3年以上の実務経験
*指定学科の例
・土木工事:土木工学科、都市工学科、農業土木学科など
・建築工事:建築学科、都市工学科など
・電気工事:電気工学科、電気通信工学科など
・管工事:機械工学科、衛生工学科など
(2)10年以上の実務経験
(3)国家資格等の保有
*国家資格等の例
1級、2級建築施工管理技士
1級、2級土木施工管理技士
1級、2級電気工事施工管理技士
1級、2級管工事施工管理技士 など
2-2. 特定建設業許可の場合
特定建設業許可の場合は、一般建設業許可よりもさらに厳しい要件が求められます。
(1)1級の国家資格等の保有
*国家資格等の例
1級建築士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士 など
(2)一般建設業の要件+指導監督的実務経験
一般建設業の専任技術者の要件を満たした上で、さらに、元請として4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験が必要です。
*指導監督的実務経験とは?
建設工事の設計や施工の全般について、工事現場主任者や工事現場監督者といった立場で、技術面を総合的に指導監督した経験のことです。
(3)国土交通大臣が認定した者
*上記(1)または(2)と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が個別に認定した者については、
⇒指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)については、(1)の国家資格者、または、(3)の大臣認定者のみが特定建設業の専任技術者になれます。
(参考:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」、岩手県「建設業許可申請の手引き」)
3誤解しやすい!「専任」の意味と注意点
専任技術者の「専任」とは、どういう意味でしょうか?
ここでは、「専任」の意味と、よくある誤解について解説します。
3-1. 「専任」とは、その営業所に常勤すること
「専任」とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む)して、原則、その職務に専従することをいいます。
つまり、通常の勤務時間中は、その営業所に勤務している必要があります。
3-2. こんな場合は「専任」と認められない!
〇通勤不可能な場所に住んでいる場合
専任技術者の住所やテレワークを行う場所と、営業所の所在地が著しく離れていて、通勤が不可能な場合は、「専任」とは認められません。
〇他の法令で専任が求められている場合
他の法令で専任が求められている者(例:専任の宅地建物取引士、管理建築士など)は、原則として建設業の専任技術者にはなれません。
〇現場の主任技術者・監理技術者との兼務
原則として、専任技術者は、工事現場の主任技術者や監理技術者と兼務することはできません。
これは、専任技術者は営業所で職務を行う必要があり、営業所を離れて工事現場に出ることができないためです。
3-3. 例外的に兼務が認められるケースも
例外的に、以下の要件を全て満たす場合は、専任技術者が主任技術者を兼務できる場合があります。
・専任技術者が所属する営業所で契約した建設工事であること
・工事現場と営業所が近接しており、常時連絡が取れる体制にあること
・所属する営業所において、請負契約に係る建設工事の施工に従事していること。
・当該工事が、主任技術者の専任配置を要する工事(請負代金が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上))でないこと
*ただし、一部の自治体では、専任技術者が主任技術者になることを認めていない場合もあります。事前に確認が必要です。
(参考:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」、岩手県「建設業許可申請の手引き」
4専任技術者の役割:技術面から会社を支える!
専任技術者は、営業所において、どのような役割を担っているのでしょうか?
ここでは、専任技術者の具体的な役割について、さらに詳しく解説します。
4-1. 営業所の技術力を確保する:専門知識で契約をサポート
専任技術者は、許可を受けようとする建設業の種類に関する専門知識を持っています。
そのため、営業所においては、以下のような業務を通じて、契約の適正な締結をサポートします。
・工法の検討: どのような工法で工事を行うのが最適か、専門的な見地から検討します。
・技術的説明: 顧客(発注者)に対して、工事の内容や工法について、技術的な側面からわかりやすく説明します。
・見積り作成: 工事にかかる費用を正確に見積もります。専門知識がないと、適切な見積もりはできません。
・入札: 公共工事などの入札に参加する際、技術的な観点から、適切な入札価格を決定します。
・契約締結: 請負契約の内容が、技術的に見て適切かどうかを判断し、問題があれば指摘します。
これらの業務を通じて、専任技術者は、営業所が不適切な契約を結んでしまうリスクを減らし、会社の利益を守る役割を果たしています。
4-2. 工事現場の技術者を指導監督する:品質と安全を守る要
専任技術者は、工事現場に出る技術者に対して、建設工事の施工が適正に行われるよう、指導監督するという役割も担っています。
これは、工事の品質を確保し、安全性を高めるために、非常に重要な役割です。
具体的には、以下のような業務を行います。
・施工計画の確認: 工事が計画通りに進んでいるか、技術的な観点からチェックします。
・技術指導: 若手技術者などに対して、専門的な知識や技術を教え、指導します。
・問題解決: 工事現場で技術的な問題が発生した場合、解決策を提案し、対応します。
・安全管理: 工事が安全に行われるよう、安全管理に関する指導や監督を行います。
・品質管理: 工事の品質が基準を満たしているかを確認し、必要に応じて改善策を指示します。
専任技術者は、現場の技術者と密接に連携し、工事が円滑に進むよう、技術面からサポートします。
いわば、現場の「技術の番人」とも言える存在です。
4-3. 技術情報の収集・分析:最新技術のキャッチアップ
建設業界は、技術革新が日進月歩で進んでいます。
専任技術者は、常に最新の技術情報を収集し、分析する役割も担っています。
・講習会やセミナーへの参加
・インターネットでの情報収集
・他社との情報交換
これらの活動を通じて得られた情報は、社内で共有され、技術力の向上に役立てられます。
4-4. 社内教育・研修の実施:技術力の底上げ
専任技術者は、社内の技術者に対して、教育や研修を行うこともあります。
・新人教育、技術研修、安全教育
これらの活動を通じて、会社全体の技術力の底上げを図ります。
5気になる疑問を解決!:経営業務の管理責任者との兼務は可能?
「経営業務の管理責任者と専任技術者は、同じ人が兼務できるの?」
ここでは、このよくある質問について解説します。
5-1. 兼務できる条件は?
結論から言うと、経営業務の管理責任者と専任技術者は、一定の条件を満たせば兼務できます。
その条件とは、以下の2つです。
どちらも同じ営業所に「常勤」していること
経営業務の管理責任者としての要件、専任技術者としての要件を、それぞれ満たしていること
5-2. 「常勤」ってどういうこと?
「常勤」とは、原則として、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している状態をいいます。
そのため、複数の会社に所属し、いずれも常勤であるという状態は認められません。
5-3. 常勤性の確認方法は?
常勤であることの確認は、以下のような方法で行われます。
・健康保険証:建設業許可を申請する会社で健康保険に加入しているか。
・役員報酬:常勤に相応した役員報酬が支払われているか。
・住所:営業所と住所が、毎日通勤できる距離にあるか。
これらの確認方法は、許可を出す行政によって異なる場合があります。
5-4. 兼務が認められないケース
例えば、ある人が、A社の常勤の代表取締役であり、かつB社の常勤の取締役である、というケースは認められません。
しかし、片方が非常勤の取締役であれば、もう片方が常勤であることは認められます。
5-5. 同一営業所内でのみ兼務可能
経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務は、同一営業所内でのみ可能です。
例えば、本店で経営業務の管理責任者になっている人が、本店の専任技術者を兼務することはできますが、支店の専任技術者を兼務することはできません。
6営業所ごとに専任が必須!複数営業所がある場合は?
建設業を営む営業所が複数ある場合は、それぞれの営業所ごとに、専任技術者を配置する必要があります。
ここでは、複数営業所がある場合の注意点について解説します。
6-1. 営業所ごとに専任技術者が必要
本店(主たる営業所)だけでなく、支店(従たる営業所)など、複数の営業所がある場合は、それぞれの営業所ごとに、専任技術者を配置する必要があります。
また、複数の業種の許可を受ける場合は、それぞれの業種ごとに専任技術者が必要です。
6-2. 営業所間の兼務はできない
専任技術者は、所属する営業所に常勤し、専らその職務に従事する必要があるため、他の営業所の専任技術者を兼務することはできません。
6-3. 専任技術者の情報はデータベースで管理
専任技術者は、どの営業所に配置されているか、行政側のデータベースでしっかり管理されています。
そのため、ごまかすことはできません。配置された営業所が変更になる場合は、建設業法で定められた変更の手続きが必要になります。
7経営業務の管理責任者と専任技術者になれる人とは?
最後に、経営業務の管理責任者と専任技術者になれる人について、改めて整理しておきましょう。
7-1. 経営業務の管理責任者になれる人
経営業務の管理責任者になるためには、役員(個人の場合は、本人または支配人)であることが条件になります。
「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、商業登記の有無を基準にして判断されます。
7-2. 専任技術者になれる人
一方、専任技術者は、その営業所に常勤で、一定の資格や実務経験があれば、役員でも従業員でもなることができます。
専任技術者は、経営業務の管理責任者のように、地位(役職)は求められていません。
7-3. 役員は両方になれる可能性がある
役員という地位は、経営業務の管理責任者としても、専任技術者としても認められます。
つまり、本店(主たる営業所)に常勤する役員が、経営業務の管理責任者の要件も満たし、一定の国家資格を有していて、専任技術者の要件も満たしている場合は、経営業務の管理責任者にも、専任技術者にも、両方なれる、ということになります。
そして、兼務が可能であるということは、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」(第5条、第6条関係)にも、記載されています。
ただし、兼務ができるのは、営業所が同一の場合だけです。
本店で経営業務の管理責任者となっていれば、本店の専任技術者を兼務することはできますが、常勤性の問題から、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
8まとめ
建設業許可の取得・更新に不可欠な「専任技術者」について、その要件や役割、よくある疑問について解説しました。
専任技術者の選任は、許可取得の重要なポイントであると同時に、建設業を営む上で、技術的な信頼性を確保するための要でもあります。
建設業許可の取得・更新は、事業の発展に欠かせない重要な手続きです。
しかし、法改正や制度の複雑さから、「難しそう…」「面倒…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
行政書士藤井等事務所は、建設業許可の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
9お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ<許認可申請>