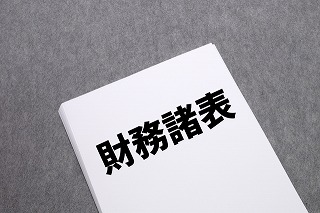.jpg)
建設業許可の取得・更新を検討中の皆様、こんなお悩みはありませんか?
「財産的基礎ってどうやって証明するの?」「うちの財務状況で許可は下りるのか不安…」
こうした疑問や不安は、適切な準備と知識で解消できます。
この記事では、建設業許可における「財産的基礎等」の要件について、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、許可申請の準備がスムーズに進み、安心して建設業に専念できるでしょう。
岩手県(北上市など)や宮城県(仙台市)の建設業者の皆様、ぜひ参考にしてください。
1建設業許可における「財産的基礎等」とは?
建設業許可の要件の一つである「財産的基礎等」とは、事業者が建設業を営む上で必要となる資金力や信用力を示すものです。
具体的には、自己資本の額や資金調達能力などが審査されます。
この要件が設けられているのは、建設工事には資材の購入や人件費など多額の費用がかかるため、事業者が安定して工事を遂行できるかどうかを判断する必要があるからです。
1-1財産的基礎等が重視される背景
建設業は、他の産業と比較して、工事の規模が大きく、工期も長期にわたることが多いため、安定した経営基盤が求められます。
もし、資金繰りが悪化し、工事が中断したり、下請業者への支払いが滞ったりすれば、発注者や社会全体に大きな影響を与えかねません。
そのため、建設業法では、許可要件の一つとして、財産的基礎等を厳しく審査しています。
1-2一般建設業許可の場合
以下の「いずれか」に該当する必要があります。
①自己資本の額が500万円以上であること
・自己資本とは、企業の純資産のことで、貸借対照表の純資産の部に計上されている金額を指します。
・具体的には、資本金、資本剰余金、利益剰余金などの合計額です。
・自己資本が500万円以上あることで、事業者が一定の自己資金を持っていることを示し、経営の安定性が認められます。
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
・資金調達能力とは、金融機関などから融資を受けられる能力のことです。
・具体的には、預金残高証明書や融資証明書などで証明します。
・自己資本が不足している場合でも、必要な時に資金を調達できる能力があれば、財産的基礎があると認められます。
③許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
・過去5年間、継続して建設業を営んできた実績があれば、一定の経営基盤があると認め・られます。
・この場合、毎年の決算書や工事実績報告書などで証明します。
1-3特定建設業許可の場合
以下の『すべて』に該当する必要があります。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・欠損とは、企業の累積赤字のことで、繰越利益剰余金の負の額を指します。
・欠損が資本金の20%を超えている場合、経営状態が著しく悪化していると判断されます。
②流動比率が75%以上であること
・流動比率とは、企業の短期的な支払い能力を示す指標で、流動資産を流動負債で割って算出します。
・流動比率が75%以上であれば、短期的な支払い能力が高いと判断されます。
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
・特定建設業許可は、大規模な工事を請け負うために必要な許可であるため、一般建設業許可よりも高い資本金と自己資本が求められます。
ここで、各専門用語を、以下のとおり説明します。
・自己資本:
法人の場合は貸借対照表の純資産合計、個人の場合は事業主資本に負債の部の利益留保性引当金・準備金を加えた額。
・500万円以上の資金を調達する能力:
金融機関からの融資証明などで証明します。
・欠損の額:
法人の場合は繰越利益剰余金の負の額が資本剰余金などを上回る額、個人の場合は事業主損失が事業主借などを上回る額。
・流動比率:
流動資産÷流動負債×100で算出。
・資本金:
法人は払込資本金や出資金、個人は期首資本金。
参考として、具体的なイメージが分かるよう事例紹介をします。
事例1:自己資本が500万円未満のA社は、金融機関から500万円の融資証明を取得し、一般建設業許可を取得しました。
事例2:資本金3,000万円のB社は、欠損額が500万円であったため、特定建設業許可の要件を満たすことができませんでした。
事例3:設立3年目の個人事業主Cさんは、過去3年間の確定申告書を提出し、一般建設業許可を取得しました。
2財産的基礎等の確認タイミング
財産的基礎等は、許可申請時(新規、更新、業種追加など)の直近の決算書で確認されます。
決算ごとに確認されるわけではありません。
2-1確認のタイミング
・新規許可申請時:新たに建設業許可を取得する場合
・更新許可申請時:建設業許可の有効期間が満了し、更新する場合
・業種追加許可申請時:既に取得している建設業許可に、新しい業種を追加する場合
2-2決算書の重要性
財産的基礎等の確認は、直近の決算書に基づいて行われます。
そのため、日頃から正確な会計処理を行い、適切な決算書を作成しておくことが重要です。
2-3特定建設業許可の注意点
特定建設業許可を持つ事業者が業績悪化で要件を満たさなくなった場合でも、すぐに許可が取り消されるわけではありません。
ただし、次回の更新時には要件を満たす必要があるので、注意が必要です。
2-4一般建設業許可への変更
もし、特定建設業許可の更新が難しい場合は、事前に一般建設業許可への変更を検討する必要があります。
一般建設業許可の場合は、過去5年間の継続営業実績があれば、その後は財産的基礎等の確認は基本的に行われません。
参考として、具体的なイメージが分かるよう事例紹介をします。
・事例1:特定建設業許可を持つD社は、業績悪化により直近の決算で流動比率が70%に低下しました。しかし、許可の有効期間内であったため、すぐに許可が取り消されることはありませんでした。
・事例2:一般建設業許可を持つE社は、設立から6年目を迎えました。過去5年間の継続営業実績があるため、更新時には財産的基礎等の確認は行われませんでした。
3財産的基礎等の確認方法
財産的基礎等は、主に財務諸表によって確認されます。
設立間もない企業の場合は、創業時の財務諸表が判断材料となります。
特定建設業許可の場合、資本金が不足している場合は、増資によって要件を満たすことが可能です。
3-1確認に必要な書類
・財務諸表:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など
・納税証明書:法人税、消費税などの納税状況を証明する書類
・登記簿謄本:法人の基本情報を証明する書類
・預金残高証明書:金融機関の預金残高を証明する書類
・融資証明書:金融機関からの融資可能額を証明する書類
3-2財務諸表の確認ポイント
・貸借対照表:純資産額、流動資産、流動負債などを確認します。
・損益計算書:利益額、売上高などを確認します。
・株主資本等変動計算書:資本金の増減、利益剰余金の変動などを確認します。
3-3設立間もない企業の確認方法
設立間もない企業の場合は、創業時の貸借対照表や事業計画書などが確認されます。
これらの書類に基づいて、事業の実現可能性や資金調達能力が審査されます。
3-4増資による対応
特定建設業許可の資本金要件を満たしていない場合は、増資によって対応することが可能です。
増資を行うことで、資本金の額を増やし、要件を満たすことができます。
事例紹介
・事例1:特定建設業許可の取得を目指すF社は、資本金が1,500万円であったため、500万円の増資を行い、要件を満たしました。
・事例2:設立2年目のG社は、創業時の貸借対照表と事業計画書を提出し、一般建設業許可を取得しました。
3-5専門家による確認の重要性
財務諸表の確認は、専門的な知識が必要となる場合があります。
不安な場合は、税理士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
4建設業許可申請をスムーズに進めるためのポイント
4-1早めの準備・相談など
以下の項目について、事前に準備しておく必要があります。
・早めの準備:
許可申請には時間がかかるため、余裕をもって準備を始めましょう。
特に、決算時期と重なる場合は、早めに準備を始めることが重要です。
・専門家への相談:
行政書士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
専門家は、申請書類の作成だけでなく、必要書類の収集や提出、許可要件に関するアドバイスなども行ってくれます。
・財務状況の把握:
日頃から自社の財務状況を把握し、改善に努めましょう。
定期的に財務諸表を作成し、経営状況を分析することで、問題点を早期に発見し、対策を講じることができます。
・必要書類の準備:
財務諸表、納税証明書、登記簿謄本など、必要な書類を漏れなく準備しましょう。
書類に不備があると、申請が遅れたり、許可が下りなかったりする場合があります。
4-2建設業許可に関する最新情報
国土交通省や岩手県のホームページでは、建設業許可に関する最新情報や申請手続きの手引きが公開されています。
これらの情報を参考に、正確な情報を収集しましょう。
〇国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」
〇岩手県「建設業許可申請の手引き」
〇宮城県「建設業の手引き」
4-3その他、確認する点
・経営業務の管理責任者等の確認
許可を受けるためには、経営業務の管理責任者や専任技術者などの人的要件も満たす必要があります。
・欠格要件の確認
過去に建設業法違反などで処分を受けた場合など、許可を受けられない場合があります。
・添付書類の確認
申請書類に添付する書類は、申請内容によって異なります。
事前に必要な書類を確認し、準備しましょう。
5まとめ
建設業許可の取得・更新は、事業の発展に欠かせない重要な手続きです。
しかし、法改正や制度の複雑さから、「難しそう…」「面倒…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
行政書士藤井等事務所は、建設業許可の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に依頼した方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1)お問い合わせフォーム
(2)事務所ホームページ<許認可申請>