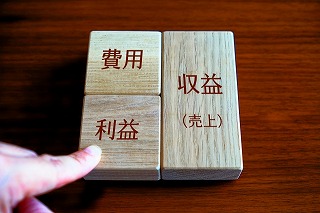こんな悩みはありませんか?
〇「建設業許可を取りたいけど、何から手をつければいいか分からない…」
〇「更新期限が迫っているけど、手続きが面倒で後回しにしてしまっている…」
〇「自分で申請しようとしたけど、書類の多さに挫折しそう…」
ご安心ください!これらの悩みは、今回の記事で全て解決できます。
建設業許可の取得・更新は、専門的な知識が必要で、手続きも煩雑。
しかし、この記事では、建設業許可に関するあらゆる情報を、行政書士が分かりやすく解説します。
今回は、建設業許可に関する、あなたのお困りごとを解決し、スムーズな事業運営をサポートする内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
1 建設業許可とは?~あなたの事業に必要な理由~
(1) 建設業許可の必要性
建設業を営む上で、なぜ建設業許可が必要なのでしょうか?
それは、建設工事が国民の生活や安全に深く関わる重要な産業であるため、一定の品質を確保し、不良・欠陥工事を防ぐ必要があるからです。
建設業許可制度は、建設業者の技術力や経営能力を審査し、適格な業者を選別することで、発注者を保護し、建設業界全体の健全な発展を図ることを目的としています。
① 許可が必要となる工事の規模
建設業許可が必要となるのは、「軽微な工事」を除く全ての建設工事です。この「軽微な工事」の定義を理解することが、許可の要否を判断する上で非常に重要になります。
② 軽微な工事の定義
建設業法では、「軽微な工事」を以下のように定めています。
〇 建築一式工事以外の場合:
工事1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
この金額には、材料費や運搬費など、工事に必要な全ての費用が含まれます。
〇 建築一式工事の場合:
・工事1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事
・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
-「木造住宅」とは、主要構造部が木造である住宅を指します。
-「延べ面積」とは、各階の床面積の合計を指します。
③ 請負代金の考え方
請負代金の計算においては、契約書に記載された金額だけでなく、以下の点に注意が必要です。
・材料費の扱い:
発注者から材料が提供される場合(施主支給): 提供された材料の市場価格(通常の取引価格)を請負代金に加算します。
・材料の運送費:
発注者が材料を運搬し、その費用を負担する場合、その運送費も請負代金に加算します。
・機械器具設置工事における機械器具の扱い:
機械器具設置工事(例: エレベーター設置工事、昇降機設置工事、プラント設備工事など)では、機械器具の価格も請負代金に含めて計算します。
これは、機械器具が工事の目的物そのものであり、材料と同様に扱われるためです。
・元請業者から貸与された建設機械の扱い:
下請業者が元請業者から建設機械(例: 油圧ショベル、クレーンなど)を借りて工事を行う場合、その建設機械の費用は請負代金に含める必要はありません。
これは、建設機械が工事の目的物ではなく、あくまで工事を施工するための道具であるためです。
-具体例-外壁塗装工事:
あなたが外壁塗装業者だとします。発注者から塗料を提供され、その塗料を使って外壁塗装を行う場合、塗料の市場価格を請負代金に含めて計算します。
塗料代を含めた請負代金が500万円以上になる場合は、建設業許可(塗装工事業)が必要です。
-具体例ーエレベーター設置工事:
エレベーターの設置工事を請け負う場合、エレベーター本体の価格を請負代金に含めて計算します。
エレベーター本体の価格を含めた請負代金が500万円以上になる場合は、建設業許可(機械器具設置工事業)が必要です。
(2) 建設業許可が不要なケース
上記で説明した「軽微な工事」に該当する場合以外にも、建設業許可が不要となるケースがあります。
①自社で建物を建設する場合:
建設業者自身が、自社で使用する建物を自ら建設する場合(自社施工)は、建設業許可は不要です。
ただし、建設した建物を第三者に販売・賃貸する場合は、建設業許可が必要となる場合があります。
②下請としてのみ工事を行う場合:
元請業者から工事の一部を下請として請け負う場合、下請金額が軽微な工事の範囲内であれば、建設業許可は不要です。
ただし、下請業者であっても、特定建設業の許可が必要となる場合があります(詳細は後述)。
2 建設業許可の種類~大臣許可と知事許可の違い~
建設業許可には、「国土交通大臣許可(大臣許可)」と「都道府県知事許可(知事許可)」の2種類があります。
この区分は、建設業を営む営業所の所在地によって決まります。
(1) 大臣許可と知事許可の区分
・国土交通大臣許可(大臣許可):
営業所が2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合に必要となります。
例えば、本社が岩手県にあり、支店が宮城県にある場合は、大臣許可が必要です。
・都道府県知事許可(知事許可):
営業所が1つの都道府県内にのみ存在する場合に必要となります。
例えば、本社と営業所が岩手県内にのみある場合は、岩手県知事許可が必要です。
(2) 営業所の定義
ここで重要なのが、「営業所」の定義です。建設業法上の「営業所」とは、単なる事務所や出張所のことではありません。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。
① 常時請負契約を締結する事務所とは
「常時請負契約を締結する事務所」とは、以下のいずれかの行為を行う事務所を指します。
・請負契約の見積もり: 工事の見積書を作成し、発注者に提示する。
・入札: 公共工事などの入札に参加する。
・契約締結: 請負契約書に署名・押印し、契約を締結する。
これらの行為を、継続的に(一時的ではなく)行う事務所が「営業所」となります。
② 営業所の注意点
・契約書の名義人: 契約書の名義人が、その事務所の代表者である必要はありません。
・営業所の届出: 建設業許可の申請時に、営業所として届け出る必要があります。
営業所以外での契約締結: 建設業許可を受けた営業所以外の場所で、請負契約を締結することはできません。
(3) 知事許可でも県外工事は可能か
「岩手県知事許可」を取得した建設業者が、宮城県や青森県など、他の都道府県で工事を行うことはできるのでしょうか?
結論から言うと、可能です。
建設業許可は、工事を行う場所を制限するものではありません。
知事許可であっても、大臣許可であっても、全国どこでも建設工事を行うことができます。
ただし、注意しなければならないのは、「請負契約」を締結する場所です。
請負契約は、建設業許可を受けた「営業所」で行う必要があります。
例えば、岩手県知事許可の建設業者が宮城県で工事を行う場合、以下のいずれかの方法で契約を締結する必要があります。
-岩手県内の営業所で、宮城県の工事の請負契約を締結
-宮城県に営業所を設置し、大臣許可を取得
(4) 大臣許可と知事許可のどちらを選ぶべきか
大臣許可と知事許可のどちらを選ぶべきかは、事業の規模や将来の展望によって異なります。
・小規模事業者で、当面は県内でのみ事業を行う場合: 知事許可で十分です。
・将来的に県外にも営業所を設置する可能性がある場合: 最初から大臣許可を取得しておくことも検討できます。
・既に複数の都道府県に営業所がある場合: 大臣許可が必要です。
3 建設業法上の「営業所」とは?~契約締結の重要拠点~
建設業法における「営業所」の定義は、一般的にイメージする「営業所」とは異なる場合があります。
ここでは、建設業法上の「営業所」について、さらに詳しく解説します。
(1) 営業所の役割
建設業法上の「営業所」は、単に事務作業を行う場所ではなく、建設工事の請負契約に関する重要な拠点となります。
具体的には、以下の役割を担います。
・見積もり: 工事の見積書を作成し、発注者に提示します。
・入札: 公共工事などの入札に参加します。
・契約締結: 請負契約書に署名・押印し、契約を締結します。
・技術的な指導監督:
本店または支店が、他の営業所に対して、請負契約に関する技術的な指導監督を行う場合、その本店または支店も「営業所」に該当します。
これは、本店または支店が、建設業の営業に実質的に関与しているとみなされるためです。
(2) 営業所に該当しない事務所
以下の事務所は、建設業法上の「営業所」には該当しません。
・単なる連絡所: 連絡業務のみを行う事務所
・資材置き場: 資材や建設機械を保管する場所
・作業員宿舎: 作業員が寝泊まりする場所
・工事現場の仮設事務所: 工事期間中のみ設置される仮設の事務所
これらの事務所は、建設工事の請負契約に関する実質的な行為を行わないため、「営業所」とはみなされません。
(3) 営業所の届出
建設業許可を申請する際には、営業所として届け出る必要があります。届出をしていない事務所では、請負契約の見積もり、入札、契約締結などの行為を行うことはできません。
(4) 営業所の実態確認
建設業許可の審査においては、申請された営業所が、実際に建設業法上の「営業所」としての実態を備えているかどうかが確認されます。
・事務所の設備: 事務机、電話、FAX、パソコン、コピー機など、事務作業に必要な設備が整っているか。
・契約関係書類の保管: 請負契約書、見積書、請求書などの契約関係書類が適切に保管されているか。
・常勤の従業員: 営業所に常勤の従業員がいるか。
これらの点について、実地調査や書類審査が行われることがあります。
(5) 営業所の変更
営業所の所在地や名称を変更した場合、または営業所を廃止した場合は、変更後30日以内に変更届を提出する必要があります。
4 建設業許可取得のメリット~信頼と事業拡大のチャンス~
建設業許可を取得することには、多くのメリットがあります。
ここでは、主なメリットを具体的に解説します。
(1) 社会的信用度の向上
建設業許可を取得しているということは、建設業法に基づき、一定の基準を満たした事業者であることの証明となります。
・発注者からの信頼:
許可業者であることは、技術力、経営能力、財務状況などについて、一定の審査をクリアしていることを意味します。
発注者は、安心して工事を依頼することができます。
特に、公共工事や大規模な民間工事では、許可業者であることが入札参加の条件となることが多くあります。
・金融機関からの信頼:
融資を受ける際、許可業者であることは、返済能力があると判断されるためのプラス材料となります。
無許可業者に比べて、融資を受けやすくなる可能性があります。
・取引先からの信頼:
資材の仕入れ先や協力業者など、取引先からの信頼も高まります。
より良い条件で取引ができる可能性があります。
(2) 大規模工事への参入
建設業許可を取得することで、請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うことができるようになります。
・事業規模の拡大:
より大規模な工事を受注できるようになり、売上アップにつながります。
事業の成長を加速させることができます。
・新たなビジネスチャンス:
これまで参入できなかった分野の工事に挑戦できるようになります。
新たな顧客を獲得する機会が増えます。
(3) 法令遵守(コンプライアンス)
建設業許可を取得し、建設業法を遵守することは、企業の社会的責任を果たす上で非常に重要です。
・適正な経営:
建設業法に基づく許可制度は、建設業界の健全な発展を目的としています。
許可を取得し、法令を遵守することで、適正な経営を行うことができます。
・トラブルの防止:
建設業法には、請負契約に関するルールや、下請業者保護のための規定などが定められています。
これらのルールを守ることで、発注者や下請業者とのトラブルを未然に防ぐことができます。
・企業イメージの向上:
法令遵守は、企業の社会的評価を高めます。
顧客や取引先からの信頼を得る上で、非常に重要な要素となります。
(4) 特定建設業許可の取得
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。
・特定建設業許可:
発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる場合に必要となる許可です。
特定建設業許可を取得することで、より大規模な工事を下請に出すことができるようになります。
ただし、特定建設業許可は、一般建設業許可よりも厳しい要件が課せられます。
(5)その他のメリット
・経営事項審査(経審)の受審:
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査(経審)を受ける必要があります。
建設業許可を取得していることが、経審を受けるための前提条件となります。
・建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録:
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、建設技能者の資格や就業履歴などを登録・管理するシステムです。
建設業許可を取得していることが、CCUSに登録するための要件の一つとなっています。
5 建設業許可取得のステップ~行政書士がサポートします~
建設業許可を取得するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。
ここでは、具体的な手順と、行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
(1) 許可要件の確認
まず、自社(または個人)が建設業許可の要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。
主な要件は以下の通りです。
① 経営業務の管理責任者(経管)の設置:
建設業の経営業務について、一定期間(原則5年以上)の経験を持つ者を、常勤役員等として配置する必要があります。
経管は、建設業の経営に関する知識や経験が豊富であることが求められます。
② 専任技術者(専技)の設置:
許可を受けようとする建設業の種類ごとに、一定の資格または実務経験を持つ技術者を、営業所ごとに専任で配置する必要があります。
専技は、工事の施工に関する技術的な知識や経験が豊富であることが求められます。
③ 財産的基礎:
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有している必要があります。
具体的には、自己資本の額や、営業実績などが審査されます。
④ 欠格要件に該当しないこと:
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、暴力団員など、一定の欠格要件に該当しないことが必要です。
これらの要件は、許可の種類(一般建設業許可または特定建設業許可)や、建設業の種類(例: 土木工事業、建築工事業、電気工事業など)によって異なる場合があります。
(2) 必要書類の準備
許可要件を満たしていることが確認できたら、次は申請に必要な書類を準備します。
必要な書類は多岐にわたりますが、主なものは以下の通りです。
・建設業許可申請書:
所定の様式に、必要事項を記入します。
・添付書類:
経営業務の管理責任者に関する書類: 履歴書、住民票、経験を証明する書類(例: 過去の工事請負契約書、注文書など)
専任技術者に関する書類: 資格証明書(例: 1級建築士、1級土木施工管理技士など)、実務経験証明書
・財務諸表:
直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など)
・営業所の写真:
営業所の外観、内部の写真
・その他:
納税証明書、登記簿謄本(法人の場合)、住民票(個人の場合)など
これらの書類は、県によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
(3) 申請書の作成
必要書類が揃ったら、建設業許可申請書を作成します。申請書は、所定の様式に正確に記入する必要があります。
〇記載事項:
申請者の基本情報(商号または名称、所在地、代表者氏名など)
営業所の情報(名称、所在地、電話番号など)
許可を受けようとする建設業の種類
経営業務の管理責任者、専任技術者の氏名、資格など
その他、必要な事項
申請書の作成は、記入漏れや誤りがないように注意が必要です。
(4) 申請
申請書と添付書類が完成したら、管轄の行政庁に申請します。
・申請先:
大臣許可の場合: 本店所在地を管轄する地方整備局
知事許可の場合: 本店所在地を管轄する都道府県庁
・申請方法:
窓口に直接持参、郵送、オンライン申請
申請の際には、手数料(収入印紙または現金)が必要となります。
(5) 審査
申請が受理されると、行政側による審査が行われます。
・審査内容:
申請書類の内容が、許可要件を満たしているかどうかが審査されます。
必要に応じて、追加の書類提出などが行われます。
・審査期間:
審査期間は、都道府県によって異なりますが、通常は1ヶ月前後が目安です。
(6) 許可取得
審査を通過すると、建設業許可が取得できます。
・許可証の交付:
許可証が交付されます。
許可証には、許可番号、許可年月日、許可の有効期間、許可を受けた建設業の種類などが記載されています。
・許可の有効期間:
建設業許可の有効期間は、5年間です。
有効期間が満了する前に、更新手続きを行う必要があります。
(7) 行政書士に依頼するメリット(詳細)
建設業許可の申請は、専門的な知識が必要で、書類の作成も煩雑です。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
・時間と労力の節約:
煩雑な書類収集・作成、申請手続きを代行してもらうことで、本業に集中することができます。
特に、建設業の経営者は多忙なことが多いため、時間と労力の節約は大きなメリットとなります。
・正確な申請:
建設業許可に関する専門知識を持つ行政書士が、不備のない申請書類を作成します。
申請書類の不備による再提出や、審査の遅延を防ぐことができます。
・スムーズな許可取得:
行政書士は、許可取得までの流れを熟知しているため、スムーズな許可取得をサポートします。
許可取得までの期間を短縮できる可能性があります。
・許可後のサポート:
許可取得後の変更届(例: 営業所の所在地変更、役員の変更など)や、更新手続きもサポートします。
建設業法に関する相談にも応じます。
・法改正への対応:
建設業法は、改正されることがあります。
行政書士は、最新の法改正情報にも精通しているため、適切なアドバイスを受けることができます。
6 岩手県北上市で建設業許可なら、行政書士藤井等事務所へ!
当事務所は、岩手県北上市を中心に、建設業許可の取得・更新をサポートしています。
(1) 当事務所の強み(詳細)
・地域密着:
北上市、花巻市、奥州市、遠野市、金ケ崎町など、岩手県内の建設業者様を強力にサポートします。
地域の建設業界の事情に精通しており、地域に根ざしたサービスを提供します。
・豊富な経験:
建設業許可に関する豊富な知識と経験があります。
様々なケースの申請実績があり、お客様の状況に応じた最適なサポートを提供します。
・丁寧な対応:
お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、分かりやすく説明します。
疑問や不安に寄り添い、安心して手続きを進められるようサポートします。
・初回相談無料:
まずはお気軽にご相談ください。
相談内容に応じて、費用や手続きの流れなどを具体的に説明します。
・ワンストップサービス:
建設業許可だけでなく、会社設立、融資、補助金申請など、建設業に関する様々な手続きをサポートします。
・迅速な対応:
迅速な対応を心がけ、お客様のビジネスをスムーズに進めるお手伝いをします。
(2) 当事務所のサービス内容
・建設業許可申請(新規・更新・業種追加)
・変更届(役員変更、営業所変更など)
・経営事項審査(経審)申請
・建設キャリアアップシステム(CCUS)登録
・その他、建設業に関する各種手続き
7 まとめ
建設業許可は、建設業を営む上で非常に重要な許可であり、その取得は事業の信頼性を高め、ビジネスチャンスを広げる上で不可欠です。
しかし、建設業許可の申請手続きは複雑で、専門的な知識が求められ、多くの書類を準備や正確に申請書を作成するなど、行政の審査を通過しなければなりません。
ご自身でこれらの手続きを行うことも可能ですが、多くの時間と労力を費やすことになり、不備があれば再提出や審査の遅延につながる可能性もあります。
建設業の経営者にとって、本業に集中する時間を確保することは非常に重要です。
そこで、当事務所は、建設業許可の専門家として、皆様の許可取得を全力でサポートいたします。
豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案し、スムーズな許可取得を実現します。
「許可が取れるかどうか不安」「何から手をつければいいか分からない」「忙しくて手続きをする時間がない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回相談は無料です。
お客様の疑問や不安を解消し、安心して許可取得を進めていただけるよう、丁寧にご説明いたします。
建設業許可の取得は、あなたのビジネスの新たな一歩を踏み出すための重要なステップです。
当事務所においては、その一歩を共に歩み、あなたのビジネスの発展を全力でサポートいたします。
8 問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ<許認可申請>