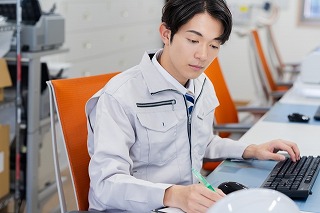「建設業許可の廃業手続きってどうすればいい?」
「テレワークでも常勤と認められる?」
「事業承継で許可を引き継ぐには?」
「廃業と行政処分による取消しの違いは?」
こんなお悩みや疑問はありませんか?
ご安心ください。
今回の記事では、建設業許可の廃業手続き、テレワークと常勤性の関係、事業承継(M&A、相続)における許可の承継、廃業と行政処分による取消しの違い、許可の有効期限と更新手続きなど、建設業許可に関する様々な疑問を徹底解説します。
この記事を読めば、建設業許可に関する手続きや注意点が理解でき、将来の事業展開を見据えた適切な対応が可能になります。
岩手県、宮城県(仙台市含む)で建設業を営む皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1建設業許可の「廃業」:手続きと注意点
建設業許可を取得した事業者が、事業をやめる場合や、許可が不要になった場合には、「廃業」の手続きが必要になります。
ここでは、建設業許可の廃業手続きと、その際の注意点について解説します。
1-1. 廃業届が必要なケース:7つのケースをチェック!
以下のいずれかに該当する場合は、建設業許可の廃業届を提出する必要があります。
(1)個人事業主の死亡:
建設業許可を受けていた個人事業主が亡くなった場合。
(2)法人の合併による消滅:
建設業許可を受けていた法人が、合併により消滅した場合。
(3)法人の破産手続開始決定:
建設業許可を受けていた法人が、破産手続開始決定により解散した場合。
(4)法人の解散(上記2,3以外):
建設業許可を受けていた法人が、株主総会の決議などにより解散した場合(合併、破産以外)。
(5)建設業許可の要件を満たさなくなった場合:
例えば、経営業務の管理責任者や専任技術者が不在になった場合など。
(6)建設業許可の更新手続きを行わなかった場合:
建設業許可の有効期間(5年間)が満了し、更新手続きを行わなかった場合。
(7)建設業の廃止:
許可を受けていた建設業を廃止した場合(一部の業種を廃止する場合も含む)。
1-2. 廃業届の提出先と提出期限
(1)提出先:
・大臣許可:主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局など
・知事許可:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県
(2)提出期限:
・上記1,2,3の場合:廃業等の事由が発生した日から30日以内
・上記4の場合: 廃業等の事由が発生した日から2週間以内
・上記5,6,7の場合:廃業等の事由が発生した日から30日以内
1-3. 廃業届の提出を怠ると?:罰則の可能性も
廃業届の提出を怠ると、建設業法違反となり、罰則(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)が科せられる可能性があります。
必ず期限内に提出しましょう。
1-4. 廃業届提出後の流れ:許可取消通知
廃業届を提出すると、許可行政庁から「許可の取消通知」が送付されます。
これにより、建設業許可が正式に取り消されたことになります。
1-5. 一部業種廃止の場合:変更届も必要
許可を受けている建設業のうち、一部の業種のみを廃止する場合は、廃業届に加えて、「変更届出書(様式第二十二号の二)」も提出する必要があります。
2建設工事の施工中に廃業した場合:工事は継続できる?
建設業許可を廃業した場合でも、既に請け負っている工事がある場合は、どうなるのでしょうか?
ここでは、工事施工中に廃業した場合の取り扱いについて解説します。
2-1. 原則:施工中の工事は継続可能
建設業許可を廃業(または取消)した場合でも、既に請け負って施工中の工事については、引き続き施工することができます。
これは、建設業法の目的の一つである「発注者保護」の観点から、工事が途中で中断されることによる発注者の不利益を避けるためです。
2-2. 契約締結済みの工事も施工可能
工事の施工中だけでなく、建設工事の請負契約を締結した後に廃業となった場合も、同様に、その工事に限って施工することが可能です。
2-3. 発注者の契約解除権
ただし、発注者は、建設業者が許可を失ったことを理由に、締結済みの請負契約を解除することができます。
これは、発注者が無許可業者に工事を依頼することに抵抗がある場合などを考慮したものです。
2-4. 根拠法令:建設業法第29条の3
これらの取り扱いは、建設業法第29条の3に規定されています。
3廃業と行政処分による取消:再取得への影響の違い
建設業許可の取消には、「廃業による取消」と「行政処分による取消」の2種類があります。
ここでは、それぞれの違いと、再取得への影響について解説します。
3-1. 廃業による取消:再取得は比較的容易
廃業による許可の取消の場合は、許可要件を満たせば、取消後すぐに建設業許可を再度取得することができます。
3-2. 行政処分による取消:5年間は再取得不可
一方、行政処分による許可の取消の場合は、建設業法違反などによるものであり、より重いペナルティが課せられます。
具体的には、取消処分を受けた日から5年間は、建設業許可を再度取得することができません(建設業法第8条)。
3-3. 行政処分の例
行政処分による許可取消の例としては、以下のようなものがあります。
・建設業法違反(一括下請負、無許可業者との契約など)
・不正な手段による許可取得
・営業停止処分に違反した
・欠格要件に該当した
4テレワークと常勤性:経管・専技・令3条使用人の要件
建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」(経管)、「専任技術者」(専技)、「令3条使用人」には、常勤性が求められます。
ここでは、テレワークと常勤性の関係について解説します。
4-1. テレワークでも常勤と認められる
令和3年12月の建設業許可事務ガイドラインの改正により、テレワークによっても常勤性が認められることが明確になりました。
これは、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、テレワークが普及したことを受けたものです。
4-2. テレワークの定義
建設業許可事務ガイドラインにおけるテレワークの定義は、以下のとおりです。
「営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所で職務に従事している場合と、同等の職務が遂行でき、かつ、当該所定の時間中において、常時連絡を取ることが可能な環境下において、その職務に従事することをいう」
4-3. テレワークの注意点
専任技術者の場合: 常識上、通勤不可能な場所でのテレワークは、「専任」としての要件を満たさないものとされています。
・兼務の禁止: 一人の専任技術者が、複数の営業所の専任技術者を兼務することはできません。
4-4. 国土交通省のQ&A
国土交通省は、「営業所専任技術者のテレワークに関するQ&A」を公開しています。
テレワークに関する疑問がある場合は、こちらを参照してください。
5実態のない営業所は設置できる?:テレワークとの関係
専任技術者や令3条使用人がテレワーク可能となると、実態のない営業所(ペーパー営業所)の設置が可能になるのではないか、という疑問が生じるかもしれません。
5-1. 実態のない営業所は認められない
結論から言うと、実態のない営業所の設置は認められません。
建設業法では、営業所について、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と定義しています。
単に登記上の住所があるだけ、電話やFAXがあるだけ、といった状態では、営業所として認められません。
5-2. 営業所の要件
営業所として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
・建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること
電話、FAX、机などの事務設備が備えられていること
・契約の締結などに関する権限を付与された者(令3条使用人など)が常勤していること
専任技術者が常勤していること
5-3. テレワークとの関係
テレワークは、あくまでも「営業所で職務に従事している場合と、同等の職務が遂行できる」ことが前提です。
したがって、営業所としての実態がなければ、テレワークを行っていても、常勤性や専任性を満たしているとは認められません。
6建設業の事業承継:M&A、相続における許可の承継
建設業の事業承継には、大きく分けて、社内承継(親族内承継、従業員承継)と、社外への承継(M&Aなど)があります。
ここでは、それぞれのケースにおける建設業許可の承継について、さらに詳しく解説します。
6-1. 社内承継の場合:スムーズな承継が可能だが、変更届は忘れずに
社内承継の場合は、会社自体は存続するため、建設業許可の要件を満たしていれば、許可は問題なく承継されます。
(1)親族内承継:
代表者や役員が親族に交代する場合、役員変更などの変更届を提出する必要があります。
経営業務の管理責任者や専任技術者が変更になる場合は、それぞれの要件を満たす人物を新たに選任し、変更届を提出する必要があります。
(2)従業員承継:
役員や従業員に事業を承継する場合も、同様に、役員変更などの変更届が必要です。
経営業務の管理責任者や専任技術者が変更になる場合は、それぞれの要件を満たす人物を新たに選任し、変更届を提出する必要があります。
いずれの場合も、変更届の提出を怠ると、建設業法違反となる可能性があるため、注意が必要です。
6-2. M&A(事業譲渡・合併・分割)の場合:事前認可制度で空白期間を解消
M&A(事業譲渡・合併・分割)の場合は、事業の承継に伴い、建設業許可の取り扱いが複雑になります。
令和2年10月に施行された改正建設業法により、事業承継の際に、事前に行政庁の認可を受けることで、空白期間なく建設業許可を承継できる制度(事業譲渡等認可制度)が導入されました。
6-2-1. 事前認可制度のメリット:事業継続性の確保
従来は、M&Aによる事業承継後、承継者が新たに建設業許可を取り直す必要がありました。
この場合、許可が下りるまでの間、建設業を営むことができない期間(空白期間)が生じ、事業の継続性に支障をきたす可能性がありました。
事前認可制度を利用することで、この空白期間をなくし、事業譲渡等の日から、承継者が建設業許可に基づく事業を継続できるようになりました。
これは、M&Aを検討する事業者にとって、大きなメリットとなります。
6-2-2. 事前認可の手続き:流れと必要書類
事前認可の手続きは、以下の流れで行います。
・事前相談:
許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に、事業承継の計画について事前に相談します。
(1)認可申請:
承継者は、許可行政庁に対して、事業譲渡等の認可申請を行います。申請には、以下の書類などが必要です。
・事業譲渡等認可申請書
・事業譲渡契約書、合併契約書、分割契約書などの写し
・譲渡人(または合併消滅法人、分割会社)の建設業許可通知書の写し
・譲受人(または合併存続法人、分割承継法人)の登記事項証明書、定款
・その他、許可行政庁が必要と認める書類
(2)審査:
許可行政庁は、申請内容を審査し、建設業許可の要件を満たしているか、事業承継が適正に行われるかなどを確認します。
(3)認可・不認可の通知:
許可行政庁は、審査結果を承継者に通知します。認可された場合、事業譲渡等の日に、建設業許可も承継されます。
(4)事業譲渡等の実行:
事業譲渡等を行います。
(5)変更届等の提出:
承継者は、事業譲渡等の日から30日以内に、許可行政庁に変更届等を提出します。
6-2-3. 事前認可の注意点:承継できないケース、許可の一部承継は不可
(1)承継できないケース:
一般建設業許可を受けている建設業者が、同一業種の特定建設業許可を受けている者の地位を承継する場合
特定建設業許可を受けている建設業者が、同一業種の一般建設業許可を受けている者の地位を承継する場合
これらのケースでは、承継元または承継先のいずれかが、当該業種について事前に廃業手続きを行う必要があります。
(2)許可の一部承継は不可:
承継の対象となるのは、建設業許可を受けている事業者の「地位」であり、許可の一部(特定の業種のみなど)を承継することはできません。
6-2-4. 許可の有効期間:承継後の取り扱い
事業譲渡等により建設業許可を承継した場合、承継後の許可の有効期間は、事業譲渡等の日から5年間となります。
これは、承継する許可ともともと持っている許可の両方の有効期限が更新されることを意味します。
6-3. 個人事業主の相続の場合:事前認可制度でスムーズな承継
個人事業主が建設業許可を受けている場合、その事業主が死亡すると、建設業許可は失効します。
しかし、令和2年10月の改正建設業法により、相続人が事前に認可を受けることで、被相続人(亡くなった個人事業主)の建設業許可を承継できる制度(相続認可制度)が導入されました。
6-3-1. 事前認可の手続き:流れと必要書類
事前認可の手続きは、以下の流れで行います。
(1)相続の発生:
個人事業主が死亡します。
(2)相続人の確定:
相続人を確定します。
(3)認可申請:
相続人は、被相続人の死亡後30日以内に、許可行政庁に対して、相続の認可申請を行います。申請には、以下の書類などが必要です。
・相続認可申請書
・被相続人の建設業許可通知書の写し
・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人全員の同意書
・相続人の住民票
・その他、許可行政庁が必要と認める書類
(4)審査:
許可行政庁は、申請内容を審査し、相続人が建設業許可の要件を満たしているかなどを確認します。
(5)認可・不認可の通知:
許可行政庁は、審査結果を相続人に通知します。認可された場合、相続人は、被相続人の建設業許可を承継します。
(6)変更届等の提出:
相続人は、認可後速やかに、許可行政庁に変更届等を提出します。
6-3-2. 事前認可のメリット:空白期間なく事業を継続
事前認可制度を利用することで、相続人は、被相続人の死亡後、空白期間なく建設業を継続することができます。
これは、事業の継続性を確保する上で、非常に大きなメリットとなります。
6-3-3. 認可申請期間中の取り扱い:みなし許可
相続人が認可申請を行った場合、認可・不認可の通知があるまでは、相続人は建設業許可を受けたものとみなされます。
つまり、この期間は、建設業を営むことができます。
6-3-4. 相続人が複数いる場合:全員の同意が必要
相続人が複数いる場合は、相続人全員の同意が必要です。
同意が得られない場合は、相続認可を受けることができません。
6-3-5. 許可の有効期間:残存期間を引き継ぐ
相続により建設業許可を承継した場合、承継後の許可の有効期間は、被相続人の許可の残存期間となります。
認可後、改めて許可証が発行され、有効期間が記載されます。
7建設業許可の有効期限と更新手続き
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き建設業を営む場合は、有効期限が切れる前に、更新手続きを行う必要があります。
7-1. 更新手続きの期限:有効期限満了の30日前まで
建設業許可の更新手続きは、有効期限満了の30日前までに行う必要があります。
期限を過ぎると、許可が失効してしまうため、注意が必要です。
7-2. 更新手続きに必要な書類
更新手続きに必要な書類は、都道府県によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。
・建設業許可更新申請書
・決算変更届(事業年度終了報告)の控え(直近5年分)
・納税証明書
・その他、必要に応じて添付書類
7-3. 更新手続きの注意点
更新手続きの際には、改めて許可要件を満たしているかどうかが審査されます。
経営業務の管理責任者や専任技術者に変更があった場合は、変更届を提出している必要があります。
社会保険に未加入の場合は、更新が認められない場合があります。
7-4. 更新を忘れてしまった場合
更新手続きを忘れてしまい、許可の有効期限が切れてしまった場合は、新規に許可を取り直す必要があります。
この場合、許可が下りるまでの間は、建設業を営むことができません。
8まとめ
建設業許可の廃業手続き、テレワークと常勤性の関係、事業承継における許可の承継、許可の有効期限と更新手続きなど、建設業許可に関する様々な情報を解説しました。
建設業許可は、取得して終わりではなく、その後の変更手続きや更新手続き、そして事業承継など、様々な場面で適切な対応が必要になります。
「廃業手続きはどうすれば?」「事業承継で許可を引き継げる?」「更新手続きを忘れてしまった!」など、建設業許可に関するお悩みや疑問は、専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士藤井等事務所は、建設業許可の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
9お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ<許認可申請>