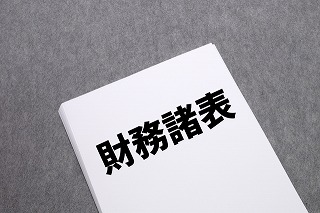「建設業の財務諸表って、普通の会計と何が違うの?」
「貸借対照表の書き方が分からない…」
「完成工事未収入金って何?」
「経審に必要な財務諸表の作り方は?」
こんなお悩みはありませんか?
建設業許可の申請や更新、そして経営事項審査(経審)を受ける際には、建設業法に基づいた特殊な形式の財務諸表を作成・提出する必要があります。
特に貸借対照表には、建設業特有の勘定科目があり、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
ご安心ください!
今回の記事では、建設業財務諸表の基本ルール、特に貸借対照表の作成方法について、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、建設業財務諸表のポイントが理解でき、スムーズな許可申請や経審の準備を進めることができます。
岩手をはじめ、各地で建設業を営む皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1建設業財務諸表の基本的なルール
建設業許可申請や経営事項審査(経審)で提出する財務諸表は、一般的な企業の財務諸表(商業簿記、工業簿記など)とは異なる、建設業法に基づいた独自のルールで作成する必要があります。
ここでは、まず押さえておきたい基本的なルールを3つ紹介します。
1-1. 単位は「千円単位」
建設業財務諸表は、すべて「千円単位」で作成します。
1,000円未満の端数処理については、四捨五入、切り上げ、切り捨てのいずれの方法でも構いませんが、「千円未満切り捨て」が最も計算が簡単でおすすめです。
(注意点)
各勘定科目を千円未満切り捨てで計上した場合、各勘定科目の合計額と、総額の合計が一致しない場合がありますが、これは問題ありません。
無理に合計を合わせる必要はありません。
1-2. 根拠は国土交通省告示
建設業財務諸表の様式や勘定科目の分類は、国土交通省の告示によって定められています。
○根拠告示
「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」(昭和57年建設省告示第1660号)
*最新改正:令和4年4月11日 国土交通省告示第473号
この告示は、建設業財務諸表を作成する上での「法律上のルールブック」です。
国土交通省のウェブサイトなどで確認できますので、財務諸表を作成する際は、必ず手元に置き、内容を確認するようにしましょう。
1-3. 表示形式は「報告式」
財務諸表の表示形式には、左右に資産と負債・純資産を配置する「勘定式」(T字型)と、上から資産、負債、純資産の順に記載していく「報告式」があります。
建設業財務諸表では、貸借対照表、損益計算書ともに、「報告式」で作成することが定められています。
2貸借対照表の構成
建設業財務諸表の貸借対照表も、基本的な構成は一般企業の貸借対照表と同様に、「資産の部」「負債の部」「純資産の部」の3つに大きく区分されます。
ただし、建設業特有の勘定科目がいくつか存在するため、注意が必要です。
2-1. 資産の部:流動資産
2-1-1. 現金預金
現金、普通預金、当座預金、定期積金などを合計した金額を記載します。
注意点として、当座借越(当座預金の残高を超えて小切手を振り出した場合など)は、負債の部の「短期借入金」として計上します。
2-1-2. 完成工事未収入金(重要!建設業特有)
完成した工事の請負代金のうち、まだ受け取っていない金額を記載します。
一般的な会計でいう「売掛金」に相当しますが、建設業では「完成工事未収入金」という勘定科目を使用します。
(注意点)
建設業以外の兼業事業(例えば、不動産賃貸業など)における売掛金や、その他の未収入金(例えば、立替金の未回収分など)とは、明確に区別して記載する必要があります。
混同を避けるため、兼業分の売掛金は「売掛金(兼業分)」、その他の未収入金は「未収入金」として、別途記載するのが一般的です。
2-1-3. 未成工事支出金(重要!建設業特有)
期末時点でまだ完成していない工事(未成工事)に関して、既に支出した費用(材料費、労務費、外注費など)を記載します。
これは、仕掛品(製造業)や半製品に相当する建設業特有の勘定科目です。
(考え方)
まだ完成していない工事のために支払った費用は、将来的に完成工事高(売上)に対応する原価となるため、費用ではなく「資産」として計上します。
(具体例)
未成工事に使用する材料を仕入れたが、まだ使用していない場合の材料費
未成工事に従事した従業員への給与
未成工事を依頼した下請業者への前払金(内金、手付金)
(注意点)
前渡金(例えば、材料購入の内金など)も、未成工事に関するものであれば、「未成工事支出金」に含めて計上します。
2-1-4. 材料貯蔵品(原材料、貯蔵品)
工事に使用する目的で購入した材料や、消耗工具器具、事務用消耗品などのうち、期末時点で未使用のものを記載します。
ただし、未成工事支出金や完成工事原価、販売費及び一般管理費として処理されたものは除きます。
2-2. 資産の部:固定資産(有形固定資産)
2-2-1. 建物・構築物、機械運搬具、工具器具備品、リース資産
これらの勘定科目は、一般的な会計と同様です。
ただし、建設業財務諸表では、それぞれの勘定科目の直下に「減価償却累計額」を記載する欄が設けられています。
取得価額から減価償却累計額を差し引いた帳簿価額を記載するのではなく、取得価額と減価償却累計額をそれぞれ記載します。
2-2-2. 建設仮勘定
自社で使用するための建物や工場、機械などを建設・製作している場合に、完成前に支払った費用を一時的に計上する勘定科目です。
工事が完成し、固定資産として使用を開始した時点で、適切な固定資産勘定(建物、機械運搬具など)に振り替えます。
2-3. 資産の部:固定資産(無形固定資産)
ソフトウェア、特許権、借地権、営業権(のれん)などが該当します。
建設業財務諸表の様式では、個別の勘定科目欄はなく、「その他」の項目にまとめて記載することが一般的です。
電話加入権も、現在では無形固定資産の「その他」に含まれます。
2-4. 資産の部:投資その他の資産
投資有価証券、長期貸付金、敷金・保証金、繰延税金資産などが該当します。
基本的な考え方は、一般企業の会計と同様です。
2-5. 資産の部:繰延資産
創立費、開業費、開発費、社債発行費などが該当します。
基本的な考え方は、一般企業の会計と同様です。
2-6. 負債の部:流動負債
2-6-1. 工事未払金(重要!建設業特有)
完成工事原価に含まれる費用のうち、まだ支払っていない金額を記載します。
一般的な会計でいう「買掛金」や「未払金」に相当しますが、建設業では「工事未払金」という勘定科目を使用します。
(具体例)
工事に使用した材料の仕入代金の未払い分
下請業者への工事代金の未払い分
工事に従事した従業員への未払い給与
(注意点)
兼業事業の買掛金や、販売費及び一般管理費に含まれる費用(例えば、事務用品の購入代金など)の未払金とは、明確に区別して記載する必要があります。
混同を避けるため、兼業分の買掛金は「買掛金(兼業分)」、その他の未払金は「未払金」として、別途記載するのが一般的です。
2-6-2. 未成工事受入金(重要!建設業特有)
まだ完成・引き渡しをしていない工事(未成工事)に関して、発注者から前受けした金額(内金、手付金など)を記載します。
一般的な会計でいう「前受金」に相当する建設業特有の勘定科目です。
(考え方)
まだ工事が完成していない段階で受け取ったお金は、将来的に工事を完成させて引き渡す義務があるため、「負債」として計上します。
工事が完成し、完成工事高(売上)に計上された時点で、この勘定科目は取り崩されます。
2-6-3. その他流動負債
短期借入金、未払法人税等、預り金、前受収益などが該当します。
基本的な考え方は、一般企業の会計と同様です。
2-7. 負債の部:固定負債
社債、長期借入金、退職給付引当金、繰延税金負債などが該当します。
基本的な考え方は、一般企業の会計と同様です。
2-8. 純資産の部
株主資本(資本金、資本剰余金、利益剰余金)、評価・換算差額等、新株予約権の3つの区分がありますが、これも基本的な考え方は、一般企業の会計と同様です。
3まとめ
建設業財務諸表、特に貸借対照表の作成は、建設業許可申請や経営事項審査(経審)において非常に重要です。
一般的な財務諸表とは異なる、建設業特有の勘定科目やルールを正しく理解し、適切な書類を作成する必要があります。
「建設業財務諸表の作成方法が分からない」「自社の財務諸表が正しいか不安」「経審の評点を上げるための財務改善について相談したい」
このようなお悩みをお持ちの方は、建設業専門の行政書士にご相談ください。
行政書士は、建設業法や関連法令、会計基準に精通しており、建設業財務諸表の作成を正確かつスムーズに行うことができます。
また、経営事項審査(経審)の申請代行や、評点アップのためのコンサルティングなど、建設業者の皆様をトータルでサポートいたします。
当事務所では、建設業許可・経営事項審査(経審)に関するご相談を幅広く承っており、お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという、他にはない「強み」を持っているところです。
建設業許可及び経営事項審査(経審)を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
この記事を読んで、少しでも建設業財務諸表について考えるきっかけになれば幸いです。
4お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>
https://office-fujiihitoshi.com/