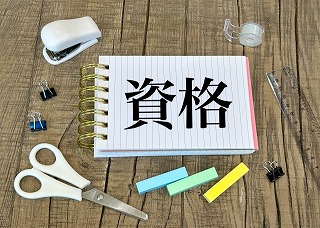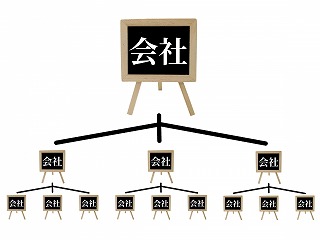「主任技術者や監理技術者は、工事期間中ずっと現場に張り付いていないとダメなの?」
「専任義務がある工事だと、他の現場の応援にも行けないのだろうか…」
「専任が不要な期間って、具体的にいつ?」
こんな疑問を感じたことはありませんか?
ご安心ください。
その疑問は、建設業法が定める「専任」の本当の意味を正しく理解することで解決できます。
この記事では、建設工事の現場に配置する技術者の「専任義務」について、その対象となる工事や期間、そして多くの人が誤解しがちな「常駐」との違いについて、分かりやすく解説します。
建設工事の適正な施工と安全を確保するため、建設業法は、一定規模以上の工事現場に「主任技術者」または「監理技術者」を専任で配置することを義務付けています。
この「専任」という言葉の解釈をめぐっては、多くの誤解が生じがちです。
「専任=現場に常駐」と考え、技術者の効率的な配置に悩む経営者様も少なくありません。
今回は、この技術者の「専任義務」について、その本質的な意味と、法令を遵守しつつも、効率的な現場管理を行うための正しい知識を詳しく見ていきましょう。
1技術者の「専任」が求められる工事とは?
まず、どのような工事で技術者の専任が求められるのか、その対象を正確に把握することが重要です。
1-1. ルールの趣旨:公共性と安全性の確保
技術者の専任義務は、特に公共性のある施設や、多数の人が利用する施設に関する工事において、より一層、施工の品質と安全を確保するために定められています。
不特定多数の人の生命や財産に関わる重要な工事だからこそ、一人の技術者が他の現場と掛け持ちすることなく、その工事に集中して技術的な管理を行うことが求められるのです。
1-2. 「専任」が必要となる工事の具体的な基準
専任義務の対象となるのは、工事1件の請負代金の額が、消費税込みで4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の建設工事です。
(※この金額は令和5年1月1日からの改正後の金額です。)
重要なのは、このルールが公共工事だけでなく、民間工事にも適用されるという点です。
個人住宅を除けば、学校、病院、百貨店、共同住宅、工場、道路、橋、ダムといった、私たちの生活に関わる多くの施設に関する工事が対象となります。
2「専任」の期間と、例外的に不要となるケース
元請負人が技術者を専任で配置すべき期間は、原則として「契約工期の全体」となります。
しかし、工事の進捗状況によっては、技術的な管理が実質的に不要な期間も存在します。
2-1. 「専任」を要しない期間の具体例
国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」などでは、発注者との書面による明確な合意があれば、以下の期間については技術者の専任を要しないとされています。
① 契約締結後、現場施工に着手するまでの準備期間(現場事務所の設置、資材の搬入路の確保など、技術的管理を必要としない期間)
② 工事を全面的に一時中止している期間(工事用地の確保の遅れ、自然災害、埋蔵文化財の調査など、元請・下請双方の都合によらない理由で、工事が完全にストップしている期間)
③ 工事完成後、後片付け等のみが残っている期間(検査も終了し、事務手続きや現場の清掃・後片付けなど、技術的な管理を要しない作業のみが残っている期間)
2-2. 下請工事における考え方
下請工事の場合、その施工期間は断続的になることが少なくありません。
そのため、下請負人が配置する主任技術者の専任期間は、契約工期全体ではなく、その下請工事が実際に施工されている期間と解釈されます。
3「専任」と「常駐」の決定的な違い
ここが最も重要なポイントです。法律が求める「専任」とは、必ずしも「常駐」を意味するものではありません。
3-1. 「専任」の本質は「兼務の禁止」
技術者に求められる「専任」とは、他の工事現場の職務と兼務することを禁止し、常時継続的に、その特定の工事現場に係る職務にのみ従事することを意味します。
つまり、「一人の技術者が、同時に複数の重要な工事の専任技術者になることはできない」というのが、このルールの本質です。
3-2. 「常駐」は義務ではない
したがって、専任技術者は、担当する工事現場の職務(施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、下請指導など)を適切に遂行できる限りにおいて、必ずしも四六時中、工事現場に張り付いている必要はありません。
例えば、短期間の休暇を取得したり、本社での必要な会議に出席したり、あるいは業務に必要な資材の調達や関係機関との協議のために現場を離れたりすることは、合理的な範囲で認められています。
重要なのは、現場を離れている間も、電話やインターネットなどで常に連絡が取れる体制を確保し、現場の管理責任者としての職務を全うできる状態にあることです。
3-3. 近年の緩和措置:監理技術者の兼任
深刻な技術者不足を背景に、近年、監理技術者の専任義務には緩和措置が設けられました。
一定の要件を満たす「監理技術者補佐」を現場に配置することで、一人の監理技術者が最大2つまでの工事現場を兼務することが可能になっています。
4整理
技術者の「専任」義務は、建設業法における最も基本的なコンプライアンス事項の一つです。
その一方で、「専任=常駐」という誤解が、技術者の非効率な配置や、企業の負担増に繋がっているケースも見受けられます。
専任の本当の意味を正しく理解し、法律が認める合理的な範囲で技術者を運用していくこと。
そして、専任が不要な期間については、発注者と書面で明確に合意しておくこと。
こうした正しい知識と運用が、法令遵守と、効率的で生産性の高い現場運営を両立させる鍵となります。
5まとめ
建設現場への主任技術者・監理技術者の「専任」配置は、建設業法が定める重要な義務です。
その一方で、「専任」は必ずしも「常駐」を意味するものではなく、その正しい理解が、企業の効率的な人材活用とコンプライアンス遵守に繋がります。
「自社の技術者配置は、法的に問題ないだろうか」「専任義務の緩和措置について、具体的に知りたい」など、技術者制度に関するお悩みは、専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、最新の法令に基づき、貴社の実情に合わせた最適なコンプライアンス体制の構築をサポートいたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/