
「最近よく聞くCM(コンストラクション・マネジメント)方式、自社でも導入を検討しているが、建設業許可は必要なのだろうか?」
「発注者の立場でCMR(コンストラクション・マネージャー)を起用したいが、そのCMRは建設業者であるべき?」
こんな疑問を感じていませんか?
ご安心ください。
その疑問は、CM方式の種類と、それぞれにおけるCMRの役割と責任を正しく理解することで解決できます。
この記事では、建設業界で注目されるCM方式について、その2つの種類と、それぞれにおいて建設業許可が必要となるケース、不要となるケースを分かりやすく解説します。
建設プロジェクトが大規模化・複雑化する現代において、その運営を効率的かつ透明に進めるための手法として「CM(コンストラクション・マネジメント)方式」が注目を集めています。
特に、専門的な技術職員の確保が難しくなっている地方公共団体の公共工事などでは、その活用が国土交通省からも推奨されており、今後ますます重要なプロジェクトマネジメント手法となっていくことが予想されます。
しかし、このCM方式を導入・活用する上で、建設業に携わる皆様が必ず理解しておかなければならないのが、「CMR(コンストラクション・マネージャー)は、建設業許可を受ける必要があるのか?」という問題です。
今回は、この問いに答えるため、CM方式の基本的な考え方と、その種類による法的な扱いの違いについて詳しく見ていきましょう。
1建設業におけるCM(コンストラクション・マネジメント)方式とは?
まず、CM方式がどのようなものなのか、その概要を掴むことが大切です。
1-1. 発注者のための専門的な支援サービス
CM方式とは、建設生産・管理システムの一つです。
専門的な知識を持つCMR(コンストラクション・マネージャー)が、発注者の補助者または代行者という立場でプロジェクトに参加し、技術的な中立性を保ちながら、発注者の利益を最大化するために各種のマネジメント業務を行います。
具体的には、企画・設計段階からのコスト管理やVE(バリュー・エンジニアリング)提案、工事発注方式の検討、施工段階での工程管理や品質管理など、プロジェクト全体のプロセスを統括的に管理・支援します。
1-2. 地方公共団体も注目する、その必要性の背景
近年、地方公共団体において、土木や建築に関する専門知識を持つ職員が減少し、公共工事を適切に発注・監督する体制の維持が困難になるという課題が深刻化しています。
CM方式は、こうした自治体の専門性を補い、公共工事の品質確保とコストの適正化を実現するための有効な手段として期待されており、国土交通省も「地方公共団体におけるピュア型CM方式活用ガイドライン」を策定するなど、その活用を後押ししています。
2建設業許可の要否を分ける、2つのCM方式
CM方式と一口に言っても、CMRの役割と責任の範囲によって、大きく「ピュア型」と「アットリスク型」の2種類に分類されます。
そして、建設業許可が必要かどうかは、どちらの方式を採用するかによって結論が全く異なります。
2-1. ピュア型CM方式
ピュア型CM方式は、CMRが純粋なマネジメント・サービスを提供する形態です。
⑴ CMRの役割:
あくまで発注者の補助者・代行者として、助言や提案、各種調整業務を行います。工事の施工そのものに対する法的な完成責任や、コスト超過のリスクは負いません。
⑵ 契約関係:
発注者は、CMRとは「マネジメント業務委託契約」を締結し、それとは別に、設計者や施工業者(元請負人)とそれぞれ直接契約を結びます。
⑶ 法的性質と建設業許可:
この場合のCMRの業務は、民法上の「準委任契約」(法律行為でない事務の委託)に該当すると解釈されます。
建設工事の完成を目的とする「請負契約」ではないため、原則として、ピュア型のCMRには建設業許可は不要です。
2-2. アットリスク型CM方式
アットリスク型CM方式は、CMRがマネジメント業務に加えて、工事の完成に対して一定の「リスク」を負う形態です。
⑴ CMRの役割:
プロジェクトの企画段階から参画し、工事費の上限(GMP:Guaranteed Maximum Price)を保証するなど、施工に関する金銭的・性能的なリスクも負担します。
CMRが直接、専門工事業者と契約することもあります。
⑵ 契約関係:
発注者とCMRとの契約は、単なる業務委託ではなく、工事全体の完成を目的とするものとなります。
⑶ 法的性質と建設業許可:
この場合、CMRは実質的に「元請負人」と同様の責任と役割を担うことになります。
したがって、その業務は「建設工事の請負」に該当し、アットリスク型のCMRには建設業許可が必要となると考えられます。
3判断に迷った場合の注意点
ピュア型とアットリスク型の区別は、契約書の名称ではなく、あくまでその実態で判断されます。
3-1. 契約内容の精査が重要
たとえ契約書が「業務委託契約」となっていても、その中に工事の完成保証や、工事費の超過分をCMRが負担する旨の条項が含まれていれば、アットリスク型と見なされ、建設業許可が必要となる可能性があります。
3-2. 行政への事前協議のすすめ
特に公共工事などでCM方式の導入を検討する場合や、自社の契約形態がどちらに該当するか判断に迷う場合には、必ず発注者や許可行政庁の担当窓口、あるいは行政書士などの専門家に事前に相談し、その業務に建設業許可が不要であることを確認しておくことが、コンプライアンス上のリスクを回避するために不可欠です。
4全体の整理
CM方式は、建設プロジェクトを成功に導くための有効な手法であり、建設業者の皆様にとっても、新たなビジネスチャンスとなる可能性を秘めています。
しかし、その活用にあたっては、ピュア型とアットリスク型という2つの方式の違いと、それぞれに適用される建設業法のルールを正しく理解しておくことが大前提となります。
自社がCMRとして業務を行う場合も、発注者としてCMRを起用する場合も、その契約の実態が建設業法上の「建設工事の請負」に該当するのかどうかを慎重に見極め、適法な体制でプロジェクトに臨むことが、企業の信頼を守り、未来の発展へと繋がるのです。
5まとめ
CM方式の導入など、建設業界における新しい事業形態には、建設業許可に関する新たな法的論点が付随します。
「この新しいビジネスモデルに、建設業許可は必要なのだろうか?」といった疑問は、事業の将来を左右する重要な問題です。
コンプライアンスに関する自己判断は、時に大きなリスクを伴います。そのような時は、ぜひ専門家にご相談ください。
当事務所は、建設業法務の専門家として、最新の法令やガイドラインに基づき、貴社の事業内容に最適な許認可戦略をご提案します。
元岩手県職員としての経験と他士業との連携により、貴社の「無限の可能性」を法務面から力強くサポートいたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/


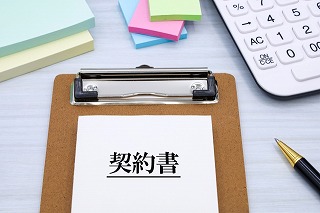


.jpg)