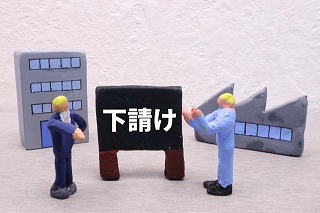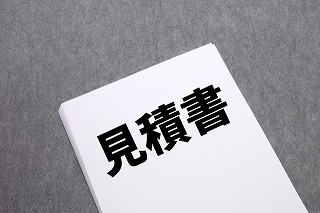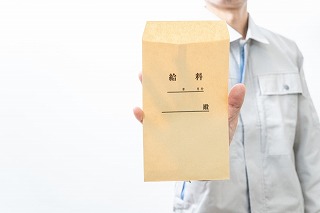
「下請への見積依頼で、労務費をどこまで考慮すればいいのだろう…」
「元請から、かなり厳しい金額を提示されたが、これって適法なの?」
「新しい法律で『著しく低い労務費の禁止』が導入されると聞いたけど、具体的に何が変わるの?」
こんな疑問や不安を感じていませんか?
ご安心ください。
そのお悩みは、2025年(令和7年)12月までに施行される改正建設業法の新ルールを正しく理解することで解決できます。
この記事では、建設業界の未来を左右する「適正な労務費の確保」について、その背景と具体的なルール、そして違反した場合のリスクまで分かりやすく解説します。
建設業界は、長年にわたり、労働者の高齢化と若者の入職者減少という深刻な「担い手不足」の問題に直面しています。
その大きな原因の一つが、他産業と比較して、労働環境に見合った適切な賃金水準が確保されてこなかったという現実です。
特に、請負契約における重層下請構造の中で、材料費などに比べて相場が不透明な「労務費」が、コスト削減の対象とされやすいという構造的な課題がありました。
この状況を打開し、建設業の持続可能な発展と、技能労働者の処遇改善を図るため、2024年(令和6年)6月、建設業法が改正され、新たに「著しく低い労務費の禁止」という、極めて重要なルールが導入されることになりました。
今回は、この新しいルールについて、その核心と企業がとるべき対応を詳しく見ていきましょう。
1「著しく低い労務費」とは?
まず、なぜ「著しく低い労務費」が法律で禁止されるのか、その背景と定義を正確に理解することが重要です。
1-1. ルール導入の目的
このルールの最大の目的は、元請・下請を問わず、建設工事の請負契約において、技能労働者の経験や能力が正当に評価され、その労働環境に見合った「適正な水準の賃金」が支払われるようにすることです。
労務費を不当に削減する慣行に歯止めをかけ、業界全体の処遇を改善し、将来の担い手を確保・育成していくことが狙いです。
1-2. 「著しく低い労務費」の定義
法律で禁止される「著しく低い労務費」とは、「その建設工事の施工地域において、通常必要と認められる労務費」に比べて、著しく低い額の労務費を指します。
ここでいう「労務費」には、単に賃金だけでなく、事業主が負担すべき法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)も含まれる、という点が非常に重要なポイントです。
2適正な労務費の道しるべ
では、「通常必要と認められる労務費」とは、何を基準に判断されるのでしょうか。
その客観的な道しるべとなるのが、国土交通省の中央建設業審議会が作成する「労務費の基準」です。
2-1. 交渉・監督の客観的なものさし
この「労務費の基準」は、公共工事で用いられている「公共工事設計労務単価」などを参考に、地域や職種ごとの標準的な労務費の目安を示すものです。
この基準は、以下のような場面で活用されることが想定されています。
⑴ 当事者間の価格交渉の指標:
元請負人と下請負人が請負代金を決定する際の、公正な交渉の材料となります。
⑵ 行政による指導・監督の参考指標:
許可行政庁が、「著しく低い労務費」に該当するかどうかを判断する際の客観的な参考資料となります。
2-2. すべての契約が対象
この基準の考え方は、公共工事だけでなく、民間工事を含むすべての建設工事の、元請・下請間、下請・二次下請間といった、あらゆる階層の請負契約に適用されます。
3建設業法が定める「適正な労務費確保」のための4つのルール
今回の法改正では、「著しく低い労務費の禁止」を実効性のあるものにするため、見積もりから契約、そして契約後の協議に至るまで、一連のプロセスにおいて以下の4つのルールが定められました。
3-1. ルール①
注文者(元請負人)は、労務費の基準を参考にせず、一方的に低い金額で見積もりを依頼してはなりません。
同様に、受注者(下請負人)も、受注したいがために、基準を著しく下回る労務費で見積書を提出することが禁止されます。
3-2. ルール②
たとえ当事者双方が合意していたとしても、標準労務費や下請負人の見積もりから見て、明らかに労務費相当額を著しく下回る請負代金で契約を締結することが禁止されます。
これは、いわゆる「原価割れ契約」を労務費に関しても厳しく規制するものです。
3-3. ルール③
これは、以前の記事で解説した「おそれ情報の通知」とも関連します。
労務費の高騰が見込まれる場合など、工期や請負代金に影響を及ぼす可能性のある情報を、契約前に当事者間で共有することが求められます。
3-4. ルール④
契約後に予期せぬ労務費の高騰などが生じた場合、受注者は注文者に対して契約内容の変更協議を申し出ることができます。
そして、申し出を受けた注文者(元請負人)は、その協議に誠実に応じる義務があります。
4ルールに違反した場合のリスク
これらの新しいルールに違反した場合、注文者・受注者の双方に対して、行政による監督や処分が行われる可能性があります。
4-1. 注文者(元請負人)への措置
著しく低い労務費での見積もりを依頼したり、契約を締結したりしたと認められた場合、許可行政庁はその注文者に対して勧告を行い、正当な理由なく勧告に従わない場合は、その事実を公表することができます。
注文者が建設業者である場合は、さらに重い指示処分や営業停止処分の対象ともなり得ます。
4-2. 受注者(下請負人)への措置
受注者側も、不当に低い労務費で見積もりを提出したり、契約を受け入れたりした場合には、同様に監督処分の対象となります。
4-3. 独占禁止法違反の可能性
特に、元請負人がその優越的な地位を利用して、下請負人に不当に低い労務費を強いるような行為は、独占禁止法が禁じる「優越的地位の濫用」に該当する可能性もあり、その場合は公正取引委員会による調査や排除措置命令の対象となり得ます。
5全体の整理
「著しく低い労務費の禁止」は、建設業界の構造的な課題にメスを入れ、技能労働者の処遇を改善し、業界の未来を築くための、大きな一歩です。
これからは、すべての建設業者が、自社の利益だけでなく、現場を支える一人ひとりの技能労働者の価値を正当に評価し、それを「労務費」として請負代金に適切に反映させていくことが、法令遵守の観点からも、企業の持続可能性の観点からも不可欠となります。
この新しいルールを正しく理解し、公正な取引慣行を実践していくことが、これからの建設業者に求められる姿と言えるでしょう。
6まとめ
2025年12月までに施行される改正建設業法の「著しく低い労務費の禁止」は、すべての建設業者に関わる重要な新ルールです。
自社の見積もりや契約慣行が、この新しい基準に適合しているか、今一度ご確認いただくことが、将来のコンプライアンスリスクを回避するために不可欠です。
「新しい労務費の基準に、どう対応すれば良いか」「元請との価格交渉で悩んでいる」など、法改正への対応や契約に関するお悩みは、専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、最新の法令に基づいたコンプライアンス体制の構築をサポートいたします。
7お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/