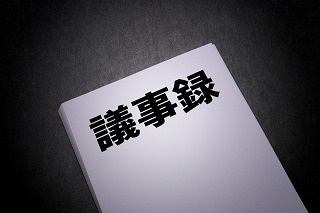
「医療法人を設立したいが、設立総会の議事録や趣意書って何をどう書けばいいのか?」
「自己流で作成して、行政の審査で差し戻されたらどうしよう…」
こんな悩みはありませんか?
その悩み、本記事で解決できます。
医療法人の設立認可は、提出書類の「一貫性」と「明確な意思」が鍵です。
今回の提案は、審査をスムーズに通過するための議事録・趣意書の作成ポイントを、行政書士が分かりやすく紹介します。
【医療法人設立における議事録・趣意書の重要性】
医療法人の設立は、単に書類を提出すれば完了するものではありません。都道府県知事(場合によっては厚生労働大臣)による「認可」という、行政機関の厳格な審査を経て初めて実現します。
この審査において、設立者の皆様の「本気度」と「計画の具体性」を証明する最重要書類が、「設立総会議事録」と「設立趣意書」です。
これらは単なる形式的な書類ではなく、法人の根本的な意思決定の証拠であり、なぜ法人化するのかという「魂」を吹き込む文書です。ここに不備や矛盾があれば、認可が遅れるだけでなく、最悪の場合、認可が下りない可能性すらあります。
本記事では、この重要な二つの書類作成におけるポイントを、行政書士の視点から徹底的に解説します。
1 設立総会とは何か?
医療法人を設立するためには、まず「設立者」が集まる必要があります。
設立者は、法改正により原則として「社員」となる人々であり、法人の最高意思決定機関(社員総会)の構成員となります。
この設立者が集まり、「どのような医療法人を作るのか」という根本的なルール(定款)や、法人の基本的な体制(役員、資産、事業計画など)について合意形成を行う場が「設立総会」です。
1-1. 設立総会の参加者(設立者)
医療法人は「人」の集合体である「社団」が基本です。
そのため、設立者(設立後の社員)は、最低でも3名以上集めることが強く推奨されます。(県によっては3名以上が必須と指導されます)
一般的に、設立総会に参加した方々が、そのまま設立後の「社員」や「役員(理事・監事)」に就任するケースがほとんどです。
この総会での決定事項が、法人の土台となります。
2 設立総会議事録と設立趣意書
設立認可申請の際、行政機関は「設立総会が適法に開催され、重要な決定が確実になされたこと」を証明する書類を求めます。
それが「設立総会議事録」です。
また、「なぜ個人事業ではなく、あえて医療法人を設立するのか」という動機や経緯を具体的に説明する書類が「設立趣意書」です。
2-1. 設立総会議事録に盛り込む必須事項
議事録は「いつ、どこで、誰が、何を議論し、どう決まったか」を正確に記録する公的な証拠書類です。
記載漏れは絶対に許されません。
① 開催日時・場所:
実際に総会が開催された日時と場所を正確に記載します。
② 出席者の情報:
設立者(出席者)全員の住所・氏名を記載します。
これは「印鑑登録証明書」の記載通り、一字一句違わずに記載する必要があります。
③ 設立趣旨の承認:
なぜ法人を設立するのか、その目的を全員で確認したことを記録します。
④ 設立時社員の確認:
出席者が、設立後の「社員」となることを確認します。
⑤ 定款案の承認:
法人の憲法とも言える「定款」の全条文を審議し、承認した記録を残します。
⑥ 資産と基金(拠出)に関する承認:
設立時に法人の財産となる資産(現金、不動産、医療機器など)の詳細を記した「財産目録」を承認します。
特に、それが返済義務のない「拠出」なのか、返済予定のある「基金」なのかを明確に区別し、基金の場合はその返還ルール(利息をつけない、解散時の扱い等)も明記します。
⑦ 役員(理事・監事)・管理者の選任:
設立時の理事(理事長を含む)と監事を選任します。
また、法人が開設するクリニックの「管理者(院長)」も選任します。
⑧ 設立代表者の選任:
認可申請手続きを代表して行う人物(通常は理事長予定者)を選任します。
⑨ その他の承認事項:
個人事業主から引き継ぐリース契約や賃貸借契約、設立後の役員報酬の予定額なども、ここで承認を得ておくとスムーズです。
2-2. 設立趣意書で「想い」を伝える記載事項
趣意書は、議事録という「事実の記録」に対し、設立の「背景と情熱」を説明する書類です。
行政の担当者に「この法人は地域医療に貢献する意思が固い」と納得してもらうための重要な文書です。
① これまでの経緯:
個人診療所としていつ開設し、どのような医療を提供し、地域でどのような役割を果たしてきたかを具体的に記載します。
② 医療法人設立の意図:
なぜ法人化が必要なのか。「医療体制の安定化」「事業承継の円滑化」「分院展開による医療提供体制の拡充」など、具体的な目的を明確にします。
③ 医療法人の名称の由来:
法人の名称に込めた想いや、選定した理由を説明します。
④ 事業内容:
開設する診療所の概要や、今後予定している事業(例:訪問診療の強化、専門外来の新設など)を記載します。
3 議事録・趣意書の重要チェックポイント
書類作成で最も注意すべきは、行政が「不自然だ」と感じる点を作らないことです。
特に「名義貸し」や「実体のない法人」は厳しくチェックされます。
3-1. チェックポイント①:出席者の住所・氏名
議事録に記載する出席者の住所・氏名は、添付する「印鑑登録証明書」と完全に一致している必要があります。
「岩手県」を「岩手」と省略したり、「渡邉」を「渡辺」と記載したりするミスは許されません。
3-2. チェックポイント②:拠出(寄附)と基金の明確な区別
現在、医療法人設立の主流は「基金拠出型医療法人」です。
これは、設立時に提供した資金(基金)を、将来的に(一定の条件下で)拠出者に返還できる制度です。
議事録や定款で、「拠出(寄附)」なのか「基金」なのかを明確に分け、基金の場合は「利子をつけない」「返還時期の定め」などを明記しないと、認可が下りません。
3-3. チェックポイント③:管理者(院長)は必ず「理事」に
医療法人が開設する診療所の管理者(院長)は、法律上、その医療法人の「理事」でなければならないと定められています。(医療法第46条の5第6項)
設立総会で、管理者予定者を「理事」として選任していることを議事録に明記する必要があります。
3-4. チェックポイント④:「名義貸し」の疑いを払拭する
行政が最も警戒するのが「名義貸し」です。
例えば、以下のようなケースは、その理由を趣意書や別途の申立書で合理的に説明する必要があります。
⑴ ケースA:
設立代表者(申請者)と、理事長予定者が異なる場合。
⑵ ケースB:
理事長予定者が拠出(基金)する財産の割合が、全体の50%を大きく下回る場合。
(例:理事長の妻や親族が資産の大部分を拠出する場合)
これらは「実際には別の人(出資者)が法人を支配し、理事長は名前だけの存在ではないか」と疑われる原因となります。
3-5. チェックポイント⑤:「永続性」の証明(事業承継)
医療法人は、個人の寿命とは切り離され、「永続的」に地域医療を支えることが期待されます。
そのため、例えば理事長予定者が70歳以上など高齢の場合、県によっては「後継者(次の理事長候補や管理者候補)の氏名や計画」を趣意書などに記載するよう指導されることがあります。
これは、設立後すぐに後継者不在で解散する事態を防ぐための重要な審査ポイントです。
3-6. チェックポイント⑥:個人診療所からの発展的経緯
趣意書には、個人診療所の開設年月日や、これまで行政(保健所など)に行った届出の状況を正確に記載します。
これは、今回の法人設立が、ゼロからのスタートではなく、これまでの医療活動を継続・発展させるものであることを証明するために必要です。
4 まとめ
医療法人の設立、そして設立総会議事録や趣意書の作成は、単なる事務作業ではありません。
定款、事業計画書、財産目録など、他の申請書類すべてと完璧な「整合性」が求められる、極めて専門的な手続きです。
「どの書類から手を付けていいか分からない」「日々の診療で忙しく、書類作成まで手が回らない」というのが、多くの先生方の本音ではないでしょうか。
これらの複雑な手続きや行政機関との折衝は、専門家である行政書士にトータルでお任せいただくことで、先生方は診療に集中でき、かつ「認可」という確実な安心を得ることができます。
当事務所は、医療法人設立を目指す先生方に寄り添い、最善の解決策をご提案します。
最大の特徴として、当事務所は弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった他士業と緊密に連携しており、設立後の登記、税務、労務問題までワンストップで対応できる体制を整えています。
さらに、代表は元岩手県職員として、企業誘致や県立大学新設といった行政内部での調整業務に携わってきた経験があります。
国や県、保健所といった行政機関の「考え方」や「手続きの進め方」を熟知しており、皆様の代理人として迅速かつ円滑に調整・対応できる点は、他にはない「強み」であると自負しております。
他の事務所と異なり、土日・祝日も営業、朝8時から夜20時まで対応しておりますので、診療後のお忙しい時間でもお気軽にご相談いただけます。
医療法人の設立は、皆様のクリニックの未来を左右する大きな一歩です。
その第一歩を、私たち専門家が全力でサポートします。
★ 注意事項
厚生労働省(地方厚生局)や都道府県、各保健所への医療法人設立認可申請や、その後の各種届出について、行政書士は法律に基づき、他人の依頼を受けて申請書類を作成し、代理提出することが認められている唯一の国家資格者です。
行政書士以外の者(コンサルタント等を名乗る者)が、報酬を得てこれらの申請代理業務を行うことは、行政書士法違反として固く禁止されています。
5 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ
https://office-fujiihitoshi.com/






