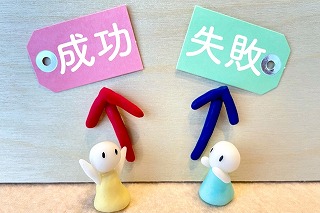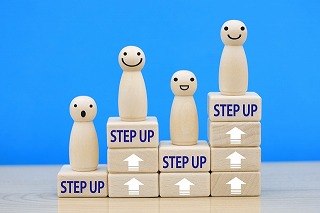「医療法って、何のためにあるの?」
「昔と今で、医療制度はどう変わった?」
「最近の医療法改正で、何が変わったの?」
こんな疑問をお持ちではありませんか?
日本の医療制度は、江戸時代から現代に至るまで、時代とともに大きく変化してきました。
特に、戦後の医療法制定以降、数々の改正が行われ、医療提供体制や医療機関のあり方は大きく変貌を遂げています。
医療法人を設立・運営するにあたっては、医療法だけでなく、医師法など関連法規の知識も不可欠です。
ご安心ください!
今回の記事では、日本の医療制度の歴史を紐解きながら、医療法改正のポイント、医療法人制度、医師法との関係などを分かりやすく解説します。
この記事を読めば、医療制度の全体像が理解でき、今後の医療経営に役立つ知識が得られます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)で医療機関の開設・運営に携わる皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1江戸時代
日本の医療の歴史は古く、江戸時代には、町医者や漢方医が人々の健康を支えていました。
1-1. 町医者と漢方
江戸時代の医療は、現代のような西洋医学ではなく、中国から伝わった漢方医学が中心でした。
町医者は、患者の自宅を訪問して診察し、漢方薬を調合・処方していました。
当時の医療は、師匠から弟子へと技術が伝えられる、家業のような側面が強いものでした。
1-2. 蘭方医の登場
江戸時代後期になると、長崎の出島を通じて西洋医学(蘭方)が伝来し、蘭方医が登場します。
しかし、江戸幕府は、西洋医学を厳しく制限し、漢方医学を保護していました。
2明治時代~戦後
明治維新後、日本は急速に近代化を進め、医療制度も大きく変化しました。
2-1. 医制(太政官布告)
明治7年(1874年)、明治政府は「医制」を公布し、西洋医学に基づく医療制度を確立しました。
これにより、医師免許制度が導入され、医師になるためには試験に合格することが必要となりました。
2-2. 医師開業試験
明治9年(1876年)からは、「医術開業試験」が始まり、医師の資格が厳格に審査されるようになりました。
ただし、甲種医学校(現在の大学医学部)の卒業生は、無試験で開業免許が与えられました。
2-3. 旧医師法・旧歯科医師法
明治39年(1906年)には、旧医師法と旧歯科医師法が制定され、初めて医師免許制度が確立されました。
これにより、医師の資格要件や業務範囲などが明確に定められました。
2-4. 健康保険法
大正11年(1922年)には、健康保険法が制定され、公的医療保険制度がスタートしました。
当初は、炭鉱や鉱山の労働者を対象とする職域保険でしたが、徐々に対象が拡大されていきました。
2-5. 国民医療法
戦時中の昭和17年(1942年)には、医療関連の法制度が国民医療法に統合されました。
3戦後
戦後、GHQ(連合国軍総司令部)の指導のもと、日本の医療制度は大きく改革されました。
3-1. 医療関連法の制定
昭和23年(1948年)には、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法(当時は保健婦助産婦看護婦法)、医療法などが一斉に制定されました。
これにより、医療従事者の資格や業務範囲、医療機関の開設・運営に関するルールなどが明確に定められました。
3-2. 医療法人制度の創設
昭和25年(1950年)には、医療法が改正され、医療法人制度が創設されました。
当初は、医師または歯科医師が3名以上常時勤務することが医療法人設立の要件でしたが、昭和60年(1985年)の医療法改正により、医師または歯科医師が1人でも医療法人を設立できるようになりました(一人医師医療法人)。
3-3. 社会保険診療報酬支払基金
昭和23年(1948年)には、社会保険診療報酬支払基金が発足し、医療機関への診療報酬の支払いが、この基金を通じて行われるようになりました。
4「医療法」改正の歴史(主な改正点)
医療法は、社会情勢の変化や医療技術の進歩、国民のニーズの多様化などに合わせて、これまで何度も改正されてきました。
ここでは、主な改正点とその背景、目的、具体的な内容、そして医療機関や患者に与えた影響について、さらに詳しく解説します。
4-1. 昭和60年(1985年)改正:医療計画と病床規制の導入
この改正は、高度経済成長期を経て、病院数や病床数が急増し、医療資源の地域偏在や過剰な医療供給が問題となっていた状況を受けて行われました。
(1)背景:
・病院数・病床数の急増と地域偏在
・医療費の増大
・医療の質に対する懸念
(2)目的:
・医療資源の適正配置
・医療提供体制の効率化
・医療の質の向上
(3)主な改正内容:
①医療計画制度の導入:
都道府県に対し、地域の医療提供体制の整備を図るための計画(医療計画)の策定を義務付けました。
医療計画では、地域の医療需要を推計し、必要な病床数や医療機能などを定めることになりました。
②病床規制の導入:
病院の開設や増床を許可制とし、医療計画に基づいて病床数を規制する「病床規制」が導入されました。
これにより、都道府県知事は、医療計画に適合しない病院の開設や増床を許可しないことができるようになりました。
③一人医師医療法人の設立:
医師または歯科医師が1人でも医療法人を設立できるようになりました。
これにより、個人開業医の事業承継や経営の安定化が図られるようになりました。
④医療法人の会計年度の統一:
医療法人の会計年度が、原則として4月1日から3月31日までに統一されました(以前は自由な期間設定が可能でした)。
(4)影響:
医療計画制度と病床規制の導入により、医療資源の適正配置が進み、地域間の医療格差の是正が図られました。
一人医師医療法人の設立が可能になったことで、個人開業医の事業承継が円滑に進むようになり、地域医療の継続性が確保されるようになりました。
4-2. 平成4年(1992年)改正:特定機能病院と情報提供
この改正は、高度化・専門化する医療に対応するため、医療機関の機能分化を推進し、患者への情報提供を充実させることを目的として行われました。
(1)背景:
・医療技術の高度化・専門化
・患者のニーズの多様化
・患者の自己決定権の尊重
(2)目的:
・医療機関の機能分化
・患者への情報提供の充実
・患者の自己決定権の尊重
(3)主な改正内容:
特定機能病院と療養型病床群の制度化: 高度な医療を提供する「特定機能病院」と、長期療養を必要とする患者のための「療養型病床群」が制度化されました。
これにより、医療機関の機能分化が進み、患者は自身の病状やニーズに合った医療機関を選択できるようになりました。
①広告規制の一部緩和:
医療機関の広告規制が一部緩和され、専門外来の名称や診療時間、入院設備の有無などが広告できるようになりました。
②院内掲示の義務化:
医療機関は、診療時間、診療科目、医師の氏名、提供する医療サービスの内容などを院内に掲示することが義務付けられました。
これにより、患者は、医療機関を選択する上で必要な情報を得やすくなりました。
(4)影響:
医療機関の機能分化が進み、患者は自身の病状やニーズに合った医療機関を選択できるようになりました。
医療機関の情報公開が進み、患者の自己決定権が尊重されるようになりました。
4-3. 平成9年(1997年)改正:地域医療連携の推進
この改正は、地域における医療機関の連携を強化し、患者が適切な医療を継続的に受けられる体制を整備することを目的として行われました。
(1)背景:
・高齢化の進展
・疾病構造の変化(慢性疾患の増加)
・医療の専門分化
(2)目的:
・地域医療連携の推進
・かかりつけ医機能の強化
・患者中心の医療の実現
(3)主な改正内容:
①地域医療支援病院の制度化:
かかりつけ医を支援し、地域医療連携の中核となる「地域医療支援病院」が制度化されました(総合病院は廃止)。
地域医療支援病院は、地域の医療機関からの紹介患者に対する医療提供、医療機器の共同利用、地域の医療従事者への研修などを行うことが求められます。
②医療法人の付帯業務の拡大:
医療法人の付帯業務として、訪問介護、短期入所生活介護、通所介護などが認められるようになりました。
これにより、医療法人が介護サービスを提供しやすくなり、医療と介護の連携が進みました。
(4)影響:
地域医療支援病院の制度化により、地域の医療機関の連携が進み、患者はより適切な医療を受けやすくなりました。
医療法人の付帯業務の拡大により、医療と介護の連携が進みました。
4-4. 平成12年(2000年)改正:病床区分の見直しと医療の質の向上
この改正は、医療提供体制の効率化と、医療の質の向上を図ることを目的として行われました。
(1)背景:
・医療費の増大
・病床利用の効率化の必要性
・医療の質の向上に対する社会的要請
(2)目的:
・医療提供体制の効率化
・医療の質の向上
・患者の安全確保
(3)主な改正内容:
①病床区分の見直し:
病院の病床区分が、「一般病床」と「療養病床」の2つに整理されました。
これにより、病院の機能分化が進み、医療資源の効率的な利用が図られるようになりました。
②広告規制の緩和:
医療機関の広告規制がさらに緩和され、専門医の氏名や診療実績、手術件数などが広告できるようになりました。
これにより、患者は、医療機関を選択する上でより多くの情報を得られるようになりました。
医師・歯科医師の臨床研修の義務化: 医師・歯科医師の卒後臨床研修が義務化されました(2年以上の臨床研修)。
これにより、医師・歯科医師の質の向上が図られるようになりました。
(4)影響:
病床区分の見直しにより、病院の機能分化が進み、医療資源の効率的な利用が図られました。
広告規制の緩和により、患者は、医療機関を選択する上でより多くの情報を得られるようになりました。
医師・歯科医師の臨床研修の義務化により、医師・歯科医師の質の向上が図られました。
4-5. 平成18年(2006年)改正:医療情報の公開と医療法人制度改革
この改正は、患者が医療機関を適切に選択できるよう情報提供を推進するとともに、医療法人制度を見直し、経営の透明化やガバナンス強化を図ることを目的として行われました。
(1)背景:
・患者の医療機関選択の自由の拡大
・医療機関の経営の透明化・効率化の必要性
・医療法人制度の悪用事例の発生
(2)目的:
・患者による医療機関の適切な選択の支援
・医療法人制度の見直し
・医療機関の経営の透明化・効率化
(3)主な改正内容:
①医療機能情報提供制度:
都道府県が、医療機関の基本的な情報(所在地、診療科目、診療時間、提供する医療サービスの内容、医療従事者の数など)を集約し、Webなどで公表する「医療機能情報提供制度」が導入されました。
これにより、患者は、医療機関を選択する上で必要な情報を容易に入手できるようになりました。
②社会医療法人制度の創設:
へき地医療、小児救急医療など、公共性の高い医療を提供する医療法人を「社会医療法人」として認定する制度が創設されました。
社会医療法人には、税制上の優遇措置などが設けられています。
持分なし医療法人への移行促進: 持分の定めのある社団医療法人(出資持分のある医療法人)の新規設立が認められなくなり、既存の社団医療法人に対しては、持分の定めのない医療法人(出資持分のない医療法人)への移行が促されるようになりました。
これは、医療法人の非営利性を徹底し、経営の透明化を図るための措置です。
(4)影響:
医療機能情報提供制度の導入により、患者は、医療機関を選択する上で必要な情報を容易に入手できるようになりました。
社会医療法人制度の創設により、公共性の高い医療を提供する医療法人が増加しました。
持分なし医療法人への移行促進により、医療法人の経営の透明化が進みました。
4-6. 平成26年(2014年)改正:地域包括ケアシステムの推進
この改正は、高齢化が急速に進展する中で、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域における医療・介護サービスの連携を強化することを目的として行われました。
(1)背景:
・高齢化の急速な進展
・医療・介護ニーズの増大
・地域包括ケアシステムの構築の必要性
(2)目的:
・地域包括ケアシステムの構築
・医療・介護サービスの連携強化
・在宅医療・介護の推進
(3)主な改正内容:
①地域包括ケアシステムの構築:
地域における医療・介護サービスの連携を強化し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、「地域包括ケアシステム」の構築が推進されました。
②病床機能報告制度:
病院・診療所が、自院の病床の機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)を都道府県に報告する「病床機能報告制度」が導入されました。
これにより、地域の医療資源の状況が「見える化」され、医療機関の機能分化・連携が進められるようになりました。
③認定医療法人制度:
一定の要件を満たす医療法人を「認定医療法人」として認定する制度が創設されました。認定医療法人には、税制上の優遇措置などが設けられています。
(4)影響:
地域包括ケアシステムの構築が進み、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるための体制整備が進みました。
病床機能報告制度の導入により、地域の医療資源の状況が「見える化」され、医療機関の機能分化・連携が進みました。
4-7. 平成27年(2015年)改正:医療法人のガバナンス強化
この改正は、医療法人の経営の透明化やガバナンス強化を図り、地域医療連携を推進することを目的として行われました。
(1)背景:
・医療法人の経営の不透明性
・医療法人のガバナンスの脆弱性
・地域医療連携の必要性
(2)目的:
・医療法人の経営の透明化・ガバナンス強化
・地域医療連携の推進
・医療法人の健全な発展
(3)主な改正内容:
①地域医療連携推進法人制度の創設:
複数の医療機関や介護事業所などが連携し、地域包括ケアシステムを推進するための新たな法人形態「地域医療連携推進法人」が創設されました。
②医療法人のガバナンス強化:
医療法人の理事長の要件が厳格化され、原則として医師または歯科医師であることが求められるようになりました。
また、一定規模以上の医療法人には、理事会・評議員会の設置が義務付けられました。
③医療法人の分割:
医療法人の分割(吸収分割、新設分割)が可能となりました。
これにより、医療法人の事業再編が容易になりました。
④社会医療法人制度の見直し:
社会医療法人の認定要件などが見直されました。
(4)影響:
地域医療連携推進法人制度の創設により、地域における医療・介護サービスの連携が進みました。
医療法人のガバナンス強化により、医療法人の経営の透明化が進み、地域住民からの信頼が高まりました。
4-8. 平成29年(2017年)改正:医療広告規制の強化
この改正は、医療に関する広告について、患者を誤認させるような虚偽・誇大広告を規制し、患者の適切な医療機関選択を支援することを目的として行われました。
(1)背景:
・医療に関する虚偽・誇大広告の増加
・患者の適切な医療機関選択の阻害
・医療に対する信頼の低下
(2)目的:
・医療に関する広告規制の見直し
・患者の適切な医療機関選択の支援
・医療に対する信頼の確保
(3)主な改正内容:
①医療に関する広告規制の強化:
医療に関する広告について、虚偽・誇大広告や、患者を誤認させるような広告が禁止されました。
具体的には、以下のような広告が禁止されました。
・虚偽広告(例:事実と異なる内容の広告)
・比較優良広告(例:「日本一」「最高」など、客観的な根拠がない広告)
・誇大広告(例:効果を過大に表現する広告)
・患者の体験談(例:個人の感想に基づく広告)
・その他、公序良俗に反する広告など
②ウェブサイトの規制対象化:
従来、規制対象外であった医療機関のウェブサイトも、広告規制の対象となりました。
③持分なし医療法人移行計画認定制度の要件緩和・期間延長:
持分の定めのない医療法人への移行を促進するため、移行計画の認定要件が緩和され、認定期間が延長されました。
④開設者への監督規定整備:
医療機関の開設者に対する監督規定が整備され、都道府県知事の指導・監督権限が強化されました。
(4)影響:
医療に関する広告規制の強化により、患者は、より正確な情報に基づいて医療機関を選択できるようになりました。
医療機関のウェブサイトも広告規制の対象となったため、医療機関は、ウェブサイトの記載内容に注意する必要が生じました。
4-9. 平成30年(2018年)改正:医師偏在対策
この改正は、医師不足が深刻な地域への医師の偏在を解消し、地域間の医療格差を是正することを目的として行われました。
(1)背景:
・医師不足の深刻化
・医師の地域偏在
・地域間の医療格差の拡大
(2)目的:
・医師偏在対策の推進
・医師不足地域への医師の確保
・地域間の医療格差の是正
(3)主な改正内容:
複数の医療機関の管理が可能である場合の要件の明確化: 医療法人が複数の医療機関を管理する場合の要件が明確化されました。
〇医師偏在対策:
医師偏在対策として、医師の確保に関する計画の策定、医師の派遣に関する規定などが設けられました。
具体的には、都道府県が、医師の確保に関する計画(医師確保計画)を策定し、医師不足地域への医師の派遣を促進することなどが定められました。
(4)影響:
医師偏在対策が進み、医師不足地域への医師の確保が図られることが期待されます。
これらの改正は、医療提供体制の確保、医療の質の向上、患者の安全確保、そして地域医療の充実など、多岐にわたる目的のために行われてきました。
医療法は、今後も社会情勢の変化や医療技術の進歩などに合わせて、改正されていくことが予想されます。
医療機関の経営者や管理者は、常に最新の情報を把握し、適切な対応をとることが求められます。
5まとめ
日本の医療制度は、江戸時代から現代に至るまで、様々な変遷を経てきました。
特に、戦後の医療法制定以降、医療提供体制の整備、医療の質の向上、患者の権利保護などを目的として、数多くの改正が行われてきました。
医療法は、医療機関の開設・運営に関する基本的なルールを定めた法律であり、医療機関の経営者や管理者にとっては、必ず理解しておかなければならない法律です。
また、医師法は、医師の資格や業務範囲、義務などを定めた法律であり、医師にとっては、最も重要な法律の一つです。
医療法や医師法は、頻繁に改正されるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。
また、医療法や医師法だけでなく、健康保険法、介護保険法、薬機法(旧薬事法)など、医療に関連する様々な法律があり、これらの法律を総合的に理解しておくことが、適切な医療経営を行う上で不可欠です。
しかし、医療関連の法制度は複雑であり、一般の方には理解しにくい部分も多くあります。
また、医療機関の開設・運営には、様々な手続きが必要であり、専門的な知識や経験が必要となる場面も少なくありません。
行政書士藤井等事務所は、医療法人設立・運営の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
医療法や医師法などの法律は複雑で分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「医療法人を設立したい」「医療法改正について詳しく知りたい」「医療機関の運営について相談したい」という方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
なお、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や都道府県といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。
この記事を読んで、少しでも医療の行政対応について考えるきっかけになれば幸いです。
6注意事項
厚生労働省(地方厚生局)や都道府県、各保健所への申請については、行政書士が、唯一行政機関への申請が認められている国家資格者です。
行政書士以外の者(医療コンサルタントなど)が、他人の依頼を受けて、必要な申請などを代理することは法律で禁止されており、違法な申請代理をした場合は「罰則」が適用されるので、十分注意する必要があります。
7お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ