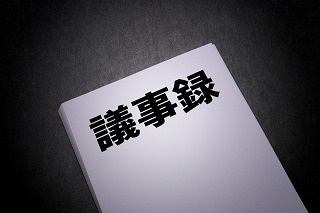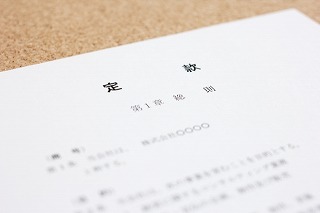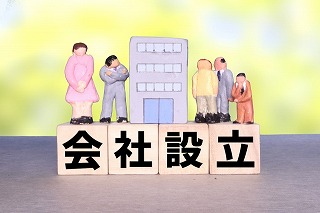
「節税や将来の相続対策、事業の多角化など、クリニック経営の悩みは尽きない…」
「MS法人という言葉は聞くけれど、自院にとって本当にメリットがあるのか、どう活用すればいいか分からない」
こんなお悩みはありませんか?
その漠然とした不安や疑問は、MS法人を正しく理解することで解決できるかもしれません。
この記事では、クリニック経営者の皆様へ、MS法人設立のメリットから法改正による注意点まで、専門家の視点で分かりやすく解説します。
1 MS法人という選択肢
クリニック経営者の皆様なら、「MS法人」という言葉を一度は耳にしたことがあるかもしれません。
しかし、MS法人(メディカル・サービス法人)は、実は法律で明確に定義された法人形態ではありません。
一般的に、院長先生やそのご親族が経営し、医療機関との間で不動産賃貸や医療事務の委託など、何らかの取引を行う株式会社や合同会社のことを指します。
また、直接的な取引がなくても、クリニックに併設してコンタクトレンズや化粧品、サプリメントなどを販売する会社もMS法人と呼ばれることがあります。
では、なぜ多くの医療機関がMS法人を設立するのでしょうか。その目的は、主に以下の点に集約されます。
〇 MS法人設立の一般的な目的
MS法人を設立する目的として、一般的には以下のような項目が挙げられます。
⑴ 相続・事業承継対策
⑵ 医療法人では実施できない事業の展開 (例:介護サービス、サプリメントの通信販売など)
⑶ 不動産(土地・建物)の管理
⑷ 節税対策
⑸ 医療法人の資産を適切に管理・分散するため
ただし、ここで注意したいのが「⑷節税対策」です。
安易に「節税」だけを目的として設立すると、かえって消費税の課税事業者となり、想定外の税負担が発生するなど、期待した効果が得られないケースも少なくありません。
MS法人の真価は、節税という一面だけでなく、クリニック経営の自由度を高め、将来のリスクに備えるための戦略的な一手となり得る点にあります。
2 個人開業クリニックにおけるMS法人活用のメリット
特に個人開業の先生方にとって、MS法人の活用は医療法人化せずとも経営の選択肢を広げる大きなメリットをもたらします。
医療法人化は、都道府県への申請や登記、毎年の事業報告など、手続きが非常に煩雑です。
その点、MS法人は比較的スムーズに設立・運営が可能です。
〇 経営の自由度を高める具体的なメリット
個人開業のクリニックがMS法人を活用することで、具体的に以下のようなメリットが生まれます。
⑴ 経営者への給与支払い:
院長先生個人への所得集中を避け、MS法人から役員報酬として給与を支払うことで所得を分散できます。
⑵ 親族の役員就任と報酬支払い:
ご家族を役員に迎え、業務内容に応じた適切な役員報酬(非常勤も可)を支払うことで、世帯全体での所得分散が図れます。
⑶ 生命保険の活用:
役員を被保険者とする生命保険に加入し、支払った保険料を法人経費として計上できます。これは、将来の退職金準備としても有効です。
⑷ 役員退職金の支給:
勇退される役員に対して退職金を支払うことができ、これは税制上も大きな優遇措置が受けられます。
⑸ 役員社宅の提供:
MS法人が所有または賃借した物件を役員社宅として貸与することで、家賃負担を軽減できます。
⑹ 税率の違いによる節税:
個人の所得税率は累進課税で最大45%ですが、法人税率は一定です。
所得が一定額を超える場合、法人税率の方が低くなるため、節税につながります。
このように、MS法人という「器」を持つことで、個人事業のままでは実現が難しい、多様な経営戦略を展開することが可能になるのです。
3 医療法人がMS法人を活用すべき3つのケース
すでに出資持分なし医療法人を経営されている先生方にとっても、MS法人の設立は重要な経営判断となる場合があります。
3-1. ケース1:不動産所有による経営リスク
医療法人は非営利性が原則であり、社員(出資者)は1人1票の議決権を持ちます。
そのため、社員間の対立など、万が一の事態が発生した場合、経営の主導権を失う「乗っ取り」のリスクがゼロではありません。
もし、クリニックの土地・建物といった重要な資産をすべて医療法人で所有していると、経営権を失った場合にすべての財産を失う危険性があります。
MS法人で不動産を所有し、医療法人へ賃貸する形をとることで、このリスクを効果的に分散できます。
3-2. ケース2:円満な相続・事業承継
医療法人の理事長は、原則として医師または歯科医師でなければなりません。
そのため、クリニックを承継できるのは、医師になったお子様一人に限られるのが一般的です。
お子様が複数いらっしゃる場合、医院を継がないご子息・ご令嬢との間で、将来の相続トラブルに発展するケースは後を絶ちません。
その点、MS法人であれば、代表取締役に資格要件はなく、配当も可能です。
不動産など収益性の高い資産をMS法人に持たせることで、医院を継がないご家族にも資産を分配しやすくなり、円満な相続の実現を助けます。
3-3. ケース3:医療法人の資金を活用
ご存知のとおり、医療法人では利益の配当が禁止されており、内部留保された資金を自由に使うことはできません。
MS法人へ適正な対価(業務委託料や賃料など)を支払う形で資金を移転し、その資金を元手に新たな事業展開を図るなど、より柔軟で戦略的な資金活用が可能になります。
ただし、この取引は医療法人の非営利性を損なわないよう、取引価格の妥当性などに細心の注意を払う必要があります。
4 最大の注意点
MS法人を有効に活用する上で、避けては通れないのが「関係事業者との取引の状況に関する報告書」の提出義務です。
平成27年度の医療法改正により、医療法人は決算届を提出する際、理事長の配偶者が代表を務めるMS法人など、特定の関係事業者との取引状況を都道府県に報告することが義務化されました。
例えば、「年間の取引額が1,000万円以上、かつ、それが医療法人の総事業費用の10%以上を占める取引」などが対象となります。
この報告制度は、医療法人とMS法人との間の取引が、不当に高額でないか、実態が伴っているかなどを、行政が厳しくチェックするようになったことを意味します。
税務調査においても、MS法人との取引は最も注視されるポイントの一つです。
⑴契約書の整備:
取引内容を明確にした契約書を必ず作成する。
⑵金額の算定根拠:
なぜその金額なのか、客観的な根拠資料(相見積もりなど)を準備する。
⑶業務の実態:
委託した業務が、MS法人側で実際に適切に行われていることを証明できるようにする。
これらの点を疎かにすると、税務署から取引自体を否認され、追徴課税などの重いペナルティを課されるリスクがあります。
5 まとめ
医療法人の設立から日々の運営、そしてMS法人の活用に至るまで、先生方が向き合うべき許認可申請や法的手続きは、年々複雑化しています。
「何から手をつけていいか分からない」「日々の診療で忙しく、手続きまで手が回らない」というのが、多くの先生方の本音ではないでしょうか。
このような複雑で専門性の高い手続きは、専門家である行政書士に一括してお任せいただくことで、先生は安心して本業である医療に専念いただけます。
私たちは、煩雑な書類作成から行政機関との折衝まで、あらゆるプロセスを代行し、スムーズな手続きの実現をサポートします。
当事務所は、単に手続きを代行するだけではありません。
医療の最前線で奮闘される先生方に徹底的に寄り添い、それぞれのクリニックが抱える課題に対し、最善の解決策を提案することをお約束します。
【当事務所の強み】
当事務所の最大の強みは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労士といった他士業の専門家と緊密な連携体制を構築している点です。
MS法人設立に伴う税務相談から労務管理まで、あらゆる問題にワンストップで、かつ迅速に対応いたします。
さらに、私自身が元岩手県職員として、企業誘致や県立大学の新設といった大規模プロジェクトに携わってきた経験があります。
この経験から、国や県、各保健所といった行政機関の内部事情や意思決定のプロセスを熟知しております。
行政側の視点を理解し、「担当者が何を求めているのか」を先読みした的確な対応・調整ができることは、他にはない絶対的な強みであると自負しております。
初回のご相談は無料です。
ぜひ一度、お気軽にお声がけください。
★注意事項
厚生労働省(地方厚生局)や県、保健所などへの許認可申請書類の作成および代理提出は、行政書士法に基づき、行政書士のみに認められた業務です。
行政書士の資格を持たない者が、報酬を得てこれらの業務を行うことは、法律で固く禁じられています。
大切なクリニックの未来に関わる手続きは、必ず国家資格者である行政書士にご依頼ください。
6 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ
https://office-fujiihitoshi.com/