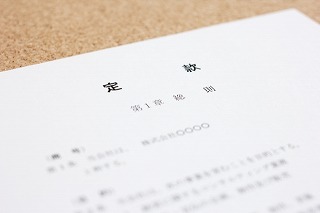「医療法人を設立したいが、役員(理事・監事)と『社員』の違いがよく分からない」
「社員の人数や決め方で失敗したくない」
こんな悩みはありませんか?
その悩み、本記事で解決できます。医療法人の「社員」は、株式会社の株主とは全く異なり、その理解不足が将来の経営トラブルに直結します。
今回の記事では、岩手県で医療法人設立を目指す先生方へ、運営の根幹となる「社員」の役割や注意点を、行政書士が分かりやすく解説します。
1 医療法人の最重要機関:「社員」とは?
医療法人の設立準備において、「社員」という言葉は非常によく使われますが、その定義は一般社会で使われる意味とは全く異なります。
まず、この「社員」の正確な役割を理解することが、医療法人運営の第一歩です。
1-1. 社員 = 従業員ではない!
多くの方が混同しがちなのが、「社員」と「従業員(スタッフ)」の違いです。
⑴ 従業員(スタッフ):
先生のクリニックで働く看護師、医療事務、技師の方々です。雇用契約に基づき、労働力を提供する方々を指します。
⑵ 社員(法律用語):
社団医療法人の「社員総会」の構成員を指します。
「社員総会」とは、その医療法人の最高意思決定機関です。
株式会社でいうところの「株主総会」に相当します。
つまり、「社員」とは、医療法人の経営における最重要事項(例:定款の変更、役員(理事・監事)の選任・解任、事業計画の承認、解散など)を決定する権限を持つ、「法人のオーナー」とも言える存在なのです。
通常、医療法人を設立する際の発起人(設立者)が、そのまま設立後の「社員」となります。
1-2. 株式会社の「株主」とも異なる「議決権」
「社員総会が株主総会のようなものなら、社員は株主と同じか」というと、これも決定的に異なります。
株式会社の場合、原則として「1株1議決権」であり、出資額(株式数)が多いほど、経営に対する影響力が強くなります。
しかし、社団医療法人の場合、医療法によって「出資額の多寡に関わらず、一人一票」の平等な議決権を持つことが定められています。
例えば、院長先生が1,000万円、他の社員Aが100万円を出資していたとしても、社員総会での議決権は、院長先生も社員Aも「同じ1票」です。
この「非営利性・公共性」こそが医療法人の大きな特徴であり、株式会社と同じ感覚でいると、将来の経営権(コントロール)に問題が生じる可能性があります。
2 なぜ「社員」の人数と構成が重要なのか?
では、具体的に「社員」を何人に設定すれば良いのでしょうか。ここにも実務上の重要なポイントがあります。
2-1. 「社員3名以上」が推奨される実務的な理由
医療法において、「社員の数は〇人以上でなければならない」という法律上の明確な規定はありません。
しかし、厚生労働省が示しているモデル定款や、多くの都道府県の設立認可実務においては、「社員は3名以上とすることが望ましい」と指導されます。
(神奈川県は、4名以上と定めている例もあります)
なぜでしょうか。
それは、社員総会が円滑に機能し、安定した法人運営を確保するためです。
2-2. 社員総会の「定足数」と「議決」の仕組み
医療法人の社員総会は、原則として「総社員の過半数」が出席しなければ会議を開くことができません(=定足数)。
そして、会議での議決は、「出席した社員の過半数」の賛成によって決まります(=議決)。
ここで、もし社員が2名だったらどうなるか考えてみましょう。
定足数は過半数なので「2名」です。
つまり、常に2名全員が出席しなければ会議が成立しません。
もし1名が欠席すれば、何も決められないことになります。
また、2名が出席しても、ある議案に対して賛否が1対1で割れた場合、議決ができず、法人の運営が停滞してしまいます。
これに対し、社員が3名の場合はどうでしょうか。
定足数は過半数なので「2名」です。
3名中2名が出席すれば、会議は成立します。
もし2名が出席した場合、議決にはその過半数(つまり2名全員)の賛成が必要です。
もし3名全員が出席した場合、議決には過半数(つまり2名)の賛成があれば可決されます(2対1)。
このように、社員を3名以上(特に奇数)にしておくことで、議決が停滞するリスクを減らし、安定した法人運営が可能となるのです。
3 最も注意すべき「社員の入退社」問題
法人の運営において、役員(理事・監事)の変更は頻繁に発生しますが、それ以上に慎重に扱わなければならないのが「社員」の変更(入社・退社)です。
3-1.「持分あり医療法人」の退社問題
特に注意が必要なのが、平成19年(2007年)の医療法改正前に設立された「持分の定めのある医療法人」です。
(※現在、新規設立できるのは「持分の定めのない医療法人」のみです)
「持分あり」の法人の社員が退社する際、その社員は法人に対し「持分払戻請求権(出資額の払戻しを求める権利)」を有します。
問題は、払い戻される金額が「当初の出資額」ではない、という点です。
払戻額は、「退社時点での法人の純資産額 × その社員の出資持分率」で計算されます。
例えば、設立時に100万円を出資した社員がいたとします。
そのクリニックが長年の経営努力で大きく成長し、退社時点での純資産(土地、建物、医療機器、内部留保など)が5億円になっていた場合、その社員の持分率(仮に20%)によっては、法人は「1億円」もの大金を払い戻さなければならない可能性があるのです。
これが、いわゆる「出資持分問題」であり、医療法人の円滑な継承や存続を脅かす最大のリスクの一つです。
3-2. 紛争を防ぐ「定款」の重要性
社員の入退社に関するルールは、医療法では細かく定められていません。
だからこそ、法人の根本ルールである「定款」で、これらの規定をいかに整備しておくかが、将来の紛争を防ぐ鍵となります。
厚生労働省のモデル定款では、以下のような規定を置くことが推奨されています。
⑴入社:
新たに社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。
⑵資格喪失:
社員は、「死亡」「除名」「退社」によってその資格を失う。
⑶退社:
退社を希望する際は、理事長に届け出て、「その同意」を得て退社することができる。
特に最後の「同意」規定は重要です。
仮に前述の持分あり法人の社員から、突然、高額な払戻請求を伴う退社届が出された場合でも、定款に「法人の同意が必要」と定めておくことで、一方的な退社を防ぐ一定の防衛策となり得ます。
4 手続きの専門家「行政書士」を活用するメリット
ここまで見てきたように、「社員」の設計一つとっても、医療法人は株式会社とは全く異なる、専門的な知識と手続きが要求されます。
4-1. 医療法人設立・運営は「行政手続き」の連続
医療法人の設立は、単に登記をすれば終わりではありません。
主たる事務所(クリニック)の所在地を管轄する県知事の「設立認可」を得る必要があります。
この認可申請には、難解な定款の作成、事業計画書、予算書の策定、保健所との事前調整など、膨大な書類作成と複雑な行政手続きが伴います。
また、設立後も、社員が変更(死亡・入退社)すれば「社員名簿の変更届」、役員が変更すれば「役員変更届」、事業年度が終了すれば「事業報告書等届」など、定期・不定期に岩手県や保健所への届出が義務付けられています。
4-2. 専門家による「ワンストップ」の安心感
これらの手続きを、先生方や医療事務スタッフが、日々の診療と並行して行うのは大変なご負担です。
「何から手を付けていいか分からない」 「書類の不備で何度も行政機関に足を運ぶことになった」 「重要な届出を忘れていて、行政指導を受けてしまった」
こうした事態に陥る前に、医療法務の専門家である行政書士にご相談ください。
5 まとめ
医療法人の設立や、設立後の行政機関への許認可・届出について、何から手を付けていいか分からない、というのが多くの先生方の本音ではないでしょうか。
複雑な行政手続きを、その道の専門家である行政書士にトータルでお任せいただくことで、先生方には本業である医療に専念いただく「安心」をご提供できます。
当事務所は、常に医療サイドに寄り添い、個々のクリニックの状況(継承問題、分院展開、MS法人との連携など)に合わせた最善の解決策をご提案いたします。
当事務所の最大の特徴は、弁護士、司法書士(登記)、税理士(税務)、社会保険労務士(労務)といった他士業との強力な連携です。
医療法務に関連するあらゆる問題に対し、ワンストップで迅速に対応できる体制を整えています。
さらに、私自身が元岩手県職員として、企業誘致や県立大学新設といった大型プロジェクトの行政調整に携わった経験がございます。
この経験こそが、国や岩手県、管轄の保健所といった行政機関の「考え方」を熟知し、迅速かつ的確な調整・折衝を行える、他にはない「強み」です。
岩手県内での医療法人設立・運営でお困りの際は、ぜひ一度、行政書士藤井等事務所にご相談ください。
★注意事項
厚生労働省(地方厚生局)や県、各保健所への医療法人設立認可申請や各種届出は、行政書士法に基づき、行政書士が唯一、業として他人の依頼を受けて申請書等を作成し、提出を代理することが認められている国家資格者です。
行政書士以外の者(経営コンサルタント等)が、報酬を得てこれらの申請代理業務や書類作成を行うことは、法律で固く禁止されています。
6 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ
https://office-fujiihitoshi.com/