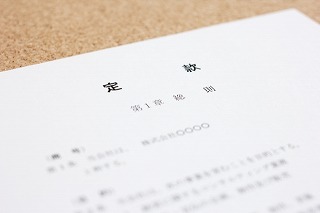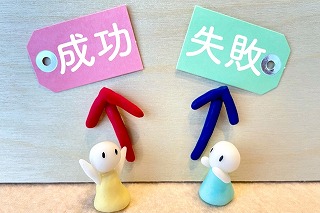「そろそろ医療法人化を検討しているが、個人資産の移転が複雑で分からない」
「クリニックの土地建物や高額な医療機器をすべて拠出(寄附)すると、手元の資金が不安だ」
「個人時代の借入金はどうなるのか…」
こんな悩みはありませんか?
そのお悩み、今回の記事で解決できるかもしれません。
医療法人設立時の資産移転は、必ずしもすべてを拠出する必要はなく、もっと柔軟な方法が存在します。
今回は、先生方の資金繰りや将来設計を守りながら賢く法人化するための「資産移転のテクニック」について、具体的な方法と注意点を分かりやすく紹介します。
1 なぜ「資産を拠出しない」選択肢が重要なのか?
医療法人化というと、個人事業主時代に事業(クリニック)で使っていた資産=土地、建物、医療機器、車両、未収金などを、すべて新設する医療法人に「拠出(寄附または基金)」しなければならない、と思い込んでいる先生方が少なくありません。
もちろん、それも一つの方法です。
しかし、特に不動産のような高額な資産を拠出してしまうと、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
⑴ 設立時の運転資金が圧迫される(拠出財産とは別に、設立後2ヶ月分以上の運転資金も必要)
⑵ 個人の財産形成が難しくなる
⑶ 将来の相続や事業承継の際に手続きが複雑化する
⑷ 不動産にローンの残債(抵当権)があると、金融機関の承諾が必要で手続きが難航する
そこで、医療法人の財産的基礎を確保しつつも、これらのデメリットを回避する方法として、「売買契約」や「賃貸借契約」を活用するテクニックが非常に有効となります。
2 「売買・賃貸」を活用した資産移転、4つの重要ポイント
個人(院長先生)と新設する医療法人の間で、資産の「売買」や「賃貸」を行う具体的な手法と注意点を解説します。
2-1. ポイント①:不動産(土地・建物)は「賃貸借契約」が最適解
クリニックの土地や建物が先生ご個人の所有である場合、最も推奨される方法は、医療法人へ拠出せず、先生個人と医療法人の間で「賃貸借契約」を結ぶことです。
先生個人は医療法人から毎月「家賃収入」を得ることができ、法人は家賃を「経費」として計上できます。
これにより、個人の資産形成と法人の節税効果を両立できます。
【注意点:適正家賃の設定】
この際、家賃が不当に高額だと税務署から否認されたり、行政指導の対象となったりするリスクがあります。
必ず、近隣の類似物件の賃料(いわゆる「近傍類似値」)を調査し、その調査資料を根拠として適正な家賃を設定する必要があります。
この「近傍類似値」は、不動産鑑定士に依頼せずとも、インターネットの不動産情報サイトなどで検索した結果を資料として添付することで認められるケースが一般的です。
2-2. ポイント②:医療機器は「分割払い売買」で運転資金を温存
次に、高額な医療機器です。
これをリース契約にしているクリニックも多いですが、法人化の際にそのまま引き継ぐのは注意が必要です。
リース会社ではない個人(あるいはMS法人)が、反復継続して医療法人に機器をリース(賃貸)すると、その行為自体が「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可を必要とする事業とみなされ、無許可営業として薬機法違反に問われるリスクがあります。
そこでお勧めするのが、医療法人との「売買契約」です。
さらに、その代金を一括ではなく「分割払い」にするのがミソです。
これにより、医療法人は設立当初に多額の購入資金を準備する必要がなくなり、設立認可で求められる「設立後2年間の運転資金」の必要額を低く抑えることができます。
【売買代金はどう決める?】
売買代金は、一般的に個人事業時代の「固定資産台帳の簿価(未償却残高)」を使用します。
① 税込経理方式の場合: そのまま簿価
② 税抜経理方式の場合: 簿価に消費税を加算した金額
とするのが実務上スムーズです。
2-3. ポイント③:個人時代の「借入金引継ぎ」問題の解決策
法人化の際、最も頭の痛い問題の一つが「個人時代の借入金」の扱いです。
原則として、医療法人が設立時に引き継げる負債は「設備資金(拠出した資産の購入資金)」に限られ、「運転資金」の借入は引き継げません。
また、引継ぎには金融機関の「負債引継ぎ承諾書」が必要となり、交渉に時間がかかることもあります。
しかし、前述の「医療機器の分割払い売買」を活用すると、この問題もクリアできる可能性があります。
(具体例)
・先生個人が、簿価1,000万円の医療機器を、医療法人へ1,000万円で売却(分割払い)。
・医療法人には、先生個人に対する「未払金 1,000万円」が発生します。
・一方、先生個人には、銀行に対する「借入金 1,000万円」が残っています。
・医療法人は、この「未払金」を先生に分割で支払っていきます。
・先生は、その支払いを受けたお金で、銀行への返済を続けることができます。
実質的に、法人が個人の借入金を肩代わりしているのと近い形を作れるのです。
さらに、医療法人が、先生が銀行に支払っている利息(年利)部分を「未払金に対する利息」として負担する、といった柔軟な設計も交渉可能です。
2-4. ポイント④:「利益相反取引」の手続きを忘れずに
ここまで解説した「個人(理事長)と医療法人の契約(売買・賃貸)」は、法律上「利益相反取引」と呼ばれます。
理事長個人の利益と、医療法人の利益が相反する可能性がある取引だからです。
かつて(平成28年9月以前)は、こうした取引には都道府県知事による「特別代理人」の選任が必要で、非常に手続きが煩雑でした。
しかし、医療法改正により、現在はこの「特別代理人」制度は廃止されています。
その代わり、医療法人の「理事会」において、その取引の重要な事実を開示し、承認を受けることが必須となりました。
この理事会での承認(もちろん、利害関係者である理事長自身は議決に参加できません)さえ適正に行えば、堂々と取引が可能です。
この「理事会議事録」は、認可申請やその後の登記手続きにおいても重要な証拠書類となります。
3 「MS法人」を活用する場合の3つの注意点
先生がすでにお持ちの「MS法人(メディカル・サービス法人)」から、医療法人が資産を買い取ったり、賃借したりする方法もあります。
基本的な考え方は個人との取引と同じですが、特有の注意点があります。
3-1. 注意点①:適正価格の根拠は必須
個人との取引同様、MS法人との取引も「適正な価格」で行う必要があります。
特に不動産の賃料については、MS法人が所有者であっても、医療法人は「近傍類似値」の資料を揃え、家賃の妥当性を証明しなくてはなりません。
3-2. 注意点②:最も重要な「役員兼務」の禁止
MS法人を活用する上で、行政が最も厳しく見ているのが「役員の兼務」です。
医療法人は非営利性が求められるため、営利法人であるMS法人との間で不透明な利益の移動が行われることを防ぐ目的があります。
特に、「医療法人の理事長」が「MS法人の代表取締役」を兼務することは、利益相反の観点から原則として認められません。
医療法人設立認可申請の段階、少なくとも売買や賃貸の契約を締結する時点では、この兼務状態は解消しておく必要があります。
3-3. 注意点③:都道府県への「取引状況の報告義務」
平成29年4月2日以降に開始する会計年度から、医療法人は「関係事業者(MS法人など)との取引の状況に関する報告書」を、毎年の事業報告書と共に都道府県へ提出することが義務化されました。
すべての取引が対象ではなく、例えば「年間1,000万円以上、かつ法人の総事業収益の10%以上を占める取引」など、一定の基準額を超える取引が報告対象となります。
MS法人との取引を継続する場合は、この報告義務があることを常に念頭に置いておく必要があります。
4 まとめ
医療法人の設立、特に個人資産の移転や借入金の引継ぎに関する計画は、ここまでご覧いただいた通り、非常に複雑な法律・税務・会計の知識が絡み合います。
「どの資産を、どの方法(拠出・売買・賃貸)で移転するのが最適か?」 「金融機関との交渉はどう進めるべきか?」 「理事会の承認手続きや契約書の作成は?」
これらを先生ご自身や医療事務のスタッフ様だけで判断し、実行するのは大変な労力であり、もし手順を一つ間違えれば、認可が下りなかったり、将来思わぬ税務リスクを抱えたりする可能性も否定できません。
このような複雑な手続きだからこそ、専門家である行政書士にトータルで任せることで、先生方には「安心」をご提供できます。
煩雑な書類作成や行政機関との折衝から解放され、先生ご自身は日々の診療に集中していただくことが可能になります。
当事務所は、単なる手続き代行に留まりません。
医療サイドに徹底的に寄り添い、先生のビジョンや将来設計を丁寧にお伺いした上で、最善の解決策をご提案いたします。
【行政書士藤井等事務所の「強み」】
① ワンストップ対応:
当事務所の最大の特徴は、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった他の専門家と強固な連携体制を組んでいることです。
法人設立後の登記、税務顧問、労務管理まで、医療経営に関わるあらゆる問題をワンストップでサポートし、迅速に対応いたします。
② 行政対応力(元・岩手県職員の経験):
元岩手県職員として、企業立地や県立大学新設といった大規模プロジェクトの行政調整に携わった経験があります。厚生労働省(地方厚生局)や都道府県、保健所といった行政機関の「考え方」や「判断基準」を熟知しており、許認可申請において、どこがポイントになるかを的確に見極め、素早く的確な調整・対応ができる点は、他にはない「強み」です。
③ 利便性(土日祝日・夜間も対応):
ご多忙な先生方のために、当事務所は土日・祝日も営業しております。
また、営業時間は朝8時から夜20時までとしており、診療後のお時間でも柔軟にご相談いただけます。
★注意事項
厚生労働省(地方厚生局)や都道府県、各保健所への医療法人設立認可申請や、その他の許認可申請書類の作成・提出代理は、行政書士法に基づき、行政書士のみが行うことを認められた独占業務です。
行政書士の資格を持たないコンサルティング業者などが、報酬を得る目的で、他人の依頼を受けてこれらの申請を代理することは、法律で固く禁止されています。大切な許認可手続きは、国家資格者である行政書士にご依頼ください。
5 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ
https://office-fujiihitoshi.com/