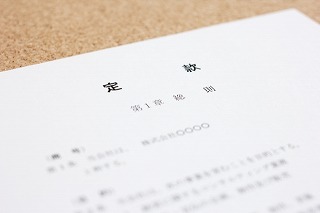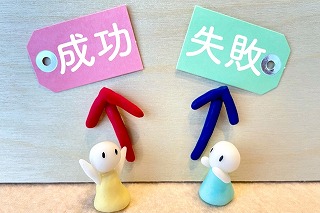
「医療法人化を考えているが、何から手をつければいいか分からない」
「申請手続が複雑で、本業の診療に集中できない」
こんな悩みはありませんか?
その悩みは、申請前の「正しい準備」を知ることで解決できます。
今回の記事では、岩手県で医療法人設立を目指す先生方のお困りごとを解決するため、認可申請前に押さえるべき重要ポイントを5つに絞って具体的に紹介します。
1 現状の「個人診療所」の届出は万全ですか?
医療法人設立の準備と聞いて、多くの方は新しい法人の定款作成や資産の拠出(きょしゅつ)などをイメージされます。
しかし、その前に確認すべき「見落とされがちな落とし穴」があります。
それは、「現在運営している個人診療所の届出内容が、最新の状況と一致しているか」という点です。
これが一致していないと、医療法人設立の認可申請そのものがストップしたり、審査が通常以上に厳しくなったりする可能性があります。
いわば、現在の土台がしっかりしていなければ、新しい家(医療法人)の建築許可は下りない、ということです。
1-1. 保健所への届出事項と「ズレ」はありませんか?
診療所を開設する際、保健所に様々な事項を届け出ています。
例えば、以下の項目です。
① 診療所の名称、開設場所
② 診療科目
③ 医師、歯科医師、看護師などの従業員の定数
④ 敷地の面積や建物の構造概要、平面図
⑤ 管理者の住所・氏名
これらの情報が、現在の状況と「完全に」一致している必要があります。
特に注意が必要なのが「図面」です。
【具体例:図面のズレ】
個人開業の当初はAという間取りだったが、数年後に患者さんの動線を考えてパーティションの位置を少し変えた。
あるいは、スタッフルームを確保するために小さな増改築を行った。
こうした変更の際に、「診療所開設許可事項一部変更届」を保健所に提出していますでしょうか?
もし、この届出を忘れていると、保健所が把握している図面と、今回医療法人設立のために提出する図面が食い違い、問題となります。
設立認可申請の前提として、まず現状の変更届を提出し、保健所の承認を得る作業が「先」に必要になります。
1-2.免許証の「名義変更」という時間のかかる罠
もう一つの大きな注意点が、資格免許証です。
【具体例:婚姻による姓の変更】
ご結婚などで姓が変わった場合、医師免許証や歯科医師免許証の「名義書換」は完了していますか?
この手続きは、厚生労働省(医籍・歯科医籍の登録担当)で行いますが、申請から新しい免許証が手元に届くまで、3ヶ月以上かかることも珍しくありません。
医療法人設立認可申請では、役員に就任する医師・歯科医師の免許証の写しを提出します。
この氏名と、履歴書や印鑑登録証明書の氏名が異なれば、当然ながら申請は受理されません。
「申請直前に気づいた」では手遅れになる、時間のかかる手続きの代表例です。
1-3. 保険医登録票の確認
県外から移転してこられた先生の場合、以前の県で登録した「保険医登録票」のままになっていないでしょうか。
診療を行っている岩手県(東北厚生局)への登録変更が済んでいるか、今一度ご確認ください。
これらの「現状の不備」を解消するだけで、数ヶ月単位の時間がかかることがあります。医療法人化を決意したら、まず一番に確認すべきポイントです。
2 定款と申請書類の準備
現状の診療所の足場を固めたら、次はいよいよ設立申請書類の作成です。
県に医療法人設立認可申請を行うには、膨大な量の書類が必要となります。
① 医療法人設立認可申請書
② 定款(法人の「憲法」とも言える最重要書類)
③ 設立総会議事録(設立の意思決定を証明する書類)
④ 財産目録、財産目録明細書、拠出申込書
⑤ リース物件一覧表(医療機器などがリースの場合)
⑥ 役員及び社員の名簿
⑦ 履歴書(役員就任予定者全員分)
⑧ 印鑑登録証明書(役員就任予定者全員分)
⑨ 管理者就任承諾書
(その他、事案に応じた補足資料など)
2-1. なぜこれほど多くの書類が必要なのか?
医療法人は、その公益性の高さから、株式会社など通常の会社設立(法務局への登記のみ)とは異なり、県知事による「認可」という、より厳格な行政手続きが求められます。
県は、「この新しい法人が、安定して地域医療を提供し続けられるか」を、これらの書類を通して厳しく審査します。
特に「定款」は、法人の根本規則を定めるものです。
役員の定数、社員総会の運営、資産の管理、解散時の残余財産の帰属先など、将来にわたって法人を縛るルールをここで全て決定します。
2-2. 書類間で「矛盾」があると申請は通りません
これらの書類は、全ての内容が完璧に一致(整合性が取れている)している必要があります。
例えば、財産目録に記載された拠出(出資)額と、設立総会議事録に記載された決議額が1円でも違えば、申請は差し戻し(やり直し)となります。
役員名簿の漢字と、履歴書の漢字が微妙に違うだけでも、修正を求められます。
この「膨大な書類の束を、一字一句ミスなく、法的要件を満たしたうえで作成する」作業こそ、医療法人設立における最大のハードルと言えます。
3 盲点となる「不動産賃貸借契約書」の罠
先生の診療所が「賃貸物件」である場合、非常に重要な確認事項があります。
それは、「現在の不動産賃貸借契約書」です。
現在は「個人(院長先生)」としてオーナー(大家)と契約しています。
医療法人を設立すると、この契約の名義を「医療法人」に変更(承継)する必要があります。
【具体例:契約書の落とし穴】
現在の契約書に、「賃借権の譲渡や転貸(またがし)を禁ずる」という条項しかなく、「設立する法人への承継」に関する取り決めが何もなかったらどうなるでしょう?
この場合、オーナーの「承認」が別途必要になります。
もしオーナーが「法人への名義変更は認めない」「変更するなら賃料を大幅に値上げする」と言い出したら、どうされますか?
最悪の場合、その場所で医療法人として運営することができなくなり、設立計画そのものが暗礁に乗り上げてしまいます。
申請書類の準備をすべて終えた後でこの問題が発覚しても、手遅れです。
必ず、申請準備の「初期段階」で賃貸借契約書を確認し、必要であればオーナー側と承継に関する交渉(覚書の締結など)を済ませておく必要があります。
4 申請スケジュールが大幅に遅れる2つの典型例
医療法人の設立認可申請の受付は「年2回(例:春と秋)」など、時期が厳格に決まっていることが一般的です。
この「決まった時期」に間に合わなければ、計画は半年、自動的に遅延します。
このスケジュールを揺るがす、申請間際によくある変更依頼(トラブル)を2つ紹介します。
4-1. 医療法人名称の変更
「やはり、法人の名称をAからBに変えたい」
この変更が、いかに大変な作業かご存知でしょうか。
法人の名称は、定款、設立認可申請書、設立総会議事録、財産目録…ほぼ全ての申請書類に記載されます。
名称が変われば、それら全ての書類を作り直すことになります。
また、医療法人の名称には「近隣に類似の名称がないか」「医療機関としてふさわしいか」といった一定のルールがあります。
申請直前に慌てて考えた名称が、そのルールに抵触して使えない可能性もあります。
名称は、ルールを確認した上で、初期段階でしっかり決定し、その後は変更しないことが鉄則です。
4-2. 管理者(院長)予定者の変更
最も深刻なのが、人の変更です。
特に「管理者(院長)」予定者の変更は、計画全体に致命的な影響を与えます。
【具体例:管理者予定者の辞退】
A先生を理事長兼管理者に、B先生を理事(勤務医)として設立準備を進めていた。
しかし、申請直前になってB先生が「やはり理事になるのは辞退したい」と言い出した。
この場合、B先生の履歴書や印鑑登録証明書を差し替えるだけでは済みません。
役員の構成が変わるため、定款の役員規定を見直し、設立総会を(形式上)やり直し、議事録を作り替え、場合によっては資産の拠出計画にも影響が出るかもしれません。
もし、A先生(管理者予定者)自身が何らかの事情で辞退するようなことがあれば、計画は完全に白紙撤回となります。
次の申請時期(半年後)まで、全てが遅延することを意味します。
管理者や役員の就任予定者には、医療法人の理事や管理者になることの重みをしっかり説明し、固い意志を確認しておく必要があります。
5 申請様式は最新版を入手
最後に、基本的なことですが重要な点です。
申請様式や手引書は、インターネットで検索すれば様々なものが見つかります。
しかし、医療法人設立の手続きは、県によって必要書類や様式、ローカルルールが異なる場合があります。
古い情報や、他の都道府県の様式を使って書類を作成してしまうと、全てが無駄になります。
必ず、「県庁の担当課(医療政策室など)」や、「管轄の保健所」の窓口で最新の情報を確認し、正しい様式を入手してから準備をスタートしてください。
6 まとめ
ここまで、医療法人設立認可申請の前に準備すべき重要なポイントを見てきました。
これらは、全体の手続きのほんの一部に過ぎません。
医療法人の設立、行政機関への許認可の申請書作成・提出方法について、何から手を付けていいか分からない、というのが多くの先生方の本音ではないでしょうか。
複雑な行政機関への対応や、膨大な書類作成に追われ、先生の貴重な時間が奪われ、本業である診療に集中できなくなってしまっては本末転倒です。
そこで、専門家である行政書士にトータルで任せることで、法的な要件をクリアした確実な手続きと、何より「安心」を得ることができます。
当事務所では、常に医療サイドに寄り添い、先生方にとっての最善の解決策を提案いたします。
当事務所の最大の強みは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった他士業と強力な連携を組んでいる点です。
設立時だけでなく、設立後の労務管理や税務、万が一の法的トラブルまで、ワンストップでの対応が可能です。
さらに、私自身が元岩手県職員として、企業立地や県立大学新設のプロジェクトに携わった経験があります。
この「行政の視点」を熟知しているからこそ、国や県、保健所といった行政機関との調整を迅速かつ円滑に進められるという、他にはない「強み」を持っています。
初回のご相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
★注意事項
厚生労働省(地方厚生局)や岩手県、各保健所への許認可申請は、行政書士が、唯一、行政機関への申請手続きの代理が認められている国家資格者です。
行政書士以外の者(コンサルタント等を名乗る者を含む)が、報酬を得る目的で他人の依頼を受け、必要な申請書類の作成や提出を代理(代行)することは、法律(行政書士法)で固く禁止されています。
7 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ
https://office-fujiihitoshi.com/