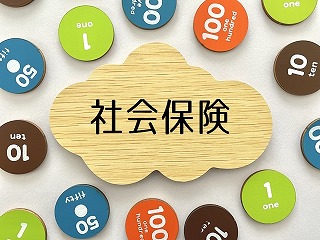「医療法人の社員って、従業員のこと?」
「社員総会と理事会の違いがよく分からない…」
「役員には誰がなれるの?」「理事長の責任って?」
こんな疑問をお持ちではありませんか?
医療法人を設立・運営するにあたって、社員、社員総会、理事、理事会などの機関の役割や権限、責任などを正しく理解しておくことは、非常に重要です。
これらの機関は、株式会社の株主、株主総会、取締役、取締役会に似ていますが、医療法人特有のルールもあります。
ご安心ください!
今回の記事では、医療法人の機関について、その役割、権限、株式会社との違いなどを、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、医療法人の組織運営に関する疑問が解消され、円滑な法人運営の第一歩を踏み出せます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)で医療法人を運営されている、または設立を検討されている皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1医療法人の機関
医療法人は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院などを開設・運営することを目的として設立される法人です。
医療法人の運営には、株式会社と同様に、意思決定機関や業務執行機関が必要となります。
しかし、医療法人は、非営利性などの点で株式会社とは異なる特徴を持っており、その機関の役割や権限も異なります。
1-1. 医療法人の主な機関
医療法人の主な機関は、以下のとおりです。
(1)社員総会:
社団医療法人の最高意思決定機関(株式会社の株主総会に相当)
(2)理事会:
医療法人の業務執行機関(株式会社の取締役会に相当)
(3)理事:
医療法人の業務を執行する機関(株式会社の取締役に相当)
(4)理事長:
医療法人を代表し、業務を統括する(株式会社の代表取締役に相当)
(5)監事:
医療法人の業務や財産の状況を監査する機関(株式会社の監査役に相当)
1-2. 株式会社との比較
以下に、医療法人と株式会社の主な違いを項目ごとに比較します。
(1)構成員
・医療法人: 社員(出資者とは限らない)
・株式会社: 株主(出資者)
(2)議決権
・医療法人: 一人一票(出資額に関わらず)
・株式会社: 原則として、一株一議決権(出資額に応じて議決権が増える)
(3)意思決定機関
・医療法人: 社員総会(社団の場合)、評議員会(財団の場合)
・株式会社: 株主総会
(4)業務執行機関
・医療法人: 理事会
・株式会社: 取締役会
(5)代表者
・医療法人: 理事長
・株式会社: 代表取締役
(6)監査機関
・医療法人: 監事
・株式会社: 監査役(または監査役会、監査等委員会、指名委員会等)
(7)営利性
・医療法人: 非営利(剰余金の配当はできない)
・株式会社: 営利(株主への配当が可能)
(8)設立根拠法
・医療法人: 医療法
・株式会社: 会社法
2医療法人の社員
医療法人の「社員」とは、一般的にイメージする「従業員」とは異なります。
医療法人の社員とは、社団医療法人の構成員であり、社員総会において、一人一票の議決権を持つ、重要な存在です。
2-1. 社員とは?
社団医療法人の「社員」とは、法人の設立に際して定款を作成し、法人運営の基本的事項を決定する権限を持つ、法人の構成員のことです。
株式会社の「株主」に相当する存在ですが、医療法人は非営利法人であるため、社員に出資持分や剰余金の配当はありません。
2-2. 社員の役割と権限
社員は、社員総会において、以下の事項について議決権を行使します。
①役員(理事・監事)の選任・解任
②定款の変更
③事業計画の承認
④予算・決算の承認
⑤重要な財産の処分
⑥借入金の限度額の決定
⑦社員の入社・除名
⑧医療法人の解散
⑨医療法人の合併・分割
⑩その他、医療法人の運営に関する重要な事項
2-3. 社員になるには?
医療法人の社員になるための資格や要件は、医療法には特に規定されていません。
各医療法人の定款で定められています。
一般的には、医療法人の設立趣旨に賛同し、入社(入社)の申し込みをし、社員総会で承認されることで、社員になることができます。
2-4. 社員の退社
社員は、自由に退社することができます。
ただし、定款で退社に関する規定がある場合は、それに従う必要があります。
また、社員が死亡した場合や、除名された場合も、社員の資格を喪失します。
3社員総会
社員総会は、社団医療法人の最高意思決定機関であり、株式会社の株主総会に相当します。
社員総会では、医療法人の運営に関する重要な事項について、社員の多数決によって意思決定を行います。
3-1. 社員総会の種類
社員総会には、以下の2種類があります。
(1)定時社員総会:
少なくとも毎年1回、必ず開催される社員総会です。通常、事業年度終了後に開催され、決算の承認や役員の選任などが行われます。
(2)臨時社員総会:
必要に応じて、臨時に開催される社員総会です。定款変更や理事の解任など、緊急の議題がある場合に開催されます。
3-2. 社員総会の招集
社員総会は、原則として理事長が招集します。
ただし、一定の要件を満たせば、社員や監事が社員総会の招集を請求することもできます。
3-3. 社員総会の決議事項
社員総会で決議できる事項は、医療法や定款で定められています。
主な決議事項は、以下のとおりです。
①役員(理事・監事)の選任・解任
②定款の変更
③事業計画の承認
④予算・決算の承認
⑤重要な財産の処分
⑥借入金の限度額の決定
⑦社員の入社・除名
⑧医療法人の解散
⑨医療法人の合併・分割
⑩その他、医療法人の運営に関する重要な事項
3-4. 社員総会の議決方法
社員総会の議決は、原則として、出席社員の過半数をもって行います。
ただし、定款変更や役員の解任など、重要な事項については、特別決議(出席社員の3分の2以上の賛成など)が必要となる場合があります。
3-5. 社員総会議事録
社員総会を開催した場合は、議事録を作成し、保管する必要があります。
議事録には、開催日時、場所、出席者、議事の経過、決議事項などを記載します。
4医療法人の役員
医療法人には、役員として、理事と監事を置かなければなりません(医療法第46条の5)。
理事は、医療法人の業務を執行し、監事は、理事の職務執行を監査します。
4-1. 理事
理事は、株式会社の取締役に相当する存在であり、医療法人の業務執行を担います。
理事は、社員総会(社団医療法人の場合)または評議員会(財団医療法人の場合)で選任されます。
①理事の人数: 原則として3名以上
②理事の任期: 2年を超えることはできません。ただし、再任は妨げられません。
③理事の資格: 原則として自然人(個人)である必要があります。法人は理事になれません。また、医療法では、理事の欠格事由が定められており、これに該当する人は理事になれません。
④理事の職務:医療法人の業務執行、理事会での議決に参加、理事長を補佐し医療法人の業務を執行
4-2. 監事
監事は、株式会社の監査役に相当する存在であり、医療法人の業務や財産の状況を監査する役割を担います。
監事は、社員総会(社団医療法人の場合)または評議員会(財団医療法人の場合)で選任されます。
①監事の人数: 1名以上
②監事の任期: 2年を超えることはできません。ただし、再任は妨げられません。
③監事の資格: 医療法人の理事、職員、または、その配偶者、親族などは、監事になることができません。
④監事の職務:医療法人の業務・財産状況の監査、理事会への出席と意見陳述、社員総会(評議員会)への報告、不正行為の発見時の報告義務
4-3. 理事長
理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務を統括する、最も重要な役員です。
理事長は、理事の中から、理事会で選出されます。
①理事長の資格:
原則として、医師または歯科医師である理事の中から選出されます。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師または歯科医師でない理事を理事長に選出することも可能です。
②理事長の職務:
医療法人を代表する、医療法人の業務を統括する、理事会を招集し議長を務める、その他法令や定款で定められた職務
4-4. 常務理事
定款で定めることにより、常務理事を置くことができます。
常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき(病気や出張など)は、その職務を代行します。
5理事会
理事会は、理事によって構成される合議体であり、医療法人の業務執行に関する意思決定機関です。
株式会社の取締役会に相当します。
5-1. 理事会の職務
理事会は、以下の職務を行います。
①医療法人の業務執行の決定
②理事の職務執行の監督
③理事長の選出および解職
5-2. 理事会の決議事項
理事会で決議する事項は、医療法や定款で定められています。
主な決議事項は、以下のとおりです。
①重要な財産の処分および譲受け
②多額の借財
③重要な役割を担う職員(管理者など)の選任および解任
④重要な組織の設置、変更、廃止
⑤その他、法令や定款で定められた事項
5-3. 理事会の運営
理事会は、理事長が招集し、議長を務めます。
理事会の決議は、原則として、理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって行います。
理事会を開催した場合は、議事録を作成し、保管する必要があります。
6医療法人役員の責任
医療法人の役員(理事、監事)は、その職務を行うにあたり、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)を負います。
これは、医療法人に対して、誠実かつ適切に職務を遂行する義務です。
6-1. 法人に対する責任
役員が、その任務を怠り、医療法人に損害を与えた場合は、医療法人に対して損害賠償責任を負います(医療法第49条の5)。
例えば、
・理事長が、独断で不必要な高額医療機器を購入し、医療法人に損害を与えた場合
・理事が、杜撰な管理により、医療法人の財産を流出させた場合
・監事が、理事の不正行為を見逃し、医療法人に損害を与えた場合
などです。
6-2. 法人外(第三者)に対する責任
役員が職務を行うにあたり、悪意または重大な過失があった場合は、第三者に対しても損害賠償責任を負います(医療法第49条の6)。
例えば、
・理事長が、医療法人の資金を私的に流用し、取引先に損害を与えた場合
・理事が、虚偽の情報を開示し、患者に損害を与えた場合
・監事が、理事の不正行為を知りながら見過ごし、債権者に損害を与えた場合
などです。
6-3. 損害賠償責任の免除
役員の医療法人に対する損害賠償責任は、原則として、総社員の同意がなければ免除することができません(医療法第49条の5第2項)。
ただし、一定の要件を満たす場合は、責任の一部免除や、役員等賠償責任保険(D&O保険)による補償を受けることができます。
7医療法人の理事の解任
医療法人の理事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができます(医療法第49条の3)。
これは、株式会社の取締役の解任と同様の規定です。
7-1. 解任の理由
理事の解任は、特に理由を必要としません。
社員総会で過半数の賛成があれば、理事を解任することができます。
7-2. 正当な理由がない場合の損害賠償
ただし、正当な理由がないのに理事を解任した場合は、医療法人は、解任された理事に対して、損害賠償責任を負う可能性があります(医療法第49条の3第2項)。
「正当な理由」とは、例えば、理事の職務怠慢、不正行為、心身の故障など、理事としての適格性を欠くような事情がある場合を指します。
8出資者と社員の違い
医療法人の「社員」は、株式会社の「株主」とは異なり、出資者である必要はありません。
医療法人には、「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」があり、それぞれ社員の地位や権利が異なります。
8-1. 持分あり医療法人
持分あり医療法人は、設立時に出資した社員が、出資額に応じて「持分」を持つ法人です。
社員は、持分に応じて、法人の財産に対する権利(残余財産分配請求権など)を持ちます。
しかし、医療法人の社員の地位(議決権)は、出資持分とは結びついておらず、社員は出資額に関わらず、一人一票の議決権を持ちます。
8-2. 持分なし医療法人
持分なし医療法人は、社員に出資持分がない法人です。
社員は、法人の財産に対する権利を持たず、法人が解散した場合でも、残余財産の分配を受けることはできません。
8-3. 株式会社の出資と医療法人への出資
株式会社は、営利法人であり、医療法人は非営利法人であるため、株式会社が医療法人に出資することはできますが、社員になることはできません。
厚生労働省の行政指導や判例でも、営利法人が医療法人の意思決定に関与することは許されないとされています。
9まとめ
医療法人の機関(社員、社員総会、役員、理事会)は、株式会社の機関と似ている部分もありますが、医療法特有のルールも多く、複雑です。
医療法人を設立・運営するにあたっては、これらの機関の役割や権限、責任などを正しく理解し、適切な運営を行う必要があります。
「医療法人の社員って何?」「理事会は何を決めればいいの?」「役員の責任って?」など、医療法人の運営に関する疑問や不安は、専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士は、医療法人設立・運営に関する専門家であり、定款作成、社員総会・理事会の運営サポート、役員変更手続き、行政庁への届出など、医療法人の運営をトータルでサポートすることができます。
行政書士は、関係する法律にも精通しており、総合的なアドバイスを提供することができます。
当事務所では、医療法人設立・運営に関するご相談を幅広く承っており、お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。
医療法人について、何から手を付けていいか分からない、専門的なアドバイスが欲しいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします。
この記事を読んで、少しでも医療法人について考えるきっかけになれば幸いです。
10お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ