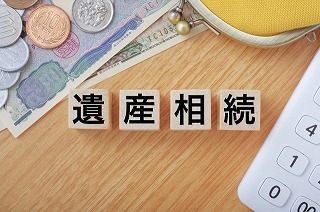「相続って、誰が、何を、どれくらいもらえるの?」
「もし、子どもが先に亡くなっていたら、孫は相続できる?」
「養子縁組をすると、相続はどうなるの?」
こんな疑問や不安をお持ちではありませんか?
相続は、誰もがいつか直面する問題ですが、その仕組みは複雑で、分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
しかし、相続の基本的な知識を知っておくことで、いざという時に慌てずに済み、大切な家族を守ることにもつながります。
ご安心ください。
今回の記事では、相続人の範囲や順位、代襲相続、養子縁組など、相続に関する基本的な知識を、分かりやすく解説します。具体例を豊富に盛り込み、図解も交えながら、より理解を深めていただけるように工夫しました。
この記事を読めば、相続の基本が理解でき、あなたとご家族にとって、より良い相続の準備を始めることができます。
岩手県、宮城県、仙台市にお住まいの皆様、ぜひ最後までお読みください。今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1相続人の範囲と順位
相続人とは、亡くなった本人(被相続人)の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を受け継ぐ人のことです。
民法では、相続人になれる人の範囲と順位が定められており、このルールに従って相続人が決まります。
1-1. 配偶者は常に相続人
亡くなった本人(被相続人)に配偶者(夫または妻)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
これは、夫婦が長年協力して築き上げてきた財産を、残された配偶者が引き継ぐのが当然であると考えられているからです。
(1)ポイント:
ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある人のことを指し、内縁関係(事実婚)の人は含まれません。内縁関係の人は、遺言書がない限り、相続人にはなれません。
(2)注意点:
別居中の夫婦であっても、法律上の婚姻関係が継続していれば、配偶者は相続人になります。
(3)具体例:
・夫が亡くなり、妻(法律上の婚姻関係)がいる場合、妻は常に相続人。
・夫が亡くなり、内縁の妻がいる場合、内縁の妻は相続人にはなれない(遺言書があれば別)。
・夫が亡くなり、別居中の妻がいる場合、妻は相続人になる。
1-2. 血族相続人には順位がある
配偶者以外の血族(血のつながりのある親族)は、次の順位で相続人になります。
先順位の人がいない場合に限り、後順位の人が相続人になります。
(1)第1順位:子
亡くなった本人(被相続人)に子がいる場合、子が第1順位の相続人になります。
子には、実子だけでなく、養子も含まれます(養子については後述)。
子が複数いる場合は、全員が同じ割合で相続します。
①嫡出子と非嫡出子:
法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を「嫡出子」、そうでない子を「非嫡出子」といいます。
かつては、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、現在は法律が改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じになりました。
②特別養子と普通養子:
養子には、「特別養子」と「普通養子」の2種類があります(詳細は後述)。
どちらの養子も、実子と同じように第1順位の相続人になります。
子が先に亡くなっている場合: 子が亡くなった本人(被相続人)より先に亡くなっている場合は、代襲相続が発生します(詳細は後述)。
③具体例:
夫が亡くなり、妻と子2人(長男・長女)がいる場合、妻が2分の1、長男と長女がそれぞれ4分の1ずつ相続します。
夫が亡くなり、妻と、夫と前妻との間の子(非嫡出子)がいる場合、妻が2分の1、子が2分の1を相続します。
(2)第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
亡くなった本人(被相続人)に子がいない場合(子全員が相続放棄した場合も含む)、直系尊属(父母、祖父母など)が第2順位の相続人になります。
父母と祖父母がいる場合は、父母が優先されます。
父母が複数いる場合は、全員が同じ割合で相続します。
①直系尊属とは:
自分より上の世代の、縦の血縁関係にある人のことを指します。
具体的には、父母、祖父母、曾祖父母などです。
②養父母は?:
養子縁組をしている場合、養父母も直系尊属として相続人になります。
③具体例:
夫が亡くなり、妻と夫の父がいる場合、妻が3分の2、夫の父が3分の1を相続します。
夫が亡くなり、妻と夫の父母がいる場合、妻が3分の2、夫の父が6分の1、夫の母が6分の1を相続します。
(3)第3順位:兄弟姉妹
亡くなった本人(被相続人)に子も直系尊属もいない場合(子や直系尊属全員が相続放棄した場合も含む)、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、全員が同じ割合で相続します。
①異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹:
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹)も、兄弟姉妹として相続人になります。
ただし、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)に比べて、相続分は2分の1になります。
②兄弟姉妹が先に亡くなっている場合:
兄弟姉妹が亡くなった本人(被相続人)より先に亡くなっている場合は、代襲相続が発生します(詳細は後述)。
③具体例:
夫が亡くなり、妻と夫の兄がいる場合、妻が4分の3、夫の兄が4分の1を相続します。
夫が亡くなり、妻と、夫の兄(全血兄弟姉妹)と夫の妹(異母兄弟姉妹)がいる場合、妻が4分の3、夫の兄が6分の1、夫の妹が12分の1を相続します。
1-3. 相続分の具体例
上記の例をさらに詳しく見てみましょう。
(1)例1: 妻と子2人(長男・長女)が相続人の場合
法定相続分:妻は2分の1、長男と長女はそれぞれ4分の1。
もし、長男が亡くなった本人(被相続人)より先に亡くなっていて、長男に子(亡くなった本人(被相続人)の孫)が2人いる場合:
妻:2分の1
長女:4分の1
孫A:8分の1(長男の相続分4分の1を2人で分ける)
孫B:8分の1(長男の相続分4分の1を2人で分ける)
(2)例2: 妻と夫の父が相続人の場合
法定相続分:妻は3分の2、夫の父は3分の1。
もし、夫の母も存命の場合:
妻:3分の2
夫の父:6分の1
夫の母:6分の1
2代襲相続
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、亡くなった本人(被相続人)より先に亡くなっている、または相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合に、その人の子などが代わりに相続人になる制度です。
これは、本来相続人になるはずだった人の子孫に、財産を承継させることで、その生活を保障しようとするものです。
2-1. 代襲相続が起こる場合
(1)子が亡くなっている場合:
亡くなった本人(被相続人)に子がいる場合、その子が亡くなった本人(被相続人)より先に亡くなっていれば、その子(亡くなった本人(被相続人)の孫)が代襲相続人になります。
・具体例: 夫が亡くなり、妻と長男がいるが、長男はすでに亡くなっており、長男には子(AさんとBさん)がいる場合、妻が2分の1、AさんとBさんがそれぞれ4分の1ずつ相続します(長男の相続分2分の1をAさんとBさんで分ける)。
(2)兄弟姉妹が亡くなっている場合:
亡くなった本人(被相続人)に子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹が亡くなった本人(被相続人)より先に亡くなっていれば、その子(亡くなった本人(被相続人)のおい・めい)が代襲相続人になります。
・具体例: 夫が亡くなり、子も直系尊属もおらず、兄がいるが、兄はすでに亡くなっており、兄には子(Cさん)がいる場合、妻が4分の3、Cさんが4分の1を相続します(兄の相続分4分の1をCさんが相続)。
2-2. 代襲相続が起こらない場合
(1)相続放棄:
相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は起こりません。
相続放棄は、その人一代限りのものであり、その人の子に相続権が移ることはありません。
「相続放棄=最初から相続人でなかったことになる」と考えると分かりやすいでしょう。
(2)相続欠格・廃除:
相続人が、相続欠格(例えば、亡くなった本人(被相続人)を故意に死亡させた場合など)や廃除(亡くなった本人(被相続人)から生前に相続人から除外されている場合)によって相続権を失った場合も、代襲相続は起こりません。
(3)再代襲:
代襲相続することのできた被相続人の子の子(孫)が、被相続人より先に死亡したり、相続欠格・廃除により相続権を失った場合で、その孫の子(ひ孫)がいるときは、そのひ孫が、被相続人を代襲相続することができる。
これを、再代襲という。
この再代襲は、被相続人の子にのみ適用があり、被相続人の兄弟姉妹には適用がない(つまり、ひ孫はOKだが、おい・めいの子は、代襲相続ができない)
2-3. 代襲相続の具体例
(1)例1: 夫が亡くなり、妻と長男がいるが、長男はすでに亡くなっており、長男には子(Aさん)がいる。
さらに、Aさんも亡くなっており、Aさんには子(Bさん)がいる場合。
妻:2分の1
Bさん:2分の1(長男の相続分をAさんが代襲相続し、さらにBさんが再代襲相続)
(2)例2: 夫が亡くなり、子も直系尊属もおらず、兄がいるが、兄はすでに亡くなっており、兄には子(Cさん)がいる。
さらに、Cさんも亡くなっており、Cさんには子(Dさん)がいる場合。
妻:4分の3
Cさん:4分の1(兄の相続分を代襲相続) *Dさんは、再代襲はできない。
3胎児の相続権
民法では、胎児(お腹の中の赤ちゃん)は、相続に関しては、すでに生まれたものとみなされます。
つまり、胎児にも相続権があります。
これは、生まれてくる子の将来の生活を保障するための制度です。
3-1. 胎児が相続人になる場合
(1)具体例: 夫が亡くなった時点で、妻が妊娠中であり、夫に他に相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)がいない場合、生まれてくる子は、夫の財産を単独で相続します。
(2)具体例: 夫が亡くなった時点で、妻が妊娠中であり、夫には他に子(長男)がいる場合、生まれてくる子は、長男と同じ割合で相続します(妻が2分の1、長男と生まれてくる子がそれぞれ4分の1ずつ)。
3-2. 胎児が相続人にならない場合
死産の場合: 胎児が死産だった場合は、相続権は認められません。
この場合、胎児はいなかったものとして、他の相続人で遺産分割を行います。
3-3. 遺産分割の注意点
胎児がいる場合の遺産分割は、胎児が出生するまで待つ必要があります。
胎児が出生する前に遺産分割を行ってしまうと、後でトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。
(1)理由:
・胎児が生まれてくるまでは、性別や人数が確定しないため、相続分を確定できない。
・死産だった場合、遺産分割協議をやり直す必要がある。
(2)対策:
・胎児が出生するまで、遺産分割協議を保留する。
・胎児の出生後、改めて遺産分割協議を行う。
・必要に応じて、家庭裁判所に胎児のための特別代理人を選任してもらう(母と胎児の利益が相反する場合)。
4養子縁組と相続
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、それぞれ相続関係が異なります。
どちらの養子縁組をするかによって、相続関係が大きく変わるため、注意が必要です。
4-1. 普通養子縁組
普通養子縁組は、実親との親子関係を維持したまま、養親との間にも親子関係を作る制度です。
普通養子縁組をした場合、養子は、実親と養親の両方の相続人になります。
(1)特徴:
実親との親子関係は継続する。
養親との間にも親子関係が発生する。
実親と養親、両方の相続人になる。
苗字は、原則として養親の苗字になる。
(2)具体例: Aさんには、実子Bさんと、普通養子縁組をしたCさんがいる場合、Aさんが亡くなると、BさんとCさんは、どちらもAさんの相続人になります(相続分も同じ)。
また、Cさんは、実親の相続人にもなります。
(3)注意点:
普通養子縁組は、比較的簡単にできるため、相続対策として利用されることもあります。
しかし、安易な養子縁組は、後々トラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。
4-2. 特別養子縁組
特別養子縁組は、実親との親子関係を終了させ、養親との間にのみ親子関係を作る制度です。
特別養子縁組をした場合、養子は、実親の相続人にはならず、養親の相続人になります。
(1)特徴:
実親との親子関係は終了する。
養親との間だけに親子関係が発生する。
実親の相続人にはならない。
養親の相続人になる。
原則として、養親の苗字になる。
家庭裁判所の審判が必要。
(2)具体例: Aさんには、実子Bさんと、特別養子縁組をしたCさんがいる場合、Aさんが亡くなると、BさんとCさんは、どちらもAさんの相続人になります。
しかし、Cさんは、実親の相続人にはなりません。
(3)注意点:
特別養子縁組は、原則として6歳未満の子どもを対象とする制度です(例外あり)。
家庭裁判所の審判が必要であり、実親の同意や、養親となる者の年齢、経済力など、厳しい要件があります。
特別養子縁組は、子どもの福祉を最優先に考えた制度であり、相続対策として安易に利用するべきではありません。
5まとめ
相続は、誰もがいつか直面する問題であり、その仕組みは複雑です。
しかし、相続人の範囲や順位、代襲相続、養子縁組など、基本的な知識を知っておくことで、いざという時に慌てずに済み、大切な家族を守ることにもつながります。
「自分の場合は誰が相続人になるのか?」「相続でトラブルにならないためにはどうすればいいのか?」など、相続に関する疑問や不安は、専門家である行政書士にご相談ください。
相続について、何から手を付けていいか分からないのが現状です。
よって、専門家である行政書士に、トータルで任せることで安心が得られます。
相続は、各種の法的な手続きなど、複雑な問題がからむことがあります。
そこで、専門家である行政書士に依頼することで、スムーズに、相続に関する様々な問題を進めることができます。
相続は、決して、身内を「ないがしろ」にするものではありません。
むしろ、次の世代に向けて、亡くなった方の意思・思いを引き継ぎ、未来に向けて、前向きな人生を充実させるために必要なバトンタッチです。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案します。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。
この記事を読んで、少しでも相続について考えるきっかけになれば幸いです。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ