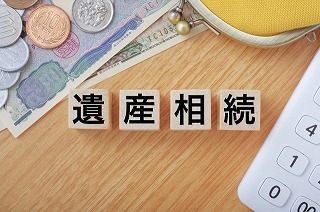「遺産分割って、どうやって進めるの?」
「相続人全員の合意が必要って本当?」
「遺産分割協議書って、自分で作れるの?」
「もめないためには、どうすればいい?」
こんな悩みはありませんか?
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の遺産は、相続人全員の共有財産となります。
しかし、このままでは、個々の財産を誰が相続するのかが決まらず、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更などができません。
そこで必要となるのが、「遺産分割」です。
ご安心ください!
今回の記事では、遺産分割の基本から、具体的な方法、注意点、そしてトラブルを防ぐためのポイントまで、詳しく解説します。
この記事を読めば、遺産分割に関する疑問が解消され、スムーズな相続手続きを進めるための第一歩を踏み出せます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)にお住まいの皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1遺産分割とは?
遺産分割とは、相続が開始した後、亡くなった本人(被相続人)の遺産を、各相続人に具体的に分ける手続きのことです。
相続が開始すると、亡くなった本人(被相続人)の遺産は、相続人全員の共有状態(遺産共有)となります(民法898条)。
この状態では、各相続人は、個々の財産について自由に処分することができません。
例えば、預貯金を引き出したり、不動産を売却したりするためには、原則として相続人全員の同意が必要になります。
遺産分割は、この共有状態を解消し、個々の財産を誰が相続するかを確定させるための手続きです。
遺産分割が完了して初めて、各相続人は、自分が相続した財産を自由に処分できるようになります。
1-1. 遺産分割の対象となる財産
遺産分割の対象となるのは、亡くなった本人(被相続人)が所有していた全ての財産です。
これには、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
(1)プラスの財産(資産)
①不動産: 土地、建物(自宅、別荘、アパート、マンション、店舗、事務所、工場など)。
(注意点) 共有名義の不動産の場合は、亡くなった本人(被相続人)の持分のみが相続財産となります。また、抵当権などの担保権が設定されている場合は、その担保権も一緒に相続することになります。
②預貯金: 普通預金、定期預金、貯蓄預金、外貨預金など。
(注意点) 亡くなった本人(被相続人)名義の預貯金は、原則として、相続開始と同時に凍結されます。凍結を解除するためには、遺産分割協議書などの書類を金融機関に提出する必要があります。
③現金: 自宅や金庫などに保管されていた現金。
④有価証券: 株式、投資信託、国債、社債など。
(注意点) 上場株式の場合は、相続開始日の終値で評価します。非上場株式の場合は、会社の規模や経営状況などによって評価方法が異なります。
⑤自動車:
(注意点) 自動車には、相続税評価額と別に、中古車市場での時価評価額というものがあります。相続税の申告においては、相続税評価額を用いますが、遺産分割協議においては、時価評価額を用いることもあります。
⑥貴金属、宝石、美術品:
(注意点) 専門家による鑑定評価が必要となる場合があります。
⑦ゴルフ会員権:
(注意点) 会員権の種類によっては、譲渡や相続ができない場合があります。
⑧著作権、特許権:
(注意点) 著作権や特許権などの知的財産権も、相続の対象となります。
⑨その他: 貸付金、売掛金、慰謝料請求権など。
(注意点) 貸付金や売掛金は、回収可能性を考慮して評価する必要があります。
(2)マイナスの財産(負債)
①借金: 住宅ローン、自動車ローン、カードローン、消費者金融からの借入、事業資金の借入など。
(注意点) 連帯債務や保証債務も相続の対象となります。
②未払金: クレジットカードの未払い、家賃、光熱費、医療費、税金など。
(注意点) 亡くなった本人(被相続人)が死亡した後に発生した費用(例えば、死亡後の家賃や光熱費など)は、原則として相続財産には含まれません。
③保証債務: 他の人の借金の保証人になっている場合、その保証債務も相続の対象となります。
(注意点) 保証債務は、主債務者が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負うものです。相続放棄をしない限り、保証債務も相続することになります。
④その他: 連帯債務、損害賠償債務など。
1-2. 遺産分割の当事者
遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。
相続人が一人でも欠けると、遺産分割協議は無効になります。
これは、遺産分割が、相続人全員の共有状態にある遺産を、それぞれの相続分に応じて分割する手続きであるため、全員の合意が必要となるからです。
(注意点)
①行方不明の相続人がいる場合:
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する必要があります。
②未成年者の相続人がいる場合:
原則として、親権者(または未成年後見人)が未成年者を代理して遺産分割協議に参加します。
ただし、親権者と未成年者が共に相続人である場合など、利益が相反する場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
③判断能力がない相続人がいる場合:
認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合は、成年後見制度を利用し、成年後見人等が遺産分割協議に参加する必要があります。
1-3. 遺産分割前の預貯金の払戻し制度
相続された預貯金は、遺産分割が終わるまでは、相続人全員の共有財産となり、原則として、各相続人が単独で払い戻しをすることができません。
しかし、これでは、葬儀費用や当面の生活費の支払いに困るケースが出てきます。
そこで、令和元年7月1日から、遺産分割前でも、一定の要件のもとで、預貯金の払い戻しを受けることができる制度が始まりました。
この制度には、以下の2つの方法があります。
(1)家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払い戻しを受ける方法
一定の範囲の預貯金については、家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口で払い戻しができます。
この制度は、相続人の資金需要に迅速に対応するためのものです。
①払戻しができる金額:
・同一の金融機関における預貯金の合計額が150万円まで
・相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 当該払戻しを行う相続人の法定相続分
上記のいずれか低い方の金額が、払い戻しの上限額となります。
②必要書類:
・亡くなった本人(被相続人)の除籍全部事項証明書、戸籍全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍全部事項証明書
・払い戻しを希望する相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・払い戻しを希望する相続人の印鑑証明書
・金融機関所定の払戻請求書
・その他、金融機関が求める書類
(2)家庭裁判所の判断による預貯金の仮払い制度
家庭裁判所に申し立てを行い、仮払いが必要であると認められた場合は、他の相続人の利益を害しない限り、預貯金の仮払いを受けることができます。
この制度は、上記の方法では資金が不足する場合や、遺産分割協議が長引いている場合などに利用されます。
①申立先: 亡くなった本人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
②申立人: 相続人または遺言執行者
③必要書類:
・申立書
・亡くなった本人(被相続人)の戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍全部事項証明書
・遺産分割協議書(未了の場合)
・預貯金通帳のコピーまたは残高証明書
・仮払いの必要性を証明する資料(葬儀費用の領収書、医療費の請求書など)
・その他、家庭裁判所が求める書類
2遺産分割の方法
遺産分割の方法には、主に以下の4つがあります。
2-1. 遺言による分割(指定分割)
亡くなった本人(被相続人)が遺言書を残している場合は、原則として、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。
遺言書で、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定などができます。
(1)遺言書の種類:
①自筆証書遺言: 遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印した遺言書。
②公正証書遺言: 公証人が作成する遺言書。証人2人以上の立会いが必要。
③秘密証書遺言: 遺言者が遺言書を作成し、封印した後、公証人と証人2人以上の前で、自分の遺言書である旨などを申述し、公証人がその旨を封紙に記載する遺言書。
(2)遺言書の確認:
(3)自筆証書遺言・秘密証書遺言:
家庭裁判所で検認の手続きが必要(法務局の保管制度を利用している自筆証書遺言を除く)。
(4)公正証書遺言:
検認は不要。
(5)遺言書がある場合の注意点:
遺言書の内容が、遺留分を侵害している場合は、遺留分権利者から遺留分侵害額請求をされる可能性がある。
遺言書の内容が不明確な場合や、複数の遺言書が存在する場合は、遺言書の解釈をめぐって相続人間で争いになる可能性がある。
2-2. 遺産分割協議による分割
遺言書がない場合、または遺言書で遺産分割の方法が指定されていない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、合意によって遺産分割の方法を決めます。
これが、最も一般的な遺産分割の方法です。
(1)遺産分割協議の進め方
①相続人の確定:
戸籍全部事項証明書などを収集し、相続人を確定します。
②相続財産の調査:
亡くなった本人(被相続人)の財産(プラスの財産とマイナスの財産)を調査し、財産目録を作成します。
③遺産分割協議:
相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合います。
④遺産分割協議書の作成:
遺産分割協議が成立したら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
(2)遺産分割協議の注意点
①相続人全員の参加:
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効になります。
相続人の中に行方不明者や判断能力がない人がいる場合は、別途手続きが必要です。
②行方不明者がいる場合:
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
③判断能力がない相続人がいる場合:
成年後見制度を利用し、成年後見人等が遺産分割協議に参加します。
④未成年者がいる場合:
原則として、親権者(または未成年後見人)が未成年者を代理して、遺産分割協議に参加することになるが、親権者と未成年者が共に相続人である場合など、利益が相反する場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てます。
⑤全員の合意:
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
一人でも反対する相続人がいる場合は、遺産分割協議は成立しません。
⑥書面での合意(遺産分割協議書):
口頭での合意だけでは、後々トラブルになる可能性があります。
必ず、合意内容を書面に残し(遺産分割協議書)、相続人全員が署名・押印(実印)し、印鑑証明書を添付しましょう。
(3)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続人自身で作成することも可能ですが、以下の理由から、行政書士などの専門家に作成を依頼することをおすすめします。
①法的に有効な書類を作成できる:
遺産分割協議書は、相続手続きにおいて非常に重要な書類であり、不備があると、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻しなどができなくなる可能性があります。
専門家は、法律の規定に沿った、有効な遺産分割協議書を作成することができます。
②トラブルを防止できる:
遺産分割協議書の内容が不明確だったり、相続人の権利関係が曖昧だったりすると、後々トラブルに発展する可能性があります。
専門家は、相続に関する知識や経験に基づいて、トラブルを未然に防ぐためのアドバイスをすることができます。
③手続きをスムーズに進められる:
遺産分割協議書の作成だけでなく、相続人調査、相続財産調査、金融機関との交渉など、遺産分割に関する様々な手続きをサポートしてもらえます。
2-3. 家庭裁判所の調停・審判による分割
相続人同士で話し合っても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
(1)遺産分割調停
遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いを仲介し、合意による解決を目指す手続きです。
調停委員は、相続に関する専門的な知識や経験を持つ人から選ばれ、中立的な立場から、相続人に対して助言や提案を行います。
①メリット:
・話し合いによる解決を目指すため、円満な解決が期待できる。
・調停委員が間に入るため、感情的な対立を避けやすい。
・費用が比較的安い。
②デメリット:
・必ずしも合意に至るとは限らない。
・時間がかかる場合がある。
(2)遺産分割審判
遺産分割調停が不成立になった場合は、家庭裁判所が、遺産分割の方法を決定する審判を行います。
審判では、裁判官が、相続人から提出された資料や意見などを参考に、法律に基づいて、遺産分割の方法を決定します。
①メリット:
・最終的な解決が得られる。
②デメリット:
・当事者の意向が反映されにくい場合がある。
・費用が高額になる場合がある。
・時間がかかる場合がある。
2-4. 遺産分割の具体的方法
遺産分割の具体的な方法には、以下の4つがあります。
①現物分割:
遺産を現物のまま、各相続人に分ける方法です。
例えば、土地を分筆して、それぞれの相続人に分ける場合などです。
・メリット: 分かりやすく、公平感がある。
・デメリット: 遺産の種類や性質によっては、分割が難しい場合がある(例えば、1つの家を複数の相続人で分ける場合など)。
②代償分割:
特定の相続人が遺産を現物で取得する代わりに、他の相続人に対して、相続分に応じた金銭(代償金)を支払う方法です。
例えば、長男が自宅を相続する代わりに、次男に代償金を支払う場合などです。
・メリット: 現物分割が難しい場合でも、遺産分割が可能になる。
・デメリット: 代償金を支払う相続人に、十分な資金力が必要となる。
③換価分割:
遺産を売却し、その代金を相続人で分ける方法です。
例えば、不動産を売却して、その代金を相続人で分ける場合などです。
・メリット: 現金で分けるため、公平な分割がしやすい。
・デメリット: 遺産を売却する必要があるため、希望する価格で売却できない場合がある。
④共有分割:
遺産を相続人全員の共有とする方法です。
例えば、不動産を相続人全員の共有名義にする場合などです。
・メリット: 遺産分割を先延ばしにできる。
・デメリット: 共有状態が続くと、将来的にトラブルになる可能性がある。
どの方法を選択するかは、遺産の種類や相続人の状況などによって異なります。
相続人全員でよく話し合い、最適な方法を選択することが重要です。
3まとめ
遺産分割は、相続人全員の合意が必要であり、手続きも複雑です。
また、遺産分割協議書の作成を誤ると、後々トラブルになる可能性もあります。
「遺産分割協議がまとまらない」「遺産分割協議書の書き方が分からない」「相続手続きが煩雑で困っている」など、遺産分割に関するお悩みは、専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士は、法律と手続きの専門家であり、遺産分割協議書の作成、相続人調査、相続財産調査、金融機関との交渉、不動産の名義変更(相続登記は司法書士の業務)に必要な書類の収集など、遺産分割に関する様々な手続きをサポートすることができます。
また、相続人間の話し合いが円滑に進むよう、中立的な立場からアドバイスをすることも可能です。
当事務所では、遺産分割に関するご相談を幅広く承っており、お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。
相続について、何から手を付けていいか分からない、専門的なアドバイスが欲しいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
相続は、決して、身内を「ないがしろ」にするものではありません。
むしろ、次の世代に向けて、亡くなった方(被相続人)の意思・思いを引き継ぎ、未来に向けて、前向きな人生を充実させるために必要な手続きです。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします。
この記事を読んで、少しでも遺産分割について考えるきっかけになれば幸いです。
4お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ