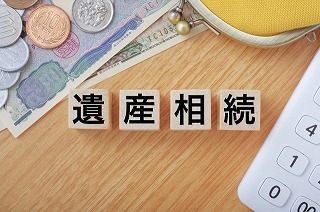「亡くなった親に借金があるみたい…相続した方がいい?」
「実家を相続したけど、誰も住む予定がない。どうすれば?」
「相続放棄って、いつまでにすればいいの?」
こんな悩みはありませんか?
相続が発生すると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになります。
そのため、相続人は、①「単純承認」、②「限定承認」、③「相続放棄」の3つの選択肢から、自分にとって最適な方法を選ぶ必要があります。
そして、その選択には「3ヶ月」という期限があるため、注意が必要です。
ご安心ください!
今回の記事では、相続における3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)と、判断のポイント、手続き、注意点などを、分かりやすく解説します。
特に、判断の難しい不動産(実家など)の取り扱いについても詳しく説明します。
この記事を読めば、相続に関する疑問が解消され、あなたにとって最善の選択をするための判断材料が得られます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)にお住まいの皆様、ぜひ最後までお読みください。今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1相続の3つの選択肢
相続が発生した場合、相続人は、以下の3つの選択肢から、相続の方法を選ぶことができます。
(1)単純承認:
プラスの財産もマイナスの財産も、すべて無条件で引き継ぐ方法
(2)限定承認:
プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ方法
(3)相続放棄:
プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がない方法
どの方法を選ぶかによって、その後の手続きや、相続人に与える影響が大きく変わってきます。
それぞれの選択肢について、詳しく見ていきましょう。
1-1. 単純承認
単純承認とは、亡くなった本人(被相続人)のプラスの財産(不動産、預貯金、株式など)も、マイナスの財産(借金、未払金など)も、すべて無条件で引き継ぐ方法です。
単純承認は、特別な手続きは必要ありません。
相続開始を知った時から「3ヶ月」以内に、限定承認または相続放棄の手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。
(1)単純承認のメリット
・手続きが簡単:
特別な手続きは必要ありません。
・財産を自由に使える:
相続した財産を、自由に使うことができます。
(2)単純承認のデメリット
・マイナスの財産も引き継ぐ:
亡くなった本人(被相続人)に多額の借金があった場合、その借金もすべて引き継ぐことになります。
・後から変更できない:
一度単純承認をすると、後から相続放棄や限定承認に変更することはできません。
(3)単純承認が適しているケース
・亡くなった本人(被相続人)の財産が、プラスの財産の方が多いことが明らかな場合
・相続財産の内容が明確で、後から多額の借金が見つかる可能性が低い場合
・相続手続きを簡単に済ませたい場合
(4)法定単純承認:注意!意図せず単純承認になることも
以下のいずれかに該当する行為をした場合、相続人が単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認、民法921条)。
①相続財産の全部または一部を処分したとき:
・預貯金を引き出して使ってしまった
・不動産や自動車などを売却してしまった
・相続財産を、自分のために使ってしまった(例:自分の借金の返済に充てた)
②例外:
相続財産の保存行為(例:腐りやすいものを売却して現金化する)や、短期賃貸借は、法定単純承認にはあたりません。
③熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき:
相続開始を知った時から「3ヶ月」以内に、限定承認または相続放棄の手続きをしなかった場合、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
④相続財産の隠匿・消費など:
相続人が、限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿したり、自分のために消費したり、わざと財産目録に記載しなかったりした場合、単純承認をしたものとみなされます。
法定単純承認は、相続人の意思とは関係なく、法律上当然に単純承認の効果が生じるため、注意が必要です。
1-2. 限定承認
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、亡くなった本人(被相続人)のマイナスの財産(借金など)を引き継ぐ方法です。
例えば、相続財産が、不動産500万円、借金700万円の場合、限定承認をすれば、500万円の範囲内で借金を返済し、残りの200万円の借金については、返済義務を負いません。
(1)限定承認のメリット
①借金超過でも安心:
亡くなった本人(被相続人)に多額の借金があっても、相続したプラスの財産の範囲内で返済すればよいため、自分の財産から返済する必要がありません。
②家や土地を残せる可能性:
相続財産の中に、どうしても手放したくない財産(自宅など)がある場合、その財産の価額を支払うことで、その財産を取得できる可能性があります(先買権)。
(2)限定承認のデメリット
①手続きが複雑:
家庭裁判所への申述、相続財産管理人の選任、債権者への公告・催告、財産の換価など、手続きが複雑で、時間も費用もかかります。
②相続人全員で行う必要がある:
相続人が複数いる場合は、全員で限定承認をする必要があります。
一人でも単純承認をする人がいると、限定承認はできません。
③税金がかかる場合がある:
相続財産を換価した場合、譲渡所得税がかかる場合があります。
(3)限定承認が適しているケース
・亡くなった本人(被相続人)の財産状況が不明で、借金があるかもしれない場合
・相続財産の中に、どうしても手放したくない財産(自宅など)がある場合
・相続人全員が限定承認に同意している場合
(4)限定承認の手続き
①家庭裁判所への申述:
相続人全員で、相続開始を知った時から「3ヶ月」以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をします。
②必要書類:
・限定承認申述書(家庭裁判所のホームページからダウンロードできます)
・亡くなった本人(被相続人)の戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍全部事項証明書
・相続財産目録
・その他、家庭裁判所が必要と認める書類
③相続財産管理人の選任:
家庭裁判所は、相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、相続財産の管理や清算を行います。
④債権者への公告・催告:
相続財産管理人は、官報に公告し、知れている債権者には個別に催告を行い、債権の申出を求めます。
⑤相続財産の換価:
相続財産を換価(現金化)します。
⑥債務の弁済:
相続財産の範囲内で、債務を弁済します。
⑦残余財産の分配:
債務を弁済して残った財産があれば、相続人に分配します。
1-3. 相続放棄
相続放棄とは、亡くなった本人(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産も、一切相続しない方法です。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされます。
(1)相続放棄のメリット
①借金を相続しない:
亡くなった本人(被相続人)に多額の借金があった場合でも、その借金を引き継ぐ必要がありません。
②相続争いから解放される:
遺産分割協議に参加する必要がなくなり、他の相続人との関わりを断つことができます。
③手続きが比較的簡単:
限定承認に比べて、手続きが比較的簡単です。
(2)相続放棄のデメリット
①プラスの財産も相続できない:
預貯金や不動産など、プラスの財産も一切相続できません。
②撤回できない:
一度相続放棄をすると、原則として撤回することはできません。
③次の順位の相続人に影響:
自分が相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
例えば、子が相続放棄をすると、亡くなった本人(被相続人)の親が相続人になります。
(3)相続放棄が適しているケース
・亡くなった本人(被相続人)に多額の借金がある場合
・相続財産がほとんどない場合
・他の相続人と関わりたくない場合
(4)相続放棄の手続き
①家庭裁判所への申述:
相続開始を知った時から「3ヶ月」以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
②必要書類:
・相続放棄申述書(家庭裁判所のホームページからダウンロードできます)
・亡くなった本人(被相続人)の住民票除票または戸籍附票
・申述人(相続放棄をする人)の戸籍全部事項証明書
・亡くなった本人(被相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)全部事項証明書
・その他、家庭裁判所が必要と認める書類
③相続放棄申述受理通知書の受領:
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理すると、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
2熟慮期間<3ヶ月以内>
相続人は、相続開始を知った時から「3ヶ月」以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
2-1. 熟慮期間の起算点
熟慮期間の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
通常は、亡くなった本人(被相続人)の死亡の事実を知った日ですが、例外もあります。
〇具体例:
①亡くなった本人(被相続人)と疎遠で、死亡の事実を知らなかった場合:
死亡の事実を知った日が起算点となります。
②自分が相続人であることを知らなかった場合:
自分が相続人になったことを知った日が起算点となります。
③先順位の相続人が全員相続放棄をした場合:
先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った日が起算点となります。
2-2. 熟慮期間内にすべきこと
熟慮期間内に、以下のことを行い、相続の方法を決定する必要があります。
①相続人の調査:
戸籍全部事項証明書などを収集し、相続人を確定します。
②相続財産の調査:
亡くなった本人(被相続人)の財産(プラスの財産とマイナスの財産)を調査します。
③相続方法の検討:
単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択します。
2-3. 熟慮期間の延長
相続財産が複雑で調査に時間がかかる場合など、3ヶ月以内に相続方法を決定できない場合は、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長することができます。
2-4. 熟慮期間を過ぎるとどうなる?
熟慮期間内に限定承認または相続放棄の手続きをしないと、単純承認をしたものとみなされます。
単純承認をすると、亡くなった本人(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
3特定の不動産(家、土地)と相続
相続財産の中に、不動産(特に、家や土地)が含まれている場合は、注意が必要です。
3-1. 不動産の評価
不動産の相続税評価額は、路線価方式または倍率方式で計算します。
路線価は、国税庁のホームページで確認できます。
また、固定資産税評価証明書に記載されている評価額も参考になります。
3-2. 共有名義は避ける
不動産を複数の相続人で共有すると、後々トラブルになる可能性があります。
例えば、
・不動産を売却したい場合に、共有者全員の同意が必要になる。
・共有者の一人が死亡した場合、さらに相続が発生し、共有者が増えてしまう。
・共有者間で意見が対立し、不動産の管理が難しくなる。
などの問題が発生する可能性があります。
できる限り、単独名義にするか、売却して現金化することを検討しましょう。
3-3. 相続登記
不動産を相続した場合は、法務局で相続登記(名義変更)の手続きを行う必要があります。
相続登記には、遺産分割協議書、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、住民票、固定資産評価証明書などの書類が必要です。
相続登記は、司法書士に依頼するのが一般的です。
3-4. 農地の相続
農地を相続した場合は、農業委員会への届出が必要です。
また、農地を農地以外の用途に転用する場合は、農地転用の許可が必要となります。
3-5. 相続したくない不動産
相続した不動産が不要な場合は、売却、寄付、相続放棄などの方法を検討します。
ただし、相続放棄は、すべての財産を放棄することになるため、慎重に判断する必要があります。
また、令和5年4月27日から開始された「相続土地国庫帰属制度」を利用して、一定の要件を満たせば、相続した土地を国に引き取ってもらうことも可能です。
4まとめ
相続は、誰もがいつか直面する問題ですが、法律や手続きが複雑で、不安に感じることも多いでしょう。
特に、相続財産に不動産が含まれる場合や、借金がある場合は、慎重な対応が必要です。
「何から手を付けていいか分からない」「手続きが複雑で面倒」「相続人同士で意見が合わない」「借金を相続したくない」「いらない土地をどうにかしたい」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
行政書士は、相続に関する専門知識を持ち、戸籍収集、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、各種名義変更手続き、相続放棄申述書の作成支援、相続土地国庫帰属制度の利用に関する相談など、相続手続きをトータルでサポートできます。
また、相続に関するお悩みや疑問について、親身になって相談に応じ、お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。
当事務所では、相続に関するご相談を幅広く承っており、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。
相続について、何から手を付けていいか分からない、専門的なアドバイスが欲しいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
相続は、決して、身内を「ないがしろ」にするものではありません。
むしろ、次の世代に向けて、亡くなった方(被相続人)の意思・思いを引き継ぎ、未来に向けて、前向きな人生を充実させるために必要な手続きです。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします。
この記事を読んで、少しでも相続について考えるきっかけになれば幸いです。
5お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ