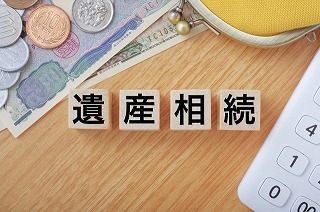
「相続が発生したけど、誰がどれだけ相続できるの?」
「法定相続分って、必ず守らないといけないの?」
「長年介護してきたのに、他の兄弟と同じ相続分なの?」
こんな疑問や不安をお持ちではありませんか?
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産は、相続人に引き継がれます。
しかし、誰が、どれだけの割合で相続するかは、法律で定められており、必ずしも均等に分けるとは限りません。
また、遺言書がある場合や、特定の相続人が「特別な貢献」をした場合など、状況によって相続分は変わってきます。
ご安心ください!
今回の記事では、法定相続分、指定相続分、具体的相続分、特別の寄与など、相続分に関する様々なルールを分かりやすく解説します。
この記事を読めば、相続分に関する疑問が解消され、適切な遺産分割協議を進めるための第一歩を踏み出せます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)にお住まいの皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1法定相続分とは?
法定相続分とは、民法で定められた、各相続人が相続する財産の割合のことです。
遺言書がない場合や、遺言書で相続分が指定されていない場合は、法定相続分に従って遺産分割を行うことになります。
1-1. 相続人の範囲と順位
まず、誰が相続人になるのかを確認しましょう。
民法では、以下の順位で相続人が定められています。
・配偶者: 常に相続人となります。内縁関係の人は含まれません。
・第1順位:子 (子が亡くなっている場合は孫(代襲相続))
・第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)(子がいない場合)
・第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪(代襲相続))(子も直系尊属もいない場合)
1-2. 法定相続分の割合
法定相続分は、相続人の組み合わせによって、以下のように定められています。
・配偶者と子: 配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合は均等に分ける)
・配偶者と直系尊属: 配偶者2/3、直系尊属1/3(直系尊属が複数の場合は均等に分ける)
・配偶者と兄弟姉妹: 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数の場合は均等に分ける)
・子のみ: 子が全てを相続(子が複数の場合は均等に分ける)
・直系尊属のみ: 直系尊属が全てを相続(直系尊属が複数の場合は均等に分ける)
・兄弟姉妹のみ: 兄弟姉妹が全てを相続(兄弟姉妹が複数の場合は均等に分ける)
(注意点)
・非嫡出子(婚外子)の相続分:
以前は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、法改正により、現在は嫡出子と同等の相続分が認められています。
・異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹:
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1となります。
1-3. 法定相続分の具体例
例1: 夫が死亡、相続人は妻と子2人(長男・長女)
・妻:1/2
・長男:1/4
・長女:1/4
例2: 夫が死亡、相続人は妻と夫の母
・妻:2/3
・夫の母:1/3
例3: 夫が死亡、相続人は妻と夫の兄
・妻:3/4
・夫の兄:1/4
2指定相続分とは?
指定相続分とは、亡くなった本人(被相続人)が、遺言書によって、法定相続分とは異なる相続分を指定することです。
遺言書がある場合は、原則として、遺言書の内容が優先されます。
2-1. 指定相続分の有効性
遺言書で相続分を指定する場合は、以下の点に注意が必要です。
(1)遺言書の有効性:
遺言書が、法律で定められた方式に従って作成されている必要があります(自筆証書遺言、公正証書遺言など)。
(2)遺言能力:
遺言書を作成する際に、遺言者に遺言能力(遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力)がある必要があります。
(3)遺留分の侵害:
特定の相続人に多くの財産を相続させると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
2-2. 指定相続分の具体例
例1: 夫が「妻に全財産を相続させる」という遺言書を作成した場合
⇒妻が全財産を相続します。
例2: 夫が「妻に2分の1、長男に4分の1、次男に4分の1を相続させる」という遺言書を作成した場合
⇒妻、長男、次男が、遺言書で指定された割合で相続します。
例3: 夫が「長男に自宅を相続させ、その代わりに長男は次男に代償金として500万円を支払う」という遺言書を作成した場合
⇒長男が自宅を相続し、次男は長男から500万円を受け取ります。
3具体的相続分とは?<特別受益と寄与分>
法定相続分や指定相続分は、あくまでも遺産分割の出発点であり、必ずしもこれらの割合で遺産分割をしなければならないわけではありません。
共同相続人の中に、亡くなった本人(被相続人)から特別な利益(特別受益)を受けた人や、亡くなった本人(被相続人)の財産の維持・増加に特別な貢献(寄与分)をした人がいる場合は、これらの事情を考慮して、相続分を修正することがあります。
この修正された相続分を、「具体的相続分」といいます。
3-1. 特別受益とは?
特別受益とは、共同相続人の中に、亡くなった本人(被相続人)から、
①遺贈(遺言による贈与)
②婚姻、養子縁組のため、または生計の資本としての生前贈与
を受けた人がいる場合に、その受けた利益のことをいいます。
特別受益がある場合、相続人間の公平を図るため、相続分の計算において、特別受益分を相続財産に加算(持ち戻し)して、各相続人の相続分を計算します。
3-1-1. 特別受益となるもの、ならないもの
(1)特別受益となるもの:
①相続人に対する特定遺贈、包括遺贈
②婚姻・養子縁組のための贈与(持参金、支度金など)
③生計の資本としての贈与(居住用不動産の贈与、事業資金の援助、高額な学費など)
(2)特別受益とならないもの:
①生命保険金(受取人が指定されている場合)
②死亡退職金(受取人が指定されている場合)
③通常の扶養の範囲内の贈与(生活費、教育費など)
④社交的な贈与(お祝い金、香典など)
3-1-2. 特別受益の持ち戻し免除
亡くなった本人(被相続人)が、特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をしていた場合は、持ち戻しは行われません。
持ち戻し免除の意思表示は、遺言書で行うことが一般的ですが、口頭や手紙などでも有効です。
3-1-3. 配偶者保護のための方策(持ち戻し免除の意思表示の推定)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(自宅など)の遺贈または贈与が行われた場合、原則として、亡くなった本人(被相続人)は、特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をしたものと推定されます。
これにより、配偶者は、居住用不動産を確実に取得でき、その後の生活の安定が図られます。
3-2. 寄与分とは?
寄与分とは、共同相続人の中に、亡くなった本人(被相続人)の財産の維持または増加に、特別な貢献をした人がいる場合に、その貢献度に応じて、相続分を増やす制度です。
3-2-1. 寄与分が認められるケース
①亡くなった本人(被相続人)の事業に関する労務の提供:
家業を手伝っていた、農業を手伝っていたなど。
②亡くなった本人(被相続人)の事業に関する財産上の給付:
事業資金を援助した、土地を提供したなど。
③亡くなった本人(被相続人)の療養看護:
長年、病気の親の介護をしていたなど。
その他: 上記に準じるような、特別な貢献があった場合。
3-2-2. 寄与分の算定方法
寄与分は、まず相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立て、寄与分を定めてもらうことになります。
寄与分の額は、具体的な事情に応じて、個別に判断されます。
例えば、療養看護の場合は「期間・程度・得られた経済的利益・他の相続人との関係」
などを総合的に考慮して、寄与分の額が決定されます。
3-3. 具体的相続分の計算方法
特別受益や寄与分がある場合の、具体的相続分の計算方法は、以下のとおりです。
(1)みなし相続財産の算出:
相続開始時の相続財産の価額に、特別受益の価額を加え、寄与分がある場合は、寄与分の額を差し引きます。
(2)各相続人の相続分の算出:
みなし相続財産に、各相続人の法定相続分または指定相続分を掛けます。
(3)具体的相続分の算出:
・特別受益者の場合: 上記2で計算した相続分から、特別受益の額を差し引きます。
・寄与分がある場合: 上記2で計算した相続分に、寄与分の額を加えます。
(具体例)
・相続人:妻、長男、長女
・相続財産:5000万円
・特別受益:長男が生前に1000万円の住宅購入資金の贈与を受けていた
・寄与分:長女が長年、亡くなった父の介護をしていた(寄与分200万円と評価)
↓
<計算>
(1)みなし相続財産: 5000万円 + 1000万円 – 200万円 = 5800万円
(2)各相続人の相続分:
妻:5800万円 × 1/2 = 2900万円
長男:5800万円 × 1/4 = 1450万円
長女:5800万円 × 1/4 = 1450万円
(3)具体的相続分:
妻:2900万円
長男:1450万円 – 1000万円 = 450万円
長女:1450万円 + 200万円 = 1650万円
3-4. 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)
寄与分は、相続人にのみ認められる制度です。
そのため、相続人ではない人(例えば、長男の妻など)が、亡くなった本人(被相続人)の療養看護などに貢献した場合、寄与分は認められません。
しかし、令和元年7月1日施行の改正相続法により、「特別の寄与」の制度が新設されました。
これにより、相続人以外の親族(例えば、長男の妻)が、無償で療養看護などの労務を提供し、亡くなった本人(被相続人)の財産の維持または増加に貢献した場合、相続人に対して、金銭の支払いを請求できるようになりました。
4まとめ
相続分は、遺言書の有無、相続人の構成、特別受益や寄与分の有無など、様々な要因によって変わってきます。
今回の記事では、法定相続分、指定相続分、具体的相続分、特別の寄与など、相続分に関する様々なルールを解説しました。
しかし、実際の遺産分割は、個別の事情によって判断が異なる場合も多く、専門的な知識が必要となることも少なくありません。
「自分の場合はどうなるの?」「遺産分割で揉めないためにはどうすればいい?」など、相続に関する疑問や不安は、専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士は、法律と手続きの専門家であり、相続に関する様々な問題について、的確なアドバイスとサポートを提供することができます。
遺産分割協議書の作成、相続人調査、相続財産調査、相続放棄の手続きなど、相続に関するあらゆる手続きを代行することができます。
当事務所では、相続に関するご相談を幅広く承っており、お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。
相続について、何から手を付けていいか分からない、専門的なアドバイスが欲しいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
相続は、決して、身内を「ないがしろ」にするものではありません。
むしろ、次の世代に向けて、亡くなった方(被相続人)の意思・思いを引き継ぎ、未来に向けて、前向きな人生を充実させるために必要なバトンタッチです。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします。
この記事を読んで、少しでも相続について考えるきっかけになれば幸いです。
5お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ





