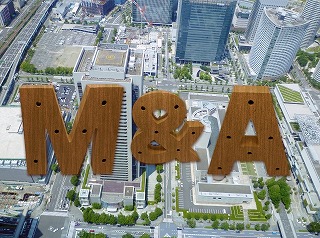「建設業法に違反すると、具体的にどんな罰則があるのだろう?」
「『監督処分』って、罰金とは違うの?」
「営業停止や許可取消しになるのは、一体どんなケース?」
こんな疑問や、漠然とした不安を感じていませんか?
ご安心ください。
その不安は、建設業法が定める制裁の仕組みと、その具体的な内容を正しく理解することで、明確な「備え」へと変わります。
この記事では、建設業者の皆様が絶対に知っておくべき、建設業法違反に対する「罰則」と「監督処分」という2種類の制裁について、その違いと内容を分かりやすく解説します。
建設業を営む上で、その根幹をなす法律が「建設業法」です。
この法律は、建設業の健全な発展を促すためのルールブックであり、そのルールを破った者には、厳しい制裁が科せられます。
「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされないこれらの制裁は、時に企業の存続そのものを揺るがしかねない、非常に重いものです。
今回は、すべての建設業者が知っておくべき、建設業法違反に対する2種類のペナルティ、「罰則」と「監督処分」について、その違いと具体的な内容を詳しく見ていきましょう。
1「罰則」と「監督処分」の決定的な違い
まず、この2つの制裁は、その性質が全く異なります。
1-1. 罰則(ばっそく)
「罰則」とは、刑事罰のことを指します。
警察による捜査や、検察による起訴を経て、最終的に裁判所が判断を下す、最も重い制裁です。
「懲役刑」や「罰金刑」がこれに該当します。
1-2. 監督処分(かんとくしょぶん)
「監督処分」とは、行政罰のことを指します。
建設業の許可を与えた国土交通大臣や都道府県知事といった「許可行政庁」が、法律違反や不適切な行為に対して、直接的に下す処分です。「指示」「営業停止」「許可取消し」がこれに該当します。
重要なのは、一つの違反行為に対して、罰則と監督処分の両方が科される可能性があるということです。
2知っておくべき「罰則」の具体的な内容
建設業法には、違反行為の悪質性に応じて、いくつかの段階の罰則が定められています。
2-1. 最も重い罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
これらは、建設業法の根幹を揺るがす、極めて悪質な違反行為に適用されます。
⑴ 無許可営業:
建設業許可を受けずに、許可が必要な規模の工事を請け負う行為。
⑵ 特定建設業許可違反:
特定建設業許可がないにもかかわらず、基準額(下請総額5,000万円/建築一式8,000万円以上)を超える下請契約を締結する行為。
⑶ 営業停止処分中の営業行為:
営業停止処分を受けているにもかかわらず、営業活動を行う行為。
さらに、これらの違反を法人が行った場合、法人に対して「1億円以下の罰金」という、極めて重い罰金が科される両罰規定もあります。
2-2. その他の罰則
⑴ 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金:
許可申請書や経営状況分析申請書などに、虚偽の記載をして提出する行為など。
⑵ 100万円以下の罰金:
工事現場への主任技術者・監理技術者の不設置など。
⑶ 10万円以下の過料(かりょう):
建設業許可票の不掲示や、廃業届の未提出など。
2-3. 罰則がもたらす最悪のシナリオ
罰金以上の刑罰を受けることは、建設業許可の「欠格要件」に該当します。
これは、許可が取り消されるだけでなく、その後5年間、新たに建設業許可を取得することができなくなるという、事実上の「業界からの退場」を意味します。
3許可行政庁が下す「監督処分」
刑事罰である「罰則」とは別に、許可行政庁は、建設業者の不正行為に対して、以下の3段階で監督処分を行います。
3-1. ①指示処分
最も軽い処分です。法令違反や不適切な行為に対して、それを是正するために必要な措置をとるよう、具体的な「指示」が出されます。
3-2. ②営業停止処分
「指示」に従わない場合や、違反行為が悪質な場合に下される、より重い処分です。
1年以内の期間を定めて、建設業の営業の全部または一部が停止させられます。
営業停止期間中は、新たな請負契約を締結することは一切できません。
3-3. ③許可取消処分
最も重い処分です。
営業停止処分に違反した場合や、不正行為が極めて悪質で、社会的な影響が大きい場合に、建設業許可そのものが取り消されます。
3-4. どのような行為が処分の対象となるのか
実際にどのような行為が監督処分の対象となっているのかは、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で、過去の事例を検索することができます。
例えば、以下のような、日々の業務に潜む違反行為が、厳しい処分の対象となっています。
① 技術者の不適切配置:
主任技術者・監理技術者の不設置や、名義貸し、専任義務違反。
② 一括下請負(丸投げ):
禁止されている工事の丸投げ。
③ 不適切な契約行為:
書面による契約締結義務の違反や、不当に低い請負代金での契約。
4整理
建設業法違反に対する罰則や監督処分は、企業の経営に致命的なダメージを与えかねない、非常に厳しいものです。
「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断や、知らなかったという言い訳は通用しません。
日々の業務において、建設業法をはじめとする関連法令を遵守する意識を、経営者様から従業員一人ひとりに至るまで、社内全体で共有すること。
それこそが、これらの厳しい制裁から会社を守り、社会からの信頼を勝ち得て、持続的に成長していくための「最強の鎧」となるのです。
5まとめ
建設業法に違反した場合、「罰則」と「監督処分」という、二つの厳しい制裁が待ち受けています。
特に、罰金以上の刑罰は、5年間の許可欠格期間に繋がり、事業の継続を極めて困難にします。
「自社のコンプライアンス体制は、本当に万全だろうか」と少しでも不安に感じたら、手遅れになる前に、ぜひ専門家にご相談ください。
当事務所は、建設業法務の専門家として、企業のコンプライアンス体制の構築をサポートします。
元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、貴社を法務リスクから守り、健全な事業運営を力強く支援いたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/