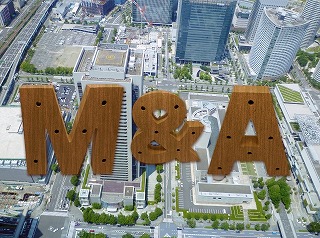「日々の会計帳簿とは別に、建設業法で定められた特別な『帳簿』が必要だって本当?」
「その帳簿には、具体的に何を書けばいいの?」
「工事が終わった後、契約書や図面は、いつまで保管しておけば安心?」
こんな疑問や不安を感じていませんか?
ご安心ください。
その悩みは、建設業法が定める「帳簿」と「営業に関する図書」の作成・保存ルールを正しく理解することで解決できます。
この記事では、すべての建設業許可業者に課せられた、重要な書類の記録と保存に関する義務について、その具体的な内容から保存期間までを分かりやすく解説します。
建設業の許可を取得し、事業を運営していく上で、日々の取引を正確に記録し、その証拠書類を適切に保存することは、企業のコンプライアンスとリスク管理の根幹をなすものです。
特に建設業法では、一般的な会計帳簿とは別に、建設業の営業に特化した「帳簿」と「営業に関する図書」という、2種類の重要な書類の作成・保存を、許可業者に対して義務付けています。
これらのルールは、しばしば「知らなかった」「そこまでやる必要はないと思っていた」と見過ごされがちですが、立入検査の際には必ずチェックされる重要項目です。
今回は、企業の信頼を守るための、この書類管理のルールについて詳しく見ていきましょう。
1建設業許可業者の義務(「帳簿」の作成・保存)
まず、すべての建設業許可業者が、各営業所において備え付け、保存しなければならない「帳簿」について解説します。
1-1. 「帳簿」とは何か?
建設業法第40条の3で定められた「帳簿」とは、個々の建設工事の請負契約の内容を、法律が求める事項に沿って記録した、いわば「工事契約の公式記録台帳」です。
この帳簿を備え付け、常に最新の状態に保つことは、建設業許可業者の基本的な義務です。
1-2. 帳簿の記載事項
帳簿の様式は任意ですが、以下の事項を漏れなく記載する必要があります。
① 営業所の代表者に関する事項:
代表者の氏名と、その者が代表者になった年月日。
② 元請として締結した契約に関する事項:
工事名、場所、工期、契約日、注文者の情報、完成検査の日付、引渡し日など。
③ (元請として)新築住宅の契約に関する事項:
住宅瑕疵担保履行法に関連する、床面積や保険加入状況など。
④ 下請として締結した契約に関する事項:
担当工事の内容、工期、契約日、下請負人の情報、完成検査・引渡しを受けた日付など。
⑤ 特定建設業者が注文者となる下請契約に関する事項:
下請代金の支払額、支払日、支払手段(手形の場合はその詳細)、遅延利息など。
1-3. 帳簿の保存期間と罰則
作成した帳簿は、事業年度の終了後、5年間の保存が義務付けられています。
ただし、新築住宅に関する契約については、買主保護の観点から10年間の保存が必要です。
この帳簿の作成や保存を怠った場合、10万円以下の過料という罰則の対象となります。
2帳簿と一体で管理すべき「添付書類」
帳簿は、それ単体で存在するものではありません。
その記載内容が事実であることを証明するための「添付書類」と一体で管理・保存する必要があります。
立入検査の際には、この添付書類もセットで確認されます。
2-1. 主な添付書類
① 契約書の写し:
発注者と締結した元請契約書、および、すべての下請負人と締結した下請契約書(注文書・請書も含む)の写し。
② 支払いを証明する書類:
特定建設業者が下請代金を支払ったことを証明する、領収書の写しなど。
③ 施工体制台帳を作成した場合の関連書類:
施工体制台帳そのものや、配置した監理技術者の資格・雇用関係を証明する書面など。
3元請業者に課せられる、もう一つの保存義務:「営業に関する図書」
帳簿とは別に、発注者から直接建設工事を請け負った元請負人に限り、その営業に関する特定の「図書」を10年間保存することが義務付けられています。
3-1. 「営業に関する図書」とは何か?
これは、主に工事の技術的な内容や、発注者とのやり取りの経緯を記録した書類で、将来の紛争(特に瑕疵=欠陥をめぐるトラブル)に備えるための重要な証拠資料となります。
具体的には、以下の3種類の書類を指します。
① 完成図:
工事が完成した時点の図面。
② 発注者との打合せ記録:
仕様変更の協議など、発注者との重要なやり取りの記録(協議書、議事録など)。
③ 施工体系図:
施工体制台帳の作成が義務付けられている工事で作成したもの。
3-2. 保存の重要性
建設工事の目的物は、引き渡しから数年後に不具合が発覚することも少なくありません。その際に、これらの図書がなければ、当時の施工状況や責任の所在を客観的に証明することが困難になります。適切な書類保存は、将来の自社を守るための重要なリスク管理なのです。
この図書の保存を怠った場合も、10万円以下の過料の対象となります。
4整理
建設業法が求める「帳簿」と「営業に関する図書」の作成・保存は、一見すると煩雑な事務作業に思えるかもしれません。
しかし、これらは、自社の業務の適正性を内外に証明し、万が一のトラブルから会社を守り、そして行政からの立入検査にも胸を張って対応するための、不可欠な企業防衛のツールです。
デジタル化も進み、電磁的記録による保存も認められています。
自社の記録管理体制が、法律の求める基準を満たしているか、この機会にぜひ一度、見直してみてはいかがでしょうか。
5まとめ
建設業許可業者には、建設業法に基づき、「帳簿」と「営業に関する図書」という、2種類の重要な書類の作成・保存が義務付けられています。
その記載事項や保存期間は厳格に定められており、これを怠ると罰則の対象となるだけでなく、企業の信用問題にも発展しかねません。
「自社の書類管理体制で、本当に大丈夫だろうか」「法律が求める帳簿の作り方が分からない」など、日々の記録管理に関するお悩みは、専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、最新の法令に基づいた、コンプライアンスとリスク管理の両面から、貴社の事業運営を力強くサポートいたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/