
「建設業許可の『令3条使用人』って何?支店長のこと?」
「令和2年の法改正で、社会保険加入が必須になったって本当?」
「申請書類が簡素化されたと聞いたけど、具体的に何が変わったの?」
こんな疑問はありませんか?
ご安心ください。
今回の記事では、建設業許可における「令3条使用人」の定義や常勤性と、令和2年からの社会保険加入義務化、そして申請書類の簡素化について、詳しく解説します。
この記事を読めば、建設業許可に関する最新情報が理解でき、スムーズな許可申請・更新への道筋が見えてきます。
岩手県や宮城県で建設業許可取得・更新をお考えの皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1建設業許可の「令3条使用人」とは?:営業所の代表者
建設業許可において、「令3条使用人」という言葉が出てきます。
これは、一体どのような人を指すのでしょうか?
ここでは、「令3条使用人」の定義や役割について解説します。
1-1. 「令3条使用人」の正式名称と定義
「令3条使用人」とは、正式には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」といいます。具体的には、建設業を営む営業所の代表者のことです。
具体例:
・支店の支店長
・営業所の所長
・支配人
その他、副支店長、支店次長、事業部長などの肩書で、その営業所において建設工事の見積り、入札、請負契約の締結などの権限を実質的に有している者
1-2. 「令3条使用人」の役割:営業所の権限を持つ
令3条使用人は、その営業所における建設工事の見積り、入札、請負契約の締結などを行う権限を持っています。
つまり、営業所の代表者として、建設業に関する重要な業務を行うことができる立場です。
1-3. 注意点:役職名だけでは判断できない
重要なのは、役職名だけで令3条使用人に該当するかどうかが決まるわけではない、ということです。
例えば、「支店長」という肩書であっても、上記の権限を持っていなければ、令3条使用人には該当しません。
逆に、「副支店長」という肩書であっても、上記の権限を持っていれば、令3条使用人に該当します。
1-4. 役員である必要はない
令3条使用人は、必ずしも役員である必要はありません。
従業員であっても、上記の権限を持っていれば、令3条使用人になることができます。
2令3条使用人に常勤性は必要?:建設業法上の規定と実務
令3条使用人に、常勤性は求められるのでしょうか?
ここでは、建設業法上の規定と、実務上の取り扱いについて解説します。
2-1. 建設業法上の規定:常勤性の規定はない
実は、建設業法には、令3条使用人が常勤でなければならない、という明確な規定はありません。
つまり、法律上は、非常勤の令3条使用人も認められる、ということになります。
2-2. 国土交通省の見解:原則として常勤
ただし、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」では、令3条使用人について、「原則として、当該営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事している者が、これに該当する」とされています。
つまり、国土交通省としては、原則として常勤であることを求めている、ということです。
2-3. 実務上の取り扱い:常勤が望ましい
実務上も、令3条使用人は常勤であることが望ましいとされています。
特に、建設業許可の新規申請や更新の際には、常勤性を確認されることがあります。
非常勤の令3条使用人を置く場合は、事前に許可行政庁に相談し、確認しておくことをおすすめします。
3令和2年4月から書類簡素化:令3条使用人関連書類はどうなった?
国土交通省は、令和2年4月1日から、建設業許可に関する申請書類を大幅に簡素化しました。
ここでは、令3条使用人関連の書類がどのように変わったのかを解説します。
3-1. 書類簡素化の背景:申請者の負担軽減
書類簡素化の背景には、建設業許可の申請手続きが煩雑で、申請者の負担が大きいという問題がありました。
特に、大臣許可においては、確認資料の提出が多く、書類作成に多大な時間と労力がかかっていました。
3-2. 簡素化された書類:令3条使用人関連
大臣許可において、以下の令3条使用人関連の書類が、提出不要となりました。
①営業所の確認資料:
営業所の地図
不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書等の写し
営業所の写真(新設の営業所を除く)
②令3条使用人の確認資料:
住民票など(現住所確認)
健康保険証の写し
辞令・委任状(権限確認)
3-3. 注意点:知事許可は都道府県によって異なる
上記の書類簡素化は、大臣許可の場合です。知事許可の場合は、都道府県によって取り扱いが異なる場合があります。
岩手県や宮城県(仙台市を含む)の取り扱いについては、それぞれのホームページで確認するか、行政書士藤井等事務所までお気軽にお問い合わせください。
4改正建設業法:社会保険加入が許可要件に
令和2年10月に施行された改正建設業法では、「適切な社会保険への加入」が建設業許可の要件となりました。
ここでは、この改正の背景、具体的な内容、そして許可申請への影響について、さらに詳しく解説します。
4-1. 改正の背景:社会保険未加入問題の深刻化と対策
建設業界では、長年にわたり、社会保険未加入問題が深刻な課題となっていました。
この問題は、以下のような悪循環を引き起こしていました。
①不公平な競争環境:
社会保険料を負担しない企業が、不当に低い価格で工事を受注し、適正な価格で受注できない企業が競争上不利になる。
②労働環境の悪化:
社会保険に加入できない労働者は、十分な保障を受けられず、安心して働くことができない。
③若年入職者の減少:
将来への不安から、若者が建設業界を敬遠し、人手不足が深刻化する。
これらの問題を解決するため、国土交通省は、平成24年度から「社会保険未加入対策」を推進してきました。
様々な取り組みが行われた結果、建設業における社会保険加入率は年々増加しましたが、未加入企業が依然として存在し、問題の完全な解決には至っていませんでした。
4-2. 改正の内容:許可申請時の加入状況確認の義務化
改正建設業法では、建設業許可の申請時(新規・更新・業種追加など)に、適切な社会保険に加入しているかどうかを確認することが義務付けられました。
具体的には、以下の社会保険について、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、建設業許可を受けることができません。
①健康保険: 協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など
②厚生年金保険: 厚生年金
③雇用保険: 雇用保険
これにより、社会保険未加入企業は、建設業許可を取得・維持することができなくなり、建設市場から排除されることになります。
4-3. 適切な社会保険とは?:加入すべき保険の種類と判断基準
「適切な社会保険」とは、具体的にどの保険を指すのでしょうか?加入すべき社会保険の種類は、事業所の形態(法人か個人か)、従業員の数、働き方などによって異なります。
①法人:
原則として、健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)と厚生年金保険に加入する義務があります。
従業員を雇用する場合は、雇用保険にも加入する義務があります。
役員報酬がゼロの場合でも、健康保険と厚生年金保険の加入義務があります(ただし、一定の条件を満たす場合は、適用除外となる場合があります)。
②個人事業主:
従業員が5人未満の場合は、健康保険と厚生年金保険の加入義務はありません(任意加入)。
ただし、従業員を雇用する場合は、雇用保険に加入する義務があります。
従業員が5人以上の場合でも、一部の業種(理容・美容業、飲食店など)では、健康保険と厚生年金保険の加入義務がない場合があります。
・国民健康保険と国民年金に加入
・一人親方⇒国民健康保険と国民年金に加入
詳細については、国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」や、厚生労働省のホームページなどで確認するか、社会保険労務士や行政書士などの専門家にご相談ください。
4-4. 許可申請への影響:提出書類と審査のポイント
建設業許可の申請時には、社会保険の加入状況を証明する書類の提出が必要になります。
・提出書類の例:
健康保険証の写し
社会保険料の領収証書または納入証明書
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
その他、加入状況を証明できる書類
審査のポイントは、以下のとおりです。
①加入義務の有無:
事業所の形態や従業員の数などから、加入義務があるかどうかを判断します。
②加入状況:
加入義務がある社会保険に、適切に加入しているかどうかを確認します。
③保険料の納付状況:
保険料が適切に納付されているかどうかを確認します。
社会保険の加入状況に不備がある場合は、許可申請が受理されない、または許可が下りない可能性があります。
5社会保険加入に関する下請指導ガイドライン:元請・下請の役割
国土交通省は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を策定し、建設業における社会保険加入を推進しています。
このガイドラインでは、元請企業と下請企業それぞれが果たすべき役割と責任が明確にされています。ここでは、その内容をさらに詳しく解説します。
5-1. 元請企業の役割と責任:多岐にわたる取り組み
元請企業は、自社だけでなく、下請企業も含めた建設現場全体の社会保険加入を推進する責任があります。
その役割は多岐にわたります。
①協力会社組織を通じた指導:
協力会社組織(協力会など)を通じて、社会保険加入の重要性や、加入手続きなどについて、定期的に情報提供や指導・啓発を行います。
安全大会などの機会を活用して、社会保険に関する講習会を実施することも有効です。
②下請企業選定時の確認・指導:
下請企業を選定する際に、見積書や契約書などで、社会保険の加入状況を確認します。
未加入の企業に対しては、加入を強く指導し、加入しない場合は、原則として下請契約を締結しない、という厳しい姿勢で臨むことが求められます。
建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用して、下請企業の社会保険加入状況を確認することも推奨されています。
③再下請通知書を活用した確認・指導:
下請企業から提出される再下請通知書には、社会保険の加入状況を記載する欄があります。この欄を活用して、下請企業の社会保険加入状況を確認し、未加入の場合は指導を行います。
④作業員名簿を活用した確認・指導:
下請企業から提出される作業員名簿には、作業員の社会保険の加入状況を記載する欄があります。この欄を活用して、社会保険加入状況を確認します。
建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録された技能者の情報を活用することも推奨されています。
⑤施工体制台帳の作成を要しない工事における取扱い:
施工体制台帳の作成が義務付けられていない小規模な工事(請負金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満))であっても、下請企業の社会保険加入状況を確認し、指導を行うことが求められます。
⑥建設工事の施工現場における周知啓発:
工事現場に、社会保険加入を促すポスターを掲示するなど、労働者に対して社会保険加入の重要性を周知します。
朝礼などの機会を利用して、社会保険に関する情報提供を行うことも有効です。
⑦法定福利費の適正な確保:
見積もり時に、法定福利費(社会保険料の事業主負担分)を内訳明示し、下請企業にも適正な金額を支払うようにします。
下請企業から提出された見積書に法定福利費が明示されていない場合は、その理由を確認し、必要に応じて内訳明示を求めます。
⑧一人親方の実態の適切性の確認:
一人親方と請負契約を締結する場合は、その実態が労働者でないか(偽装一人親方でないか)を確認します。
偽装一人親方である場合は、労働者として扱い、社会保険に加入させる必要があります。
一人親方は、通常、国民健康保険と国民年金に加入していますが、労災保険には特別加入が必要となります。
5-2. 下請企業の役割と責任:自社の加入と元請への協力
下請企業は、自社の労働者を適切に社会保険に加入させる責任があります。また、元請企業が行う社会保険加入に関する指導に協力する義務があります。
①労働者の社会保険への加入:
雇用する労働者を、適切に社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入させます。
加入手続きを怠ったり、虚偽の申告をしたりすることは、法律違反です。
②一人親方への対応:
一人親方と請負契約を締結する場合は、その実態が労働者でないか(偽装一人親方でないか)を確認します。
偽装一人親方である場合は、労働者として扱い、社会保険に加入させる必要があります。
一人親方に対して、社会保険加入の重要性を説明し、加入を促すことが望ましいです。
③元請企業が行う指導への協力:
元請企業が行う社会保険加入に関する指導や調査に協力します。
元請企業から求められた場合は、社会保険の加入状況に関する書類を提出します。
④労働者の法定福利費の適正な確保:
労働者の賃金から、法定福利費(社会保険料の本人負担分)を適切に控除し、事業主負担分と合わせて、社会保険料を納付します。
⑤再下請に対する適正な法定福利費の確保:
再下請企業に対しても、法定福利費を適切に確保するよう指導します。
再下請企業から提出された見積書に法定福利費が明示されていない場合は、その理由を確認し、必要に応じて内訳明示を求めます。
5-3. 無許可業者への対応:社会保険未加入は許されない
令和2年10月の改正法施行により、建設業者は、社会保険の加入が要件となりました。
これは、許可業者だけでなく、無許可業者に対しても同様に適用されるべきと考えられています。
元請企業は、下請企業を選定する際に、建設業許可の有無にかかわらず、社会保険の加入状況を確認し、未加入の業者を下請として選定しない、という厳しい対応が求められます。
6まとめ
建設業許可における「令3条使用人」の定義、常勤性、社会保険加入義務化、申請書類の簡素化について解説しました。
建設業許可の取得・更新は、専門的な知識が必要なだけでなく、手続きも煩雑です。
「令3条使用人って誰を指名すればいい?」「社会保険に未加入だと許可は取れない?」など、疑問や不安があれば、お気軽に専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士藤井等事務所は、建設業許可の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
7お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ<許認可申請>


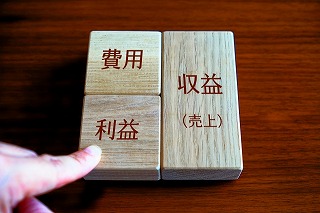

.jpg)

