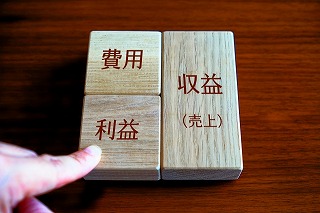「建設業許可、海外での経験は活かせないの?」
「経営管理責任者って、具体的にどんな経験が必要?」
「大臣認定って何?どうすれば取得できるの?」
こんな悩みはありませんか?
ご安心ください。今回の記事では、建設業許可における「経営業務の管理責任者」の要件や、海外での経験を活かすための「国土交通大臣認定」について詳しく解説します。
その悩みは、今回の説明で解決できます。
岩手県で建設業許可取得をお考えの皆様、必見の内容です。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1 建設業許可のキーパーソン:「経営業務の管理責任者」に求められる経験とは?
岩手県で建設業を営む皆様、建設業許可を取得・更新する上で避けて通れないのが「経営業務の管理責任者」(通称:経管)の要件です。
この経管、一体どんな経験が必要なのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
1-1. 「経営業務の管理責任者」ってどんな人?
経管とは、その名の通り、建設業の経営について「総合的」に管理する責任者のことです。
会社の「舵取り役」と言えるでしょう。
許可を受けるためには、この経管が、一定の経験を持っていることが必要です。
1-2. 求められるのは「総合的な管理経験」
具体的に求められるのは、「営業取引上対外的に責任ある地位」で、「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」です。
少し難しい言葉が並んでいますが、要するに、会社の経営層の一員として、建設業の経営全般に関わってきた経験が必要ということです。
1-3. 具体例でチェック!:こんな経験は認められる?
(1)OK例:
・建設会社の役員として、5年以上経営に携わった。
・個人事業主として、5年以上建設業を営んだ。
・建設会社の支店長として、5年以上、その支店の経営を任された。
(2)NG例:
建設会社の工事部門の責任者として、5年以上働いた。(経営には関わっていない)
建設会社の経理担当として、5年以上働いた。(経営には関わっていない)
*参考:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」、岩手県「建設業許可申請の手引き」
2 グローバルな経験も強みに!:「国土交通大臣認定」で海外経験を活かす!
「海外の建設会社で役員をしていた経験があるけど、これは建設業許可に活かせないの?」
そんな疑問をお持ちの方もいるかもしれません。
実は、一定の条件を満たせば、「国土交通大臣認定」を受けることで、海外での経験も経管の経験として認められる場合があります。
ここでは、その詳細をさらに深掘りしていきます。
2-1. なぜ「大臣認定」が必要なの?:制度の背景と目的
原則として、経管の経験は日本国内でのものが対象です。
これは、日本の建設業法や商慣習に精通していることを求めるためです。
しかし、グローバル化が急速に進む現代において、海外での豊富な経験を持つ人材も増えています。
これらの人材の能力を日本の建設業で活かすため、例外的に設けられたのが「国土交通大臣認定」制度です。
この制度は、単に海外経験を評価するだけでなく、日本の建設業の国際競争力を高めるという目的も持っています。
海外の技術やノウハウを取り入れることで、日本の建設業全体のレベルアップを図る狙いもあるのです。
2-2. 大臣認定のメリット:日本人にも外国人にも適用可能!幅広い適用範囲
大臣認定の大きなメリットは、その適用範囲の広さにあります。
まず、申請者の国籍は問いません。日本人だけでなく、外国人でも申請可能です。
これは、海外で活躍する日本人だけでなく、日本で建設業を営みたい外国人も対象にしているということです。
さらに、経験した企業が日本企業か外国企業かも問いません。
例えば、日本の建設会社が海外に設立した子会社での役員経験も、大臣認定の対象となり得ます。
2-3. 専任技術者などにも適用可能!:技術者のキャリアパスも広がる
大臣認定は、経管だけでなく、営業所の専任技術者や、主任技術者、監理技術者についても受けることができます。これは、技術者にとっても大きなメリットです。
例えば、海外の大学で建築学を専攻した人が、日本の建設会社で働く場合、通常は日本の学歴要件を満たさないため、専任技術者になれないことがあります。
しかし、大臣認定を受けることで、海外での学歴を日本の学歴と同等とみなしてもらい、専任技術者として活躍できる道が開けます。
2-4. 大臣認定の具体例:こんなケースで活用できる!
(1)ケース1:
日本の建設会社に勤務後、アメリカの建設会社で役員として10年勤務。
帰国後、日本で建設会社を設立したいが、日本の役員経験だけでは5年に満たない。
→ 大臣認定でアメリカでの役員経験を認めさせ、経管の要件を満たす。
(2)ケース2:
中国出身で、中国の建設会社で長年役員を務めてきた。
日本で建設業許可を取得したいが、日本の経験がない。
→ 大臣認定で中国での役員経験を認めさせ、経管の要件を満たす。
(3)ケース3:
カナダの大学で土木工学を専攻し、卒業後、現地の建設会社で5年間技術者として勤務。
日本の建設会社に転職したが、学歴要件を満たさないため専任技術者になれない。
→ 大臣認定でカナダでの学歴と実務経験を認めさせ、専任技術者となる。
3大臣認定申請への道:必要書類と手続きの流れ
大臣認定を受けるためには、どのような手続きが必要なのでしょうか?ここでは、具体的なステップと注意点をさらに詳しく解説します。
3-1. 準備が肝心!:海外からの書類取り寄せと翻訳のポイント
まず、海外での経験を証明するための書類を、現地から取り寄せる必要があります。
この際、以下の点に注意しましょう。
・必要書類の確認:
どの書類が必要かは、経験した国や企業、役職などによって異なります。
事前に国土交通省の担当部署に確認し、正確な情報を把握しましょう。
・原本の入手:
原則として、書類の原本が必要です。コピーでは認められない場合が多いため、注意が必要です。
・翻訳の正確性:
外国語で書かれている書類は、日本語への翻訳が必要です。
翻訳は、専門の翻訳会社に依頼するなど、正確性を確保しましょう。
誤訳があると、審査に影響が出る可能性があります。
・翻訳証明:
翻訳した書類には、翻訳者が署名・捺印した「翻訳証明」を添付する必要があります。
3-2. 「公証」って何?:書類の信頼性確保
「公証」とは、公証人が、私文書に認証を与えることで、その文書の成立や記載が真正であることを証明する制度です。
大臣認定の申請においては、海外から取り寄せた書類や、その翻訳文の信頼性を高めるために、公証が必要となる場合があります。
・公証の種類:
公証には、私署証書の認証、外国文認証など、いくつかの種類があります。
どの種類の公証が必要かは、提出する書類によって異なります。
・公証役場:
公証は、公証役場で行います。公証役場は、全国各地にあります。
・手数料:
公証には、手数料がかかります。手数料は、公証の種類や書類の内容によって異なります。
3-3. 時間に余裕を持って!:申請までの準備期間とスケジュール
海外からの書類取り寄せ、翻訳、公証…これらの手続きには、かなりの時間がかかるります。数ヶ月かかることも珍しくありません。
<スケジュール例>
・情報収集(1週間):
国土交通省のホームページや担当部署への問い合わせで、必要書類や手続きの流れを確認。
・書類取り寄せ(1ヶ月〜3ヶ月):海外の企業や機関に連絡し、必要書類を取り寄せる。・翻訳(1週間〜2週間):翻訳会社に依頼し、日本語への翻訳を行う。
・公証(1週間): 公証役場で、必要書類の公証を受ける。
・申請書作成(1週間): 国土交通省の指定様式に従い、申請書を作成。
・提出・審査(1ヶ月〜数ヶ月): 国土交通省に申請書を提出し、審査を受ける。
上記はあくまで一例ですが、全体のスケジュール感を把握し、余裕を持って準備を進めることが重要です。
3-4. 提出書類の一例:詳細と注意点
大臣認定を受けるための提出書類は、個々のケースによって異なりますが、一般的には以下のものが挙げられます。
(1)建設業法施行規則第7条第1号イの場合(個人の経験を認定)
・認定申請書:国土交通省の指定様式を使用します。
・認定を受けようとする者の履歴書:詳細な職務経歴を記載します。
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書:国土交通省の指定様式を使用します。
・役員就任・退任議事録又は会社登記簿謄本(原本証明が必要):
海外の企業の場合、日本の登記簿謄本に相当する公的書類が必要です。国によっては、入手が困難な場合もあります。
・会社組織図:役職や部署間の関係がわかるように記載します。
・建設工事を施工した契約書の写し(原本証明が必要):
海外での建設工事の実績を証明する書類です。契約書の言語が外国語の場合は、翻訳も必要です。
・会社概要資料(パンフレット、建設業許可証の写し、会社登記簿謄本など):
海外の企業の概要を説明する資料です。
(2)建設業法施行規則第7条第1号ロの場合(組織としての経験を認定)
・認定申請書:国土交通省の指定様式を使用します。
・認定を受けようとする者、補佐人の履歴書:詳細な職務経歴を記載します。
・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書:国土交通省の指定様式を使用します。
・役員就任、退任議事録又は会社登記簿謄本(原本証明が必要):海外の企業の場合、日本の登記簿謄本に相当する公的書類が必要です。
・補佐人に対する確認資料:補佐人の役職や経験を証明する書類です。
・会社組織図:役職や部署間の関係がわかるように記載します。
・建設工事を施工した契約書の写し(国内経験で許可業者であれば許可通知書)(原本証明が必要):
海外および日本での建設工事の実績を証明する書類です。
・会社概要資料(パンフレット、建設業許可証の写し、会社登記簿謄本など):
海外および日本の企業の概要を説明する資料です。
※注意: 上記はあくまで一例です。審査の過程で、追加資料を求められることもあります。国土交通省の担当部署に事前に相談し、必要書類を十分に確認することが重要です。
3-5. 提出先は?:国土交通省の担当部署への提出方法
準備が整ったら、申請書を国土交通省の不動産・建設経済局国際市場課に提出します。
4まとめ
経営業務の管理責任者の要件や、海外での経験を活かすための大臣認定について解説しました。
建設業許可の取得は、複雑で分かりにくい手続きが多いですが、専門家である行政書士に相談することで、スムーズに進めることができます。
「自分の経験は認められる?」「大臣認定の申請はどうすれば?」など、疑問や不安があれば、お気軽にご相談ください。
5お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ<許認可申請>

.jpg)