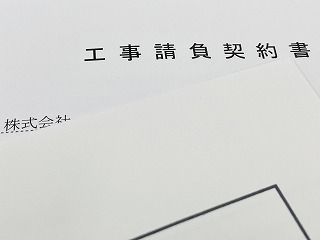
「この工事、建設業許可は必要なの?」「『請負契約』じゃないけど、大丈夫?」「『付帯工事』って、どこまで許可なしでできるの?」
こんな疑問や不安はありませんか?
建設業許可を申請するにあたって、自社が行う、あるいはこれから行う「建設工事」の概要を具体的に知っておくことは、非常に重要です。
建設業法では、「建設工事」の定義や、「請負契約」の考え方、さらには許可が不要な「軽微な工事」や「付帯工事」について、細かく規定されています。
ご安心ください!今回の記事では、これらの疑問を解消し、建設業許可の要否を正しく判断できるよう、分かりやすく解説します。
岩手県、宮城県(仙台市含む)で建設業を営む皆様、ぜひ最後までお読みください。今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。(全角318文字)
1建設業における建設工事とは?
建設業許可を取得する前に、まず理解しておくべきことは、「建設業法における建設工事とは何か」ということです。
ここでは、建設工事の定義、具体例、そして建設工事に該当しないケースについて、詳しく解説します。
1-1. 建設工事の定義:建設業法第2条
建設業法第2条では、「建設工事」を次のように定義しています。
土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
ただ、この条文だけでは、具体的にどのような工事が建設工事に該当するのか、分かりにくいかもしれません。
ちなみに、「別表第一の上欄に掲げるもの」とは、土木一式工事から解体工事まで、29種類の建設工事のことです。
これらの工事が、建設業法上の「建設工事」に該当し、一定規模以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。
1-2. 具体例:建設工事に該当するもの
具体的にどのような工事が建設工事に該当するのか、イメージしやすいように例を挙げます。
・建物の新築工事: 一戸建て住宅、マンション、店舗、事務所、工場などの新築工事は、「建築一式工事」または「大工工事」に該当します。
・建物の増改築工事: 既存の建物の増築、改築、リフォームなども、建設工事に該当します。工事の内容によって、「建築一式工事」「大工工事」「内装仕上工事」「屋根工事」「塗装工事」など、様々な業種に該当する可能性があります。
・外構工事: 塀、門扉、駐車場、庭などの工事は、「とび・土工・コンクリート工事」「造園工事」「舗装工事」などに該当します。
・設備の設置工事: 電気設備、空調設備、給排水設備、ガス設備などの設置工事は、「電気工事」「管工事」「機械器具設置工事」などに該当します。
・土木工事: 道路やトンネルの工事は、「土木一式工事」あるいは「舗装工事」に該当します。
これらの工事は、建設業法上の「建設工事」に該当するため、請負金額が一定額を超える場合は、建設業許可が必要となります。
1-3. 建設工事に該当するか否か
ある工事が建設工事に該当するかどうかは、建設業法の適用があるかどうか、という点で非常に重要です。
建設業法の適用があるということは、
・一定規模以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要
・建設業法に基づく様々な義務(主任技術者等の配置、契約書の作成、標識の掲示など)を負う、ということを意味します。
もし、建設工事に該当する工事を、建設業許可なしに行ったり、建設業法上の義務を怠ったりすると、罰則(懲役や罰金)や行政処分(営業停止など)を受ける可能性があります。
1-4. 建設工事の判断基準
具体的にどのような工事が建設工事に該当するのか、判断に迷うケースもあるでしょう。
そのような場合は、建築基準法など、他の法令を参考にすると、判断の目安になります。
建築基準法では、「建築物」を「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義しています(建築基準法第2条第1号)。
また、「建築設備」を「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針」と定義しています(建築基準法第2条第3号)。
これらの定義を参考にすると、建設業法上の「建設工事」は、
〇建築物、建築設備、その他土地に定着する工作物について、
①新しく作る(取り付ける)
②作り直す
③取り除く
④解体する
工事である、と考えることができます。
ただし、これはあくまでも目安であり、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
個別の工事が建設工事に該当するかどうかは、工事の内容、規模、目的などを総合的に考慮して判断する必要があります。
2建設工事に該当しないものの例
建設業法上の「建設工事」に該当しない工事も、数多く存在します。
ここでは、茨城県の「建設業許可の手引き」に掲載されている例を参考に、具体的にどのような工事が建設工事に該当しないのかを解説します。
2-1. 茨城県の「建設業許可の手引き」
茨城県の「建設業許可の手引き」では、建設工事に該当しないものの例として、以下のものが挙げられています。
・保守点検、維持管理: 建物や設備の定期的な点検、メンテナンス、修理など。
・除草、草刈り、伐採: 庭や空き地の除草、草刈り、樹木の伐採など。
・除雪、融雪剤散布: 道路や駐車場の除雪、融雪剤の散布など。
・測量、地質調査: 土地の測量、地質調査、ボーリング調査など。
・造林、採石: 植林、間伐、採石など。
・調査目的のボーリング: 地質調査や地下水調査のためのボーリング。
・造船: 船舶の製造、修理。
・機械器具製造・修理: 各種機械器具の製造、修理。
・建売住宅の販売: 建売住宅の販売(建設工事自体は、別途建設業許可が必要)。
・浄化槽清掃: 浄化槽の清掃、汚泥の引き抜き。
・ボイラー洗浄: ボイラーの洗浄、メンテナンス。
・側溝清掃: 道路側溝の清掃。
・コンサルタント、設計: 建設コンサルタント業務、建築設計業務。
・資材の販売、物品販売: 建設資材の販売、建設機械の販売、建築設備の販売。
・清掃: 建物や施設の清掃。
・自社建物の建設: 自社で使用する建物を、自社の社員が建設する(請負契約ではなく、雇用契約に基づく)。
これらの工事は、建設業法上の「建設工事」には該当しないため、建設業許可は不要です。
2-2. 造船が建設工事に該当しない理由
茨城県の「建設業許可の手引き」には、「造船」が建設工事に該当しない例として挙げられています。
これは、船が「土地に定着する工作物」ではないためです。
建設業法上の「建設工事」は、土地に定着する工作物を対象としています。
船は、海や川に浮かんで移動するものであり、土地に固定されていないため、「土地に定着する工作物」とはみなされません。
そのため、船の建造や修理、内装工事などは、建設業法の適用を受けず、建設業許可も不要となります。
ただし、造船所内のドックやクレーンなどの建設工事は、建設業許可が必要となる場合があります。
2-3. 建設工事に該当しない工事の判断
建設工事に該当しない工事の例をいくつか挙げましたが、これらはあくまでも例示であり、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
個別の工事が建設工事に該当するかどうかは、工事の内容、規模、目的、契約形態などを総合的に考慮して判断する必要があります。
判断に迷う場合は、必ず、都道府県(岩手県、宮城県など)や市区町村の建設業許可担当部署に相談し、確認するようにしてください。
3請負契約と建設業許可の関係
建設業許可は、「建設工事の請負」を行う事業者に必要な許可です。
ここでは、「請負契約」とは何か、建設業許可との関係、そして「委託契約」との違いについて、詳しく解説します。
3-1. 請負契約の定義
民法第632条では、「請負」を次のように定義しています。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
この定義から分かるように、請負契約には、以下の3つの要素があります。
・仕事の完成: 請負人は、契約で定められた仕事を完成させる義務を負います。
・報酬の支払い: 注文者は、仕事の完成に対して、請負人に報酬を支払う義務を負います。
当事者間の合意: 請負人と注文者の間で、仕事の内容、報酬、納期などについて合意が成立していること。
3-2. 建設工事の請負契約
建設業における「請負契約」とは、上記の民法の定義に基づき、当事者の一方(請負人=建設業者)が建設工事を完成することを約束し、もう一方(注文者)が建設工事の完成に対して、その報酬を支払うことを約束する契約、ということになります。
そして、建設業法では、一定規模以上の建設工事の請負契約を締結する場合は、建設業許可が必要であると定めています。
具体的には、
・建築一式工事:
請負金額が1500万円以上(税込)の工事、または、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
・建築一式工事以外の工事:
請負金額が500万円以上(税込)の工事
これらの金額以上の工事を請け負う場合は、工事の種類に応じた建設業許可が必要となります。
3-3. 請負契約の特徴
請負契約は、仕事の完成に対して報酬が支払われる契約です。
つまり、請負人は、単に作業を行うだけでなく、契約で定められた成果物(完成した建物や設備など)を引き渡す義務を負います。
もし、工事が完成しなかったり、完成した建物に欠陥があったりした場合は、請負人は、契約不履行の責任を問われることになります。
具体的には、
・契約解除:
注文者から契約を解除される可能性があります。
・損害賠償請求:
工事の遅延や欠陥によって生じた損害について、賠償を請求される可能性があります。
・瑕疵担保責任:
完成した建物に隠れた欠陥があった場合、一定期間、無償で修補する義務を負います(建設業法第34条の2)。
これらの責任は、請負契約の特徴であり、後述する「委任契約」との大きな違いです。
4委託契約とは?
「委託契約」という言葉も、ビジネスの現場でよく使われますが、法律上、明確な定義はありません。
一般的には、「請負契約」または「委任契約(準委任契約)」のいずれかの性質を持つ契約を指して、「委託契約」と呼ぶことが多いです。
4-1. 委任契約(準委任契約)の定義
民法では、「委任」を次のように定義しています。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。(民法第643条)
また、法律行為でない事務の委託は、「準委任」と呼ばれます(民法第656条)。
4-2. 請負契約と委任契約(準委任契約)の違い
請負契約と委任契約(準委任契約)の主な違いは、以下のとおりです。
(1)請負契約
・目的:仕事の完成
・報酬:仕事の完成に対して支払われる
・責任:
請負人は、仕事の完成義務を負う。完成した仕事に欠陥があった場合は、瑕疵担保責任を負う。
・具体例:建設工事、ソフトウェア開発、物品の製造など
・建設業許可:請負契約に基づいて建設工事を行う場合は、原則として建設業許可が必要。
(2)委任契約(準委任契約)
・目的:事務処理
・報酬:事務処理に対して支払われる(成果の有無は問わない)
・責任:
受任者は、善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)をもって、委任事務を処理する義務を負う。ただし、仕事の完成義務や瑕疵担保責任は負わない。
・具体例:弁護士への訴訟委任、税理士への税務申告代行、コンサルタントへの経営相談など
・建設業許可:委任契約(準委任契約)に基づいて業務を行う場合は、建設業許可は不要。
4-3. 建設業における委託契約
建設業において、「業務委託契約」という名称の契約書が使われることがありますが、その内容が建設工事の完成を目的とするものであれば、実質的には「請負契約」とみなされ、建設業許可が必要となる場合があります。
例えば、
「リフォーム工事業務委託契約」という名称でも、工事の内容が壁紙の張り替えや設備の交換など、建設工事に該当する場合は、請負契約とみなされ、建設業許可が必要となる可能性があります。
「コンサルタント契約」や「設計委託契約」という名称でも、その業務内容に建設工事が含まれる場合は、請負契約とみなされ、建設業許可が必要となる可能性があります。
契約書のタイトルだけでなく、契約の内容をよく確認し、建設業許可が必要かどうかを判断する必要があります。
5契約書のタイトルだけで判断しないこと!
建設業許可が必要かどうかは、契約書のタイトルだけで判断するのではなく、契約の「実質」で判断する必要があります。
これは、建設業法第24条(請負契約とみなす場合)に規定されています。
建設工事の完成を目的とする契約は、その名目のいかんを問わず、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
つまり、契約書のタイトルが「業務委託契約」や「売買契約」などであっても、その内容が実質的に建設工事の完成を目的とするものであれば、建設業法上の「請負契約」とみなされ、建設業許可が必要となる場合がある、ということです。
5-1. 悪質なケース:許可逃れ
建設業許可を取得していない業者が、建設業許可が必要な工事を請け負うために、意図的に契約書のタイトルを「業務委託契約」などと偽装するケースがあります。
これは、建設業法違反であり、罰則や行政処分の対象となります。
5-2. 機械の売買契約と設置工事
機械の販売業者が、機械の販売と併せて、その機械の設置工事を行う場合があります。
この場合、契約書のタイトルが「売買契約」となっていることがありますが、設置工事の内容によっては、建設業許可が必要となる場合があります。
例えば、
大型の機械で、設置に際して、基礎工事やアンカー固定、配管工事、電気配線工事などが必要となる場合は、建設業許可が必要となる可能性が高いです。
家庭用のエアコンなど、簡易な設置工事で済む場合は、建設業許可は不要です。
5-3. 実質判断のポイント
契約の実質を判断する際には、以下の点を総合的に考慮します。
・工事の内容: 建設工事に該当する作業が含まれているか。
・契約金額: 工事の規模や難易度に見合った金額か。
・当事者の意図: 建設工事を請け負う意思があったか。
・報酬の支払われ方: 仕事の完成に対して支払われるのか、作業時間に対して支払われるのか。
6建設業許可が無くてもできる工事とは?
建設業法では、建設業許可がなくても請け負うことができる工事が、2種類規定されています。
①軽微な建設工事
②付帯工事
ここでは、これらの工事について、詳しく解説します。
6-1. 軽微な建設工事:金額基準
建設業許可がなくても請け負うことができる「軽微な建設工事」は、工事1件の請負代金の額が、以下の金額未満の工事です(建設業法第3条、建設業法施行令第1条の2)。
・建築一式工事:
1500万円未満(税込)の工事、または、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
・建築一式工事以外の工事:
500万円未満(税込)の工事
この金額は、消費税込みの金額であり、材料費や運搬費なども含めた総額です。
6-2. 軽微な工事の注意点
・金額の分割:
一つの工事を、意図的に複数の契約に分割し、それぞれの請負金額を軽微な工事の範囲内に収めることは、建設業法違反となります。
・原価ではなく請負金額:
請負金額が基準となるため、工事の原価が500万円以上であっても、請負金額が500万円未満であれば、軽微な工事として扱われます。
・注文者の分割発注:
注文者が、一つの工事を複数の業者に分割して発注する場合は、それぞれの業者は、自己の請負金額が軽微な工事の範囲内であれば、建設業許可は不要です。
6-3. 付帯工事:主たる工事に付随する工事
建設業許可を受けている建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事(主たる工事)に「付帯する」他の建設業に係る工事(附帯工事)を、請け負うことができます(建設業法第4条)。
6-4. 付帯工事の要件
「付帯工事」として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
・主たる工事との関係:
主たる建設工事を施工するために、必要不可欠な工事であること。
主たる建設工事の施工により、必要が生じた工事であること。
・工事の独立性:
それ自体が独立の使用目的に供されるものではないこと。つまり、付帯工事単独では意味をなさず、主たる工事と一体となって初めて意味を持つ工事であること。
・金額:
原則として、付帯工事の請負金額が、主たる工事の請負金額を上回らないこと。
6-5. 付帯工事の具体例
付帯工事の具体例としては、以下のようなものがあります。
・電気配線の修繕工事に伴う壁の補修工事:
-主たる工事:電気工事(電気配線の修繕)
-付帯工事:内装仕上工事(壁の補修)
・建物の外壁塗装工事に伴う足場の設置工事:
-主たる工事:塗装工事
-付帯工事:とび・土工・コンクリート工事(足場の設置)
・ビルのエレベーター設置工事に伴う電気配線工事:
-主たる工事:機械器具設置工事(エレベーター設置)
-付帯工事:電気工事(電気配線)
・駐車場の舗装工事に伴う造成工事:
-主たる工事:舗装工事
-付帯工事:とび・土工・コンクリート工事(造成工事)
これらの例からも分かるように、付帯工事は、主たる工事を施工するために必要不可欠な工事、または、主たる工事の施工によって必要となる工事であり、それ自体が独立した目的を持つものではありません。
6-6. 付帯工事の判断方法
国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」では、付帯工事の判断について、以下のように示されています。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等にあたり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に判断する。
つまり、付帯工事かどうかは、工事の必要性、工事の関連性、請負契約の慣行などを総合的に考慮して判断される、ということです。
6-7. 付帯工事の注意点
・専門技術者の配置:
付帯工事であっても、建設業法上の主任技術者または監理技術者の配置義務は免除されません。
・下請への一括委託:
付帯工事を下請業者に一括して委託することは、原則として禁止されています。
・判断に迷う場合:
付帯工事に該当するかどうかの判断が難しい場合は、許可行政庁や建設業許可を専門とする行政書士に相談することをおすすめします。
7まとめ
建設業許可の取得・更新は、事業の発展に欠かせない重要な手続きです。
しかし、法改正や制度の複雑さから、「難しそう…」「面倒…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、今回解説した「建設工事」の定義、請負契約と委託契約の違い、軽微な工事と付帯工事の範囲などは、判断が難しいケースも少なくありません。
行政書士藤井等事務所は、建設業許可の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」「どの業種に該当するか分からない」という相談だけでも構いません。
建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
8お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ<許認可申請>



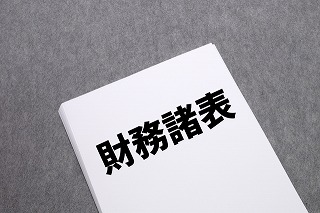
.jpg)

