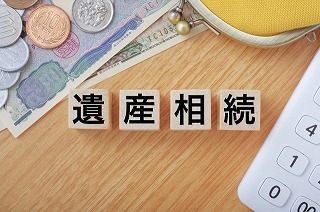「家族が亡くなったけど、何から手をつければいいの?」
「相続手続きって、具体的に何をすればいい?」
「期限はあるの?」
「専門家に頼んだ方がいいの?」
こんな悩みはありませんか?
相続手続きは、多くの方にとって初めての経験であり、戸籍全部事項証明書の収集、遺産分割協議、相続税の申告など、様々な手続きが必要となります。
また、相続は、亡くなった本人(被相続人)の財産や権利・義務を受け継ぐことであり、その手続きは、法律で細かく定められています。
これらの手続きを、ご自身で全て行うのは、時間も手間もかかり、大変な作業です。
ご安心ください!
今回の記事では、相続の基本的な流れ、必要書類、期限、注意点などを、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、相続手続きの全体像が理解でき、スムーズに手続きを進めるための第一歩を踏み出せます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)にお住まいの皆様、ぜひ最後までお読みください。今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1相続の開始:いつから、何が始まる?
相続は、人の死亡によって開始します(民法882条)。
亡くなった方(被相続人)が所有していた財産(土地、建物、預貯金、株式など)や、権利・義務(借金など)は、原則として、相続人に引き継がれます。
1-1. 死亡の確認
相続の開始は、通常、医師による死亡診断書によって確認されます。
死亡診断書は、死亡届を提出する際に必要となる重要な書類です。
1-2. 死亡の確認(例外)
死亡の事実が確実に証明されない場合でも、例外的に「死亡したものとみなす」制度があります。
それが、「失踪宣告」と「認定死亡」です。
(1)失踪宣告:生死不明の場合
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です(民法30条)。
失踪宣告には、以下の2種類があります。
①普通失踪:
不在者の生死が7年間不明なとき(民法30条1項)
②特別失踪(危難失踪):
戦争、船舶の沈没、震災などの特別な危難に遭遇し、その危難が去った後1年間生死が不明なとき(民法30条2項)
失踪宣告は、家庭裁判所に申し立てを行い、審判を受ける必要があります。
申し立てができるのは、利害関係人(不在者の配偶者、相続人など)です。
失踪宣告が確定すると、普通失踪の場合は7年間が経過した時に、特別失踪の場合は危難が去った時に、死亡したものとみなされ、相続が開始します。
(2)認定死亡:死亡が確実だが死体が見つからない場合
認定死亡とは、水難や火災などの事故により、死亡したことが確実であるにもかかわらず、死体が発見されない場合に、その調査にあたった官公署が死亡を認定し、戸籍に死亡の記載をする制度です(戸籍法89条)。
認定死亡の場合、戸籍に記載された死亡年月日に死亡したものと推定され、相続が開始します。
1-3. 相続開始後のタイムスケジュール
相続が開始したら、様々な手続きを行う必要があります。主な手続きと期限は、以下のとおりです。
(1)相続開始(被相続人の死亡):
相続が開始します。
(2)遺言書の確認:
遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産分割を行います。
(3)相続人の調査・確定:
戸籍全部事項証明書などを収集し、相続人を特定します。
(4)相続財産の調査:
亡くなった本人(被相続人)のプラスの財産(預貯金、不動産、株式など)とマイナスの財産(借金など)を把握します。
(5)相続方法の決定: 相続放棄、限定承認、単純承認のいずれかを選択します。
・単純承認: プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続する方法。
・相続放棄: プラスの財産もマイナスの財産も、一切相続しない方法。
・限定承認: プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する方法。
★注意: 相続放棄と限定承認は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
(6)所得税等の準確定申告:
亡くなった本人(被相続人)の1月1日から死亡日までの所得金額を計算し、税務署に申告・納付します。
★注意:相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内。
(7)遺産分割協議:
相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決めます。合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
(8)相続税の申告・納付:
相続税が発生する場合は、税務署に申告し、納税します。
★注意:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内。
(9)財産の名義変更:
相続した不動産、預貯金、株式などの名義変更手続きを行います。
1-4. 相続開始を知った日
上記のタイムスケジュールで示した期限は、多くの場合、「相続開始を知った日」が起算点となります。
「相続開始を知った日」とは、通常は、亡くなった本人(被相続人)の死亡の事実を知った日です。
ただし、相続放棄や限定承認の場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」が起算点となります。
これは、例えば、先順位の相続人が相続放棄をしたことにより、自分が相続人になったことを知った日、など、具体的事情によって異なります。
2遺言書の確認(最優先事項)
相続が開始したら、まず最初に行うべきことは、遺言書の有無の確認です。
遺言書がある場合は、原則として、遺言書の内容に従って遺産分割を行うことになります。
2-1. 遺言書の種類
遺言書には、主に以下の3つの種類があります。
①自筆証書遺言:
遺言者が、全文、日付、氏名を自筆で書き、押印した遺言書。
②公正証書遺言:
公証人が作成する遺言書。証人2人以上の立会いが必要。
③秘密証書遺言:
遺言者が遺言書を作成し、封印した後、公証人と証人2人以上の前で、自分の遺言書である旨などを申述し、公証人がその旨を封紙に記載する遺言書。
2-2. 自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、形式不備で無効になるリスクがあります。
また、紛失や改ざんのリスクもあります。
自筆証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります(民法1004条)。
2-3. 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクがありません。
また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
費用はかかりますが、最も確実な遺言方法と言えます。
3相続人の調査・確定(誰が相続人?)
遺言書がない場合、または、遺言書で遺産の分け方が指定されていない場合は、民法で定められた相続人(法定相続人)が遺産を相続します。
誰が相続人になるのかを確定させるためには、亡くなった本人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書などを収集し、調査する必要があります。
3-1. 法定相続人
民法では、以下の順位で法定相続人が定められています。
・第1順位: 子(子が死亡している場合は孫)
・第2順位: 直系尊属(父母、祖父母など)
・第3順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪)
なお、配偶者は、常に相続人となります。
3-2. 法定相続分
法定相続分とは、各相続人が相続する財産の割合のことです。
法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
・配偶者と子: 配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合は均等に分ける)
・配偶者と直系尊属: 配偶者2/3、直系尊属1/3
・配偶者と兄弟姉妹: 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
3-3. 戸籍全部事項証明書等の収集
相続人を確定させるためには、亡くなった本人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを収集する必要があります。
これらの書類は、本籍地の市区町村役場で取得できます。
3-4. 相続関係説明図の作成
収集した戸籍全部事項証明書などをもとに、相続関係説明図を作成すると、相続関係が一目で分かりやすくなります。
4相続財産の調査:プラスの財産とマイナスの財産
相続財産には、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も含まれます。
相続財産を正確に把握することは、相続方法(単純承認、相続放棄、限定承認)を決定する上で、非常に重要です。
4-1. プラスの財産(資産)
・不動産: 土地、建物(自宅、別荘、アパート、マンション、店舗、事務所、工場など)・預貯金: 普通預金、定期預金など
・現金
・有価証券: 株式、投資信託、国債、社債など
・自動車
・貴金属、宝石、美術品
・ゴルフ会員権
・著作権、特許権
・その他:生命保険金(受取人が指定されている場合は、原則として相続財産に含まれない)、未収金(家賃、地代など)
4-2. マイナスの財産(負債)
・借金: 住宅ローン、自動車ローン、カードローン、消費者金融からの借入など
・未払金: クレジットカードの未払い、家賃、光熱費、医療費、税金など
・保証債務: 他の人の借金の保証人になっている場合
・その他: 連帯債務、損害賠償債務など
4-3. 財産調査の方法
・預貯金: 金融機関に残高証明書の発行を依頼する、通帳を記帳する
・不動産: 固定資産税の課税明細書を確認する、法務局で登記事項証明書を取得する
・株式: 証券会社に照会する、株券を確認する
・借金: 信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)に情報開示を請求する、亡くなった本人(被相続人)の郵便物や契約書などを確認する
5相続方法の選択:単純承認・相続放棄・限定承認
相続財産の調査結果をもとに、相続人は、以下の3つの相続方法の中から、いずれかを選択する必要があります。
5-1. 単純承認
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて無条件で相続する方法です。
単純承認をする場合は、特別な手続きは必要ありません。
相続開始を知った時から「3ヶ月以内」に、相続放棄または限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認したことになります。
5-2. 相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、一切相続しない方法です。
相続放棄をする場合は、相続開始を知った時から「3ヶ月以内」に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
5-3. 限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する方法です。
相続財産の中に、借金などのマイナスの財産がどのくらいあるか不明な場合や、どうしても手放したくない財産(自宅など)がある場合に有効な方法です。
限定承認をする場合は、相続開始を知った時から「3ヶ月以内」に、相続人全員で家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出する必要があります。
5-4. 3ヶ月の熟慮期間
相続放棄と限定承認は、相続開始を知った時から「3ヶ月以内」に手続きを行う必要があります。
この3ヶ月の期間は、「熟慮期間」と呼ばれます。
熟慮期間内に、相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされます。
なお、熟慮期間は、家庭裁判所に申し立てることにより、延長することができます。
6まとめ
相続は、一生のうちに何度も経験することではありません。
そのため、何から手を付けていいか分からず、不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
また、相続は、法律や税金が複雑に絡み合うため、専門的な知識が必要となる場面も多くあります。
相続について、何から手を付けていいか分からないのが現状です。
よって、専門家である行政書士に、トータルで任せることで安心が得られます。
相続は、各種の法的な手続き、それと銀行との連絡調整など、複雑な手続きが必要です。
そこで、専門家である行政書士に依頼することで、スムーズに相続手続を進めることができます。
相続は、決して、身内を「ないがしろ」にするものではありません。
むしろ、次の世代に向けて、亡くなった方の意思・思いを引き継ぎ、未来に向けて、前向きな人生を充実させるために必要なバトンタッチです。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案します。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという、他にはない「強み」を持っているところです。
この記事を読んで、少しでも相続について考えるきっかけになれば幸いです。
7お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ