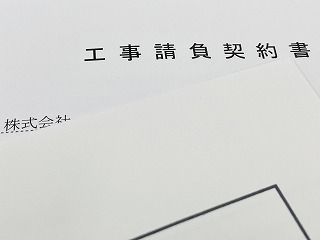「建設業許可の更新が近いけど、必要な財務諸表って税務署に出す決算書とは違うの?」
「経営事項審査(経審)の点数を上げるには、どんな財務諸表を作ればいいんだろう…」
「手続きが複雑そうで、自社だけで正しく作成できるか不安…」こんな悩みはありませんか?
その悩み、この記事を読めばスッキリ解決できます。
建設業許可や経審に特有の財務諸表は、税務署提出用の決算書とは異なる点が多く、正確な作成が許可取得や評点確保の鍵となります。
今回の提案は、建設業財務諸表の基本的な違いから、作成における重要なポイントまで、あなたのお困りごとを解決する具体的な内容として詳しく紹介します。
1.建設業財務諸表と税務申告用決算書の根本的な違い
建設業を営む法人等が、事業年度終了後に作成・提出する書類には、大きく分けて税務署へ提出するものと、建設業法に基づき許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)へ提出するものがあります。
これらは似て非なるものであり、その違いを理解することが、建設業許可の取得・維持、そして公共工事受注に不可欠な経営事項審査(経審)において極めて重要です。
まず、最も根本的な違いは、それぞれの書類が作成される「目的」と準拠する「法律」です。
1-1. 目的と根拠法の違い
⑴税務署提出用決算書(計算書類)
・目的: 法人税や消費税などの正確な税額計算と申告。
・根拠法: 法人税法、会社法、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(会計基準)。
・主な構成書類(一般的な中小企業の場合):
①貸借対照表
②損益計算書
③株主資本等変動計算書
④個別注記表
(勘定科目内訳明細書、事業概況説明書なども添付)
⑵建設業許可・経審用 建設業財務諸表
・目的: 建設業法に基づく許可要件(特に財産的基礎)の確認、経営状況の分析、経営事項審査(経審)における評点算出。
・根拠法: 建設業法、建設業法施行規則、関連告示(特に「建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」)。
・主な構成書類(法人の場合):
①貸借対照表(様式第十五号)
②損益計算書(様式第十六号) ※完成工事原価報告書を含む
③(兼業がある場合)兼業事業売上原価報告書(様式第二十五号の十二)
④株主資本等変動計算書(様式第十七号)
⑤注記表(様式第十七号の二)
⑥(大会社等特定の条件に該当する場合)附属明細書(様式第十七号の三)
⑦(株式会社の場合、決算変更届時に必要)事業報告書(任意様式だが記載事項は法定)
このように、税務申告用決算書が「納税額の確定」を主眼とするのに対し、建設業財務諸表は「建設業者としての適格性・経営状態の評価」を目的としています。
そのため、準拠する法律や規則が異なり、結果として用いる勘定科目や様式、作成ルールに違いが生じるのです。
建設業財務諸表を作成する上で最も注意すべき点の一つが、勘定科目の分類です。
建設業法及び関連告示では、建設業特有の会計処理を反映させるため、独自の勘定科目の分類が定められています。
1-2. 勘定科目の分類と表示方法の違い
⑴具体例(貸借対照表):
①流動資産:
税務申告用では「売掛金」として一括りにされるものでも、建設業財務諸表では「完成工事未収入金」「未成工事支出金」などに細分化されます。
「未成工事支出金」は、いわゆる製造業での「仕掛品」に相当しますが、建設業会計特有の科目です。
また、「未成工事受入金」(前受金に相当)は流動負債に計上されます。
②固定資産:
大きな違いはありませんが、建設仮勘定の扱いや表示に注意が必要です。
⑶流動負債:
税務申告用では「買掛金」とされるものでも、「工事未払金」として区別されます。
前述の「未成工事受入金」もここに計上されます。
⑵具体例(損益計算書):
①売上高:
「完成工事高」と「兼業事業売上高」に明確に区分されます。
②売上原価:
「完成工事原価」と「兼業事業売上原価」に区分されます。
特に「完成工事原価」は、材料費、労務費、外注費、経費の4つに分類して詳細を記載する「完成工事原価報告書」の作成が求められます。
これは税務申告用の損益計算書にはない、建設業財務諸表の大きな特徴です。
製造原価報告書に近い考え方ですが、建設業の実態に合わせて科目が設定されています。
③販売費及び一般管理費:
税務申告用と大きな違いはありませんが、勘定科目の集計ルールが若干異なる場合があります。
これらの勘定科目の違いを無視して、税務申告用の決算書をそのまま流用してしまうと、許可行政庁から訂正を求められたり、最悪の場合、経審の評点が不当に低くなる可能性があります。
1-3. 様式と表示ルール
建設業財務諸表は、建設業法施行規則で定められた様式(様式第十五号~)に従って作成する必要があります。
⑴表示形式:
税務申告用の貸借対照表は、左右に資産と負債・純資産を配置する「勘定式」も認められますが、建設業財務諸表の貸借対照表(様式第十五号)は、上から下に科目を列挙していく「報告式」で作成されます。
損益計算書(様式第十六号)も同様に報告式です。
⑵金額単位:
金額は「千円単位」で表示し、千円未満は切り捨てて記載するのがルールです。
税務申告用決算書が「円単位」である点と異なります。
⑶注記表(様式第十七号の二):
税務申告用の「個別注記表」とは別に、建設業法で定められた事項(会計方針の変更、重要な後発事象、完成工事高に関する注記など)を記載する「注記表」の作成が必要です。
内容は一部重なりますが、要求される情報が異なります。
⑷附属明細書(様式第十七号の三):
資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社(大会社)は、より詳細な情報を記載する附属明細書の提出が義務付けられています。
これらの様式やルールを遵守しない場合、書類不備として受け付けてもらえない可能性もあります。
2.建設業財務諸表作成における3つの重要ポイント
では、具体的に建設業財務諸表を作成する上で、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
特に重要となる3つのポイントを解説します。
2-1. ポイント1:建設業会計基準の理解と適用
建設業財務諸表は、建設業法や関連告示だけでなく、「建設業会計」と呼ばれる独自の会計ルールに基づいて作成される必要があります。
これは、一般的な企業会計基準に建設業特有の取引実態(工事期間の長期化、工事進行基準の適用、未成工事の評価など)を反映させたものです。
工事進行基準と工事完成基準: 長期にわたる工事の場合、収益認識基準として「工事進行基準」または「工事完成基準」のどちらを適用するかが重要になります。
税法上の基準と必ずしも一致しない場合があり、建設業会計のルールに従って適切に選択・適用し、財務諸表に反映させる必要があります。
どちらの基準を採用するかは、会社の経営実態や管理体制によって判断しますが、経審の評価にも影響を与える可能性があります。
⑴原価計算:
完成工事原価報告書の作成からも分かるように、建設業会計では正確な原価計算が求められます。
材料費、労務費、外注費、経費を適切に集計し、進行中の工事(未成工事支出金)と完成した工事(完成工事原価)に正しく配分する必要があります。
どんぶり勘定ではなく、工事ごとの原価管理体制が整っていることが望ましいです。
⑵引当金の計上:
工事損失引当金、完成工事補償引当金など、建設業特有のリスクに備えるための引当金の計上も重要です。
税法上の損金算入要件とは別に、企業会計として、また建設業会計として、リスクを適切に見積もり、財務諸表に反映させることが求められます。
これらの建設業会計のルールを正しく理解し、日々の経理処理から適切に適用していくことが、正確な建設業財務諸表を作成するための第一歩です。
税理士が作成した税務申告用決算書を基にする場合でも、これらの建設業会計の視点から内容を精査し、必要に応じて組み替える作業が不可欠です。
2-2. ポイント2:経審(経営事項審査)を意識した勘定科目の整理
建設業財務諸表は、経営事項審査(経審)の評点算出の基礎資料となります。
経審では、財務諸表の各数値を用いて、収益性、流動性、安定性、生産性など多角的な経営分析が行われ、評点が決定されます。
この評点は、公共工事の入札参加資格ランクに直結するため、建設業者にとっては生命線とも言えます。
⑴評点に影響する主な指標:
経審の評価項目(X1~Z評点、W評点など)は多岐にわたりますが、財務諸表から算出される主な指標には以下のようなものがあります。
①X1(自己資本額および平均利益額):
自己資本額(純資産)、利払前税引前償却前利益(EBITDAに近い概念)
②X2(経営状況):
純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金など
⑵勘定科目の適切な振り分け:
これらの指標を有利に算出するためには、日々の取引を適切な勘定科目に振り分けることが重要です。
例えば、「雑収入」の中に本来は「営業外収益」や「特別利益」に分類すべきものが混在していると、正確な利益額が算出されず、評点に悪影響を与える可能性があります。
同様に、資産や負債の分類(流動・固定の区分、工事関連か否か)も、流動性や安定性の指標に影響します。
⑶不要な資産の整理:
使用していない固定資産や回収不能な売掛金などが貸借対照表に残っていると、自己資本比率などの指標を悪化させる要因になります。
決算前に資産内容を精査し、適切な評価や除却・償却を行うことも、経審対策として有効です。
単に税務申告用の決算書を建設業様式に変換するだけでなく、「どの勘定科目がどの経審指標に影響するか」を意識して、より正確かつ有利になるように財務諸表を作成・整理していく視点が求められます。
2-3. ポイント3:専門家(行政書士)との連携
これまで述べてきたように、建設業財務諸表の作成は、税務申告用決算書とは異なる専門的な知識と注意が必要です。
建設業法、関連告示、建設業会計、そして経審の評価体系までを理解した上で、正確な書類を作成するには、相応の時間と労力がかかります。
複雑な制度と頻繁な改正: 建設業法や経審の制度は、社会経済情勢の変化等に応じて改正されることがあります。最新の情報を常に把握し、適切に対応していくことは容易ではありません。
時間的コストと正確性の確保: 経営者や経理担当者の方が、本来の業務時間を割いてこれらの複雑な書類作成に取り組むのは、大きな負担となります。
また、専門知識がないまま作成すると、意図しない誤りが発生し、許可申請の遅延や不許可、経審での低評価につながるリスクがあります。
○行政書士の役割:
建設業許可申請や経審を専門とする行政書士は、これらの手続きと関連法規、そして建設業財務諸表の作成ルールに精通しています。
税理士が作成した決算書を基に、建設業法・経審の観点から内容をチェックし、適切な様式に変換・作成することができます。
また、経審の評点シミュレーションを行い、評点アップのための具体的なアドバイスを提供することも可能です。
日々の記帳や税務申告は顧問税理士に依頼し、建設業許可申請・決算変更届・経審申請に関わる財務諸表の作成や手続きは行政書士に依頼するという役割分担は、非常に効率的かつ効果的です。
専門家と連携することで、経営者や従業員の方は本来の事業活動に集中でき、かつ正確で有利な申請を実現することができます。
3.「見える化」による経営戦略への活用提案
当事務所では、単に建設業財務諸表を作成するだけでなく、その数値を経営に活かすためのサポートも重視しています。
3-1. 財務諸表の「図式化」による現状把握
報告式で表示される建設業財務諸表は、数字の羅列に見えがちで、直感的に会社の財政状態や経営成績を把握するのが難しい場合があります。
そこで当事務所では、貸借対照表や損益計算書の重要な項目を抜き出し、分かりやすく「図式化」(ビジュアル化)してお示しします。
例えば、貸借対照表であれば、資産・負債・純資産のバランスを面積図で示すことで、自己資本比率や負債の状況が一目で分かります。
損益計算書であれば、売上高から各費用がどのように引かれて利益が残るのかを棒グラフなどで示すことで、収益構造やコストの問題点を把握しやすくなります。
3-2. 財務会計から管理会計への視点
税務申告を目的とした「財務会計」は、過去の経営成績をルールに従って記録・報告することに主眼が置かれます。
一方、経営者の意思決定に役立てるための「管理会計」は、未来の経営戦略を見据え、自社の強み・弱みを分析し、目標達成のための具体的なアクションにつなげるための情報を提供します。
当事務所が提供する「図式化」された財務分析は、まさにこの管理会計の視点を取り入れたものです。
過去の数字を分かりやすく整理するだけでなく、同業他社比較(経審データなどを活用)や時系列での推移分析を通じて、「なぜこの数字になったのか」「今後どう改善していくべきか」といった、未来に向けた戦略的な議論のきっかけをご提供します。
これにより、建設業財務諸表が単なる「提出義務のある書類」から、「自社の経営を見つめ直し、未来を切り拓くための羅針盤」へと変わるお手伝いをいたします。
4.まとめ
建設業許可申請や経営事項審査(経審)は、特に公共工事の受注を目指す建設業者様にとって、避けては通れない重要な手続きです。
その中核となる建設業財務諸表の作成は、本記事で解説した通り、税務申告用の決算書とは異なる専門知識が求められ、その精度が許可の取得や経審の評点を大きく左右します。
制度の煩雑さ・複雑さから、「難しそう…」「面倒…」「どこから手をつければいいか分からない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
行政書士藤井等事務所は、建設業許可・経営事項審査(経審)の専門家として、お客様一社一社の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続き、そして建設業特有の会計ルールは複雑で、なかなか分かりにくいものです。
ご自身で膨大な時間をかけて調査・検討されるよりも、専門家にご相談いただく方が、早く、確実に、そして有利な結果を得られるケースがほとんどです。
「まずは、うちの会社が許可を取れそうかどうかだけでも知りたい」「経審の点数がどれくらいになるか、改善の余地はあるか知りたい」といった、初期段階でのご相談だけでも、もちろん大歓迎です。
また、当事務所の最大の特徴として、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)といった他士業の専門家と「チーム(士業の会)」を組織しており、許認可申請にとどまらず、会社設立や資金調達、事業承継など、経営に関わる多種多様・多面的な問題解決に、ワンストップで、いち早く対応できる体制を構築しております。
さらに、元岩手県職員としての行政経験(企業誘致、県立大学新設等担当)を有しており、国や自治体といった行政機関の考え方や手続きの流れを熟知しており、許認可申請や補助金申請等において、行政とのスムーズな連携・調整が可能であるという、他にはない「強み」を持っています。
建設業許可の新規取得、更新、業種追加、そして経営事項審査(経審)の申請や評点アップをご検討されている岩手県内、及び全国の建設業者の皆さまにおかれまして、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。
お客様の事業の発展を、全力でサポートさせていただきます。
5.お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ(トップページ):
https://office-fujiihitoshi.com/