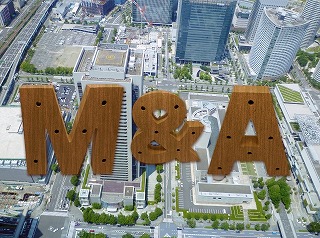「ある日突然、行政庁の職員が『立入検査』にやってきた…」
「一体、何を見られるのだろう?何を準備すればいいのか分からず、パニックに…」
「うちの会社が、立入検査の対象になる可能性はあるのだろうか?」
こんな不安を感じたことはありませんか?
ご安心ください。
その不安は、建設業法の「立入検査」の目的や、チェックされるポイントを事前に知っておくことで、適切な「備え」へと変わります。
この記事では、すべての建設業者が知っておくべき立入検査の現実と、その具体的な内容、そして万全の体制で臨むための準備について、分かりやすく解説します。
建設業を営む上で、建設業法をはじめとする各種法令の遵守(コンプライアンス)は、企業の存続を左右する最も重要な経営課題の一つです。
そして、その遵守状況を実地で確認するために、国土交通省や都道府県の職員が事業者の営業所などを訪れて行うのが「立入検査」です。
この立入検査は、決して他人事ではありません。
いつ、自社がその対象となってもおかしくない、という意識を常に持つことが、健全な企業経営の第一歩です。
今回は、この立入検査について、その目的から具体的な対策までを詳しく見ていきましょう。
1「立入検査」とは何か?
まず、立入検査がどのような根拠に基づき、何を目的として行われるのかを理解することが重要です。
1-1. 立入検査の根拠と目的
立入検査は、建設業法第31条第1項の規定に基づき、行政庁の職員に与えられた権限です。
その最大の目的は、建設業法が目指す「元請負人と下請負人との対等な関係の構築」や「公正・透明な取引の実現」が、実際の企業活動において、正しく実践されているかを確認することにあります。
1-2. 検査の対象となる事業者
重要なのは、立入検査の対象は、建設業許可の有無を問わず、建設業を営むすべての事業者であるという点です。
もちろん、許可業者であれば、その許可要件を適切に維持しているかも、当然、検査の対象となります。
1-3. 特に検査対象となりやすい5つのケース
では、どのような事業者が、特に検査の対象となりやすいのでしょうか。
一般的に、以下のようなケースが挙げられます。
① 新規に建設業許可を取得した事業者:
許可取得後、法令に則った適切な運営が行われているかを確認するため。
② 過去に行政指導や監督処分を受けた事業者:
指摘事項が改善されているか、再発防止策が講じられているかを確認するため。
③ 「駆け込みホットライン」などに通報があった事業者:
下請負人や従業員などから、法令違反に関する具体的な情報提供があった場合。
④ 各種調査に非協力的な事業者:
国土交通省が行う「下請取引等実態調査」などに未回答であったり、不適切な回答が多かったりする場合。
⑤ 繰り返し不正行為の疑いがある事業者:
複数の情報から、常習的に法令違反を行っている可能性が高いと判断された場合。
2立入検査の頻度と、当日の流れ
「一体、どのくらいの頻度で検査は行われるのか?」という点も、気になるところでしょう。
法律上、検査は「特に必要があると認めるとき」に行われるとされており、定期的なものではありません。
しかし、国土交通省が公表しているデータによれば、例えば令和5年度には、全国で806件の立入検査が実施されています。
これは、決して稀なことではない、という現実を示しています。
検査の基本的な流れは、以下の通りです。
①電話による事前連絡:
ある日突然、行政庁の担当者から、立入検査を実施したい旨の電話連絡が入ります。
②正式な通知書の送付:
その後、検査の日時、場所、目的、準備すべき書類などが記載された、正式な通知書が送られてきます。
③立入検査の実施:
約束の日時に、担当職員が営業所などを訪れ、帳簿や書類の確認、関係者へのヒアリングなどが行われます。
3立入検査でチェックされる最重要項目
立入検査では、建設業法が定める、日々の業務に関する様々な書類が網羅的にチェックされます。
特に重点的に確認されるのは、以下の項目です。
3-1. ①契約関係の書類
注文者(発注者)と、そしてすべての下請負人との間で、建設業法第19条に基づいた、適正な内容の請負契約書(注文書・請書を含む)が、着工前に、書面で取り交わされているかが、厳しくチェックされます。
3-2. ②施工体制に関する書類
作成義務のある工事において、施工体制台帳や施工体系図が、法令の求める記載事項を網羅し、適切に作成・整備されているかを確認されます。
下請からの再下請負通知書が、きちんと台帳に反映されているかも重要なポイントです。
3-3. ③技術者の配置に関する書類
各工事現場に、その規模や内容に応じて、適切な資格を持つ主任技術者・監理技術者が、法令(専任義務など)に従って正しく配置されているか、その資格や雇用関係を証明する書類と共に確認されます。
3-4. ④代金支払に関する書類
下請負人への支払いが、法律で定められた期日(例:元請が発注者から受領後1ヶ月以内)や、支払方法(労務費相当額の現金払いなど)のルールを守って、適正に行われているかを確認するため、請求書や支払記録などがチェックされます。
4整理
立入検査の通知は、多くの経営者様にとって、緊張が走る瞬間かもしれません。
しかし、その本質は、決して企業を罰するための「粗探し」ではありません。
むしろ、自社のコンプライアンス体制が、社会の求める基準に達しているかを客観的に見直す、絶好の機会と捉えるべきです。
検査で問われるのは、一夜漬けで準備した書類ではなく、日々の業務の中で、建設業法の一つひとつのルールを、いかに誠実に遵守してきたか、という企業の「姿勢」そのものです。
日頃から、法令に基づいた適正な契約、書類の作成・保管を徹底すること。それこそが、いつ立入検査の通知が来ても、慌てることのない、最高の準備と言えるでしょう。
5まとめ
建設業法に基づく「立入検査」は、許可・無許可を問わず、すべての建設業者にとって他人事ではありません。
その目的は、公正な取引慣行の実現と、建設業の健全な発展を促すことにあります。
日々のコンプライアンス遵守こそが、この検査に対する最善の備えです。
「自社の管理体制は、検査基準を満たしているだろうか」「万が一に備え、専門家によるチェックを受けたい」など、ご不安な点は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、行政の視点を踏まえた、実践的なコンプライアンス体制の構築をサポートします。
貴社を法務リスクから守り、持続的な成長を支援いたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/