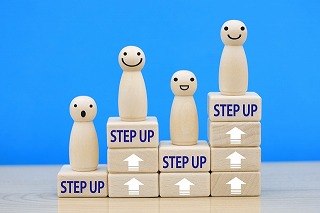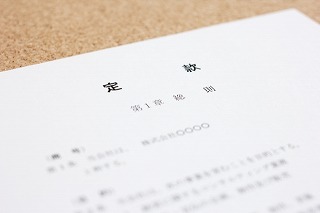「医療法人化を検討しているが、個人クリニックの資産(不動産、医療機器、借入金)の扱いはどうなるのか?」
「基金とは何をいくら準備すればいいのか、手続きが複雑そうで診療と両立できるか不安だ」
こんな悩みはありませんか?
その悩み、この記事で解決できます。今回の提案は、医療法人設立で最も重要な「財産の引継iぎ(拠出)」について、失敗しないための具体的なコツをあなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
クリニックの経営が軌道に乗り、節税対策や事業承継、分院展開などを見据えて「医療法人化」を検討される医師・歯科医師の先生方は多くいらっしゃいます。
しかし、医療法人の設立は、株式会社などと異なり、都道府県の「認可」が必要であり、その手続きは非常に専門的で複雑です。特に、先生方が最も頭を悩まされるのが、個人開業時代の資産を、どうやって新設する医療法人に引き継ぐかという「財産の拠出」の問題です。
この財産拠出の計画書(拠出財産目録や基金引受申込書など)の作成が、認可申請における最大の関門と言っても過言ではありません。
なぜなら、拠出する財産の種類や評価額、名義などを一つでも間違えると、行政(保健所や県庁)からの指導で何度も修正が必要となり、最悪の場合、予定していた設立スケジュールが大幅に遅れてしまうからです。
そこで今回は、多忙な先生方がスムーズに医療法人設立準備を進められるよう、財産拠出に関する「6つのコツ」を分かりやすく解説します。
1 コツ1
現在設立できる医療法人は「持分なし医療法人」のみであり、設立時には「基金」を拠出する必要があります。
この基金として拠出された財産は、法人の定款(法人のルールブック)上、「基本財産」と「通常財産」のいずれかに分類されます。
⑴ 基本財産: 法人の根本的な財産。土地や建物などが想定されます。
⑵ 通常財産: 基本財産以外の財産。運転資金(現金)や医療機器、医薬品などです。
ここで重要なコツがあります。
それは、「基本財産は設定せず、すべて通常財産にする」ことです。
県によっては「不動産は基本財産にすることが望ましい」といった手引きが示されている場合もありますが、基本財産に設定してしまうと、将来その財産を売却したり、担保に入れたりする際に、いちいち定款変更の認可手続きという非常に煩雑なプロセスが必要になります。
例えば、古い医療機器を売却して新しい機器に入れ替えたい場合、それが基本財産だと手続きに数ヶ月かかることもあり、機動的な経営判断の足かせとなります。
設立後の運営の自由度を確保するためにも、可能な限り、拠出財産はすべて「通常財産」に設定することをお勧めします。
2 コツ2
先生個人の名義、あるいはご家族の名義になっているクリニックの土地や建物(不動産)は、どう扱えばよいでしょうか。
結論から申し上げますと、「医療法人に拠出(寄附または基金として拠出)せず、個人から医療法人へ賃貸する」のが最もシンプルで安全な方法です。
拠出を推奨しない理由は以下の通りです。
⑴ 担保権(ローン)の問題:
もし、その不動産に先生個人の住宅ローンや事業用ローンなどの抵当権(担保)が設定されている場合、権利関係が不安定であるため、原則として拠出財産として認められません。
⑵ 評価額の問題:
万が一拠出する場合、その評価額は「不動産鑑定評価額」や「固定資産評価証明書」の額に基づき決定します。鑑定評価には別途費用と時間が必要です。
⑶ 将来の柔軟性の欠如:
一度法人に拠出すると、それは法人の財産です。
将来、先生がリタイアする際や相続が発生した際に、個人の資産計画と複雑に絡み合い、トラブルの原因となる可能性があります。
拠出ではなく、「先生個人(オーナー)」と「医療法人(借主)」との間で適正な賃料を設定し、賃貸借契約を結ぶ形が、手続き面でも税務面でも、将来の資産管理の面でも最善の選択と言えます。
3 コツ3
拠出する財産目録には、その財産が確かに存在し、その評価額が妥当であることを証明する書類(エビデンス)の添付が求められます。
財産の種類ごとに必要な書類と注意点を見ていきましょう。
3-1. 現金・預金
最も確実な財産です。設立時の運転資金として必須となります。
〇 注意点: 必ず「預金残高証明書」の原本が必要になります。
※通帳のコピーでは認められません。
この証明書は、銀行窓口で発行を依頼しますが、手数料がかかるうえ、発行までに数日~1週間程度かかる場合があります。
また、証明書の日付(基準日)は、「設立総会の日から遡って〇ヶ月以内」のように、各都道府県のローカルルールで有効期限が定められています。
申請スケジュールから逆算して、早めに準備に取り掛かる必要があります。
3-2. 医業未収金
いわゆる「レセプト(診療報酬請求)」のうち、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会から、まだ入金されていない売上のことです。
これも法人が引き継ぐ重要な財産となります。
〇 注意点: 証明書類として、「直近2ヶ月分の診療報酬の決定通知書」の写しなどを添付します。
3-3. 医療機器・備品
現在クリニックで使用している医療機器や器具備品です。
〇 注意点: 評価額は、原則として「減価償却後の簿価(帳簿上の価格)」で計算します。
リース物件は、所有権がリース会社にあるため、拠出財産(基金)にすることはできません。
リース契約自体を個人から医療法人へ引き継ぐ手続き(契約の巻き直し)が別途必要です。
3-4. 医薬品・診療材料など
在庫となっている医薬品や材料(デンタル系であれば金属など)も財産です。
〇 注意点:「決算時の棚卸表」や、基準日時点での在庫リストを根拠資料として添付し、簿価で拠出します。
4 コツ4
長年使用しており、減価償却が終わって固定資産台帳上の価値が「ゼロ円(備忘価額1円)」になっている医療機器や什器・備品(例:診察台、PC、キャビネットなど)はどうでしょうか。
これらも、まだ現役で使用できる立派な法人の財産です。
台帳にないからといって諦める必要はありません。
毎年1月末までに各市町村に提出している「償却資産申告書」の控えが、その資産がクリニックに実在する証明として使える場合があります。
帳簿上はゼロ円でも、現実に使用している資産を財産目録に加えることで、法人の財産的基礎をしっかり示すことができます。
5 コツ5
拠出する財産のうち、現金・預金以外のもの(不動産、医療機器、医薬品など)を「現物拠出」と呼びます。
ここで非常に重要なルールがあります。
それは、「現物拠出の価額の総額が500万円を超える場合」です。
この場合、その評価額が本当に妥当であるかを証明するために、弁護士、公認会計士、税理士などによる「価額が相当であることの証明書」(いわゆる価額相当証明)を添付しなければなりません。
この証明書の発行を専門家に依頼するには、数十万円単位の別途費用と、1ヶ月以上の調査期間が必要になることがあり、設立スケジュールとコストの両面で大きな負担となります。
したがって、設立をスムーズに進めるための最大のコツは、現物拠出の合計額を500万円以下に調整することです。
例えば、高額な医療機器の拠出を見送り、リース契約に切り替えるなどの工夫が考えられます。
6 コツ6
財産(プラスの資産)の話ばかりしてきましたが、忘れてはならないのが「債務(マイナスの資産)」、すなわち借入金です。
個人開業時代に、金融機関から医療機器の購入費用や運転資金として借り入れたお金がある場合、これを医療法人に引き継ぐ必要があります。
(※基金はプラスの財産なので、借入金を基金に含めることはできません)
この債務の引継ぎ(債務引受)で最も重要なのが、「債権者(お金を貸している金融機関)の同意」です。
金融機関から「個人(院長)への貸付を、新設する医療法人の債務として引き継ぐことを承諾します」という内諾書や同意書を事前にもらっておかなければ、都道府県は認可してくれません。
金融機関内の稟議には時間がかかるため、認可申請の準備と並行して、できるだけ早い段階で金融機関に相談を開始することが不可欠です。
7 まとめ
ここまで、医療法人設立における財産拠出の6つのコツを見てきました。
コツ1:「基本財産」はゼロ。「通常財産」に設定する
コツ2:不動産(土地・建物)は「賃貸借」が最善手
コツ3:財産種別ごとの「証明書類」を早めに準備する
コツ4:償却済みでも「償却資産申告書」を活用する
コツ5:現物拠出は「500万円以下」に調整する
コツ6:「債務(借入金)」の引継ぎは金融機関の同意が必須
これらはほんの一部であり、実際には都道府県ごとのローカルルールへの対応、定款や設立趣意書の作成、設立総会議事録の整備、そして保健所や県庁との事前協議など、膨大で複雑な手続きが必要です。
「診療の合間に、これらすべてを自分で調べて準備するのは現実的ではない…」 「何から手を付けていいか分からない」
それが先生方の本音ではないでしょうか。
そのような時は、ぜひ医療法務を専門とする行政書士にご相談ください。
専門家である行政書士に設立手続きをトータルで任せることで、先生方は日々の診療に集中しながら、スムーズかつ確実に法人化を進めるという「安心」を得ることができます。
★行政書士藤井等事務所の強み★
① ワンストップ対応:
当事務所の最大の強みは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった他の専門家と強固な連携を組んでいる点です。設立時の登記(司法書士)や税務(税理士)、設立後の労務管理(社労士)まで、あらゆる問題にワンストップで迅速に対応できる体制を整えています。
② 行政対応力:
代表は元岩手県職員として、企業誘致や県立大学新設といった行政内部での調整業務を経験しております。国や県、保健所といった行政機関の「考え方」や「手続きの進め方」を熟知しており、他にはない「強み」として、素早く的確な調整・対応が可能です。
③ 利便性(土日祝日):
他の事務所と異なり、土日・祝日も営業しております。営業時間は朝8時から夜20時までとしており、診療後のお忙しい時間でも、先生方のご都合に合わせて柔軟に対応いたします。
岩手県、宮城県をはじめ、東北全域の医療法人設立は、ぜひ当事務所にお任せください。
【注意事項】
・医療法人の設立認可申請や、設立後の各種届出(役員変更、決算届など)について、厚生労働省(地方厚生局)や都道府県、各保健所といった行政機関への申請書類を作成し、提出を代理することは、国家資格者である行政書士にのみ法律上認められた業務です。
・行政書士以外の者(例えば、無資格のコンサルタントなど)が、報酬を得てこれらの申請代理や書類作成を行うことは、行政書士法違反として固く禁止されています。大切な法人の設立手続きは、必ず正規の行政書士にご依頼ください。
8 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ
https://office-fujiihitoshi.com/