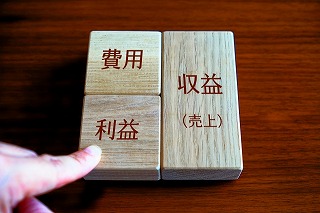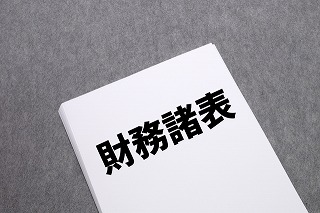「独立して建設業を始めたけれど、事務所に固定電話を引いていない…」
「携帯電話だけで仕事をしているが、これだと建設業許可は取れないの?」
こんな悩みはありませんか?
実は、建設業法には「固定電話が必須」という明文規定はありません。
しかし、申請の実務では「営業所の実態」が厳しく問われるため、地域によっては受理されないケースもあります。
その悩みは今回の説明で解決できます。
今回は、岩手県など、最新の運用ルールに基づき、固定電話がない場合でもスムーズに許可を取得するための具体的な対策と、審査をクリアするポイントを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
1 建設業許可申請における「固定電話」の法的な位置づけ
建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」や「営業所技術者」の配置など、いくつかの要件をクリアする必要があります。
その中で、意外と盲点になりがちなのが「営業所」の要件です。
★ 特に、最近増えているご相談が、
⇒「固定電話を設置していないが、許可は取れるのか?」というものです。
1-1. 法律に「固定電話必須」とは書かれていない
まず、法律の条文を確認してみましょう。
建設業法、同法施行令、同法施行規則のどこを探しても、「営業所に固定電話を設置しなければならない」という直接的な文章は存在しません。
建設業法第3条では、許可は「営業所ごとに」受けなければならないとされています。
そして、国土交通省のガイドラインでは、「営業所」とは「本店、支店等、常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と定義されています。
つまり、法律が求めているのは「電話機があること」ではなく、「そこで請負契約を締結できる実態があるか」という点なのです。
1-2. なぜ行政庁は固定電話を求めるのか?
法律に書いていないのに、なぜ大都市(大阪府など)の一部地域では「固定電話がないと受理しない」といった厳しい対応が取られるのでしょうか?
それは、行政庁(都道府県知事)が「ペーパーカンパニー」を排除したいと考えているからです。
実体のない事務所で許可を取り、不正に名義貸しを行ったり、契約トラブルを起こして連絡が取れなくなったりする業者を防ぐ義務が行政にはあります。
「固定電話がある」ということは、「その場所に根付いて営業している」という一つの証明になります。
逆に、携帯電話だけだと「いつでも移動できる=事務所の実体がないのでは?」と疑われやすくなるのです。
これが、固定電話を求められる「行政側の論理」です。
2 岩手県における最新の運用ルール
では、私たちが活動する東北エリア、特に岩手県ではどのような運用がなされているのでしょうか。
大阪府のように、門前払いされてしまうのでしょうか?
結論から申し上げますと、岩手県では、固定電話がなくても直ちに「不許可」や「受理拒否」になるわけではありません。
ただし、何もしなくて良いわけではなく、携帯電話でも「営業所として機能している」ことをしっかりと証明する必要があります。
2-1. 岩手県の場合
岩手県(県土整備部)の運用では、明文化された「固定電話必須」の規定はありません。
しかし、申請時には「営業所の確認資料」として、以下の写真の提出が求められます。
①建物の全景
②事務所の入り口(看板含む)
③事務所の内部(机、椅子、事務機器等)
この「事務機器」の中に、通信手段が含まれます。
岩手県では、原則として固定電話が望ましいと指導されますが、「事業専用の携帯電話」があり、常時連絡が取れる状態であれば、受理されるケースがほとんどです。
重要なのは、「その携帯電話番号が、対外的に公表されているか」です。
例えば、名刺や見積書、請求書、封筒、ホームページなどに、その携帯番号が記載されており、ビジネス用として確立していることを示す必要があります。
2-2. 宮城県の場合
宮城県(土木部)の運用は、岩手県に比べるとやや厳格な傾向にあります。
「建設業許可申請の手引き」においても、営業所の確認資料が重視されており、賃貸借契約書(使用目的が「事務所」となっていること)などの整合性が、「厳しく」チェックされます。
通信手段についても、原則は固定電話等の設置を求めていますが、近年はIP電話や携帯電話のみの事業所も増えているため、柔軟な対応へと変化してきています。
ただし、宮城県の場合も、単に「携帯を持っています」だけでは不十分です。
「なぜ固定電話がないのか」という理由や、「この携帯電話でどのように契約実務を行っているか」を合理的に説明できなければ、審査が長引く可能性があります。
3 固定電話なしで申請を通すための具体的な対策
「これから申請するけれど、固定電話を引く時間もコストも惜しい」
そのような法人様や個人事業主様のために、固定電話なしで審査をスムーズに通すためのテクニックをご紹介します。
3-1. 「事業専用」の携帯電話であることをアピール
審査官が最も嫌がるのは、「プライベート兼用のスマホで、仕事の電話か遊びの電話か区別がつかない」状態です。
可能であれば、仕事専用の端末を用意するか、少なくとも名刺や会社案内にはその番号を「代表電話」として明記し、実績を作っておきましょう。
3-2. 写真撮影で「実在性」を補強
固定電話がない分、他の要素で「ここは間違いなく営業所です」と主張する必要があります。
特に重要なのが「看板」と「事務所内部」の写真です。
① 看板:
テプラ等の簡易的なものではなく、しっかりと「〇〇建設」と掲げられた看板(表札)の写真を撮ります。
② 内部:
接客スペース、事務机、パソコン、プリンターなどが整然と配置され、いつお客様が来ても契約ができる状態であることを写真で証明します。
3-3. 合理的な理由を説明できるように準備
もし窓口で「なぜ固定電話がないのですか?」と聞かれた場合に、答えに詰まってはいけません。
「現場に出ている時間が長く、固定電話を置いても誰も出られないため、携帯電話を営業用として使用し、転送設定や留守電機能で顧客対応を万全にしています」といった、業務実態に即した合理的な理由を説明できるようにしておきましょう。
4 行政裁量への対応
建設業許可の申請は、書類が揃っていれば機械的に通るものではありません。
今回のように法律に明記されていない部分(行政裁量)については、役所の担当者への説明能力が問われます。
4-1. 他の東北各県の状況
参考までに、他の東北各県の傾向も見てみましょう。
⑴ 青森県・秋田県・山形県:
比較的柔軟です。
固定電話の有無よりも、看板や机・什器などの物理的な実在性を重視する傾向があります。
⑵ 福島県:
宮城県と同様に確認資料が細かいですが、通信環境の変化(固定電話の廃止等)を考慮し、柔軟な対応が可能になってきています。
どの県であっても、「ペーパーカンパニーではない」という証明が最優先事項であることに変わりはありません。
4-2. リスク管理としての申請準備
ご自身で申請を行う場合、窓口で「これでは営業所として認められない」と言われてしまうと、その後のリカバリーが非常に難しくなります。
一度「実体なし」という心証を持たれてしまうと、追加資料の提出を何度も求められ、許可が下りるまでに数ヶ月のロスが生じることも珍しくありません。
特に、自宅兼事務所の場合や、レンタルオフィスを使用している場合は、より慎重な準備が必要です。
5 まとめ
建設業許可の取得・更新は、事業の発展に欠かせない重要な手続きです。
しかし、今回解説した「固定電話」の問題のように、法律の条文にはない「ローカルルール」や「行政の運用」を知らないと、思わぬところでつまづいてしまいます。
法改正や制度の複雑さから、「難しそう…」「面倒…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
当事務所は、建設業許可の専門家として、お客様の個別の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
「うちは固定電話がないけれど大丈夫?」「自宅兼事務所だけど許可は取れる?」といった不安をお持ちの方こそ、ぜひ相談してください。
法律の規定や申請手続きは、複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて悩み、何度も役所に足を運ぶより、専門家に任せた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
岩手県や東北地域で建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
お客様のビジネスチャンスを逃さないよう、全力でバックアップいたします。
6 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/