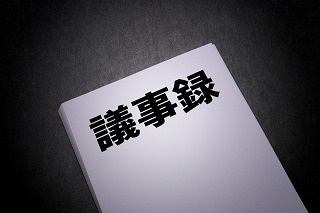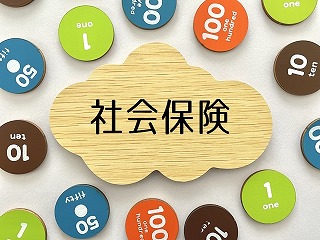「日々の診療で忙しく、医療法人化の手続きまで手が回らない」
「設立に必要な書類が複雑で、何から始めればいいか分からない」
「行政とのやり取りが面倒そうで不安だ」。
こんな悩みはありませんか?
そのお悩み、この記事で解決できます。複雑に思える医療法人の設立手続きも、根拠となる法律のルールを理解すれば、見通しが立ち、スムーズに進めることが可能です。
今回は、医療法人設立をお考えの先生方へ、知っておくべき行政手続きの重要なルールを専門家の視点で分かりやすく解説します。
1 なぜ医療法人設立には「認可」が必要なのか?
クリニックの法人化を考えたとき、最初に理解すべきなのが、なぜ株式会社のように簡単には設立できず、行政(岩手県)の「認可」という手続きが必要なのか、という点です。
法人の設立形態は、その目的や性質によって法律で定められており、主に行政がどの程度関与するかによって、以下の4つに分類されます。
①許可主義:
最も行政の関与が強く、公益性などの観点から厳しく審査される
(例:銀行、学校法人など)
②認可主義:
法律で定められた要件を満たしていれば、行政は認可しなければならない
(例:医療法人、NPO法人など)
③認証主義:
行政が法律上の要件を満たしているかを確認し、証明するもの
(例:協同組合など)
④準則主義:
法律の要件さえ満たしていれば、行政の判断を介さず登記のみで設立できる
(例:株式会社、合同会社など)
医療法人の設立は、この中の「②認可主義」にあたります。
これは、医療が人の生命や健康に関わる極めて公共性の高い事業であるため、誰でも自由に設立できるわけではなく、「医療法」という法律に基づき、資産要件や役員構成といった法定の要件をきちんと満たしているか、岩手県知事がチェックし、お墨付き(認可)を与えるという仕組みになっているからです。
ただし、これは裏を返せば、法律で定められた要件をしっかりと満たした申請書を作成・提出すれば、県の担当者の個人的な判断で不認可にされることはない、ということでもあります。
つまり、ルールに則って正確に手続きを進めることが、医療法人設立の絶対的な鍵となるのです。
2 医療法人設立を規律する「医療法」というルールブック
医療法人の設立から運営まで、すべての基本となるのが「医療法」です。
この法律によって、医療法人は常に県の監督下に置かれることになります。
例えば、毎年の事業報告書の提出義務や、役員変更時の届出、定款変更の際の認可申請など、設立後も継続的に行政への手続きが発生します。
これは、法人が設立当初の目的通り、地域医療に貢献するために適正に運営されているかを県が監督するためです。
「監督」と聞くと堅苦しく感じるかもしれませんが、これは医療の質と安全性を担保するための重要なルールです。
この医療法のルールを正しく理解し、遵守することが、安定した法人運営の第一歩となります。
3 行政手続法の4つの重要ポイント
実際に県や保健所へ申請や届出を行う際、その手続きの進め方を定めているのが「行政手続法」という法律です。
この法律を知っておくことで、行政側の対応を理解し、よりスムーズに手続きを進めることができます。特に重要な4つのポイントを見ていきましょう。
3-1.審査基準と標準処理期間
「どんな基準で審査されるのか」
「申請してから認可までどれくらい時間がかかるのか」
というのは、最も気になるところだと思います。
行政手続法では、行政庁(この場合は岩手県)に対して、申請を審査するための具体的な「審査基準」を作成し、それを公にすることを義務付けています。
また、申請が窓口に到達してから認可などの処分が下されるまでの標準的な期間、「標準処理期間」も設定し、公表するよう努めなければならないと定められています。
これにより、私たちは事前に審査のポイントや手続きのスケジュール感を把握した上で、準備を進めることができるのです。
3-2.申請に対する審査・応答
提出した申請書が、理由なく放置されることはありません。
行政手続法では、行政庁は申請があった場合、遅滞なく審査を開始しなければならないと定めています。
もし、提出した書類に記載漏れや添付書類の不足といった不備があった場合でも、速やかに申請者に対して修正(補正)を求めるか、あるいは不認可の決定をする必要があります。
つまり、行政側には迅速な対応が義務付けられているのです。
3-3.行政指導の正しい理解
申請前の事前相談などで、県の担当者から「この書類も追加してください」「ここの表現はこう直してください」といった、いわゆる「行政指導」を受けることがあります。
しかし、この行政指導は、あくまで「相手方の任意の協力によってのみ実現されるもの」と法律で明確に定められています。
つまり、法的な強制力はなく、行政側がその任務の範囲を超えた指導をすることはできません。
もちろん、手続きを円滑に進めるためのアドバイスである場合がほとんどですが、もし法的な根拠に乏しい過度な要求だと感じた場合は、その指導の趣旨や内容、責任者を明確にするよう求めることができます。
3-4.届出のルール
許認可申請とは別に、役員の変更届など、行政への「届出」が必要な手続きもあります。
この届出は、法律で定められた様式や添付書類に不備がなく、形式上の要件に適合していれば、担当窓口に到達した時点で、手続きを行う義務が果たされたものとされます。
申請のように、行政側の「受理」という行為を待つ必要はありません。
なお、県が行う行政手続きについては、国の行政手続法だけでなく、行政手続条例も関わってきます。
両方を確認しながら進めることが重要です。
4 行政書士法
では、これらの複雑な法律に基づいた医療法人設立認可申請書や、診療所開設許可申請書といった書類は、誰が作成し、提出できるのでしょうか。
この点について「行政書士法」が明確に定めています。
官公署(県や保健所など)に提出する書類の作成や、その代理提出は、国家資格者である行政書士の独占業務とされています。
これは、専門的な法律知識を要する重要な書類作成を、資格を持つ専門家が責任を持って行うことで、国民の権利利益を守るための制度です。
もちろん、先生ご自身やクリニックの職員の方が申請を行うことは可能です。
しかし、日々の診療業務でお忙しい中、膨大な手引きを読み解き、正確な書類を作成し、何度も行政窓口へ足を運ぶのは、計り知れない時間と労力を要します。
万が一、書類に不備があれば、設立スケジュールが大幅に遅れてしまう可能性もあります。
専門家である行政書士に依頼することで、これらの手続きを迅速かつ確実に行い、先生方は安心して本来の業務である医療に専念することができるのです。
5 まとめ
医療法人の設立や、それに伴う行政機関への許認可申請は、ここまで見てきたように、複数の法律が絡み合う複雑な手続きです。
何から手をつけていいか分からず、不安に感じられるのも当然です。
このような専門的な手続きは、専門家である行政書士にトータルでお任せいただくことで、大きな安心感が得られます。
私たちは、単に書類を作成するだけでなく、行政からの専門的な質問に対しても、先生の代理人として的確に対応し、手続きがスムーズに進むようサポートいたします。
当事務所では、医療の最前線でご尽力されている先生方に寄り添い、それぞれのクリニックの状況に応じた最善の解決策をご提案します。
さらに、当事務所の最大の強みは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった他の専門家と緊密な連携体制を築いている点です。
医療法人設立後の税務会計や人事労務、万が一の法務トラブルまで、あらゆる問題に対してワンストップで迅速に対応することが可能です。
加えて、私自身が元岩手県職員として、企業誘致や県立大学の新設といった行政の内部で許認可や調整業務に携わってきた経験があります。
行政側の視点や手続きの流れを熟知しているため、国や岩手県、管轄の保健所といった行政機関に対し、どこに・どのようにアプローチすれば話が早く進むのかを肌で理解しています。
これは、他の事務所にはない、お客様の手続きを円滑に進める上での確かな「強み」です。
煩雑な手続きは専門家に任せ、先生はどうぞ診療に専念してください。
まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
★ 注意事項
厚生労働省(地方厚生局)や県庁、各保健所への許認可申請に関する書類の作成・提出代理は、行政書士法により、行政書士にのみ認められた業務です。
行政書士の資格を持たない者が、報酬を得てこれらの業務を代行することは法律で固く禁じられており、違反した場合は罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。
大切な法人の設立手続きは、必ず正規の国家資格者にご依頼ください。
6 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ
https://office-fujiihitoshi.com/