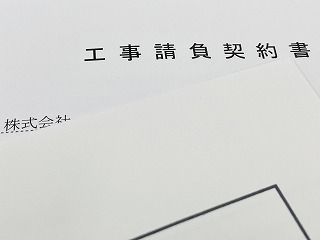「建物の解体工事を依頼したいけど、どの業者に頼めばいい?」
「『解体工事』って、建設業許可は必要なの?」
「水道工事は、『管工事』と『水道施設工事』のどっち?」
こんな疑問や不安はありませんか?
建設業許可を申請するにあたって、自社が行う、あるいはこれから行う「建設工事」の概要を具体的に知っておくことは非常に重要です。
特に、解体工事や水道工事は、許可が必要なケースと不要なケース、あるいは、どの業種の許可が必要か、判断が難しいことがあります。
ご安心ください!
今回の記事では、解体工事や撤去工事、水道工事を中心に、建設業許可の業種判断のポイントを分かりやすく解説します。
この記事を読めば、工事の種類に応じた適切な建設業許可が分かり、無許可営業などのリスクを避けられます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)で建設業を営む皆様、ぜひ最後までお読みください。今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1建設業許可における解体工事の位置づけは?
建設業許可において、「解体工事」は独立した一つの業種として位置づけられています。
しかし、平成28年の法改正以前は、「とび・土工・コンクリート工事」の一部として扱われていました。
ここでは、解体工事の定義、法改正による変更点、注意点などを詳しく解説します。
1-1. 解体工事の定義:国土交通省のガイドライン
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると、解体工事の内容は次のとおりです。
〇工作物の解体を行う工事
この定義は非常にシンプルですが、「工作物」とは具体的に何を指すのか、「解体」とはどのような行為を指すのか、といった点が問題となります。
①工作物とは:
土地に固定された人工的な構造物全般を指します。具体的には、以下のようなものが該当します。
②建物:
住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、学校、病院など、あらゆる種類の建物が含まれます。
③建築物以外の構造物:
橋梁、トンネル、ダム、道路、鉄道、上下水道、電柱、送電鉄塔、広告塔、看板、塀、擁壁、庭園など。
④解体とは:
工作物を取り壊し、更地にすること、または、その一部を除去することを指します。具体的には、以下のような行為が含まれます。
⑤全面的解体: 建物を完全に取り壊し、更地にする。
⑥部分的解体: 建物の増改築に伴い、既存の壁や床、屋根などを一部取り壊す。
⑦内装解体: 建物の内部の壁、床、天井、間仕切り、設備などを取り壊す。
⑧設備解体: ボイラー、エレベーター、空調設備など、建物に付帯する設備を取り壊す。
1-2. 法改正による変更点:解体工事業の新設
平成28年6月1日に施行された「建設業法等の一部を改正する法律」により、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されました。
それまでは、「とび・土工・コンクリート工事」の中に含まれていた解体工事が、独立した業種として扱われるようになったのです。
この法改正の背景には、
・解体工事の専門性・技術性の高まり
・解体工事に伴う事故や環境問題の増加
・不良・不適格業者の排除
などがあります。
法改正により、解体工事業の許可を取得するためには、
・一定の実務経験を有する技術者(解体工事施工技士など)の配置
・一定の財産的基礎(資本金など)
などの要件を満たす必要があります。
1-3. 経過措置の終了:令和元年5月31日
法改正に伴い、経過措置が設けられていました。
改正法施行前(平成28年5月31日以前)に「とび・土工・コンクリート工事」の許可を取得していた建設業者は、令和元年5月31日までの間は、引き続き解体工事を請け負うことができました。
しかし、令和元年6月1日以降は、解体工事業の許可を取得していないと、500万円以上(税込)の解体工事を請け負うことができなくなりました。
1-4. 注意点:解体工事に該当しないケース
すべての「取り壊し」が解体工事に該当するわけではありません。以下のようなケースは、解体工事には該当せず、他の業種の許可が必要となる場合があります。
・内装仕上工事に伴う内装の撤去:
壁紙の張り替えや、床の張り替えに伴う、既存の内装材の撤去は、「内装仕上工事」に該当します。
・設備工事に伴う設備の撤去:
空調設備の交換や、給排水設備の改修に伴う、既存の設備の撤去は、それぞれの設備工事(「管工事」「電気工事」など)に該当します。
・足場の解体:
足場の解体は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
・樹木の伐採・抜根:
樹木の伐採・抜根は、建設業許可の対象外です(ただし、造園工事に付随する場合は、「造園工事」に該当する場合があります)。
これらの工事は、解体工事ではなく、それぞれの専門工事に該当するため、注意が必要です。
2撤去工事とは?:建設業許可との関係
「撤去工事」という言葉は、建設業許可の業種区分には存在しません。
しかし、一般的には、建物や設備などを取り除くことを指す言葉として広く使われています。
ここでは、「撤去工事」と呼ばれる工事が、建設業許可のどの業種に該当するのかを解説します。
2-1. 「撤去工事」という業種はない
建設業許可には、29種類の業種がありますが、「撤去工事」という名前の業種はありません。
「撤去」という言葉は、あくまでも一般的な用語であり、法律上の定義はありません。
そのため、「撤去工事」という言葉だけでは、具体的にどの業種の許可が必要かを判断することはできません。
2-2. 幅広い意味を持つ「撤去工事」:様々な工事の可能性
「撤去工事」という言葉は、非常に幅広い意味を持ちます。
具体的には、以下のような工事が「撤去工事」と呼ばれることがあります。
・建物の撤去工事: 建物全体を取り壊す工事(解体工事)。
・足場の撤去工事: 建設現場の足場を解体する工事(とび・土工・コンクリート工事)。
・内装の撤去工事: 建物の内部の壁、床、天井、間仕切りなどを取り壊す工事(内装仕上工事)。
・設備の撤去工事: 空調設備、給排水設備、電気設備、照明器具、厨房設備などを取り外す工事(それぞれの設備工事)。
・看板の撤去工事: 看板を取り外す工事(とび・土工・コンクリート工事、または鋼構造物工事)。
・フェンスの撤去工事: フェンスを取り外す工事(とび・土工・コンクリート工事、または外構工事)。
・樹木の撤去工事: 樹木を伐採し、あるいは、抜き取る工事(造園工事)。
このように、「撤去工事」と呼ばれる工事は多岐にわたり、その内容は、撤去する対象物や工事の規模によって大きく異なります。
2-3. 撤去工事の具体例:多様なケース
具体的な撤去工事の例をいくつか挙げてみましょう。
・古くなった店舗の内装を全面的に撤去し、新しい内装にリフォームする工事:
この場合、壁、床、天井、間仕切り、照明器具、空調設備など、様々なものを取り外すことになります。
・使わなくなった工場の機械設備を撤去する工事:
この場合、大型の機械や、それに付随する配管、配線などを取り外すことになります。
・道路沿いの古くなった看板を撤去する工事:
この場合、看板本体だけでなく、看板を支える支柱や基礎なども取り外すことになります。
・住宅の庭にある古くなったフェンスを撤去する工事:
この場合、フェンス本体だけでなく、フェンスを支える支柱や基礎なども取り外すことになります。
・アパートの外階段の撤去工事:
この場合、外階段本体の撤去、及び、基礎部分の撤去が伴う場合は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
これらの工事は、いずれも「撤去工事」と呼ばれることがありますが、建設業許可の業種区分は、それぞれ異なります。
2-4. 撤去工事の業種判断のポイント:「工作物」と「専門工事」
撤去工事の業種判断をする上で、重要なポイントは、以下の2点です。
・撤去するものが「工作物」かどうか
・撤去工事が「専門工事」に該当するかどうか
2-4-1. 「工作物」の解体・撤去は「解体工事」
建設業法上の「工作物」を解体・撤去する場合は、「解体工事」に該当します。
「工作物」とは、土地に固定された人工的な構造物全般を指し、建物だけでなく、塀、擁壁、広告塔、看板なども含まれます。
例えば、
家屋の解体工事、ビルの解体工事、プレハブの解体工事、塀や擁壁の撤去工事、広告塔や看板の撤去工事(構造物全体を撤去する場合)
などは、「解体工事」に該当します。
ただし、高層ビルなどの大規模な工作物の解体工事で、総合的な企画、指導、調整が必要となる場合は、「建築一式工事」に該当する場合があります。
2-4-2. 専門工事に該当する場合は、その業種の許可が必要
「工作物」の解体・撤去であっても、その工事が特定の「専門工事」に該当する場合は、その専門工事の許可が必要となります。
例えば、
・足場の撤去工事: 「とび・土工・コンクリート工事」
・内装の撤去工事(壁紙の剥がし、床材の撤去など): 「内装仕上工事」
・電気設備の撤去工事(照明器具の取り外し、配線の撤去など): 「電気工事」
・給排水設備の撤去工事(配管の撤去、衛生器具の取り外しなど): 「管工事」
・機械設備の撤去工事: 設置されている機械の種類や、撤去の内容によって、「機械器具設置工事」「電気工事」「管工事」「とび・土工・コンクリート工事」など、様々な業種に該当する可能性があります。
これらの工事は、単に「撤去」するだけでなく、専門的な技術や知識が必要となるため、それぞれの専門工事の許可が必要となります。
2-5. 撤去工事の業種判断の具体例:詳細なケーススタディ
具体的な撤去工事の業種判断の例をいくつか挙げてみましょう。
・ビルの1室のみの内装の撤去工事:
壁紙を剥がしたり、床材を撤去したりする工事は、「内装仕上工事」に該当します。この場合、建物全体を解体するわけではないため、「解体工事」には該当しません。
・設置されている照明器具のみを撤去する工事:
「電気工事」に該当します。照明器具は電気設備であり、その撤去には電気工事の専門知識が必要となるためです。
・設置されている配管のみを撤去する工事:
「管工事」に該当します。配管は給排水設備の一部であり、その撤去には管工事の専門知識が必要となるためです。
・設置されている看板のみを撤去する工事(看板を支える支柱や基礎は残す場合):
看板の種類や設置方法によって、「とび・土工・コンクリート工事」(完成品の看板を設置する場合)または「鋼構造物工事」(現場で鋼材を加工・組み立てて看板を製作する場合)に該当します。
・組み立てられた足場の撤去工事:
「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。足場は、建設工事に一時的に使用される仮設の構造物であり、その解体はとび職の専門分野となります。
・フェンスの撤去工事(フェンス全体を撤去する場合):
「とび・土工・コンクリート工事」または「外構工事」に該当します。フェンスの種類や設置状況によって、どちらの業種に該当するかが異なります。
これらの例からも分かるように、撤去工事の業種判断は、撤去する対象物や工事の内容によって、細かく判断する必要があります。
「撤去工事=解体工事」と安易に判断せず、慎重に業種を判断することが重要です。
3建設業許可における管工事の位置づけは?
建設業許可における「管工事」は、私たちの生活に欠かせない様々な設備を設置する、重要な業種です。
ここでは、管工事の定義、具体的な工事例、水道施設工事との違い、そして機械器具設置工事との関係について、さらに詳しく解説します。
3-1. 管工事の定義:国土交通省のガイドライン
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると、管工事の内容は次のとおりです。
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
この定義から分かるように、管工事は、大きく分けて以下の2つの工事に分類されます。
・設備工事:
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、空気調和設備、給排水・給湯設備、衛生設備など、建物や施設に特定の機能を持たせるための設備を設置する工事。これらの設備は、建物や施設を利用する人々が快適に過ごすために、必要不可欠なものです。
・配管工事:
金属製等の管を使用して、水、油、ガス、水蒸気などを送配するための設備を設置する工事。これらの配管は、建物や施設のライフラインを支える重要な役割を果たしています。
3-2. 具体的な工事例:多岐にわたる設備
管工事には、以下のような工事が含まれます。
・冷暖房設備工事: エアコン、床暖房、セントラルヒーティング、FF式ストーブなど、建物の冷暖房を行うための設備を設置する工事。これらの設備は、建物内の温度を快適に保ち、居住性や作業効率を向上させるために重要な役割を果たします。
・冷凍冷蔵設備工事: 業務用冷蔵庫、冷凍庫、製氷機、ショーケースなど、食品や物品を低温で保存するための設備を設置する工事。これらの設備は、食品の鮮度を保ち、安全な食品供給を支えるために不可欠なものです。
・空気調和設備工事: 空気清浄機、加湿器、除湿器、換気扇、ダクトなど、建物の空気環境を調整するための設備を設置する工事(冷暖房設備と一体的に設置されることが多い)。これらの設備は、建物内の空気を清潔に保ち、カビやダニの発生を抑制し、健康的な環境を維持するために重要な役割を果たします。
・給排水・給湯設備工事: 水道管、排水管、給湯管、ポンプ、貯水槽、給湯器、蛇口、シャワーなど、水やお湯を供給・排出するための設備を設置する工事。
これらの設備は、私たちの生活に欠かせない水を安定的に供給し、使用済みの水を衛生的に排出するために不可欠なものです。
・厨房設備工事: 業務用厨房のシンク、調理台、レンジ、オーブン、食器洗い機、換気扇など、調理を行うための設備を設置する工事(給排水管の接続や、ガス配管工事を伴うことが多い)。これらの設備は、飲食店や食品工場など、食品を扱う事業者にとって、安全で衛生的な食品を提供するために重要な役割を果たします。
・衛生設備工事: トイレ、洗面台、浴槽、シャワーなど、衛生的な生活を送るための設備を設置する工事。これらの設備は、私たちの健康を守り、快適な生活を送るために不可欠なものです。
・浄化槽工事: 浄化槽を設置する工事(下水道が整備されていない地域で、生活排水を処理するための設備)。浄化槽は、生活排水を浄化し、環境汚染を防ぐために重要な役割を果たします。
・水洗便所設備工事: 水洗便所を設置する工事(浄化槽と一体的に設置されることが多い)。水洗便所は、衛生的なトイレ環境を維持するために不可欠なものです。
・ガス管配管工事: ガス管を配管する工事(ガスを供給するための設備)。ガス管配管工事は、ガス漏れなどの事故を防ぐために、高度な技術と専門知識が必要とされます。
・ダクト工事: 換気や空調のためのダクトを設置する工事。ダクトは、建物内の空気を効率的に循環させ、快適な空気環境を維持するために重要な役割を果たします。
・管内更生工事: 既存の配管の内側に新しい管を形成したり、樹脂を塗布したりして、配管の機能を回復させる工事。管内更生工事は、配管を交換することなく、老朽化した配管の寿命を延ばすことができるため、環境負荷の低減やコスト削減に貢献します。
3-3. 建築物の中の空調機器の設置工事
建築物の中の空調機器(エアコン、換気扇、空気清浄機など)の設置工事は、原則として「管工事」に該当します。
これは、空調機器が、冷暖房、空気調和、換気などの機能を提供し、建物内の空気環境を調整するための設備であるためです。
ただし、壁掛けタイプのエアコンの設置など、電気配線工事が主体となる簡易な工事の場合は、「電気工事」に該当することもあります。
この判断は、工事の内容、使用する機器、配線工事の規模などを総合的に考慮して行われます。
また、空調機器の設置に伴い、電気配線工事を行う場合は、「電気工事」の許可も必要となります。
これは、電気配線工事が、電気工事士の資格を持った者でなければ行うことができない、専門性の高い工事であるためです。
3-4. 家屋の敷地内の配管工事:上水道と下水道の違い
家屋の敷地内の給水管、排水管、ガス管などの配管工事は、「管工事」に該当します。
これは、これらの配管が、建物内の給排水・給湯設備、ガス設備などと接続され、建物内の水、ガスなどの供給・排出を行うための設備であるためです。
ただし、公道から敷地内への引き込み管の設置工事は、上水道と下水道で扱いが異なります。
・上水道の場合: 公道下の配水管(本管)から分岐して、宅地内のメーターまでの引き込み管を設置する工事は、「水道施設工事」に該当します。
・下水道の場合: 公道下の本管から宅地内の公共汚水桝までの取付管を設置する工事は、「土木一式工事」に該当します。
この違いは、上水道と下水道の管理主体や、工事の目的、工事の規模などが異なるためです。
4水道施設工事とは?
「水道施設工事」は、建設業許可の29業種の一つであり、私たちの生活に欠かせない水を安定的に供給するための、重要なインフラを整備する工事です。
ここでは、水道施設工事の定義、具体的な工事例、管工事との違い、そして土木一式工事との関連性について、さらに詳しく解説します。
4-1. 水道施設工事の定義:国土交通省のガイドライン
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると、水道施設工事の内容は次のとおりです。
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
この定義から分かるように、水道施設工事は、大きく分けて以下の2つの工事に分類されます。
・上水道・工業用水道関連工事:
取水施設、浄水施設、配水施設など、上水道や工業用水道を供給するための施設を築造する工事。これらの施設は、私たちが安全で清潔な水を利用できるようにするために、不可欠なものです。
・下水道関連工事:
公共下水道や流域下水道の処理設備を設置する工事。これらの施設は、私たちが使用した水を適切に処理し、環境汚染を防ぐために重要な役割を果たします。
4-2. 具体的な工事例:公共性の高い施設
水道施設工事には、以下のような工事が含まれます。
・取水施設工事: 河川や湖沼、ダムなどから水を取り入れるための施設(取水口、取水塔、取水管、取水ポンプなど)を築造する工事。これらの施設は、安定的に水を取り入れ、浄水場へと送るために重要な役割を果たします。
・浄水施設工事: 取水した水を浄化するための施設(沈殿池、ろ過池、消毒設備、薬品注入設備など)を築造する工事。これらの施設は、水中の不純物を取り除き、安全で飲用に適した水を作るために不可欠なものです。
・配水施設工事: 浄水した水を各家庭や事業所などに配るための施設(配水池、配水管、配水ポンプ、給水塔など)を築造する工事。これらの施設は、必要な場所に、必要な量の水を、安定的に供給するために重要な役割を果たします。
・下水処理設備工事: 下水を集めて処理するための施設(沈殿池、反応タンク、消毒設備、汚泥処理設備、脱臭設備など)を設置する工事。これらの施設は、下水中の汚濁物質を取り除き、環境への負荷を低減するために不可欠なものです。
これらの工事は、いずれも公共性が高く、人々の生活や産業活動に欠かせないインフラを整備する工事です。
そのため、高度な技術力、専門知識、そして安全管理体制が求められます。
4-3. 家屋の水道工事との関係:敷地外の配管工事
「水道施設工事」と聞くと、一般家庭の水道工事(蛇口の交換や、水漏れの修理など)をイメージする方もいるかもしれませんが、建設業許可における「水道施設工事」は、主に公共の水道施設に関する工事を指します。
家屋の敷地内の給水管や排水管の工事は、「管工事」に該当します。
一方、家屋の敷地「外」の公道下の配管工事、つまり、上水道本管から敷地内への引き込み管の設置工事や、下水道本管への接続工事は、「水道施設工事」(上水道の場合)または「土木一式工事」(下水道の場合)に該当します。
5上下水道施設に該当する工事の業種判断の方法
管工事、水道施設工事、そして土木一式工事は、いずれも水に関わる工事であり、その区別は非常に複雑です。
ここでは、これらの業種判断を、より分かりやすく、具体的に解説します。
長崎県の建設業許可申請の手引きを参考に、岩手県および宮城県のケースについても考察します。
5-1. 3つの業種の整理:管工事、水道施設工事、土木一式工事
まず、3つの業種の基本的な違いを整理しましょう。
・管工事: 建物や施設内の給排水・給湯設備、空調設備、ガス配管設備などの工事。主に、建物や施設「内」の配管工事や設備設置工事を行います。
・水道施設工事: 上水道や工業用水道の取水・浄水・配水施設、公共下水道や流域下水道の処理設備などの工事。主に、公共のインフラを整備する工事であり、規模が大きく、公共性の高い工事です。
・土木一式工事: 道路、橋梁、トンネル、ダム、河川、港湾、上下水道など、様々な土木構造物を建設する工事。上下水道関連では、公道下の上下水道本管の敷設工事などが該当します。
5-2. 長崎県の「建設業許可申請の手引き」(分かりやすい)
長崎県の「建設業許可申請の手引き」では、上下水道施設の業種区分について、分かりやすい図解を用いて解説しています。
この手引きは、長崎県だけでなく、他の都道府県でも参考になる内容です。
・上水道の配管工事:
公道下の配水管(本管)から分岐して、宅地内の給水装置(止水栓、メーター、給水管など)までの引き込み管を設置する工事は、「水道施設工事」に該当します。
宅地内の給水装置から、建物内の蛇口までの配管工事は、「管工事」に該当します。
・下水道の配管工事:
公共下水道の取付管(公道下の本管から宅地内の公共汚水桝までの管)を設置する工事は、「土木一式工事」に該当します。
宅地内の公共汚水桝から、建物内の排水設備(トイレ、風呂、台所など)までの配管工事は、「管工事」に該当します。
5-3. 図解による理解:境界線を明確に
長崎県の「建設業許可申請の手引き」では、上水道と下水道のそれぞれについて、どこからどこまでがどの業種に該当するのかを、図を用いて分かりやすく示しています。
この図を見ることで、
・上水道では、公道下の本管から宅地内のメーターまでの引き込み管が「水道施設工事」、それ以降が「管工事」
・下水道では、公道下の本管から宅地内の公共汚水桝までが「土木一式工事」、それ以降が「管工事」
という境界線が、一目で理解できます。
5-4. 岩手県および宮城県の場合:基本的に同様の考え方
岩手県および宮城県の建設業許可においても、長崎県と同様の考え方が適用されると考えられます。
つまり、
・上水道の引き込み管工事は「水道施設工事」
・下水道の取付管工事は「土木一式工事」
・宅地内の配管工事は「管工事」
という区分けが基本となります。
ただし、詳細な運用については、各県の建設業許可担当部署に確認することが重要です。
例えば、工事の規模や内容、使用する材料などによって、業種判断が変わる可能性もあります。
5-5. 注意点:自治体による違い、個別具体的な確認
長崎県の「建設業許可申請の手引き」や、岩手県・宮城県の基本的な考え方は非常に参考になりますが、これはあくまでも一般的な解釈であり、最終的な判断は、各自治体の建設業許可担当部署が行います。
したがって、実際の工事を行う際には、必ず事前に、工事を行う場所を管轄する都道府県(岩手県、宮城県など)や市区町村の建設業許可担当部署に確認し、指示に従うようにしてください。
電話や窓口での相談だけでなく、必要に応じて、工事の内容が分かる資料(図面、仕様書など)を持参して、具体的な相談をすることをおすすめします。
6まとめ
建設業許可の取得・更新は、事業の発展に欠かせない重要な手続きです。
しかし、法改正や制度の複雑さから、「難しそう…」「面倒…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
特に解体工事や水道工事、撤去工事は、どの業種の許可が必要か、判断が難しいケースが多くあります。
行政書士藤井等事務所は、建設業許可の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」「どの業種に該当するか分からない」という相談だけでも構いません。
建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
7お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ<許認可申請>