
「経営事項審査(経審)の申請内容を間違えてしまった!」
「もっと評点を上げるために、申請し直したい…」
「経審の結果に納得がいかない!」
こんなお悩みはありませんか?
経営事項審査(経審)を申請するにあたって、申請後に内容を修正できるのか、再審査を受けられるのかなど、その概要を知っておくことは重要です。
経審は、原則として、申請者側の都合による「受け直し」は認められていません。
しかし、例外的に再審査が可能なケースもあります。
ご安心ください!
今回の記事では、経営事項審査(経審)の「受け直し」と「再審査」について、詳しく解説します。
この記事を読めば、経審の申請で失敗するリスクを減らし、安心して公共工事の入札に臨むことができます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)で公共工事の受注を目指す建設業者の皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1経営事項審査(経審)は原則「受け直し」不可!
経営事項審査(経審)は、公共工事の入札参加資格を得るために必要な審査ですが、一度申請した内容を、申請者側の都合で「受け直し」(やり直し)することは、原則として認められていません。
1-1. なぜ「受け直し」できないのか?
経審は、建設業者の経営状況や技術力などを客観的に評価し、その結果(総合評定値P)に基づいて、公共工事の入札参加資格や格付けが行われます。
もし、申請者側の都合で自由に申請内容を変更したり、受け直しを認めたりしてしまうと、公平な評価ができなくなり、制度の信頼性が損なわれてしまいます。
1-2. 申請は慎重に!
経審の申請は、提出書類が多く、審査項目も多岐にわたるため、準備には時間と手間がかかります。
しかし、一度申請してしまうと、原則としてやり直しができないため、申請内容に誤りがないか、加点対象となる項目を見落としていないかなど、慎重に確認する必要があります。
2例外的に認められる「再審査」:2つのケース
原則として、申請者側の都合による経審の受け直しは認められていませんが、例外的に「再審査」の申立てができる場合があります。
建設業法第27条の28では、再審査ができる場合として、以下の2つのケースを規定しています。
2-1. ケース1:経営規模等評価の結果に異議がある場合
経営規模等評価(X, Z, W)の結果について、
〇行政庁の処理誤り:
計算間違いなど、行政側の処理に誤りがあり、結果通知書(経営規模等評価結果通知書/総合評定値通知書)の記載に誤りがあった場合は、経営規模等評価を行った行政庁に対して、再審査を申し立てることができます。
2-1-1. 申請期限
再審査の申立ては、結果通知書を受け取った日から「30日以内」に行う必要があります。
この期限を過ぎると、再審査の申立てはできなくなります。
2-1-2. 申請者側のミスは対象外
再審査の申立てができるのは、あくまでも行政側の処理誤りによる場合のみです。
申請者側の書類の不備や記載ミス、事実の誤認などによる場合は、再審査の対象とはなりません。
2-2. ケース2:経審の審査項目等の改正があった場合
経審の審査項目や審査基準などが改正された場合は、改正前の基準に基づいて経審を受けた建設業者も、改正後の基準に基づいて再審査を申し立てることができます。
2-2-1. 申請は義務ではない
改正に伴う再審査の申立ては、義務ではありません。
改正前の基準による結果通知書は、そのまま有効なものとして扱われます。
2-2-2. 発注機関によっては、改正後の結果を求められる場合も
ただし、公共工事の発注機関によっては、改正後の経審の結果通知書の提出を求めるところもあるため、注意が必要です。
特に、改正によって評価項目が追加されたり、評価基準が変更されたりした場合は、改正後の基準で再審査を受けた方が、有利になる可能性があります。
2-2-3. 申請期限
改正に伴う再審査の申立ては、改正の日から「120日以内」に行う必要があります。
2-2-4. 審査対象:改正項目のみ
改正に伴う再審査では、改正された項目に関する部分のみが審査の対象となります。
したがって、結果通知書の内容に変動がない場合や、誤り部分の修正、技術職員などの追加といった目的では、再審査を受けることはできません。
2-2-5. 直近の改正事例
直近では、令和3年4月1日に経審の改正がありました。
この改正では、技術職員に関する評価基準などが見直されました。
この改正に伴う再審査の申立ては、令和3年7月29日まで受け付けられていました。
3その他の理由で経審の受け直しが認められるケース(例外中の例外)
建設業法には、上記の再審査の規定しかありませんが、例外的に、他の理由で経審の受け直しが認められるケースがあります。
3-1. ケース1:業種追加をした場合
直近の審査基準日(決算日)で経審を受けた後、建設業許可の業種追加によって許可業種が増えた場合、次の審査基準日を待たずに、業種追加によって増えた業種も含めて、経審を受け直すことができる場合があります。
これは、業種追加によって、経審の評価対象となる工事実績や技術職員数などが変わる可能性があるため、特例的に認められているものです。
ただし、すべての行政庁で認められているわけではないため、事前に確認が必要です。
3-2. ケース2:申請者側の重大な過失による場合
申請者側の重大な過失により、申請内容に誤りがあった場合(例えば、技術職員の担当業種を誤った、防災協定を締結しているのにしていないと申請した、申請する業種を間違えたなど)、例外的に経審の受け直しが認められる場合があります。
これは、非常に稀なケースであり、必ずしも認められるとは限りません。
また、受け直しが認められる場合でも、ペナルティが課せられる可能性があります。
3-3. 事前に行政庁との協議が必須
上記のような例外的なケースで経審の受け直しを希望する場合は、必ず事前に許可行政庁に相談し、指示に従う必要があります。
4申請ミスを防ぐための3つの対策
経審の申請は、原則としてやり直しがきかないため、申請ミスを防ぐための対策が重要となります。
4-1. 提出書類の徹底的なチェック
申請書類に不備や誤りがないか、提出前に徹底的にチェックしましょう。
特に、以下の点に注意が必要です。
(1)記入漏れ、記入ミス:
申請書の記入漏れや記入ミスがないか、複数の目で確認する。
(2)添付書類の不足:
必要な添付書類がすべて揃っているか、リストを作成して確認する。
(3)数字の誤り:
完成工事高や技術職員数など、数字の誤りがないか、電卓などを使って再計算する。
(4)最新の様式:
申請書や添付書類の様式は、変更されることがあるため、最新の様式を使用する。
4-2. 建設業許可・経審の専門家(行政書士)に相談
建設業許可や経審の手続きは、非常に複雑で、専門的な知識が必要です。
申請書類の作成や提出、行政庁とのやり取りなど、不安な点がある場合は、建設業許可・経審を専門とする行政書士に相談することをおすすめします。
行政書士は、建設業法や関連法令に精通しており、最新の情報にも詳しいため、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。
また、申請書類の作成や提出を代行してもらうことも可能です。
4-3. 余裕を持ったスケジュールで申請
経審の申請は、決算後4ヶ月以内に行う必要がありますが、ギリギリになって慌てて準備するのではなく、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。
特に、初めて経審を受ける場合や、久しぶりに経審を受ける場合は、準備に時間がかかることがあります。
早めに準備を始めることで、申請書類の不備や誤りに気づき、修正する時間的余裕が生まれます。
また、疑問点や不明点を行政書士や行政庁に相談する時間も確保できます。
5まとめ
経営事項審査(経審)は、公共工事の元請業者となるためには、避けて通れない重要な手続きです。
しかし、申請は原則としてやり直しがきかないため、慎重に進める必要があります。
今回の記事では、経審の受け直しと再審査について、詳しく解説しました。
申請内容に誤りがないか、加点対象となる項目を見落としていないかなど、細心の注意を払って申請準備を行いましょう。
経営事項審査(経審)は、公共工事の元請業者の立場となる者には、絶対に欠かせない重要な手続きです。
ただ、制度の煩雑さ・複雑さから、「難しそう…」「面倒…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
また、申請後にミスに気づいても、原則としてやり直しはできません。
行政書士藤井等事務所は、建設業許可・経営事項審査(経審)の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「経審の申請をしたいけど、何から手をつければいいか分からない」「申請書類の書き方が分からない」「自社に有利な申請方法を知りたい」という相談だけでも構いません。
建設業許可及び経営事項審査(経審)を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
(2) 事務所ホームページ<許認可申請>





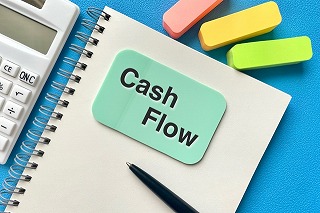
.jpg)