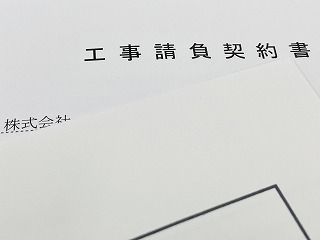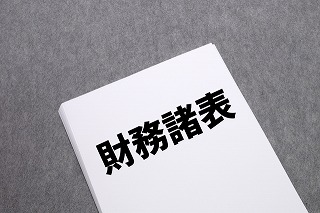
「建設業の決算書類って、貸借対照表と損益計算書だけでいいの?」
「『株主資本等変動計算書』や『注記表』って何?」
「ウチの会社も『附属明細表』や『事業報告書』を作る必要があるの?」
こんな疑問をお持ちではありませんか?
建設業許可の申請・更新や経営事項審査(経審)では、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)だけでなく、株主(社員)資本等変動計算書(S/S)や注記表、附属明細表(大会社のみ)、事業報告書といった付属書類の作成・提出も求められます。
これらの書類は、会社の財産状況や経営成績をより詳細に示し、透明性を確保するために重要な役割を果たします。
ご安心ください!
今回の記事では、建設業財務諸表における「株主(社員)資本等変動計算書」「注記表」「附属明細表」「事業報告書」について、その役割や作成のポイント、注意点を分かりやすく解説します。
この記事を読めば、これらの付属書類の必要性や作成方法が理解でき、スムーズな許可申請や経審の準備を進めることができます。
1株主(社員)資本等変動計算書(S/S)
株主(社員)資本等変動計算書(S/S)は、貸借対照表(B/S)の「純資産の部」が、一事業年度の間にどのように変動したかを示す計算書です。
貸借対照表と損益計算書(P/L)をつなぐ役割を果たしています。
1-1. S/Sの役割
貸借対照表を見れば、期首と期末の純資産額は分かりますが、その純資産が「なぜ」「どのように」変動したのかまでは分かりません。
株主(社員)資本等変動計算書は、その変動の理由を項目別に詳しく記載することで、会社の財政状態の変動要因を株主(社員)や債権者などの利害関係者に報告することを目的としています。
具体的には、以下のような純資産の変動要因を記載します。
(1)当期純利益(または当期純損失):
損益計算書で計算された当期の利益(または損失)が、利益剰余金をどれだけ増減させたか。
(2)剰余金の配当:
株主(社員)への配当金が、利益剰余金からどれだけ支払われたか(社外流出)。
(ただし、医療法人など非営利法人は配当不可)
(3)準備金・積立金の積立て:
利益剰余金から、利益準備金や別途積立金などがどれだけ積み立てられたか(内部留保)。
(4)資本金・準備金・剰余金間の振替:
例えば、資本準備金を取り崩して欠損填補に充てた場合など。
(5)新株の発行(増資):
新株発行により資本金や資本準備金がどれだけ増加したか。
(6)自己株式の取得・処分・消却:
自己株式の取引による純資産の変動。
1-2. 合同会社の場合は「社員資本等変動計算書」
合同会社の場合は、構成員が「株主」ではなく「社員」であるため、計算書の名称も「社員資本等変動計算書」となります。
基本的な役割や記載内容は、株主資本等変動計算書と同様です。
1-3. S/Sの作成義務:すべての会社で必要
株主(社員)資本等変動計算書は、2006年(平成18年)施行の新会社法で作成が義務付けられた計算書類です。
株式会社だけでなく、合同会社、合名会社、合資会社など、すべての会社形態で作成が必要です。
建設業を営む法人も、当然、この計算書の作成義務があります。
2注記表
注記表は、貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書の内容を補足し、利害関係者が会社の財政状態や経営成績を正しく理解するために必要な情報を提供する書類です。
2-1. 注記表の役割と根拠
注記表は、2006年(平成18年)施行の新会社法で作成が義務付けられました。
建設業財務諸表においては「注記表」という名称ですが、一般的には「個別注記表」と呼ばれます(内容は基本的に同じです)。
会社法では、計算書類として10年間の保存義務があります。
注記表に記載すべき事項は、会社法および会社計算規則(会社法の規定に基づき、会社の計算に関するルールを定めた法務省令)の第98条から第116条に定められています。
2-2. 記載項目:原則19項目、中小企業は6項目
注記表に記載すべき項目は、原則として19項目あります。
しかし、多くの中小企業が該当する「株式譲渡制限会社」(株式を譲渡する際に会社の承認が必要な会社)かつ「会計監査人を設置していない会社」の場合は、記載義務のある項目が大幅に簡略化され、以下の6項目の記載で足ります。
(1)重要な会計方針に係る事項に関する注記(会社計算規則第101条):
・資産の評価基準及び評価方法(例:棚卸資産の評価方法)
・固定資産の減価償却の方法
・引当金の計上基準
・収益及び費用の計上基準(例:工事収益の認識基準)
・その他、財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(2)会計方針の変更に関する注記(会社計算規則第102条):
会計方針を変更した場合、その内容、変更の理由、影響額などを記載します。
(3)表示方法の変更に関する注記(会社計算規則第102条の2):
財務諸表の表示方法を変更した場合、その内容、変更の理由などを記載します。
(4)誤謬の訂正に関する注記(会社計算規則第102条の4):
過去の財務諸表に誤りがあり、それを訂正した場合、その内容、影響額などを記載します。
(5)株主資本等変動計算書に関する注記(会社計算規則第103条):
発行済株式の種類及び総数、自己株式の種類及び株式数などを記載します。
(6)その他(定款で定めた事項など):
会社独自の注記事項があれば記載します。
2-3. 作成漏れに注意!
注記表は、会社法では作成が義務付けられていますが、法人税の確定申告では提出義務がありません。
そのため、税理士事務所によっては、注記表を作成していないケースも見受けられます。
しかし、建設業許可申請や経審においては、注記表は必須の提出書類です。
作成漏れがないように、必ず確認しましょう。
3附属明細表(大会社のみ)
附属明細表は、貸借対照表や損益計算書の内容を、さらに詳細に補足するための書類です。
しかし、この附属明細表の作成が義務付けられているのは、会社法上の「大会社」のみです。
3-1. 大会社の定義
会社法でいう「大会社」とは、以下のいずれかの要件を満たす株式会社です。
・資本金が5億円以上
・負債総額が200億円以上
日本の株式会社の大半は、この要件を満たさない中小企業(小会社)であり、附属明細表の作成義務はありません。
3-2. 附属明細表の記載項目
附属明細表の作成が必要な大会社は、以下の項目などについて、その内訳を詳細に記載する必要があります。
・有形固定資産及び無形固定資産の明細
・引当金の明細
・販売費及び一般管理費の明細
・完成工事未収入金の明細
・未成工事支出金の明細
・短期貸付金、長期貸付金の明細
・短期借入金、長期借入金の明細
・工事未払金の明細
・未成工事受入金の明細
・その他、会社の財産または損益の状況を正確に判断するために必要な事項
3-3. 作成の負担(税理士との連携)
附属明細表の作成は、非常に詳細な情報を記載する必要があり、作成にはかなりの時間と手間がかかります。
もし、自社が大会社に該当し、附属明細表の作成が必要な場合は、顧問税理士と緊密に連携し、計画的に準備を進める必要があります。
4事業報告書(株式会社のみ)
事業報告書は、株式会社が、毎事業年度における事業の状況を報告するために作成する書類です。
会社法で作成が義務付けられていますが、定まった様式はありません。
4-1. 作成義務(株式会社のみ)
事業報告書の作成義務があるのは、株式会社のみです。
持分会社である有限会社や合同会社には、作成義務はありません。
4-2. 記載内容
事業報告書に記載すべき主な内容は、会社法や会社法施行規則で定められています。
・会社の現況に関する事項(事業の経過及びその成果、財産及び損益の状況、重要な資金調達・設備投資の状況など)
・役員に関する事項(氏名、役職、担当など)
・株式に関する事項(発行済株式総数、株主数、大株主の状況など)
・その他、会社の状況に関する重要な事項
4-3. 参考様式
定まった様式はありませんが、各都道府県庁(例えば大阪府など)などで、事業報告書のひな形や記載例が公開されている場合がありますので、参考にすると良いでしょう。
5まとめ
建設業許可申請や経営事項審査(経審)においては、貸借対照表や損益計算書だけでなく、株主(社員)資本等変動計算書や注記表といった付属書類の作成・提出も重要です。
これらの書類は、会社の経営状況をより深く理解するための重要な情報を含んでおり、審査においても確認されます。
「どの書類を、どこまで作ればいいのか分からない」「注記表の書き方が難しい」「附属明細表や事業報告書は、自社に必要なのか?」
このような疑問や不安をお持ちの建設業者様は、ぜひ建設業専門の行政書士にご相談ください。
当事務所は、建設業許可・経営事項審査(経審)の専門家として、複雑な建設業財務諸表(付属書類を含む)の作成から、各種申請手続きまで、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーと、『士業の会』を主宰しており、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという、他の事務所にない「強み」を持っているところです。
建設業許可及び経営事項審査(経審)を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>
https://office-fujiihitoshi.com/