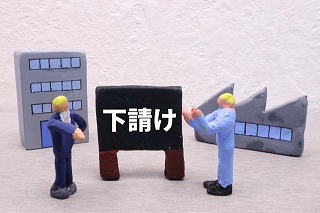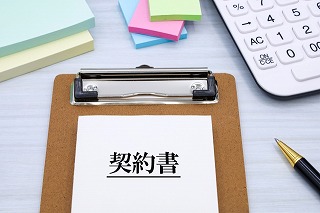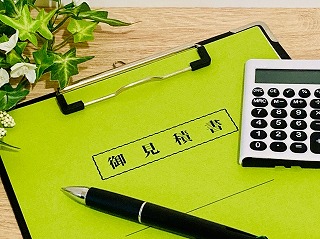「リース契約に付随する設置工事は、建設業許可が必要?」
「設備の保守契約は、建設業法と関係あるの?」
「契約書のタイトルが『業務委託契約』なら、建設業法は適用されない?」
こんな疑問を感じたことはありませんか?
ご安心ください。
そのお悩みは、建設業法における「建設工事の請負契約」の定義を正しく理解することで解決できます。
この記事では、どのような契約が建設業法の対象となるのか、その基本的な考え方と、判断に迷いやすい具体的なケースについて分かりやすく解説します。
建設業を営む上で、その根幹をなす法律が「建設業法」です。
この法律は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することを目的としています。
しかし、事業が多角化する現代において、「どの契約が建設業法の適用を受けるのか」という境界線は、時に複雑で、判断に迷う場面も少なくありません。
特に、リース契約や保守契約といった、一見すると建設工事とは異なる契約形態の中に、実質的な工事が含まれている場合、その取り扱いを誤ると、意図せず「無許可営業」と見なされてしまうリスクさえあります。
今回は、すべての建設業者が知っておくべき、建設業法が適用される「建設工事」の範囲について、その本質と具体的な判断基準を詳しく見ていきましょう。
1建設業法が適用される「建設工事の請負契約」とは?
まず、建設業法がどのような契約を対象としているのか、その基本的な定義を正確に理解することが重要です。
1-1. 2つの重要なキーワード:「報酬」と「完成目的」
建設業法第24条では、この法律が適用される契約を、「建設工事の完成を目的として締結する請負契約」と定義しています。
また、同法第2条では、「建設工事」とは土木建築に関する工事のことであり、「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約であるとされています。
ここから、以下の2つの要素を満たすものが、建設業法の適用対象となる「建設工事の請負契約」であると分かります。
① 仕事の結果に対して「報酬」が支払われること。
したがって、ボランティア活動など、無報酬で行う工事は建設業法の適用を受けません。
② 「建設工事の完成」を目的としていること。
これが最も重要な判断基準です。単に資材を販売するだけの「売買契約」や、機械を貸すだけの「賃貸借契約」、労働力を提供するだけの「委任契約(準委任契約)」などは、原則として建設工事の完成を目的としていないため、建設業法の適用はありません。
1-2. 契約の名称ではなく「実態」で判断される
注意すべきは、契約の判断は、契約書のタイトル(「業務委託契約書」「保守契約書」など)ではなく、その契約内容の実態に基づいて行われるという点です。
たとえ契約書の名称が請負契約でなくても、その内容に「建設工事の完成」を目的とする要素が含まれていれば、その部分は建設業法の適用対象となる可能性があります。
2判断に迷うケーススタディ①
では、具体的なケースで考えてみましょう。
ユーザー様ご提供の本文にもあった、非常に分かりやすい事例です。
2-1. 契約の概要
ある顧客と、業務用エアコンの保守点検を行う「保守契約」を締結しました。
この契約には、保守業務を効率的に行うため、受注者(保守業者)が使用する「遠隔監視装置」を、顧客の建物に設置する作業が含まれています。
この設置作業は、建設業法上の「建設工事」に該当するのでしょうか?
2-2. 判断のポイント
このケースの判断ポイントは、契約全体の「主たる目的」が何か、ということです。
この契約の主たる目的は、あくまで「エアコンの保守点検」という役務(サービス)の提供であり、建設工事の完成ではありません。監視装置の設置は、その保守業務を遂行するための、付随的な作業に過ぎません。
2-3. 結論
したがって、この監視装置の設置工事は、それ自体が契約の目的ではなく、また、装置も受注者が使用するものであることから、「建設工事の完成を目的とする請負契約」には該当せず、建設業法の適用はないと解釈されます。
ただし、ユーザー様のアドバイスにもある通り、このようなグレーなケースについては、判断に迷ったら、事前に行政の担当窓口や、専門家である行政書士に相談するのが最も安全な方法です。
3判断に迷うケーススタディ②
次に、よく似ていますが、結論が異なる「リース契約」のケースを見てみましょう。
3-1. 契約の概要
ある顧客と、エアコン本体の「リース契約」を締結しました。
この契約には、顧客がそのエアコンを使用できるようにするための「設置工事」が含まれています。
3-2. 判断のポイント
このケースでは、エアコンの設置工事は、リース契約をした注文者(顧客)自身が、そのエアコンを使用できるようにするために不可欠な作業です。
つまり、設置工事の完成がなければ、リース契約の目的(顧客がエアコンを使うこと)が達成されません。
この場合、設置工事は、単なる付随的な作業ではなく、「建設工事の完成」そのものが契約の重要な目的の一部であると判断されます。
3-3. 結論
したがって、このエアコンの設置工事部分は、明確に「建設工事の請負契約」に該当し、建設業法の適用を受けます。
もし、この設置工事の請負金額が500万円以上になる場合は、対応する業種(この場合は管工事業)の建設業許可が必要となります。
4全体の整理
このように、建設業法の適用対象となるかどうかは、契約の名称や形式ではなく、その取引の「実態」と「主たる目的」によって判断されます。
事業が多角化し、サービスやリースと工事が一体となった契約が増える中で、自社の行っている業務が建設業法の規制対象となる「建設工事」に該当しないかを、常に意識しておくことが重要です。
意図せず無許可営業となってしまうリスクを避けるためにも、契約内容に少しでも建設工事の要素が含まれる場合は、その契約全体が建設業法の適用を受ける可能性があることを念頭に置き、迷った際には必ず専門家にご相談ください。
5まとめ
建設業法が適用される「建設工事」の範囲は、時に判断が難しいケースがあります。
特に、リース契約や保守契約など、他の契約形態と一体となっている場合、その取り扱いを誤ると、意図せず法令違反となるリスクを伴います。
「自社のこの業務は、建設業許可が必要だろうか」「契約書の作り方に不安がある」など、建設業法に関するコンプライアンスのお悩みは、専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、貴社の事業内容を正確に分析し、適法な事業運営をサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/