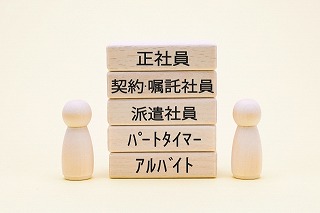
「優秀な派遣社員がいるが、彼を現場の主任技術者にすることはできないだろうか?」
「出向中の社員を、監理技術者として配置したいが可能か?」
「そもそも、現場技術者に求められる『雇用関係』とは具体的に何?」
こんな疑問を感じていませんか?
ご安心ください。
その疑問は、建設業法が定める技術者と会社との間の「雇用関係」に関するルールを正しく理解することで、明確に解決できます。
この記事では、主任技術者・監理技術者に求められる雇用関係の2つの重要な側面、「直接的」と「恒常的」の意味と、その証明方法について分かりやすく解説します。
建設工事の現場において、その品質と安全を司る「主任技術者」や「監理技術者」。
彼らの存在は、建設業許可を維持し、適正な施工体制を確保するための根幹です。
建設業法は、これらの重要な役割を担う技術者について、その資格や経験だけでなく、所属する建設業者との「雇用関係」についても、厳格なルールを定めています。
特に、人材の流動化が進む現代において、「派遣社員や出向者などの、いわゆる『外部人材』を現場の技術責任者として配置できるのか?」という問いは、多くの経営者様が直面する課題です。
今回は、この重要な「雇用関係」のルールについて、その本質と具体的な判断基準を詳しく見ていきましょう。
1なぜ「直接的かつ恒常的な雇用関係」が求められるのか?
まず、なぜ法律は、現場に配置する技術者に対して、単なる業務委託や派遣ではなく、会社との固い結びつきを求めるのでしょうか。
その理由は、建設業法の根本的な目的にあります。
1-1. 建設工事の適正な施工を確保するため
建設工事は、一つひとつの工程が複雑に絡み合い、多くの専門業者が関わる総合的な生産活動です。
その技術上の管理を担う主任技術者・監理技術者は、個人の技術力だけでなく、所属する建設業者が持つ組織としての技術力や管理体制を熟知し、それを最大限に活用して現場を指揮する必要があります。
また、建設業者は、自社が雇用する技術者を通じて、工事の品質や安全に対する最終的な責任を負います。
この責任関係を明確にするためにも、技術者と会社との間に、第三者が介在しない、安定的で継続的な結びつきが不可欠であると考えられているのです。
この「安定的で継続的な結びつき」を、法律用語では「直接的かつ恒常的な雇用関係」と表現します。
2「直接的な雇用関係」とは?-派遣社員がなれない理由
では、一つ目の要件である「直接的な雇用関係」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。
2-1. 第三者が介在しない、会社と個人の結びつき
「直接的な雇用関係」とは、主任技術者・監理技術者となる個人と、所属する建設業者との間に、第三者が介在する余地のない、直接の雇用契約が存在することを意味します。
賃金の支払い、労働時間や休暇の管理、業務上の指揮命令といった、雇用に関する権利と義務が、両者の間で直接結ばれている状態です。
2-2. 派遣社員・在籍出向者が該当しない理由
この定義に照らすと、以下のケースは「直接的な雇用関係」にあるとは言えません。
① 労働者派遣(派遣社員):
派遣社員の雇用主は、派遣元の派遣会社です。
給与の支払いや社会保険の手続きも派遣元が行います。
建設業者は、あくまで派遣先として業務上の指示を出すに過ぎず、直接の雇用関係にはありません。
② 在籍出向:
出向元の会社に籍を置いたまま、出向先の建設業者で働く場合も、雇用契約の主体は出向元にあるため、原則として直接的な雇用関係とは見なされません。
(※完全に籍を移す「移籍出向」の場合は、転職と同様に扱われ、直接的な雇用関係と認められます。)
したがって、派遣社員や在籍出向者を、主任技術者・監理技術者として現場に配置することは、原則としてできないのです。
2-3. 直接的雇用関係の証明方法
申請窓口では、この直接的な雇用関係を客観的な資料で確認します。
一般的に、以下の書類の写しが求められます。
① 健康保険被保険者証:
事業所名(=所属建設業者名)が記載されていることで、その会社に雇用されていることが確認できます。
② 住民税特別徴収税額通知書:
会社が給与から住民税を天引き(特別徴収)している事実が、正規の従業員であることの強い証明となります。
3「恒常的な雇用関係」とは?-短期雇用が認められない理由
二つ目の要件である「恒常的な雇用関係」は、その雇用の「継続性」や「安定的」な側面を問うものです。
3-1. 一定期間の継続的な勤務実態
「恒常的な雇用関係」とは、その工事の契約期間中はもちろん、その前から一定期間、継続してその建設業者に勤務している実態があることを指します。
工事の期間だけ雇用するような、日雇いや短期契約の労働者は、恒常的な雇用関係にあるとは認められません。
3-2. 公共工事における「3ヶ月ルール」
特に、公共工事の入札に参加する場合、その判断基準はより厳格になります。
経営事項審査(経審)や入札参加資格審査においては、原則として、「入札申込日以前に3ヶ月以上の雇用関係」にあることが求められます。
この「3ヶ月ルール」は、民間工事の許可申請などにおいても、恒常性を判断する上での一つの重要な目安となります。
3-3. 高齢者の継続雇用制度の特例
一方で、高齢化社会に対応するため、定年退職した技術者を継続雇用制度(再雇用制度や勤務延長制度)によって引き続き雇用している場合は、その雇用期間の長短にかかわらず、恒常的な雇用関係にあるものとみなすという特例も設けられています。
3-4. 恒常的雇用関係の証明方法
恒常的な雇用関係は、主に以下の書類の日付などから確認されます。
① 監理技術者資格者証:
交付年月日や変更履歴で、その会社への所属期間が確認できます。
② 健康保険被保険者証:
資格取得年月日が、雇用開始日を示す重要な証拠となります。
4整理
建設工事の現場責任者である主任技術者・監理技術者は、企業の技術力と信用を体現する重要な存在です。
だからこそ、建設業法は、その技術者が、名実ともにその企業の一員であること(直接的かつ恒常的な雇用関係)を厳しく求めているのです。
人材確保が難しい時代だからこそ、安易に外部人材に頼りたくなる気持ちも理解できます。
しかし、この雇用関係のルールを軽視することは、建設業許可の根幹を揺るがし、企業の存続を危うくする行為に他なりません。
自社の技術者体制が、法律の求める基準を確実に満たしているか、今一度、丁寧にご確認ください。
5まとめ
主任技術者・監理技術者に求められる「直接的かつ恒常的な雇用関係」。
このルールを正しく理解せず、派遣社員などを配置してしまうと、建設業法違反として、許可の取消しといった厳しい処分を受ける可能性があります。
「この出向社員は、技術者として認められるだろうか」「自社の雇用体制で、許可要件をクリアできるか不安だ」といったお悩みは、専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、建設業法務の専門家として、最新の法令に基づき、貴社のコンプライアンス体制構築をサポートします。
元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、貴社の事業運営を法務面から力強く支援いたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/






