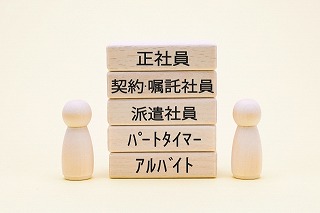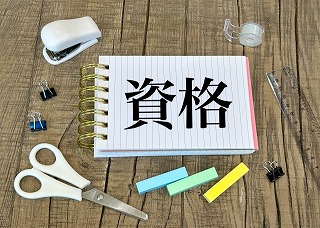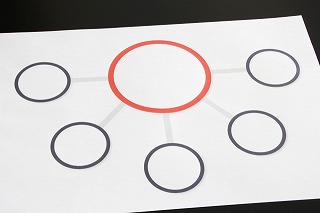「ICTを使えば、一人の監理技術者が複数の現場を兼務できると聞いたけど、具体的にどうすればいいの?」
「新しく導入された『連絡員』って、一体誰がなれて、どんな仕事をするの?」
こんな疑問を感じていませんか?
ご安心ください。
その疑問は、改正建設業法で導入された「連絡員」の役割と要件を正しく理解することで解決できます。
この記事では、建設業界の生産性向上と人材の有効活用の切り札となる「連絡員」について、その職務内容から、なるための要件までを分かりやすく解説します。
深刻な技術者不足と、建設業界全体の生産性向上という大きな課題に対応するため、建設業法は大きな変革の時代を迎えています。
その象徴的な取り組みの一つが、ICT(情報通信技術)の活用を前提とした、主任技術者・監理技術者の専任配置義務の緩和です。
そして、この新しい制度を支えるキーパーソンとして、新たに「連絡員」という役割が創設されました。
この連絡員の制度を正しく理解し、活用することは、限られた人材を最大限に活かし、企業の競争力を高める上で極めて重要です。
今回は、この新しい役割である「連絡員」について、その全てを詳しく見ていきましょう。
1技術者の兼務を支える新設の役割、「連絡員」とは?
まず、「連絡員」がどのような背景で生まれ、何を目的とした役割なのかを理解することが大切です。
1-1. 制度創設の背景
2024年(令和6年)12月までに施行される改正建設業法では、担い手確保と生産性向上の観点から、主任技術者・監理技術者の配置に関するルールが合理化されました。
その柱となるのが、一定の条件下で、一人の技術者が最大2つまでの工事現場を兼務できるという緩和措置です。
これを実現するために、遠隔で管理を行う技術者と、現場とを繋ぐパイプ役として「連絡員」の配置が義務付けられました。
1-2. 連絡員の基本的な定義
連絡員とは、主任技術者・監理技術者が、ICTを活用して複数の専任現場を兼務する際に、それぞれの工事現場に配置されなければならない者を指します。
その名の通り、現場と技術者との間の「連絡」を密にし、技術者の目が届きにくい部分を補い、適切な施工管理体制を維持することが、その主な役割です。
2連絡員が担う具体的な職務内容
連絡員は、遠隔で指揮を執る主任技術者・監理技術者の「目・耳・手足」として機能します。
その具体的な職務は、現場の状況に応じて多岐にわたりますが、主に以下のような業務が想定されています。
2-1. 主任技術者・監理技術者との密な連携
⑴ 遠隔で行われる工程会議や品質検査などに際し、現場の状況を映像や音声で正確に技術者へ伝達する。
⑵ 技術者からの指示を、現場の作業員や他の関係者へ的確に伝達し、その意図を共有する。
⑶ 日々の進捗状況や、現場で発生した軽微な問題などを、速やかに技術者へ報告する。
2-2. 施工管理業務の補助
⑴ 技術者の指示に基づき、施工記録写真の撮影や、書類の整理といった補助業務を行う。⑵ 万が一、事故やトラブルが発生した際の、初期対応や状況報告を行う。
2-3. 連絡員の配置における柔軟性
連絡員は、現場の円滑な運営を支える重要な役割ですが、その配置には一定の柔軟性が認められています。
⑴ 専任・常駐は不要:
連絡員は、その現場に専任であることや、常に常駐していることまでは求められていません。
⑵ 兼務が可能:
同一人物が、複数の工事現場の連絡員を兼務することも可能です。
⑶ 複数人配置も可能:
一つの工事現場に、複数の連絡員を置くことも認められています。
3誰が「連絡員」になれるのか?
連絡員になるための要件は、主任技術者ほど厳格ではありませんが、注意すべき重要なポイントがあります。
3-1. 雇用関係の要件
主任技術者・監理技術者とは異なり、連絡員には、所属する建設業者との間に直接的・恒常的な雇用関係は求められていません。
つまり、正社員だけでなく、派遣社員や在籍出向者などを連絡員として配置することも可能です。
これは、企業がより柔軟に人材を活用する上で、非常に大きなメリットと言えます。
ただし、その場合であっても、連絡員の行為に対する最終的な監督責任は、元請負人である建設業者が負うことを、明確に理解しておく必要があります。
3-2. 資格・経験に関する要件
連絡員には、原則として特定の国家資格などは求められません。
しかし、例外的に、担当する工事が「土木一式工事」または「建築一式工事」である場合には、連絡員は1年以上の実務経験を有している必要があります。
⑴ 実務経験の考え方:
ここでいう「実務経験」は、建設業許可における営業所技術者や主任技術者の実務経験と同様の考え方に基づきます。
⑵ 証明方法:
この実務経験は、兼務を認めてもらうために提出する「人員の配置を示す計画書」に記載することで証明します。
⑶ 一式工事以外の専門工事:
土木一式・建築一式以外の、27の専門工事業においては、連絡員に実務経験は求められません。
4整理
「連絡員」制度は、建設業界のDX化と働き方改革を推進し、深刻な技術者不足という課題を乗り越えるための、新しい時代の仕組みです。
この制度を正しく理解し、適切な人材を「連絡員」として配置・育成することで、企業は、優秀な主任技術者・監理技術者の能力を複数の現場で活かし、生産性と競争力を大きく向上させることが可能になります。
ただし、その運用には、改正された建設業法のルールの正確な理解が不可欠です。
自社の体制をこの新しい時代に適応させていくために、ぜひ専門家のアドバイスをご活用ください。
5まとめ
改正建設業法で導入された「連絡員」制度は、ICT活用による技術者の兼務を可能にする、画期的な仕組みです。
これを正しく活用すれば、企業の生産性向上と人材の有効活用に大きく貢献します。
しかし、その要件や運用方法は複雑であり、正確な理解が不可欠です。
「自社でこの制度を活用できるか」「連絡員の配置について、具体的にどうすれば良いか」など、お悩みは専門家にご相談ください。
当事務所は、建設業法務の専門家として、最新の法改正に対応したコンプライアンス体制の構築を支援します。
元岩手県職員としての経験と他士業との連携も活かし、貴社の「無限の可能性」を法務面から力強くサポートいたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/