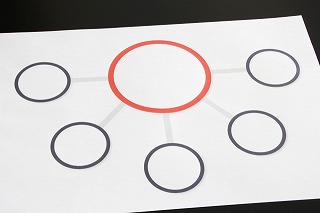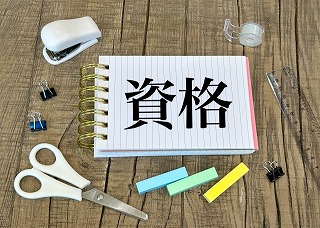「2024年4月からの時間外労働の上限規制、どう対応すれば…」
「人手不足と長時間労働から、なかなか抜け出せない」
「建設DXやICT活用と聞くけれど、法律との関係や、具体的に何をすれば良いのか分からない」
こんなお悩みを抱えていませんか?
ご安心ください。
その課題は、建設業法で新たに示された「ICT活用」のルールを正しく理解し、実践することで、解決への道筋が見えてきます。
この記事では、建設業界の未来を左右するICT活用について、法的な位置づけから、具体的な活用事例までを分かりやすく解説します。
建設業界は今、大きな変革の時代を迎えています。
長年の課題であった長時間労働の是正を目指し、2024年(令和6年)4月から、ついに建設業にも罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されました。
これに加えて、深刻化する担い手不足の問題。この二つの大きな課題を乗り越え、持続可能な産業であり続けるためには、業務のあり方を根本から見直し、「生産性の向上」を達成することが不可欠です。
そして、その最大の切り札として国が推進しているのが、ICT(情報通信技術)の活用です。2024年(令和6年)に改正された建設業法では、このICT活用が、もはや単なる選択肢ではなく、すべての建設業者が取り組むべきテーマとして明確に位置づけられました。
今回は、企業の未来を左右するこの重要な取り組みについて、詳しく見ていきましょう。
1建設業法が求める「ICT活用の努力義務」とは?
今回の法改正で、建設業に携わるすべての事業者に対し、ICT活用に関する2つの「努力義務」が新たに課せられました。
「努力義務」とは、違反しても直ちに罰則があるわけではありませんが、法律が目指す方向性として、すべての事業者が取り組むべきものとされている、非常に重い意味を持つ義務です。
1-1. 義務①:効率的な現場管理のためのICT活用
まず、元請・下請を問わず、すべての建設業者は、自社の業務において、効率的な現場管理のためにICTの活用に努めなければならないとされました。
これは、ドローンやウェアラブルカメラ、各種の業務効率化アプリなどを活用し、生産性を高める工夫をすることが、法律上の努力目標となったことを意味します。
1-2. 義務②:下請負人へのICT活用に関する指導
さらに、元請負人には、下請負人のICT活用能力が向上するよう、必要な指導や助言に努めることも求められます。
これは、元請だけがDX化を進めても、下請がついてこなければ業界全体の生産性は向上しない、という考えに基づいています。
元請には、建設生産システム全体のリーダーとして、業界全体のデジタル化を牽引する役割が期待されています。
1-3. ICT活用がもたらす具体的なメリット(規制緩和)
国は、ICT活用を推進するため、「アメ」も用意しています。
ICTの活用を条件に、以下のような規制緩和が認められています。
⑴ 技術者の兼務:
遠隔での臨場が可能なICTを用いることで、一定の条件下で、一人の主任技術者・監理技術者が最大2つの現場を兼務できる「専任特例1号」が利用可能になります。
⑵ 書類提出の簡素化:
発注者がICTを活用して施工状況をリアルタイムで確認できる場合、従来必要だった施工体制台帳の写しの提出が不要となります。
2国が示す道しるべ:「ICT指針」の重要性
「ICT活用と言っても、何から手をつければ良いのか…」という事業者のために、国土交通省は「情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針(ICT指針)」を公表しています。
この指針は、元請負人・下請負人双方の書類作成の負担増が、長時間労働の大きな原因となっているという問題意識から生まれました。
発注者や元請、下請ごとに異なる書類の様式や、バラバラな情報共有システムが、業界全体の非効率を招いていたのです。
ICT指針は、こうした問題の解決を目指し、情報共有システムの標準化や、活用すべき技術の具体例などを示しており、すべての建設業者がICT化を進める上での、重要な道しるべとなります。
3建設現場におけるICTの具体的な活用事例
では、実際に建設現場では、どのようなICTが活用されているのでしょうか。
3-1. ドローン(UAV)
従来、人手に頼っていた測量作業や、工事の進捗確認のための写真撮影、高所や危険箇所の点検などにドローンを活用することで、作業時間の大幅な短縮と安全性の向上が実現できます。
3-2. ウェアラブルカメラ・遠隔臨場システム
現場の作業員が装着したウェアラブルカメラの映像を、事務所や別の現場にいる技術者がリアルタイムで確認し、遠隔で指示や指導を行うことができます。
これは、前述した技術者の兼務を実現するための必須技術です。
3-3. 建設ロボット・ICT建機
危険を伴う作業や、単純な繰り返し作業(鉄筋の結束など)をロボットに任せたり、ICT技術で自動制御される建設機械(ICT建機)を導入したりすることで、省人化と安全性の向上を図ります。
3-4. BIM/CIM・情報共有システム
設計段階から3次元モデル(BIM/CIM)を導入し、それを元請・下請間で共有することで、初期段階での合意形成を円滑にし、手戻りを防ぎます。
また、クラウドベースの情報共有システムを使えば、図面や日報、各種書類のやり取りが一元化され、関係者間のコミュニケーションロスを劇的に削減できます。
4整理
建設業界におけるICTの活用は、もはや一部の先進的な企業だけのものではなく、時間外労働の上限規制という「2024年問題」を乗り越え、未来を生き抜くために、すべての企業が取り組むべき必須の経営課題となりました。
それは、単なるコストではなく、生産性を高め、従業員の労働環境を改善し、企業の競争力を強化するための、未来への最も重要な「投資」です。
元請負人としては、下請負人と十分に協議し、それぞれの工事に最適なICT活用法を共に模索していく姿勢が求められます。
この新しい時代の波に乗り遅れないよう、今こそ、自社のデジタル化戦略を真剣に考えてみてはいかがでしょうか。
5まとめ
建設業法で努力義務化された「ICTの活用」は、建設業界の働き方改革と生産性向上を実現するための鍵です。
最新の規制緩和をうまく活用すれば、技術者不足といった経営課題の解決にも繋がります。
しかし、「自社に合ったICTは何か」「導入にあたって、法的に注意すべき点は何か」など、その実践には専門的な知見が必要です。
当事務所は、建設業法務の専門家として、最新の法改正に対応した事業運営をサポートします。
元岩手県職員としての経験と他士業との連携により、貴社のDX化と、その先にある「無限の可能性」の実現を、法務面から力強く後押しいたします。
6お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
(1) お問い合わせフォーム:
https://office-fujiihitoshi.com/script/mailform/toiawase/
(2) 事務所ホームページ<トップページ>:
https://office-fujiihitoshi.com/